美化語 を作るには、言葉の前に 「お」 や 「ご(御)」 を付けますが、
今日は、一般的に 「お」 や 「ご(御)」 が付きやすいものと、逆に付きにくいものに分類してみましょう。
1 必ず付けるもの (地名 = 固有名詞) 言葉の向こうに、日本の歴史を垣間見る思いがします。
御茶ノ水 (おちゃのみず) 徳川秀忠の時代、近くのお寺の泉の水で を淹れて将軍に献上した。
を淹れて将軍に献上した。
御徒町 (おかちまち) に乗らずに徒歩で戦った下級武士(徒士 = かち) が住んでいた町。
に乗らずに徒歩で戦った下級武士(徒士 = かち) が住んでいた町。
お台場 江戸時代、品川沖に砲台 を建設する際、幕府に敬意を払って 「台場」 を 「御台場」 とした。
を建設する際、幕府に敬意を払って 「台場」 を 「御台場」 とした。
御殿場 (ごてんば) 徳川家康の遺体を日光東照宮に移す際に、仮の御殿を建てて安置所とした。
2 必ず付けるもの (省くと意味が分からなくなるもの) 室町時代に始まった女房言葉の名残りです。
おでん おかず おこわ おから おやつ おしぼり お年玉 お辞儀 お古
おかず おこわ おから おやつ おしぼり お年玉 お辞儀 お古  など
など
3 必ず付けるもの (省くと意味が変わってしまうもの)
おにぎり →
→  おふくろ →
おふくろ →  お眼鏡 →
お眼鏡 →  おかっぱ
おかっぱ  → 河童
→ 河童 など
など
4 付けたり省いたりするもの 話し手と聞き手の年齢や性別、立場などによって変わります。
お天気 お化粧
お化粧 
 ご本
ご本  お酒
お酒  お弁当
お弁当  お正月
お正月  お雑煮
お雑煮  など
など
5 付きにくいもの (外来語)
おビール おトイレ
おトイレ  おニュー
おニュー  おデート
おデート  おソース
おソース 
6 慣用句・ことわざ
「お馬のお耳に念仏 ? ?」 とは言いませんが、「御多分に漏れず」 では 「御」 が付きます。
?」 とは言いませんが、「御多分に漏れず」 では 「御」 が付きます。
 ちなみに 「御多分」 とは、「多数の者の意見や行動」 という意味であり、
ちなみに 「御多分」 とは、「多数の者の意見や行動」 という意味であり、
「多聞」 (多くを聞き知る) や 「他聞」 (他人に聞かれる) という漢字を使うのは誤りです。
7 言い方の変わるもの
飯(めし) → ご飯(ごはん) 腹(はら) → 御中(おなか)
腹(はら) → 御中(おなか)
 「お腹」 は当て字ですが、「御中」 や 「お中」 では意味が通じにくいため使われているようです。
「お腹」 は当て字ですが、「御中」 や 「お中」 では意味が通じにくいため使われているようです。
冒頭に、『 一般的に 「お」 や 「ご(御)」 が付きやすいもの・・・ 』 と書きましたが、
一般的な会話ではなく、たとえば のアナウンサーがニュースを読み上げる場合などは、
のアナウンサーがニュースを読み上げる場合などは、
聞き手である視聴者の年齢も性別も、さらに 美化語 に対する認識や受け止め方も多様であるため、
NHK では数年前に、「放送で使われる敬語」 というテーマで、全国調査を行なったそうです。
たしかに、季節の話題なのか、事件や事故なのか、はたまたアナウンサーが男性か女性かによっても、
幅広い年齢層の視聴者には、受け入れやすかったり、逆に違和感を覚えたりするものでしょうから、
不特定多数の視聴者に伝える側としては、広く意見を聴きながら言葉を使う必要があるのでしょうね。
参考までに、1975年に NHK がまとめた 「美化語の選別基準」 を記載します。
1 外来語に「お」は付きにくい
2 「お」で始まる語には付きにくい
3 長い語には付きにくい
4 悪感情の語には付きにくい
5 色、自然に関する語などには付きにくい
6 食事、心の動き、感情、体の働きに関する語などには付きやすい
7 女性の日常生活であまり使わない語には付きにくい
***************************************************************************************
さて、第104回 秘書検定 を受験なさった皆様には、筆記試験の結果が判明する頃でしょうか。
合格されましたら、ご自身の中でイメージしながら繰り返し練習を行ない、面接試験に臨んでくださいね。
当ブログの各カテゴリーが参考になれば、嬉しい限りです
お読みくださいましてありがとうございます。 クリックしていただけますと励みになります。
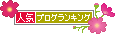

今日は、一般的に 「お」 や 「ご(御)」 が付きやすいものと、逆に付きにくいものに分類してみましょう。
1 必ず付けるもの (地名 = 固有名詞) 言葉の向こうに、日本の歴史を垣間見る思いがします。
御茶ノ水 (おちゃのみず) 徳川秀忠の時代、近くのお寺の泉の水で
 を淹れて将軍に献上した。
を淹れて将軍に献上した。御徒町 (おかちまち)
 に乗らずに徒歩で戦った下級武士(徒士 = かち) が住んでいた町。
に乗らずに徒歩で戦った下級武士(徒士 = かち) が住んでいた町。お台場 江戸時代、品川沖に砲台
 を建設する際、幕府に敬意を払って 「台場」 を 「御台場」 とした。
を建設する際、幕府に敬意を払って 「台場」 を 「御台場」 とした。御殿場 (ごてんば) 徳川家康の遺体を日光東照宮に移す際に、仮の御殿を建てて安置所とした。
2 必ず付けるもの (省くと意味が分からなくなるもの) 室町時代に始まった女房言葉の名残りです。
おでん
 おかず おこわ おから おやつ おしぼり お年玉 お辞儀 お古
おかず おこわ おから おやつ おしぼり お年玉 お辞儀 お古  など
など3 必ず付けるもの (省くと意味が変わってしまうもの)
おにぎり
 →
→  おふくろ →
おふくろ →  お眼鏡 →
お眼鏡 →  おかっぱ
おかっぱ  → 河童
→ 河童 など
など4 付けたり省いたりするもの 話し手と聞き手の年齢や性別、立場などによって変わります。
お天気
 お化粧
お化粧 
 ご本
ご本  お酒
お酒  お弁当
お弁当  お正月
お正月  お雑煮
お雑煮  など
など5 付きにくいもの (外来語)
おビール
 おトイレ
おトイレ  おニュー
おニュー  おデート
おデート  おソース
おソース 
6 慣用句・ことわざ
「お馬のお耳に念仏 ?
 ?」 とは言いませんが、「御多分に漏れず」 では 「御」 が付きます。
?」 とは言いませんが、「御多分に漏れず」 では 「御」 が付きます。 ちなみに 「御多分」 とは、「多数の者の意見や行動」 という意味であり、
ちなみに 「御多分」 とは、「多数の者の意見や行動」 という意味であり、「多聞」 (多くを聞き知る) や 「他聞」 (他人に聞かれる) という漢字を使うのは誤りです。
7 言い方の変わるもの
飯(めし) → ご飯(ごはん)
 腹(はら) → 御中(おなか)
腹(はら) → 御中(おなか) 「お腹」 は当て字ですが、「御中」 や 「お中」 では意味が通じにくいため使われているようです。
「お腹」 は当て字ですが、「御中」 や 「お中」 では意味が通じにくいため使われているようです。冒頭に、『 一般的に 「お」 や 「ご(御)」 が付きやすいもの・・・ 』 と書きましたが、
一般的な会話ではなく、たとえば
 のアナウンサーがニュースを読み上げる場合などは、
のアナウンサーがニュースを読み上げる場合などは、聞き手である視聴者の年齢も性別も、さらに 美化語 に対する認識や受け止め方も多様であるため、
NHK では数年前に、「放送で使われる敬語」 というテーマで、全国調査を行なったそうです。
たしかに、季節の話題なのか、事件や事故なのか、はたまたアナウンサーが男性か女性かによっても、
幅広い年齢層の視聴者には、受け入れやすかったり、逆に違和感を覚えたりするものでしょうから、
不特定多数の視聴者に伝える側としては、広く意見を聴きながら言葉を使う必要があるのでしょうね。
参考までに、1975年に NHK がまとめた 「美化語の選別基準」 を記載します。
1 外来語に「お」は付きにくい
2 「お」で始まる語には付きにくい
3 長い語には付きにくい
4 悪感情の語には付きにくい
5 色、自然に関する語などには付きにくい
6 食事、心の動き、感情、体の働きに関する語などには付きやすい
7 女性の日常生活であまり使わない語には付きにくい
***************************************************************************************
さて、第104回 秘書検定 を受験なさった皆様には、筆記試験の結果が判明する頃でしょうか。
合格されましたら、ご自身の中でイメージしながら繰り返し練習を行ない、面接試験に臨んでくださいね。
当ブログの各カテゴリーが参考になれば、嬉しい限りです

お読みくださいましてありがとうございます。 クリックしていただけますと励みになります。










 」、「 お茶の間 」 は 「 リビング 」、「 おさらい 」 は 「 復習 」、
」、「 お茶の間 」 は 「 リビング 」、「 おさらい 」 は 「 復習 」、
 」 へと、時代は移り変わって行きました。
」 へと、時代は移り変わって行きました。 」(大正時代の作品) に、
」(大正時代の作品) に、 」
」 の隣に
の隣に  がございます。」
がございます。」
 の会話は二人だけのものですが、このように取り次ぐことになりますと、
の会話は二人だけのものですが、このように取り次ぐことになりますと、 」 「鈴木さん
」 「鈴木さん 」では、たとえその後の言葉遣いが丁寧であっても、
」では、たとえその後の言葉遣いが丁寧であっても、 「お待ちいたしておりました。 佐藤様でございますね。」
「お待ちいたしておりました。 佐藤様でございますね。」



