















スポーツイベントや展示会の企画・運営、アクセサリーの販売などを手がけるJ.AIDING&Co.(現:J.AIDING合同会社)が制定。
「マンリーデー」(Manly Day)の日付は、2月14日の「バレンタインデー」の1ヵ月前で分かりやすいことから1月14日としたもの。
「マンリー」(manly)には、「男らしい、雄々しい(おおしい)、男性的な、勇気のある」などの意味がある。
この記念日は女性から男性に愛の告白をする2月14日の「バレンタインデー」よりも先に、「男性から女性に愛の告白をする日」「男性から女性へ心を込めた贈り物をする日」として制定された。記念日は2020年(令和2年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
男性は女性からの告白を待つのではなく、「男たるもの女性よりも先に想いを伝えるべきだ」という考えからこの記念日が誕生した。
また、「バレンタインデー」のような「義理チョコ、友チョコ、逆チョコ」などの広義における何気ない気持ちではなく、「心からの気持ちを込めた物を贈る日」にしたいとの思いが込められている。
j



ユキツバキ
ユキツバキ - 植物図鑑 - エバーグリーン (love-evergreen.com)
日本海側の多雪地に適応したヤブツバキ。
高さ1-2mにしかならず、積雪のため這うことが多い枝はしなやかで折れにくいのが特徴で、地表に接した部分で根を下ろし、独立の個体になります。
葉は薄質で鋸歯が鋭く、葉柄の上部の両側や背側に白毛があります。花は径7cmほどの一重咲きでヤブツバキと同様に花弁は5-6枚あります。ただし、花弁が広く開き薄質で、雄蕊筒が短く橙黄色-黄赤色に染まることが多いという違いがあり、果実は稀にしか成熟しないといいます。種子はヤブツバキより大型です。
ユキツバキ/ゆきつばき/雪椿
ユキツバキ(雪椿) - 庭木図鑑 植木ペディア (uekipedia.jp)
【ユキツバキとは】





東京都渋谷区道玄坂に本社を置き、国内最大級のペット写真共有SNS「パシャっとmyペット」を運営する株式会社サイバーエージェントが制定。
日付は犬と猫の鳴き声である「わん(1)」と「にゃん(2)」から毎月12日に。一般社団法人アニマル・ドネーションと共同で行う「パシャっとLOVEドネーション」プロジェクトの一環で、毎月12日には動物愛護関連団体への寄付を呼びかけるなどの活動を行う。
記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。その後、登録は終了しており、2019年(平成31年)4月時点で同協会の認定記念日としては確認できない。
他にも、銀座コージーコーナーが毎月12日を「ワンニャンの日」とし、オリジナルキャラクター「小犬と小ねこ」をモチーフにした、お買い上げプレゼントキャンペーンを行っていた。
ワンニャンミニタオル
画像元:マイナビニュース
また、上記の「パシャっとmyペット」は、2012年(平成24年)8月からサービスを提供していたが、2017年(平成29年)12月でサービスを終了している。
リンク:サイバーエージェント、銀座コージーコーナー















日付は「とんち」で有名な「一休さん」にちなんで「いっ(1)きゅう(9)」(一休)と読む語呂合わせから。
一休さん(一休宗純:いっきゅうそうじゅん、1394~1481年)は室町時代中期の臨済宗の僧。「屏風の虎退治」や「このはし渡るべからず」などが有名で、絵本や紙芝居の題材としてよく用いられる。
この日は「とんちの日」のほか、「とんち」を「クイズ」の意味にとらえて「クイズの日」とも呼ばれる。ただし、これらの記念日を制定した団体や目的については定かではない。
「とんち」(頓智/頓知)とは、「その場に応じて即座に出る知恵」「機知」という意味。「とんちのある人」「とんちで人を笑わせる」「とんちを働かす」などの使われ方がされる。
「クイズ」(quiz)とは、英語で「(何か)質問すること」「知識をテストすること」の意味であり、日本語では「知識を問う問題」の意味で使われる。
「クイズ」という言葉は完全に造語されたもので、もともと何の意味もなかった。アイルランドの首都ダブリンにおいて無意味な新語を作り、流行らせられるかという賭けをしたことをきっかけに広まったという説がある。
関連する記念日として、「ク(9)イ(1)ズ(2)」と読む語呂合わせから9月12日は「クイズの日」、「ハー(8)ト(10)」と読む語呂合わせから8月10日は「家族クイズで円満相続の日」となっている。



1935年(昭和10年)にエルヴィス・プレスリーが、1947年(昭和22年)にデヴィッド・ボウイが生まれた日。
エルヴィス・プレスリー(Elvis Presley、1935~1977年)は、アメリカのミュージシャンで、全世界の総レコード・カセット・CD等の売り上げは6億枚以上とされている。世界史上最も売れたソロアーティストであり、「キング・オブ・ロックンロール」と称される。
デヴィッド・ボウイ(David Bowie、1947~2016年)は、イングランド出身のミュージシャンで、「グラムロック」の先駆者として台頭し、ポピュラー音楽の分野で世界的名声を得る。役者の世界にも進出し、数々の受賞実績を持つマルチ・アーティストとして知られている。
この日とは別に、「ロ(6)ック(9)」と読む語呂合わせで6月9日も「ロックの日」となっている。
ロックンロール(Rock and Roll)は直訳すると揺れて(Rock)転がる(Roll)という意味である。また、古くから黒人スラングで「性交」の意味があり、1950年代はじめには「バカ騒ぎ」や「ダンス」という意味もあった。
1960年代後半には「ロック」という呼び方が一般化し、「ロックンロール」と呼ぶことは少なくなった。また、音楽ジャンルとして、ロック・ミュージック(Rock music)とも呼ばれる。
リンク:Wikipedia






【公式】ブラック・ジャック 第1話『オペの順番』

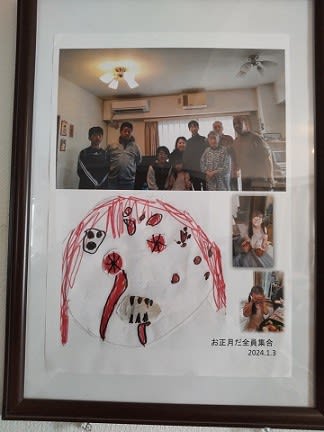







さまざまな社会問題の解決に取り組む公益財団法人・日本財団が制定。
日付は「い(1)ご(5)ん」(遺言)と読む語呂合わせと、この時期は正月で家族が集まる機会も多く、遺言について話し合えることから。相続のトラブルを少なくできる遺言書の作成の普及が目的。記念日は2016年(平成28年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。日常用語としては「ゆいごん」と読まれることが多く、法律用語としては「いごん」と読まれることが多い。
リンク:日本財団



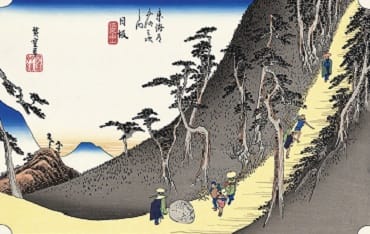




日付は「い(1)し(4)」(石)と読む語呂合わせから。
制定した団体や目的については定かではない。「ストーンズデー」ともされる。
石や岩は昔から神様の寄り付く場所として尊ばれてきた。この日に、お地蔵様や狛犬、墓石など、願いをかけた石に触れるとその願いが叶うという言い伝えがある。
広辞苑の説明によると、石というのは、岩より小さく、砂よりも大きい、鉱物質のかたまりのことである。何らかの原因で岩が割れて、いくらか小さくなったものである。特に小さな石は小石と呼ばれる。
石にまつわる伝説として「夜泣き石」が日本各地に存在する。その内容は各地で異なるが、夜に石から泣き声がする、または子どもの夜泣きが収まるなどの伝承がある。
また、神社では、通常の神様とは別に石が祀られていることも多い。古来から日本人は石や岩を霊的なものとして崇拝してきた歴史がある。

1938年(昭和13年)のこの日、女優の岡田嘉子(おかだ よしこ、1902~1992年)と日本共産党員で新協劇団の演出家であった杉本良吉(すぎもと りょうきち、1907~1939年)が、当時日本領土であった樺太の国境を越えてソ連へ亡命した。
ソ連で二人はスパイ容疑で国家警察に逮捕され、岡田は禁錮10年・強制収用所送りとなり、杉本は国家反逆罪で銃殺された。
戦後、岡田はモスクワ放送局(後のロシアの声)に入局。日本語放送のアナウンサーを務め、11歳下の日本人の同僚で、戦前の日活の人気俳優・滝口新太郎(たきぐち しんたろう、1913~1971年)と結婚し、穏やかに暮らした。また、現地の演劇学校に通い、演劇者として舞台に再び立っていた。
リンク:Wikipedia






1959年(昭和34年)のこの日、ソ連が世界初の月ロケット・ルーニク(ルナ)1号の打ち上げに成功した。
月から6500kmの所を通過して月面を観測した後、太陽の周囲を回る軌道に入り、地球と火星の間を公転する最初の「人工惑星」となった。
ソ連は1957年(昭和32年)のスプートニク1号打ち上げ以来、宇宙開発を積極的に進めていた。宇宙開発競争の一環として、月を目標にし、1958年(昭和33年)以降は月に探査機を着陸・衝突させることを目的とした「ルナ計画」を行っていた。
ルナ1号と同年の1959年9月12日に打ち上げられたルナ2号は月に命中し、世界で初めて月面に到達した人工物となった。同年10月4日に打ち上げられたルナ3号は世界で初めて月の裏側の撮影に成功、ルナ9号は1966年(昭和41年)2月3日に世界で初めて月面軟着陸に成功した。
スプートニク1号の打ち上げに成功した1957年10月4日に由来して、10月4日は「宇宙開発記念日」、10月4日~10日は「世界宇宙週間」となっている。
リンク:Wikipedia



元日(1月1日 国民の祝日) | 今日は何の日 | 雑学ネタ帳 (zatsuneta.com)
「元日(がんじつ)」は、年の最初の日。「国民の祝日」の一つ。1948年(昭和23年)に公布・施行された「祝日法」により制定。「年のはじめを祝う」ことを趣旨としている。
旧祝祭日では天皇が早朝に天地四方を拝する儀式「四方拝」にちなみ、「四方節」と呼ばれ四大節(紀元節、四方節、天長節、明治節)の一つだった。1月15日の「小正月(こしょうがつ)」に対して「大正月(おおしょうがつ)」という。
また、「元日」のことを「元旦(がんたん)」「元朝(がんちょう)」とも呼び、これらは「元日」と「元日の朝」の両方の意味を持つ。ただし、「旦」「朝」は「朝・夜明け」の意であるから、本来「元旦」「元朝」は「元日の朝」を指す言葉である。
日本各地で元日の1月1日から1月3日までの「三が日」、または門松がある期間「松の内」までを特に「お正月(おしょうがつ)」と呼ぶ。
元旦に門松で年神(歳神)様を迎え、井戸から邪気を除くとされる若水(わかみず)を汲んで神棚に供え、お雑煮やおせち料理を食べて新年を祝う。このような風習は江戸時代からあったものである。
また、正月行事として、初日の出を拝む、神社や寺院を参拝する初詣、新年の抱負をしたためる書き初め、七草粥を食べる、鏡開き、左義長(さぎちょう)などがある。