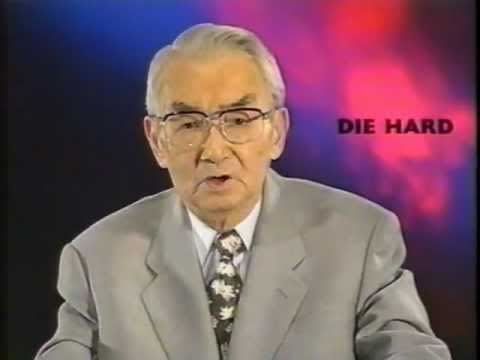後輩の女子に、どれだけ泥酔しようが挨拶だけはきちんとしている子が居て、
だから? 別れの挨拶は『東京物語』(53)の東山千栄子がいう「ありがと」のアクセントで「さようなら」という。
三重出身ゆえか、その独特なアクセントが癖になって、「さようなら」を聞くために早く呑み会をお開きしたくなる―とまでいうと嘘になるが、とにかくそんな彼女の「さようなら」が好きなのだった。
そういえば「さようなら」なんて、小学生以来いっていないことばかも・・・などと思う。
「先生さようなら、みなさんさようなら」というやつだ。
中学生になると、だいたいが「じゃあね」「ばいばい」であった。
「じゃあね」を多用したのはたぶん、おニャン子「中島美春」の影響だろう。
現在は、年下・年上を無関係にして「どうも」で統一している。
この「どうも」は出会いにも別れにも使える、たいへん便利なことばである。多用し過ぎると「ちょっとだけ」軽薄そうに捉えられるが、実際に軽薄なので気にしないことにする。
「さようなら」で想起する有名人は三人居る。
「サヨナラダケガ人生ダ」のことばを愛した映画監督、川島雄三。
映画『サヨナラ』(57)でオスカーを取ったナンシー梅木。
そして「サヨナラ、サヨナラ、…サヨナラ」で有名な淀川さんだ。
自分が淀川さんを尊敬する理由は、映画愛や名調子とかではなく、その驚異的な記憶力、これに尽きる。
幼少のころに観た映画を「きのう触れてきた」ように語られたらもう、無条件降伏するしかないでしょうよ。
主題を表現し易いからだろう、
「さようなら」というのは音楽や小説、映画のタイトルに多用されていて、先日も「さようなら」を冠したふたつの映画に出会った。
『さよならドビュッシー』は、イチオシの橋本愛が主演した「音楽とミステリをからめた」青春映画である。
「このミス」と略されることの多い「このミステリーがすごい!」大賞受賞の原作を映画化したもので、利重剛が久し振りにメガホンを持ったことでも話題になっている。
過剰な説明的台詞や描写が気にはなるが、そこらへんは愛(呼び捨て)の魅力で相殺。
結果的に及第点ぎりぎりかな、、、という出来。
愛(呼び捨て)は17歳だが、インタビューで「(魅力とされている)自分の目は、好きでも嫌いでもない。でも、武器であることは分かっています」と答えるほど、自分というものをきちんと捉えている大人っぽさがある。
いいなぁ、あの目で見つめられて「死ね」とかいわれたら、ほんとうに死んでやろうかな・・・と、ちょっとだけ思ったり。
『みなさん、さようなら』も原作ありの映画だが、映画でしか表現出来ないことをやっていて、1月の収穫といえる会心作となっている。
『ピアノ・レッスン』(93)のエイダが「喋らない」と誓ったように、
『ブリキの太鼓』(79)の少年が「成長しない」と誓ったように、
『みなさん、さようなら』の主人公(濱田岳)は「団地から出ないで一生を過ごす」ことを決める。
濱田岳は13歳から30歳まで好演しているが、この映画の成功はたぶん、
団地とその周辺の移り変わりを描くことによって、日本の近代史が浮かび上がってくる構造になっている―そこにあるのだと思う。
もちろん筋もしっかりしていて、基本は喜劇調なのに、最後のほう「ほろり」とさせる創りは巧いのだが、
自分が団地族であることと無関係ではないのだろう、寂れていくいっぽうの団地というものを主人公とした都市論なんじゃないか・・・そんな風に捉えて感心したのであった。
ただひとつ。
倉科カナのような女の子なんて、隣人には居ないよ・・・とは思ったんだけれど。
彼女みたいな子が居たら、自分だって団地から一歩も外に出なくなるよ。
…………………………………………
本館『「はったり」で、いこうぜ!!』
前ブログのコラムを完全保存『macky’s hole』
…………………………………………
明日のコラムは・・・
『悪趣味映画館』
だから? 別れの挨拶は『東京物語』(53)の東山千栄子がいう「ありがと」のアクセントで「さようなら」という。
三重出身ゆえか、その独特なアクセントが癖になって、「さようなら」を聞くために早く呑み会をお開きしたくなる―とまでいうと嘘になるが、とにかくそんな彼女の「さようなら」が好きなのだった。
そういえば「さようなら」なんて、小学生以来いっていないことばかも・・・などと思う。
「先生さようなら、みなさんさようなら」というやつだ。
中学生になると、だいたいが「じゃあね」「ばいばい」であった。
「じゃあね」を多用したのはたぶん、おニャン子「中島美春」の影響だろう。
現在は、年下・年上を無関係にして「どうも」で統一している。
この「どうも」は出会いにも別れにも使える、たいへん便利なことばである。多用し過ぎると「ちょっとだけ」軽薄そうに捉えられるが、実際に軽薄なので気にしないことにする。
「さようなら」で想起する有名人は三人居る。
「サヨナラダケガ人生ダ」のことばを愛した映画監督、川島雄三。
映画『サヨナラ』(57)でオスカーを取ったナンシー梅木。
そして「サヨナラ、サヨナラ、…サヨナラ」で有名な淀川さんだ。
自分が淀川さんを尊敬する理由は、映画愛や名調子とかではなく、その驚異的な記憶力、これに尽きる。
幼少のころに観た映画を「きのう触れてきた」ように語られたらもう、無条件降伏するしかないでしょうよ。
主題を表現し易いからだろう、
「さようなら」というのは音楽や小説、映画のタイトルに多用されていて、先日も「さようなら」を冠したふたつの映画に出会った。
『さよならドビュッシー』は、イチオシの橋本愛が主演した「音楽とミステリをからめた」青春映画である。
「このミス」と略されることの多い「このミステリーがすごい!」大賞受賞の原作を映画化したもので、利重剛が久し振りにメガホンを持ったことでも話題になっている。
過剰な説明的台詞や描写が気にはなるが、そこらへんは愛(呼び捨て)の魅力で相殺。
結果的に及第点ぎりぎりかな、、、という出来。
愛(呼び捨て)は17歳だが、インタビューで「(魅力とされている)自分の目は、好きでも嫌いでもない。でも、武器であることは分かっています」と答えるほど、自分というものをきちんと捉えている大人っぽさがある。
いいなぁ、あの目で見つめられて「死ね」とかいわれたら、ほんとうに死んでやろうかな・・・と、ちょっとだけ思ったり。
『みなさん、さようなら』も原作ありの映画だが、映画でしか表現出来ないことをやっていて、1月の収穫といえる会心作となっている。
『ピアノ・レッスン』(93)のエイダが「喋らない」と誓ったように、
『ブリキの太鼓』(79)の少年が「成長しない」と誓ったように、
『みなさん、さようなら』の主人公(濱田岳)は「団地から出ないで一生を過ごす」ことを決める。
濱田岳は13歳から30歳まで好演しているが、この映画の成功はたぶん、
団地とその周辺の移り変わりを描くことによって、日本の近代史が浮かび上がってくる構造になっている―そこにあるのだと思う。
もちろん筋もしっかりしていて、基本は喜劇調なのに、最後のほう「ほろり」とさせる創りは巧いのだが、
自分が団地族であることと無関係ではないのだろう、寂れていくいっぽうの団地というものを主人公とした都市論なんじゃないか・・・そんな風に捉えて感心したのであった。
ただひとつ。
倉科カナのような女の子なんて、隣人には居ないよ・・・とは思ったんだけれど。
彼女みたいな子が居たら、自分だって団地から一歩も外に出なくなるよ。
…………………………………………
本館『「はったり」で、いこうぜ!!』
前ブログのコラムを完全保存『macky’s hole』
…………………………………………
明日のコラムは・・・
『悪趣味映画館』