2015年1月6日に発行された日本経済新聞紙の夕刊一面の速報記事「トヨタ無償公開 燃料電池車の全特許5680件」を拝読しました。
トヨタ自動車は、2015年1月6日(米国時間)から米国ラスベガス市で始まる「2015 International CES」の前日の1月5日(米国時間)に当地で記者発表会を開催し、燃料電池車(FCV)関連の特許を無償提供すると公表したという記事内容です。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「トヨタが燃料電池車の特許を無償開放へ」として掲載しています。
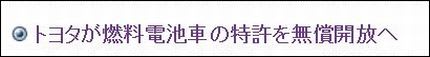
その記者発表会に登壇した米Toyota Motor Sales(TMS), U.S.A.社のSenior Vice President(上級副社長)を務めるBob Carterさんは「今日は自動車業界にとってターニングポイントになる」と強調したそうです。
トヨタ自動車は、同社が保有する燃料電池車に関連する特許の実施権を無償で提供すると発表しました。無償提供の対象となるのは、トヨタ自動車が単独で保有する世界中で約5680件の特許(審査継続中を含む)です(トヨタの子会社・関連会社が保有する特許の実施権は対象外です)。トヨタ自動車もずいぶん思い切った戦略・戦術をとるものです。
トヨタ自動車は「これからの100年は水素燃料の時代になる」(Carterさん)と説明します。現行のガソリン・軽油を燃料とする内燃機関(レシプロエンジン)搭載車から主役交代を進めさせるためには「燃料電池車の導入初期段階には、その普及を最優先し、開発・市場導入を進める他の自動車メーカーや水素ステーション整備を進めるエネルギー(ガス・石油・化学)会社などとの協調した取り組みが重要」と判断し、「今回の特許実施権を開放する決断に至った」そうです。
燃料電池システム関連の特許は2020年末までと期限があります。その特許実施権を無償提供する対象としては、燃料電池スタック(約1970件)や高圧水素タンク(約290件)、燃料電池システム制御(約3350件)といった、燃料電池車の開発・生産の根幹となる燃料電池システム関連の特許です。これらの特許を使用して燃料電池車の製造・販売をする場合は、2020年末までを期限として特許実施権を無償で提供します。この期限内は、トヨタ自動車は他社に追いつかれないと判断したようです。
一見、トヨタ自動車は太っ腹の決断のように感じますが、トヨタ自動車が発売する燃料電池車「MIRAI」は、水素ステーションが国内で不足するために、それほど急に台数が増えるわけではありません。欧米などの先進国では、水素社会向けのインフラストラクチャー構築はこれからです。
このために、トヨタ自動車は水素の供給や製造といった水素ステーション関連の特許(約70件)に関しては、水素ステーションの早期普及を図るため、水素ステーションの設置・運営を行う場合の特許実施権を、期間を限定することなく無償とする方針だそうです。
日欧米などの先進国を中心にトヨタ自動車が燃料電池車をある程度以上の台数で販売し普及させて事業として安定化させるためには、日欧米で水素社会のインフラづくりを優先させた方が早道と判断したようです。
こうした自社が持つ特許の実施権を無料で開放する手法は、米国IBMが「エコ・パテントコモン」として、2008年1月に発表したやり方です。この場合は、IBMはノキア、ピッツニーボウズ、ソニーと協力して、環境保全に貢献する特許を開放するという"パテントコモン"の概念を公表しました。環境保全のために既存技術の活用を容易にし、環境保全につながる製品開発を促進することを目的としています。
今回のトヨタ自動車の特許開放策は、まさに“オープン・クローズド戦略”です。協力者が必要な分野では、オープン戦略をとる一方、将来、ライバルが出現しそうな分野はクローズ戦略をとります。日本の大手企業がこうしたオープン・クローズド戦略を大々的に実施するのは珍しいことです。
具体的な特許権実施に際しては、当該企業はトヨタ自動車に申し込み「具体的な実施条件などについて個別協議の上で契約書を締結する」との予定です。
さすがに事実上の自動車の世界トップ企業の戦略です。
トヨタ自動車は、2015年1月6日(米国時間)から米国ラスベガス市で始まる「2015 International CES」の前日の1月5日(米国時間)に当地で記者発表会を開催し、燃料電池車(FCV)関連の特許を無償提供すると公表したという記事内容です。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「トヨタが燃料電池車の特許を無償開放へ」として掲載しています。
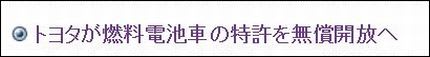
その記者発表会に登壇した米Toyota Motor Sales(TMS), U.S.A.社のSenior Vice President(上級副社長)を務めるBob Carterさんは「今日は自動車業界にとってターニングポイントになる」と強調したそうです。
トヨタ自動車は、同社が保有する燃料電池車に関連する特許の実施権を無償で提供すると発表しました。無償提供の対象となるのは、トヨタ自動車が単独で保有する世界中で約5680件の特許(審査継続中を含む)です(トヨタの子会社・関連会社が保有する特許の実施権は対象外です)。トヨタ自動車もずいぶん思い切った戦略・戦術をとるものです。
トヨタ自動車は「これからの100年は水素燃料の時代になる」(Carterさん)と説明します。現行のガソリン・軽油を燃料とする内燃機関(レシプロエンジン)搭載車から主役交代を進めさせるためには「燃料電池車の導入初期段階には、その普及を最優先し、開発・市場導入を進める他の自動車メーカーや水素ステーション整備を進めるエネルギー(ガス・石油・化学)会社などとの協調した取り組みが重要」と判断し、「今回の特許実施権を開放する決断に至った」そうです。
燃料電池システム関連の特許は2020年末までと期限があります。その特許実施権を無償提供する対象としては、燃料電池スタック(約1970件)や高圧水素タンク(約290件)、燃料電池システム制御(約3350件)といった、燃料電池車の開発・生産の根幹となる燃料電池システム関連の特許です。これらの特許を使用して燃料電池車の製造・販売をする場合は、2020年末までを期限として特許実施権を無償で提供します。この期限内は、トヨタ自動車は他社に追いつかれないと判断したようです。
一見、トヨタ自動車は太っ腹の決断のように感じますが、トヨタ自動車が発売する燃料電池車「MIRAI」は、水素ステーションが国内で不足するために、それほど急に台数が増えるわけではありません。欧米などの先進国では、水素社会向けのインフラストラクチャー構築はこれからです。
このために、トヨタ自動車は水素の供給や製造といった水素ステーション関連の特許(約70件)に関しては、水素ステーションの早期普及を図るため、水素ステーションの設置・運営を行う場合の特許実施権を、期間を限定することなく無償とする方針だそうです。
日欧米などの先進国を中心にトヨタ自動車が燃料電池車をある程度以上の台数で販売し普及させて事業として安定化させるためには、日欧米で水素社会のインフラづくりを優先させた方が早道と判断したようです。
こうした自社が持つ特許の実施権を無料で開放する手法は、米国IBMが「エコ・パテントコモン」として、2008年1月に発表したやり方です。この場合は、IBMはノキア、ピッツニーボウズ、ソニーと協力して、環境保全に貢献する特許を開放するという"パテントコモン"の概念を公表しました。環境保全のために既存技術の活用を容易にし、環境保全につながる製品開発を促進することを目的としています。
今回のトヨタ自動車の特許開放策は、まさに“オープン・クローズド戦略”です。協力者が必要な分野では、オープン戦略をとる一方、将来、ライバルが出現しそうな分野はクローズ戦略をとります。日本の大手企業がこうしたオープン・クローズド戦略を大々的に実施するのは珍しいことです。
具体的な特許権実施に際しては、当該企業はトヨタ自動車に申し込み「具体的な実施条件などについて個別協議の上で契約書を締結する」との予定です。
さすがに事実上の自動車の世界トップ企業の戦略です。









