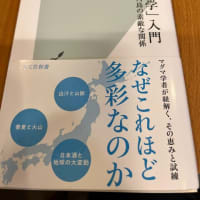赤福が営業再開するというニュースの後、中国産の冷凍食品中毒事件が報じられました。赤福も、白い恋人も、船場吉兆も、静岡から離れたところの非日常の食べ物、という感じでしたが、今回は、うちの冷凍庫の中にもあるかも、というリアルな危機感を持ちました。気候に変動される、日持ちのしない食糧を生産・流通させるビジネスというのは、いろいろな意味でリスクの多い事業であり、その分、経営者のモラルが問われるのだと改めて感じます。
昨年暮れ、老舗ファミリー企業経営の研究の第一人者・後藤俊夫先生(光産業創成大学院大学教授)のビジネス講座を受講したとき、グループミーティングで8代続く藤枝の製茶業・松田真彦さんとご一緒し、赤福問題についてレポートを書いて発表しました。他のグループでは銀行や信金等のアナリストたちが専門的な分析や解釈を理路整然と発表する中、うちのグループは老舗経営者や消費者の率直な意見を素直にぶつけ、受講者に多少の違和感を与えたようですが、私自身、酒造業をはじめ、地域のさまざまな老舗経営者の声を伝える使命を強く自覚しました。
赤福再開の報を受け、今日は、松田さんのそのときのレポートを紹介しようと思います。掲載を快諾してくださった松田さん、ありがとうございました!
経営者の立場からの観察/松田真彦 (製茶問屋 「真茶園」8代目/㈱松田商店 代表取締役)
赤福の一件で、経営者として感ずるのは、日本中の菓子業や食品に従事している人たちへの影響です。まじめに正しく菓子や食品を作っているファミリー会社がかなり迷惑を被っていること。赤福だけでなく、吉兆にしても、石屋、不二家等その責任は計り知れないものでしょう。ここに、彼らの企業としての社会的な責任の無さを痛感します。世間に注目される企業に成長したならば襟を正さなければならない。「自分たちの努力で勝ち抜いてきた!」という傲慢さを感じます。
もう一つの観点として、ファミリービジネス(家業)への正しい認識を損なわれることを懸念します。様々な意見がある中で、「家業だから、閉鎖的な社風が災いして隠蔽になった」とか「世襲制が支配した弊害」など言われております。会社でも人間でも、長所もあれば短所もあり、その両者は明確な線引きをするには無理があり「長所は短所なり。短所は長所なり」という寛容な視点が無いことを懸念します。
世に出ている経営書物やコンサルタントにしても「家業から企業へ」と言われています。つまり「家業ではレベルが低く、いち早く企業に転身しなさい」というフィードバックでしょう。さらには、「上場を目指せ!」などと付け加えられます。むろん、これも一経営論として正しいのですが、その逆(つまり家業のままでいる経営スタイル)を批判することが正しいという風潮は、間違いであると思っています。家業スタイルもまた、日本の中小企業において市民権が立派に存在するものだと確信します。また、日本の95%を占める中小零細企業(=家業)こそが日本を支えているという誇りもあります。
例えば、商店街にある夫婦で営んでいる法人でもない個人店で行列が出来ている店もあります。かたや、粉飾決算を平気でしている上場企業やセクショナリズムが横行している大企業。株をゲームのように扱い食い物にしようとする狩猟的な大企業。このような上場大企業と行列ができている夫婦店と比べる物差しにより優劣がありますが、事業で最も大切である「お客様」という観点からみて、いずれが立派であるか?
大きな組織(企業)なると、諸事にレベルが高くなる価値や長所がある反面、組織が優先で、やりたい仕事もなかなかできないこともあるでしょう。また、お客様を優先させたいという個人の思いを優先させることができなく、組織優先の場合もあるでしょう。
その点、家業というのは、組織という組織もない短所が長所であり、その場その場で「お客様のために」という仕事ができます。お客様もそのような家業の良さを買う人もたくさん存在します。有名な企業ブランドを買いたいお客様もいれば、一方では企業のような画一的なサービスは望まずに自分を大切にしてくれる家業の方が良いというお客様もいます。
自分たちの作りたい商品を作れて、それをお客様に喜んでいただけて、そこに働く社員がやりがいもって活き活きと仕事ができ、社風がよく、業績が良く社員に還元できるのであれば、企業であろうと家業であろうと問わないと思っています。
所有と経営が同じである家業は、この理想的な経営スタイルが戦略によっては可能です。家業はこれを目指すべきではないでしょうか。