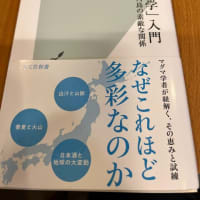ゆうべから年賀状の宛名書きを始めました。絵と文面は手描きで版下を作って印刷するので、宛名だけでも直筆で書きます。パソコン原稿を書くことが多い昨今、年賀状だけが、きちんと字を書く唯一の機会になってしまったようです。面倒でも、せめて名前と住所だけでも直接書き込むことで、その人とのつながりを再確認する…年賀状を出す意義は、そんなところにもあるような気がします。とくに、鞆の石井さんから精魂こもった直筆の手紙をいただいた直後だけに、手書きが訴えるチカラというものを肌で感じています。
24日のブログで初亀の『瓢月』クラシックボトルの紹介を書くにあたって、酒銘を揮毫された書家の大橋陽山さんといろいろお話しました。
酒造や書道といった伝統の世界で、グッドデザイン賞を獲るような表現を活かすことに理解ある人材は、実はあまり多くいません。とくに静岡の酒は、パッケージや宣伝よりも品質重視で発展し、蔵元にも小売店にも、どこか、「売り方や宣伝の仕方を考えるのは、品質に自信がないから」と考えるフシがあるように思えます。
いい酒を造り、放っておいても注文が来れば、それはそれで理想でしょう。しかし、大橋さんのように幅広いフィールドで活躍する方から見れば、「静岡で、いくらいい酒を造っても、知らない人のほうが圧倒的に多い」わけで、「より多くの人が、静岡の酒にアクセスできる機会を作るのに、デザインやパッケージで目を惹かせる作業は無駄ではないはず」です。
品質を磨こうと必死に努力する静岡の蔵元を見続けてきた私としては、パッケージにかける経費があったらいい米を買いたい、機械を新しくしたい、という声も理解できるのですが、市場が激変する今、先々酒造りを続けていくため、新たな試みに踏み出す時期に来ているのでは、という思いもしています。
大橋さんの周辺で、『瓢月』をデザインが面白いと言って買った人の多くが、「酒もすごい」と驚いているそうです。老舗というのは、そうやって新しいファンを切り拓く革新的な試みを重ねてきたからこそ、永く息づいているのでしょう。
大橋さんとの対話で、伝統産業の広報のあり方について、ツラツラと考えているうちに、
 大橋さんから、現在、東京都写真美術館で開催中の『文学の触覚』という展示会に出品している作品と、大橋さんが川崎の工業地帯の産業廃棄物処理工場で公開している『野書』の写真が届きました。人間が
大橋さんから、現在、東京都写真美術館で開催中の『文学の触覚』という展示会に出品している作品と、大橋さんが川崎の工業地帯の産業廃棄物処理工場で公開している『野書』の写真が届きました。人間が 全精力を傾けて表現する文字のチカラを、まざまざと感じました。
全精力を傾けて表現する文字のチカラを、まざまざと感じました。
酒でも、文 章でも、造り手・書き手の精力が込められているか、流れ作業・こなし作業で済ませていないか、それは当事者が一番わかっていることで、後から「あれは手を抜いたもの」と言い訳も後悔もしないよう、最善を尽くし続けたいと思います。
章でも、造り手・書き手の精力が込められているか、流れ作業・こなし作業で済ませていないか、それは当事者が一番わかっていることで、後から「あれは手を抜いたもの」と言い訳も後悔もしないよう、最善を尽くし続けたいと思います。
たかが年賀状、されど年賀状、です。