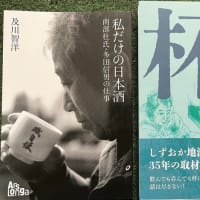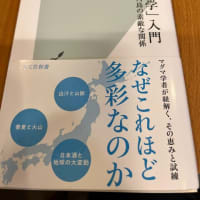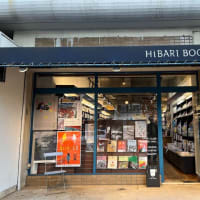29日開催のしずおか地酒サロン~地酒は地域の元気のミナモト!は昨日(26日)受付を締め切らせてもらいました。酒蔵見学でも美酒美食探訪でもなく、著名人の講演会でもないただの座談会だし、8月月末の土曜夕方、しかも選挙前のゴタゴタした日の開催なので、いつものサロン(20人前後)ほど集まらないかなぁと思っていましたが、フタを開けてみたらその倍の参加希望をいただき、嬉し限りです。アンケートも、本当に多くの方に丁寧にお答えいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
 さてさて、11日の駿河湾地震で、日本国中に強く印象付けたのが、静岡県は日本の交通・物流の大動脈が通っていて、これが寸断されたらとんでもないことになる!ということでしたね。静岡県って、改めて地図を見ると、県全体の面積の中で平野部の割合が小さくて、海と山に囲まれていて、大動脈が通る環境として決して恵まれているわけじゃないんです。
さてさて、11日の駿河湾地震で、日本国中に強く印象付けたのが、静岡県は日本の交通・物流の大動脈が通っていて、これが寸断されたらとんでもないことになる!ということでしたね。静岡県って、改めて地図を見ると、県全体の面積の中で平野部の割合が小さくて、海と山に囲まれていて、大動脈が通る環境として決して恵まれているわけじゃないんです。
先週から今週にかけて、時間を見つけては東海道の「難所」の写真を撮りに行っています。先のブログでも紹介の、北村欽哉先生にご協力いただいた朝鮮通信使ゆかりの史跡探訪の記事を書くためです。クライアントの要望は「静岡県を象徴する歴史スポットの紹介」なので、朝鮮通信使のみならず、広く静岡県史を特徴的に物語るスポットはないかと考え、目をつけたのが、ずばり「東海道」。浜名湖、大井川、薩埵峠、箱根といった「難所」は、朝鮮通信使の1000人規模の行列を通すために大々的な整備をしたのです。
 水の難所―浜名湖や大井川は、徳川幕府は防衛上、橋を造らせないという方針だったので、船やみこしで一行を運び、激しい水流のところは人間の壁を作って流れをせき止めるなど、大変な人海戦術で渡したのでした。
水の難所―浜名湖や大井川は、徳川幕府は防衛上、橋を造らせないという方針だったので、船やみこしで一行を運び、激しい水流のところは人間の壁を作って流れをせき止めるなど、大変な人海戦術で渡したのでした。
世界一長い木の橋として有名な、大井川の「蓬莱橋」は、明治初期、牧之原の茶畑開墾工事のために架けられた橋なんですね。
山の難所―薩埵峠の道は朝鮮通信使のために造られ、箱根の峠道も通信使のために整備されました。箱根の道は天気が悪いとぬかるみになりやすいので、箱根竹とよばれる自生の竹の葉を編んで道に敷き詰め、後に石畳化しました。通信使の日記使行録に「箱根道に数十里、編んだ竹が敷いてあって、何と人力を費やすことか驚いた」という記述が残っています。
 もともと竹道は、戦国時代に伊豆や相模を統治していた北条氏が手がけていたもので、毎年、竹1万7~8千本、人足3千人を動員し、ぬかるみ対策として整備していたそうです。人足は奥伊豆の1万9千余りの村々に割り当てられていました。
もともと竹道は、戦国時代に伊豆や相模を統治していた北条氏が手がけていたもので、毎年、竹1万7~8千本、人足3千人を動員し、ぬかるみ対策として整備していたそうです。人足は奥伊豆の1万9千余りの村々に割り当てられていました。
江戸幕府でもこの整備事業を継承し、1680年に1400両かけて石畳化。奥伊豆の村々は年に100両ずつ納め、幕府はこれを元金として国中に貸し付け、その利息によって石道の維持を計ったそうです。
しかし実際のところ、箱根峠が通りやすくなっちゃうと江戸の防衛に支障があるわけで、石道の修理はほとんど放ったらかしで、朝鮮通信使の来日、幕末の和宮様下向(実際は中山道を通った)、将軍家茂の上洛(実際は海路を使った)の前だけあわてて修理したそうです。・・・ったく、ひどい交通政策ですよね!!
箱根の峠道は、地元の篤志家の人々の手で、すでに9世紀ごろから旅人の避難所や救護所みたいなものが設けられていました。民間は民間で助け合うしかないんですね、やっぱり。
歴史の教科書では、とかく国と国の戦争や、国家事業レベルの話しか取り上げられませんが、その舞台を支えた多くの庶民の血と汗の存在と、交通の大動脈をどうやって整備するかが、国づくりに大きくかかわることを、改めて実感します。
一昨日(25日)は薩埵峠で、昨日(26日)は箱根峠で、そんなことをつらつらと考えました。東海大地震で東名も国1も新幹線もJRもマヒしたときは、・・・お上に頼らず、民間は民間でやれることをやるっきゃないか。