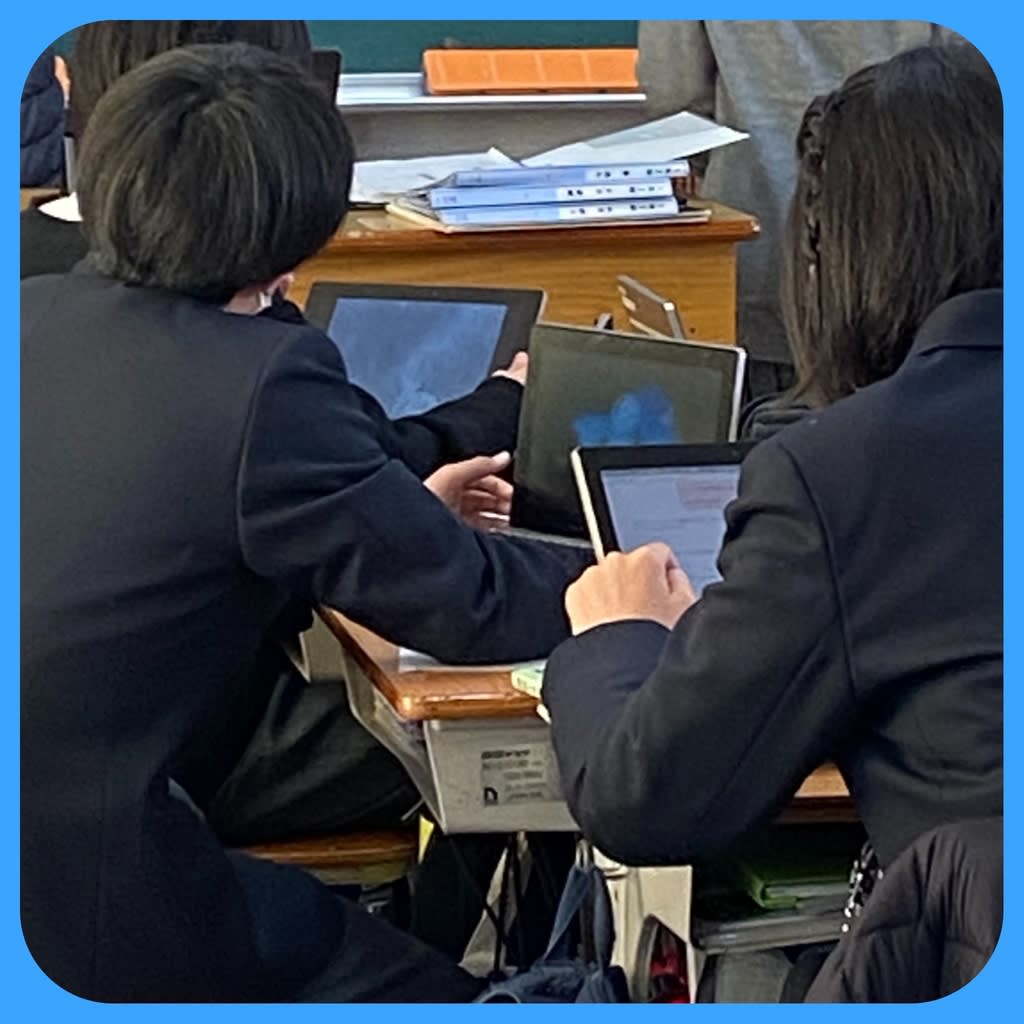文科省は全国の小中学校を対象に、学級担任をしている教員のうち、どの程度が「教諭」で、どの程度が「講師」(常勤講師)であるを調査しました。(2021年度の5月1日時点)
小学校は237099人(88.4%)が教諭で、30826人(11.5%)が講師でした。
中学校は101750人(90.7%)が教諭で、10402人(9.3%)が講師でした。
この結果を取り上げ、ある大手新聞は、「学級担任の1割が『臨時教員』」という見出しをつけ、「非正規教員が学級を担任している」というニュアンスで問題視するような記事を載せていました。(2月3日朝刊)
その記事によると、教諭も「臨時教員」も教員免許は持っているが、教諭は自治体の実施する教員採用試験に合格しており、「臨時教員」は合格していない人であるという説明がついています。
だから、非正規教員が1割も学級担任を務めているのは問題であるというタッチの記事の書き方になっていました。
しかし、現場の実態でいうと、そもそも正規・非正規という用語は学校や教員間では使われていません。臨時教員という言葉も使われていません。
教職員間で使われているのは、教諭、講師(常勤講師と非常勤講師)という呼称であり、児童生徒・保護者にとっては、すべての人が「先生」です。
臨時なら学級担任をするべきではないのでしょうか。
現場では、教諭であっても校内での役職・役割、本人の体調の問題、家庭の事情、授業の持ち時間数等の関係で学級担任ができない人がいます。
常勤講師であっても、教育的情熱を高くもち、優れた教育実践、学級経営をできる人がいます。
かつ常勤講師は、教諭と同じく月~金まで出勤し、勤務時間も同じで、教員定数(この児童生徒数の学校規模なら教員数は○人というきまった数)の中に含まれます。
学校は、その定数配置を受け、学級数に見合うだけの学級担任を教諭と常勤講師の中から校内人事で配置するのです。
そのあたりの事情を斟酌せず、民間と同じように正規・非正規、臨時などの区分分けを教員にも当てはめ問題視するのは、現場では違和感を覚えるのです。