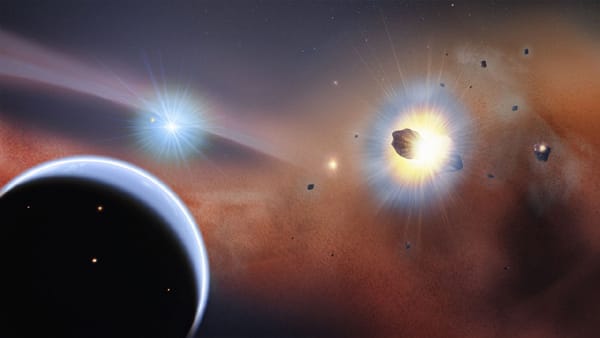レーダー地球観測衛星“だいち2号”を搭載したH-IIロケット24号機が、
5月24日に打ち上げられることが決まりました。
H-IIAロケット202型で、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられることになります。
“だいち2号”は災害時の観測や地図の作成、海洋や森林の観測などを目的とした衛星です。
レーダーの技術を使うので、昼夜や天候の影響を受けることなく観測できるんですねー
名前からも分かるように、2006年に打ち上げられ、2011年に運用を終えた“だいち”の後継機。
“だいち”が光学カメラ、合成開口レーダーを搭載しているのに対し、
“だいち2号”ではフェーズドアレイ式バンド合成開口レーダーを、さらに高解像度化して搭載したレーダー観測衛星になります。
1~3メートルの高解像度での観測が可能になり、観測範囲も“だいち”の870キロから2320キロまで広がっているんですねー
なので、より迅速に災害対応が可能になると期待されています。
打ち上げ時の質量は約2トン、最低5年間、長ければ7年間に渡って運用される予定です。
現在、衛星はすでに種子島宇宙センターに運び込まれていて、組立と検査が続けられています。
また今回も、ロケットの余剰能力を活かし、4機の小型副衛星が搭載されるほか、
現在開発が進められているH-IIAロケットの高度化に向けた、技術データの取得も行われるようです。
5月24日に打ち上げられることが決まりました。
H-IIAロケット202型で、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられることになります。
“だいち2号”は災害時の観測や地図の作成、海洋や森林の観測などを目的とした衛星です。
レーダーの技術を使うので、昼夜や天候の影響を受けることなく観測できるんですねー
名前からも分かるように、2006年に打ち上げられ、2011年に運用を終えた“だいち”の後継機。
“だいち”が光学カメラ、合成開口レーダーを搭載しているのに対し、
“だいち2号”ではフェーズドアレイ式バンド合成開口レーダーを、さらに高解像度化して搭載したレーダー観測衛星になります。
1~3メートルの高解像度での観測が可能になり、観測範囲も“だいち”の870キロから2320キロまで広がっているんですねー
なので、より迅速に災害対応が可能になると期待されています。
打ち上げ時の質量は約2トン、最低5年間、長ければ7年間に渡って運用される予定です。
現在、衛星はすでに種子島宇宙センターに運び込まれていて、組立と検査が続けられています。
また今回も、ロケットの余剰能力を活かし、4機の小型副衛星が搭載されるほか、
現在開発が進められているH-IIAロケットの高度化に向けた、技術データの取得も行われるようです。