昨夜のNHKの「クローズアップ現代」で中国の清華大学では政府主導のもと、企業との強力な連携に伴う膨大な資金力を用いて、優秀な学生を集め、最先端の機器を導入し、それに惹かれて、また世界のトップ企業が参入→また資金が増えると言う戦略を紹介していた。
そしてその結果大学の周辺に世界の企業が研究所を設置し、技術研究センターの様相を呈するまでになった。
そして日本人として見過ごせないのは、世界一、二を争うトヨタ自動車、産業機械ではトップクラスの日立と言う日本の先端企業までが同大学の近くに研究所を設立していることだ。
特にトヨタは経団連で会長を勤めた奥田碩さんや、現在の副会長の張富士夫さんなど日本の政治にも大きな発言力を持つ人がいるのに、そして日本は誰でも言う技術立国を国是としているのに、日本の強力なライバルとなった中国の技術向上に手を貸しているのだ。
私はトヨタや日立も日本の科学技術の進展に色々な面で寄与していると思うので、彼らを批判しようとは思わない。
私の言いたいのは日本の大学を含む学制のあり方だ。
つまり今の大学は企業のニーズに応えているのか。
同番組の応義大学塾長の安西祐一郎さんは中国の清華大学は殆どが応用技術の研究なのに対して、日本の大学が基礎研究がどちらかと言えば主力になっていると説明していた。
彼の説明によれば、トヨタも日立も日本の大学との応用研究の協力より、中国の大学との協力を選んだのだろうか。
日本の大学は日本企業のニーズに完全に応えているのだろうか。
日本は1949年前後に大きな学制改革を行った。
国公立で言えば、旧帝大の他に、旧制の高等学校、工業専門学校の殆ど全てが、大学になり、所謂、駅弁大学と揶揄された。
そして旧制の高等学校から大学になった多くの大学も工学部を設置した。
中国の台頭以前は技術日本として、世界第二位の経済大国になり国民全てが中流意識を持つと言う世界から羨まれ妬まれる国となった。
その点では大学も企業のニーズに応える卒業生を提供していたのだろう。
世の中は変わった。
超低賃金と膨大な人員を持つ中国の台頭による日本の相対的な競争力の低下だ。
それに伴う歳入の減少と、それまでの経済の拡大が影響に続くと考えたばら蒔き政策による800兆にもなる国の借金の負担の増加で、先進国で最低レベルまで教育費を削減された。
それに加えて、日本の少子高齢化の影響の拡大だ。
今は大学全入時代と言われている。
だから大学に入るより早く世に出た方が本人のためにも国のためにもなる生徒も希望すれば皆大学に入れる。
それに加えて厳しい受験戦争が緩和されて、生徒が余り勉強しなくても推薦やOA入試で合格できるようになった。
当然のように大学のレベルが低下した。
文芸春秋の4月号によると、世界大学ランキングで百位以内に入っているのは前述の学力低下の理由とは縁のない大学でさえ東京大学、京都大学、大阪大学、東京工大の国立4校に過ぎないそうだ。
そして世界的に理工離れが進む中で米国の大学だけは理数系に強い優秀な人材が留学してくるので、世界トップの座が譲ることはないだろうと書いている。
これを見ても例え中国でも、厳しい受験戦争をくぐり抜けたやる気満々の学生、豊富な資金をもつ大学と共同研究したくなる企業の気持ちも判るきがする。
[私の提案]
1.小学校から大学までの教育の重点の見直し
詳細は下記に資料を見て頂きたいが、「ゆとり教育」の基本的な考え方である、「自ら学び、自ら考え自ら課題を解決する力(以下「考える力]と略称する)の精神を活かし、それと今までの欠けていた躾け教育を取り入れて、今までの考える力の教育は小学校、中学校で終わり、高校教育、大学入試では詰め込みの試験から次の様に変更してはどうだろうか。
小学校では、躾け、詰め込み(80)、考える力(20)→中学校 躾け、詰め込み(70)、考える力(30)→高校(通常の進学校) 詰め込み(60)、考える力(40)と児童、生徒の発育に応じて、教育の重点を移して行き、理数系の大学入試では次のように、詰め込み(60~40)、考える力(40~60)+共通一次試験(必須)とすれば良いと思う。
参照: 教育改革はまず大学入試から
2.大学への補助金を集中的に使う
(1)共通一次試験の特定科目で一定の成績を納めた学生の全体に占める割合で国の補助金を決める
・推薦やOA入試ばかりで学生を集める大学は補助金が減るので経営が厳しくなる。
・ 従って共通一次試験が入試の必須要件となる。
・学生も共通一次試験で一定の成績を取れるよう勉強する。
・この補助金方式で増え過ぎた大学の自然淘汰が出来る。
・上記により節約できた補助金を優れた大学に廻すことが出来る。
3.大学は基礎研究、応用研究、現場に役立つ技術者の育成のいずれかに特化するかそのすべてに重点を置くかの方針を定め、効率的の運営をする。
(1)応用研究に重点
企業側
・企業は応用研究に重点を置いた大学と所謂、産学協同で研究する。
・必要あれば資金の提供をする。
・活動中に発見して優秀な学生の囲いこみする。
学生側
・学生は学校の授業では得られない企業のノウハウを学び、また企業の実態をり、就職活動に役立てることが出来る。
大学側
・運営資金が豊かになる。
・企業のノウハウを知ることが出来る。
・大学の研究が企業のニーズとかけ離れたものになることが避けられる。
(2)基礎研究に重点
・政府は1.で余裕が出来た補助金を基礎研究重点の大学に廻す。
・その補助金は大学が出した論文の数とその引用率で決める。
(3)技術者の育成に特化
・即戦力の技術者の育成
・教授陣は研究より授業に重点を置く。
・企業から教授へ受け入れ、企業の実態に則した授業をするとともに、企業とコネを付けておく。
・企業での現場実習にも重点を置く。
現在日本は中国などのBricsの厳しい追い上げに会い気息奄々の有り様だ。
唯一の頼みの技術も例にあげた清華大学の様に、日本に追いつけ追い越せの勢いだ。
そして日本の研究者数も既に中国に抜かれて世界第三位に落ちたそうだ。
エレクトロニクスの分野では一部ではあるが韓国から抜かされた。
それに対応する日本の学制改革は遅々として進まない。
ゆとり教育の基本的考え方である、「自ら学び、自ら考え自ら課題を解決する力」は正に理数系の問題の研究や技術開発にには欠かせない力だった。
然し実際に得た成果?は生徒だけでなく教師の休日増加と言う現実に突き当たって失敗に終わりまたもとの「詰め込み」へ重点が移ってしまった。
然し技術立国しか日本が世界に伍して行く道はないと誰でも言う。
文科省はじめ学校関係者、企業の人達奮起を期待したいものだ。
このブログを、より多くの人にも見て貰いたいと思っています。どうぞご協力をお願い致します。↓
人気ブログランキングへ
政治ブログへ











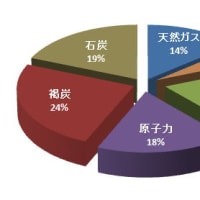
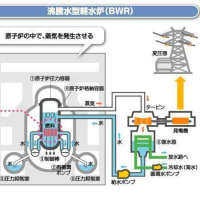
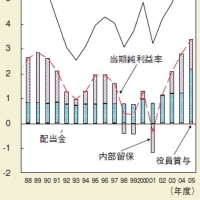
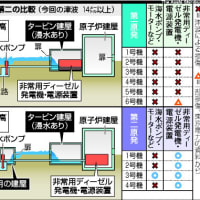


この番組は私も見ました。中国は即戦力の養成が中心、日本は基礎研究が中心だということでした。どちらが良いかということは、今後の結果を見るまで分かりません。企業は自社で研究開発部門を持っています。新入社員は、その部署で教育することで一人前の研究者になっていくのだと思いますが、基礎がしっかりできていればその応用や拡張も容易ではないかと思います。
一方、中国は即戦力を期待されているようです。しかし、20歳前後の若者に即戦力としての期待ができる業種というのは限られているように思います。番組でもIT産業の事例がでていましたが、このような業種に限られるのではないかと思います。
新しい技術は地道な研究の積み重ねの日々を経て、ある日天の啓示のようにもたらされるものなのではないでしょうか。待ち望まれる新技術の開発は若く優秀な頭脳の持ち主だけに恵まれる幸運ではないはずです。むしろ、現場で地道な研究を続けてきたものに恵まれる幸運だろうと思います。であるなら、そのような地道な研究に耐え、忍耐強く継続できる資質を若いうちから養う必要があるのではないかと思います。
慶応義塾大学塾長の安西祐一氏は、「シーズを見つけ、イノベーションを起こせる力が求められる」として、長期的視点に立った教育が大切であると述べていました。また、そのためには広い視野をもった技術者の養成が必要であるとも述べていました。私は一理ある考え方であると感じました。
いずれにせよ資源のない日本は技術立国として立つより道はなく、技術的人材の養成は喫緊の課題です。しかし、焦ってはいけないと思います。こういう時代だからこそ目先の利益のみを追うのでなく、長期的視点に立った人材育成が必要だと思います。
「急がば回れ」ということわざは名言だし、真実であると思っています。
最近、私は一連の動きに踊らされていると危ないと思うようになりました。メディアはただ煽るだけというのは太平洋戦争前から変わっていないと思います。大学にあれもやれ、これもやれといろいろと押し付けて振り回すだけ振り回しておいて、いざ潰しにかかるときには、何だ、大学の本分(教育研究)をやっていないじゃないか、という理由で攻めてくるのではないかと疑うようになりました。実際に、大学教育の質を問う動きが出始めています。大学生にふさわしくない者を出してはいけないと。
私の関係する学会は、例会の開催のために演題を募集しても、どこも演題不足で締め切りを延長するところばかりです。それだけ、学会に参加できない教員たちが増えたということです。発表できる内容がない、参加する時間がないというところでしょう。私は発表する演題があり、時間もあるので、まだ恵まれていると思います。でも、多くの仲間達がこうやって淘汰されていくのかなと思うとやりきれなさを感じます。
かくも大学が増え、少子化で誰でも入れるようになってしまったため本質が見えにくくなりましたが、学士教育とは本来、幅広く、深い教養を身につけさせるためのものではないかと思います。世の中は大学卒業後の長い間に大きく変化しますが、人類が昔から普遍的に必要としてきたことはあります。そういうことを身につけさせ人間性を磨くことが学士教育の基本ではないかと考えます。最近の学生たちを見ていて特にそう思うようになりました。生きるスタンスがしっかりしている人は、新しいこと、それがたとえ難しいことであっても取り組んで必要なことを吸収していくのではないかと私は信じます。そういう人間を一人でも多く育てるのが大学教員としての私の目標になりました。
中国からの留学生とも深い接点がありますが、だいぶ学問に対する姿勢が違い、指導に苦労しました。