第2回「ヴェールに包まれたキリストと サン・セヴェーロ礼拝堂にある美術品」のセミナーに参加してきました(2018.8.29)@高円寺ピァッツァイタリア
何年か前に ナポリ在住のイタリア人とサン・セヴェーロ礼拝堂(Cappella Sansevero)に行きとても感動したので このセミナー第2回「ヴェールに包まれたキリストと サン・セヴェーロ礼拝堂にある美術品」に参加してきました!!
第1回は「サン・セヴェーロ礼拝堂と サングロ家の呪われたライモンド王子」(サングロ家の7代目当主ライモンド王子は massoneria/フリーメイソンだったというお話で 残念ですがこちらは欠席しました)
このサン・セヴェーロ礼拝堂はなんといってもil Cristo velato/ヴェールに包まれたキリスト像が素晴らしく
私が友人と行った時も 息を呑む程感動しました
大理石でベールを掘るなんて...しかも1つの大理石からすべてを彫り出すなんて...どうやって...
また 地下にある「macchine anatomiche(人体解剖像)」の人体解剖のミイラも すごすぎて眠れない程でした~
このサン・セヴェーロ礼拝堂(Cappella Sansevero)は サン・セヴェーロ公家のサングロ(Sangro)家の一族の像等が置かれた 一族を記念するための礼拝堂で
sconsacrata(神聖さを失った)のため 今は礼拝堂ではなく美術館(Museo Cappella Sansevero)となっています
入って一番中心にあるのが このCristo velatoの像です
ライモンド王子(Raimondo di Sangro)が 彫刻家Antonio Corradini/アントニオ・コラディーニに命じて作らせた バロック様式の大理石像なのですが 彼は84才と高齢だったため
bozzetto(クロッキー) in terracotta(テラコッタ)をもとに もっと若い彫刻家 Giuseppe Sammartino/ジィゥゼッペ・サンマルティーノに彫らせます
彼はこのbozzetto(クロッキー)は使わずに 3か月で作ったとのこと
80才まで掘り続けていたのですが 伝説によると このキリスト像よりも美しい像を掘れなくするためにaccecare(盲目にする)されたそうですが...? 真実は違うようです
キリストが磔にされた十字架から降ろされ 瀕死の状態で(morente)まだ息があることを表すため 顔にかけられたベール(velo)が 鼻孔(narice)の中に吸い込まれる(息を吸っているため)
また腹(pancia)は引っ込んでいる そして額には vera(静脈)が浮き出ているのですね
実物大の大きさで(grandezza naturale) 1つの大理石からすべてを彫り出しましたが 最初は大理石ではなく 本物のベールではないかと思われた程でした
ライモンド公は錬金術師(alchimista)でもあり 色のついた臭い煙が家から出てきたこともあったそうで 人々は 本物のベールを大理石の粉につけて
大理石化(marmorizzazione)したのではないかと疑ったそうですが 正真正銘大理石(marmo)だと証明されています (科学的調査やナポリ銀行の記録等)
そして ペンチと釘(tenaglia e dei chiodi) いばらの冠(corona di spina)も置かれています
磔(はりつけ)にされた(crocifissione)時の釘の穴(buco)が 手のひらに空いているのですね...
ぐるっとまわって見るとキリストの表情は 苦しみがとれて 静かなものとなっています 同じ像ですが見る方向で変わるのです
ライモンドは1歳の時に母を亡くし 父はヨーロッパ中を旅してまわり放蕩生活を送り のちに修道院に入りました
なのでライモンドは父方の祖父(nonno paterno)に育てられたとのこと この両親の像もここにあります
彼はフリーメイソン(massoneria)に入りますが 真実はなかなかわからないものであり ベール(velo)はそれをシンボライズするとのこと
床は迷宮(labirinto)になっていますが 迷宮もやはりフリーメイソンの 人生の困難さを表すものだそうです
* * *
次に 礼拝堂にあるたくさんの像を 写真とともにひとつひとつ説明していただきました 特に気に入ったものをここに紹介しますね
ここには 10の美徳と呼ばれる像(一族をモチーフとしたもの)が置かれています
Capella Sansevero(サン・セヴェーロ礼拝堂) は こちら ← ここの下に
内部の像の配置が No.で示されています そのNo.で位置がわかります
3. Decoro (品格)
これは 3番目の王Giovan Francesco di Sangroの2人の妻にささげられた像です Antonio Corradini作
若者はライオンの頭(野生の自然を表す)を持っていますが これは人間の魂の力は野生の自然を上回ることを象徴しているそうです
また 左右違ったサンダルを履いており 天国と地獄を表しているとのこと
7. Zelo della Religione (宗教の熱意)
これは 初代当主でありこの礼拝堂の創設者Giovan Francesco di Sangroの 2人の妻を記念するための像です
老人が手にするランプ(lampada)は真実の証 また老人は足で蛇(serpente)を踏みつけて(calpestare)います 蛇は異端(eresia)のシンボルですね
9. Soavità del giogo coniugale (婚姻の絆の甘美さ)
息子Vincenzoの妻Gaetana つまり嫁に捧げた像ですが まだ彼女が生きていた時に肖像画を描いたため 素描(abbozzato)のままとなっているのですって
これは生前にちゃんとした肖像画を描くのはよくないとされていたからだそうです
これは 16. Sincertà 誠実 という ライモンドの妻Carlotta Gaetaniに捧げられた像でも同じで やはり生前に作られたために素描でした
そしてピラミッド(piramide)の形があり これは実はmassoneria(フリーメイソン)のシンボルでもあったのですね
このビラミッドの三角形は この礼拝堂の天井にも描かれていました
彼女は右手に2つの燃える心臓(cuole in fiamme)を持っていて それは夫婦の深い愛情をシンボライズしているのですが 一方左手には
羽毛で覆われたくびき(giogo)を支えていて これは甘美な服従(dolce obbedienza)をシンボライズしているのだそうです
11. Pudicizia (はにかみ) これはライモンドが1歳の時に亡くなった 母親Cecilia Gaetaniに捧げられた像で
大変美しい大理石の像です  ← ライモンドの母の像 Pudicizia
← ライモンドの母の像 Pudicizia
Antonio Corradini作ですが これを作った年に亡くなっています 彼の代表作(capolavoro)とも言われていますね
この大理石像は 半透明のベール(velo semitrasparente)に覆われた女性の身体を大理石で掘ってあり 私には他のどの像よりも魅力を感じてしまいます
ベールが女性の身体にぴったりとくっついている自然なさまを彫り出したのです ← さすが母への愛♡
さらに 左手を乗せた 壊れた墓碑(lapide spezzata) そして足元から生えている木々が la morte prematura (早死に)をシンボライズしているのです...
息子ライモンドが1歳の時に亡くなったのからですね...
14. Disinganno 悟り
この像はライモンドの父(Antonio)に捧げられた像ですが Cristo velato そしてライモンドの母のPudiciziaとともに この礼拝堂の3大作品のひとつなのですね ← ライモンドの父の像 Disinganno
← ライモンドの父の像 Disinganno
il peccato (罪)をあらわすrete(網)から逃れるさま(身体を覆う網をはずそうとしている)を表していますが
これはライモンドの父が 早くに母を亡くした息子を残して放蕩生活に出たことを指しているのですね (なので ライモンドは父方の祖父に育てられた)
この父親は老いてからナポリに戻り 罪を悔いて修道院(convento)に入ったのです
この像は intelletto umano(人間知性)のシンボルである putto(プット、大理石の子供像)が 網をはずすのを手伝っています
さらにその足元には mondanità (世俗)のシンボルである地球儀(il globo terrestre)があり その地球儀に
聖書(la bibbia)がたてかけられていますね
この作品にはmassoneria(フリーメイソン)の言及も見られるそうです 入信(inizioazioni)の時に目隠しをされた(bendati)志願者が 目をあけた時に真実がわかるという言及です
最も心を打つ要素は 目の細かい網(la fitta rete)です これは彫刻家Queiroloの熟練のたまものですが この網がまた 本物の網かと見まごう程に精巧で
実際本物の網に 大理石の粉を漬け込んで固めたのではないかと疑われたそうです (私もそう思っても不思議はないなと思いますね)
さらには この網が完成したあとで 汚れ落としのために掃除をしようとした時に 弟子たちは壊しては大変と皆断り 作者のFrancesco Queirolo(フランチェスコ・クェイローロが
仕方なく一人で掃除をしたとのことです( ゚Д゚)
第2次大戦でドイツ軍が破壊のためにここに入ってきた時に corda vera (本物のロープ)だと思われて ハンマーで打ったところ ひとかけらが
床に落ちて これは大理石だとわかり破壊を免れたそうですが こんな素晴らしい作品を こ 壊すだなんて 信じられないですよね"(-""-)"
23. Monumento a Cecco de'Sangro チェッコ・デ・サングロのモニュメント  ← Monumento a Cecco de'Sangro
← Monumento a Cecco de'Sangro
これはFracesco Celebranoの作品で 発想はおそらく前職のQueiroloのものだそうです
甲冑をつけた兵士(un guerriero armato)が 大きな箱(cassa)から出てくる像なのですが これは la rocca di Amiens(アミアンの城塞)を征服した時に
2日間棺(bara)の中で死んだふりをしてから出てきて征服した時のことを描いており かの「トロイアの木馬(il cavallo di Troia)」を連想させるだけではなく
「死と復活(morte e resurrezione)」をも連想させるのですね
最後に ライモンドの肖像画(ritratto di Raimondo di Sangro)が あとからCarlo Amalfi/カルロ・アマルフィによって描かれたのですが
年を取ってからの肖像画ですが いつ描かれたかは(datazione)定かではないものの 唯一残っている肖像画とのことで さらには 傷んでいる(robinato)のですね
これは 呪われているから(maledetto)という説もありますが(ナポリは迷信が多いのです) 実は 絵の上にガラスの天窓(lucernario in vetro)があり 何世紀も経つうちに
大気の作用が保存状態を悪化させたのではないか というのが真相のようですね...
また行きたくなりました~サン・セヴェーロ礼拝堂💛 すべての像の説明を聞いたので 今度はひとつひとつちゃんと見たいですね...
素晴らしいセミナーを開催してくださいました ピァッツァイタリア様に心よりお礼申し上げます
サン・セヴェーロ礼拝堂(Cappella Sansevero)は こちら
紹介記事は こちら
開催のお知らせは こちら
* な なんとプラモをやっているうちの家族が サン・セヴェーロについてよーく知っているとのこと( ゚Д゚) 造形をやる人間なら当然だそうでビックリ!! 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング![]() にほんブログ村
にほんブログ村
第26回ボローニャ・ブックフェアinいたばし~世界の絵本展~」開催のお知らせ(2018.8.4~8.12)@成増アートギャラリー
毎日暑いですが 成増アートギャラリーで今開催中の「2018イタリア・ボローニャ・国際絵本原画展」(7.6~7.29)のあとは いよいよ「第26回ボローニャブックフェアinいたばし」が開催されます!
ボローニャ市で毎年行われる「ボローニャ児童図書展」に今年出展され 板橋区に寄贈されたばかりの世界各国の絵本を紹介します
また特別展示として さまざまな写真を使った絵本もあわせて展示します
日時: 2018年8月4日(土)~12日(日)9時~19時(4日(土)は11時開場)
場所: 成増アートギャラリー (板橋区成増3-13-1、成増図書館向かい)
費用: 入場無料
東武東上線「成増」北口より徒歩3分 東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増」5番出口より徒歩5分
内容
・新着絵本コーナー
ボローニャから届いたばかりの世界各国の絵本をご紹介します
・写真絵本の世界
コラージュなどの技法を使った写真絵本をご覧いただけます また会場内にはオリジナルの写真絵本をつくる工作コーナーもあります
・世界の絵本おはなし会
ボランティアの皆さんにご協力いただき 毎日15時30分よりおはなし会を開催します(各回20分程度)日本語はもちろん 英語 イタリア語 アラビア語ほか 日替わりで外国語の読み聞かせを行います
・2018年ボローニャ・ラガッツィ賞
ブックデザインの優れた絵本に送られるボローニャ・ラガッツィ賞の今年の入選作品を展示します
・いたばし国際絵本翻訳大賞
板橋区では、1994年より外国語絵本の翻訳コンテストを行っています
8月4日(土)11時より、第24回受賞者の表彰式を開催し 期間中会場にて受賞作品をご覧いただけます
またこれまでの課題絵本や出版された大賞受賞作品も展示します
・ほんやさん
都内有数の子どもの本専門店ブックハウスカフェ(神保町)のご協力により 期間限定ショップがオープン!
いたばし国際絵本翻訳大賞受賞絵本 写真絵本やしかけ絵本 絵本に関するグッズなどを販売します
出店日時:土日祝日(5日、11日、12日)10時から19時
※初日(4日)のみ 11時から19時
平日(6日~10日)12時から19時
私も初日に行きます♪ 成増駅からすぐなので汗をかかずにすみますよ(笑)
今年はひさびさにドイツ語の絵本を担当させていただきました!
詳しくは こちら
* 情報をいただきましたいたばしボローニャ子ども絵本館様に心よりお礼申し上げます
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
毎日暑いですが 成増アートギャラリーで今開催中の「2018イタリア・ボローニャ・国際絵本原画展」(7.6~7.29)のあとは いよいよ「第26回ボローニャブックフェアinいたばし」が開催されます!
ボローニャ市で毎年行われる「ボローニャ児童図書展」に今年出展され 板橋区に寄贈されたばかりの世界各国の絵本を紹介します
また特別展示として さまざまな写真を使った絵本もあわせて展示します
日時: 2018年8月4日(土)~12日(日)9時~19時(4日(土)は11時開場)
場所: 成増アートギャラリー (板橋区成増3-13-1、成増図書館向かい)
費用: 入場無料
東武東上線「成増」北口より徒歩3分 東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増」5番出口より徒歩5分
内容
・新着絵本コーナー
ボローニャから届いたばかりの世界各国の絵本をご紹介します
・写真絵本の世界
コラージュなどの技法を使った写真絵本をご覧いただけます また会場内にはオリジナルの写真絵本をつくる工作コーナーもあります
・世界の絵本おはなし会
ボランティアの皆さんにご協力いただき 毎日15時30分よりおはなし会を開催します(各回20分程度)日本語はもちろん 英語 イタリア語 アラビア語ほか 日替わりで外国語の読み聞かせを行います
・2018年ボローニャ・ラガッツィ賞
ブックデザインの優れた絵本に送られるボローニャ・ラガッツィ賞の今年の入選作品を展示します
・いたばし国際絵本翻訳大賞
板橋区では、1994年より外国語絵本の翻訳コンテストを行っています
8月4日(土)11時より、第24回受賞者の表彰式を開催し 期間中会場にて受賞作品をご覧いただけます
またこれまでの課題絵本や出版された大賞受賞作品も展示します
・ほんやさん
都内有数の子どもの本専門店ブックハウスカフェ(神保町)のご協力により 期間限定ショップがオープン!
いたばし国際絵本翻訳大賞受賞絵本 写真絵本やしかけ絵本 絵本に関するグッズなどを販売します
出店日時:土日祝日(5日、11日、12日)10時から19時
※初日(4日)のみ 11時から19時
平日(6日~10日)12時から19時
私も初日に行きます♪ 成増駅からすぐなので汗をかかずにすみますよ(笑)
今年はひさびさにドイツ語の絵本を担当させていただきました!
詳しくは こちら
* 情報をいただきましたいたばしボローニャ子ども絵本館様に心よりお礼申し上げます
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
2018イタリア・ボローニャ・国際絵本原画展初日に行ってきました(2018.7.6)@成増アートギャラリー
さて今年は成増アートギャラリーで開催されるボローニャ国際絵本原画展に行ってきました!!
ここでは毎年8月に「ボローニャブックフェアin いたばし」(今年は8/4~8/12)が開催されるのですが 成増駅からすぐ近くて行きやすい!! 区立美術館(今は改修工事中)は成増駅からバスで...歩いて...暑くて...(笑)
会場こそ小さいものの すっきりとまとまって展示されておりました ただ5枚全部ではないのが少し残念
前年に出版された絵本の原画をエントリーして入賞されたもの あるいは入賞されたもので絵本を出版する話がまとまったもの等いろいろあり ざっと絵を見てから いつもの「ドキュメンタリー映像」(25分)をじっくり鑑賞 さらにインタビューで出てきた原画を再度見ると 背景もわかり再度ナットク!!
ドキュメンタリー映像の中で印象に残ったのは 「絵本が今の時代に 紙であることの必要性を考え 紙にしかけをしてみた」 なるほど本のしおりの黄色い紐と絵の内容が微妙にマッチングしている絵本等がありました!!
「新しい絵本が生まれるきっかけとなる場所」でもあるボローニャブックフェアの 今年のゲスト国は中国とのこと 1月初めの審査の風景が毎年とても興味深く 7人の審査員の方たちがどんな風にして入選作を決めてゆくのか(決まった色の付箋を次々と貼ってゆく)毎年注目しているのですが 特に 最後の2日間の審査員同士の意思の疎通が難しく 自分が推す作品が他の審査員と全く異なる(互いに)という葛藤を経て最後にようやく 「自信をもって一致団結して77作品が選ばれました」とのくだりは安心しました
また 独自のスタイルを持つ作品 5枚の絵に一貫性がある作品等が入選したとありました きらいな色を好きになる練習をしたエピソードや 白黒の絵本はあまり親が買わない傾向があるという話など ← いや反対に私 この(チラシにもある)白黒の「チーズ大作戦」(大越順子)がいっちばん気に入りましたから!! 2匹のネズミが猫の目を盗んでチーズをくすねる話で 白黒だからこそかえって強いノスタルジーを感じて アクアチントという版画の技法だそうですが 今年の私のベスト1ですね ^^) _旦~~
さらに会場奥の方には ボローニャSM出版賞を受賞された若き絵本作家によるスペイン語のインタビュー映像を聞いて 出版された絵本やデモ絵本等を見てから 次の場所である知人の剪画の個展会場に向かいました♪
 ← ボローニャブックフェアの大きな写真が!!
← ボローニャブックフェアの大きな写真が!!
2018イタリア・ボローニャ国際絵本原画展(2018.7.6~7.29)は こちら
また 成増図書館でトークイベントが開催予定です(先着順): 7/16(月/祝) 14:00~15:30 イラストレーター山田和明vs松岡館長、 7/22(日) 14:00~15:30 スペイン語翻訳者宇野和美氏、 7/28(土) 14:00~15:30 絵本評論家広松有希子 vs 松岡館長 は こちら(イベント欄) ← 今年は板橋区立美術館が改修工事のため 各所でイベントが開催されています
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
さて今年は成増アートギャラリーで開催されるボローニャ国際絵本原画展に行ってきました!!
ここでは毎年8月に「ボローニャブックフェアin いたばし」(今年は8/4~8/12)が開催されるのですが 成増駅からすぐ近くて行きやすい!! 区立美術館(今は改修工事中)は成増駅からバスで...歩いて...暑くて...(笑)
会場こそ小さいものの すっきりとまとまって展示されておりました ただ5枚全部ではないのが少し残念
前年に出版された絵本の原画をエントリーして入賞されたもの あるいは入賞されたもので絵本を出版する話がまとまったもの等いろいろあり ざっと絵を見てから いつもの「ドキュメンタリー映像」(25分)をじっくり鑑賞 さらにインタビューで出てきた原画を再度見ると 背景もわかり再度ナットク!!
ドキュメンタリー映像の中で印象に残ったのは 「絵本が今の時代に 紙であることの必要性を考え 紙にしかけをしてみた」 なるほど本のしおりの黄色い紐と絵の内容が微妙にマッチングしている絵本等がありました!!
「新しい絵本が生まれるきっかけとなる場所」でもあるボローニャブックフェアの 今年のゲスト国は中国とのこと 1月初めの審査の風景が毎年とても興味深く 7人の審査員の方たちがどんな風にして入選作を決めてゆくのか(決まった色の付箋を次々と貼ってゆく)毎年注目しているのですが 特に 最後の2日間の審査員同士の意思の疎通が難しく 自分が推す作品が他の審査員と全く異なる(互いに)という葛藤を経て最後にようやく 「自信をもって一致団結して77作品が選ばれました」とのくだりは安心しました
また 独自のスタイルを持つ作品 5枚の絵に一貫性がある作品等が入選したとありました きらいな色を好きになる練習をしたエピソードや 白黒の絵本はあまり親が買わない傾向があるという話など ← いや反対に私 この(チラシにもある)白黒の「チーズ大作戦」(大越順子)がいっちばん気に入りましたから!! 2匹のネズミが猫の目を盗んでチーズをくすねる話で 白黒だからこそかえって強いノスタルジーを感じて アクアチントという版画の技法だそうですが 今年の私のベスト1ですね ^^) _旦~~
さらに会場奥の方には ボローニャSM出版賞を受賞された若き絵本作家によるスペイン語のインタビュー映像を聞いて 出版された絵本やデモ絵本等を見てから 次の場所である知人の剪画の個展会場に向かいました♪
 ← ボローニャブックフェアの大きな写真が!!
← ボローニャブックフェアの大きな写真が!!2018イタリア・ボローニャ国際絵本原画展(2018.7.6~7.29)は こちら
また 成増図書館でトークイベントが開催予定です(先着順): 7/16(月/祝) 14:00~15:30 イラストレーター山田和明vs松岡館長、 7/22(日) 14:00~15:30 スペイン語翻訳者宇野和美氏、 7/28(土) 14:00~15:30 絵本評論家広松有希子 vs 松岡館長 は こちら(イベント欄) ← 今年は板橋区立美術館が改修工事のため 各所でイベントが開催されています
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
2018イタリア・ボローニャ国際絵本原画展が開催されます(2018.7.6~7.29)@今年は成増アートギャラリー
2018イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 今年は成増アートギャラリーで開催されます
板橋区立美術館では1981年より毎年、ボローニャ国際絵本原画展を開催してきました。38 回目を迎える本年は、大規模改修工事に伴う休館期間に重なるため、美術館から東武東上線・成増駅前のギャラリーに場所を移してご覧いただきます。
※入選作品全点を展示することはできません。あらかじめご了承ください。
会期:2018年7月6日(金)~29日(日)
開館時間:9時30分~19時30分(入館は19時まで) 会期中無休
観覧料:一般500円、高校・大学生250円、中学生以下無料
*土曜日は高校生は無料で観覧できます *20名以上団体・65歳以上・障がい者割引あり(要証明書)
会場:成増アートギャラリー(東京都板橋区成増3-13-1 アリエス3F)
東武東上線「成増駅」北口より3分(駅前ロータリーに面したアリエスビル3F)
東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増駅」(5番出口)も利用可
TEL 03-3979-3251(板橋区立美術館)/03-3977-6061(成増アートギャラリ
ー)
※板橋区立美術館は改修工事のため現在休館中です。例年とは会場が異なりますのでご注意ください。
主催:板橋区立美術館、一般社団法人日本国際児童図書評議会(JBBY)
協
ボローニャ展 関連企画: 都内各所でボローニャ展入選経験者による展示を予定しています。
また 日本からは10名の方が入選されました。おめでとうございます!!

* 毎年 板橋区立美術館で開催されているのですが 改修工事で休館中とのこと (冷房が古いので...) なのでボローニャブックフェアを例年行っている成増アートギャラリーでの開催となります こちらはフロアは小さいけど成増駅北口からすぐです( `ー´)ノ ← 真夏の炎天下でも汗をほとんどかかずに会場に到着できて嬉しいです(笑)
詳しくは こちら
* 突然PCが壊れてしまいまして...新しいPCを速攻で買いました( ;∀;)
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
2018イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 今年は成増アートギャラリーで開催されます
板橋区立美術館では1981年より毎年、ボローニャ国際絵本原画展を開催してきました。38 回目を迎える本年は、大規模改修工事に伴う休館期間に重なるため、美術館から東武東上線・成増駅前のギャラリーに場所を移してご覧いただきます。
※入選作品全点を展示することはできません。あらかじめご了承ください。
会期:2018年7月6日(金)~29日(日)
開館時間:9時30分~19時30分(入館は19時まで) 会期中無休
観覧料:一般500円、高校・大学生250円、中学生以下無料
*土曜日は高校生は無料で観覧できます *20名以上団体・65歳以上・障がい者割引あり(要証明書)
会場:成増アートギャラリー(東京都板橋区成増3-13-1 アリエス3F)
東武東上線「成増駅」北口より3分(駅前ロータリーに面したアリエスビル3F)
東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増駅」(5番出口)も利用可
TEL 03-3979-3251(板橋区立美術館)/03-3977-6061(成増アートギャラリ
ー)
※板橋区立美術館は改修工事のため現在休館中です。例年とは会場が異なりますのでご注意ください。
主催:板橋区立美術館、一般社団法人日本国際児童図書評議会(JBBY)
協
ボローニャ展 関連企画: 都内各所でボローニャ展入選経験者による展示を予定しています。
また 日本からは10名の方が入選されました。おめでとうございます!!

* 毎年 板橋区立美術館で開催されているのですが 改修工事で休館中とのこと (冷房が古いので...) なのでボローニャブックフェアを例年行っている成増アートギャラリーでの開催となります こちらはフロアは小さいけど成増駅北口からすぐです( `ー´)ノ ← 真夏の炎天下でも汗をほとんどかかずに会場に到着できて嬉しいです(笑)
詳しくは こちら
* 突然PCが壊れてしまいまして...新しいPCを速攻で買いました( ;∀;)
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
「ミケランジェロと理想の身体」展に行ってきました(2018.6.21)@国立西洋美術館
500年の時を経て 若き頃のミケランジェロの傑作「若き洗礼者ヨハネ」と 壮年期の未完の傑作「ダヴィデ=アポロ」とが ここ 国立西洋美術館の地下フロアで再び出会う...不思議な感動を覚えました
コントラポスト(contrapposto) これは古代ギリシャの身体等の理想的な表現方法です 片足に重心を置いて 反対の肩を下げて身体のひねりを出すポーズ これがこの「ダヴィデ・アポロ」にも使われていました
この作品を見て鳥肌が立ちそうになったのは 未完であるため 箟(のみ)のあとが残っているのです 表面をすべすべに仕上げる時間もないまま 「最後の審判」の制作のためにクレメンス七世によってローマに呼ばれ そのままフィレンツェに戻ることなく亡くなるのです なのでこれは故郷での最後の作品となるのですね
なんとなく 未完の大作「ピエタ」(ヴァチカンにあるのではなく ミラノで見つかったもの)にも似ている気がしました
また「若き洗礼者ヨハネ」は まだ20才の頃の作品で 早くも古代の理想美に到達しています これは洗礼者ヨハネを わずか8才の子どもの姿であらわしており 先を見通すかのような眼差しはすでに大人のものであり 成長したらどれほどの偉大な人物になるかを表している とビデオでは説明していました
ミケランジェロの彫刻は すでにその石の中に掘られるべき像があり よけいなものを取りだして命を吹き込むことだと なので「目覚める囚われ人」(今回展示されていない)という彫刻は 四方からではなく一方方向にノミを掘り進めているとのこと
古代彫刻のラオコーン像が出土され それが彼の作品に影響を与えたとのこと
それにしても 「ダヴィデ・アポロ」は ダヴィデなのか?(目録にもダヴィデとあり 踏んでいる石はゴリアテの頭と言われる) アポロなのか? (ヴァザーリ曰く) 背にかけてある未完のものが完成していたのであれば 判明したはず... 運命の皮肉ですね 彫刻家であると自負していたミケランジェロの作りたかった作品が完成させられず 「最後の審判」に5年もかけて フィレンツェに戻ってこられないままだったのですから
そしてまた 「若き洗礼者ヨハネ」は ウベダ・エル・サルバドル聖堂に移され そこで1936年にスペイン内戦の爆撃により砕けるも 修復されてよみがえった(色が違っているのはそのせい)
この2つの作品は 1537年にメディチ家の殺人事件後にコジモ一世のもとで出会うのですが 今回500年の時を経て ここ東京で 世界遺産の国立西洋美術館の地下フロアで 部屋を隔てて同じ空気の中にいるなんて...不思議でした ミケランジェロが生きているかのような気がしました
この作品に到達するまでは 古代ギリシャの彫刻(ブロンズ 大理石 テラコッタ)や 地が黒いギリシャ壺 そしてナポリ国立考古学博物館で見たのあのタッチのフレスコ画 そして最後の方では デスマスクをもとに描かれたミケランジェロの自画像等も見てゆきました
「ラオコーン」のみ撮影OK これはヴィンチェンツォ・デ・ロッシの作品で 失われた右腕は後ろに挙げている 彼なりの解釈です
 ← ロッシのラオコーン像
← ロッシのラオコーン像
入ってすぐのビデオは2回じっくり見ました イタリアの展覧会久しぶり~ よくここにサークルの皆と来たもんだと懐かしくなりました♡
「ミケランジェロと理想の身体」展(2018.6.19~9.24)は こちら
ちょぅど台湾フェスティバルもやっていました♪ (6.21~24)
 ← 上野公園の台湾フェスティバル
← 上野公園の台湾フェスティバル
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
500年の時を経て 若き頃のミケランジェロの傑作「若き洗礼者ヨハネ」と 壮年期の未完の傑作「ダヴィデ=アポロ」とが ここ 国立西洋美術館の地下フロアで再び出会う...不思議な感動を覚えました
コントラポスト(contrapposto) これは古代ギリシャの身体等の理想的な表現方法です 片足に重心を置いて 反対の肩を下げて身体のひねりを出すポーズ これがこの「ダヴィデ・アポロ」にも使われていました
この作品を見て鳥肌が立ちそうになったのは 未完であるため 箟(のみ)のあとが残っているのです 表面をすべすべに仕上げる時間もないまま 「最後の審判」の制作のためにクレメンス七世によってローマに呼ばれ そのままフィレンツェに戻ることなく亡くなるのです なのでこれは故郷での最後の作品となるのですね
なんとなく 未完の大作「ピエタ」(ヴァチカンにあるのではなく ミラノで見つかったもの)にも似ている気がしました
また「若き洗礼者ヨハネ」は まだ20才の頃の作品で 早くも古代の理想美に到達しています これは洗礼者ヨハネを わずか8才の子どもの姿であらわしており 先を見通すかのような眼差しはすでに大人のものであり 成長したらどれほどの偉大な人物になるかを表している とビデオでは説明していました
ミケランジェロの彫刻は すでにその石の中に掘られるべき像があり よけいなものを取りだして命を吹き込むことだと なので「目覚める囚われ人」(今回展示されていない)という彫刻は 四方からではなく一方方向にノミを掘り進めているとのこと
古代彫刻のラオコーン像が出土され それが彼の作品に影響を与えたとのこと
それにしても 「ダヴィデ・アポロ」は ダヴィデなのか?(目録にもダヴィデとあり 踏んでいる石はゴリアテの頭と言われる) アポロなのか? (ヴァザーリ曰く) 背にかけてある未完のものが完成していたのであれば 判明したはず... 運命の皮肉ですね 彫刻家であると自負していたミケランジェロの作りたかった作品が完成させられず 「最後の審判」に5年もかけて フィレンツェに戻ってこられないままだったのですから
そしてまた 「若き洗礼者ヨハネ」は ウベダ・エル・サルバドル聖堂に移され そこで1936年にスペイン内戦の爆撃により砕けるも 修復されてよみがえった(色が違っているのはそのせい)
この2つの作品は 1537年にメディチ家の殺人事件後にコジモ一世のもとで出会うのですが 今回500年の時を経て ここ東京で 世界遺産の国立西洋美術館の地下フロアで 部屋を隔てて同じ空気の中にいるなんて...不思議でした ミケランジェロが生きているかのような気がしました
この作品に到達するまでは 古代ギリシャの彫刻(ブロンズ 大理石 テラコッタ)や 地が黒いギリシャ壺 そしてナポリ国立考古学博物館で見たのあのタッチのフレスコ画 そして最後の方では デスマスクをもとに描かれたミケランジェロの自画像等も見てゆきました
「ラオコーン」のみ撮影OK これはヴィンチェンツォ・デ・ロッシの作品で 失われた右腕は後ろに挙げている 彼なりの解釈です
 ← ロッシのラオコーン像
← ロッシのラオコーン像入ってすぐのビデオは2回じっくり見ました イタリアの展覧会久しぶり~ よくここにサークルの皆と来たもんだと懐かしくなりました♡
「ミケランジェロと理想の身体」展(2018.6.19~9.24)は こちら
ちょぅど台湾フェスティバルもやっていました♪ (6.21~24)
 ← 上野公園の台湾フェスティバル
← 上野公園の台湾フェスティバル 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
Giovanni Piliarvu 写真展『Fluire~時の流れ』最終日に行ってきました(2018.6.17)@京橋アイランドギャラリー
これで3度目のジョヴァンニ・ピリアルヴ氏の個展 最終日の日曜の午後は人がいっぱいで 作品はシチリアの村その他 イタリア以外にも 日本の風景が3度目の個展で初めて登場していました!!
日本に長く住んでようやく自分の目で日本の風景を深いまなざしで捕らえるようになったのだなと感激です いつも撮影エピソードは色々伺っていますが...
タイトルは 「~しながら」という意味の動詞のジェルンディオが中心で味わいを感じました すべての意味は分からなかったけど...
そしてこの写真展のメッセージは 日本であれイタリアであれ どこにいたとしても自然と人間の関係は変わらない 自然から恩恵を受けて一緒に生きているというもので 自然豊かなサルデーニャ出身の先生ならではのメッセージだと思います
イタリアの風景写真は Randazzo (シチリア州のCatania県のborgo) オストゥーニ/Ostuni(プーリア州) Gagliano Castelferrato (シチリア州エンナ県) そして糸杉で有名なオルチャ渓谷などでした 私はついついシチリアに目がいってしまいます♡
日本の風景写真は 千葉県房総半島の小山 北海道の美瑛 岐阜県の郡上八幡 東京の冬景色などでした 本当にジョヴァンニ氏は忙しい中をぬって 日本の各所も色々とまわられていらっしゃいます
聞いたことのない街の名前はborgo(村)の名です まだ世に知られていない村の美しさを切り取ったジョヴァンニ氏の写真を堪能して 少しイタリア語しゃべってから帰りました
Giovanni Piliarvu 写真展『Fluire~時の流れ』(2018.6.8~6.17)は こちら
昨年の記事を見ると 昨年も吉祥寺のLCIのイタリア文化セミナーと同じ日に行っていたのですね♪
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
これで3度目のジョヴァンニ・ピリアルヴ氏の個展 最終日の日曜の午後は人がいっぱいで 作品はシチリアの村その他 イタリア以外にも 日本の風景が3度目の個展で初めて登場していました!!
日本に長く住んでようやく自分の目で日本の風景を深いまなざしで捕らえるようになったのだなと感激です いつも撮影エピソードは色々伺っていますが...
タイトルは 「~しながら」という意味の動詞のジェルンディオが中心で味わいを感じました すべての意味は分からなかったけど...
そしてこの写真展のメッセージは 日本であれイタリアであれ どこにいたとしても自然と人間の関係は変わらない 自然から恩恵を受けて一緒に生きているというもので 自然豊かなサルデーニャ出身の先生ならではのメッセージだと思います
イタリアの風景写真は Randazzo (シチリア州のCatania県のborgo) オストゥーニ/Ostuni(プーリア州) Gagliano Castelferrato (シチリア州エンナ県) そして糸杉で有名なオルチャ渓谷などでした 私はついついシチリアに目がいってしまいます♡
日本の風景写真は 千葉県房総半島の小山 北海道の美瑛 岐阜県の郡上八幡 東京の冬景色などでした 本当にジョヴァンニ氏は忙しい中をぬって 日本の各所も色々とまわられていらっしゃいます
聞いたことのない街の名前はborgo(村)の名です まだ世に知られていない村の美しさを切り取ったジョヴァンニ氏の写真を堪能して 少しイタリア語しゃべってから帰りました
Giovanni Piliarvu 写真展『Fluire~時の流れ』(2018.6.8~6.17)は こちら
昨年の記事を見ると 昨年も吉祥寺のLCIのイタリア文化セミナーと同じ日に行っていたのですね♪
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
「ミケランジェロ 理想の身体」展が開催されます(2018.6.19~9.24)@国立西洋美術館
謎の傑作 <もう一つのダヴィデ>なのか
日本で初めて公開される ミケランジェロの大型彫刻《ダヴィデ=アポロ》 《若き洗礼者ヨハネ》を中心に
古代ギリシャ・ローマ時代とルネサンス時代の作品約70点により ミケランジェロや当時の彫刻家たちが創りあげた 理想の身体美の表現に迫ります
謎の傑作、初来日です
「ミケランジェロ 理想の身体」展覧会は こちら
また LCIでは 7月にイタリア人講師と美術館へ行こう!~ミケランジェロ特別展~を開催します
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
謎の傑作 <もう一つのダヴィデ>なのか
日本で初めて公開される ミケランジェロの大型彫刻《ダヴィデ=アポロ》 《若き洗礼者ヨハネ》を中心に
古代ギリシャ・ローマ時代とルネサンス時代の作品約70点により ミケランジェロや当時の彫刻家たちが創りあげた 理想の身体美の表現に迫ります
謎の傑作、初来日です
「ミケランジェロ 理想の身体」展覧会は こちら
また LCIでは 7月にイタリア人講師と美術館へ行こう!~ミケランジェロ特別展~を開催します
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
ドキュメンタリー「時の旅人-伊東マンショ 肖像画の謎-」上映会に行ってきました(2017.12.7)@イタリア文化会館
この日は第3回フォスコ・マライ―ニ賞授賞式に引き続き ドキュメンタリー「時の旅人-伊東マンショ 肖像画の謎-」上映会と鼎談を聞きました テレビ宮崎制作の番組は九州全土で放映されたのですが 今回東京ではまず ここイタリア文化会館での上映となりました
天正遣欧少年使節のひとり 伊東マンショの肖像画がミラノで発見されたとの報道があったのは2014年のことでした 2016年 ドメニコ・ティントレット作のこの肖像画が 東京国立博物館で特別展示され その機会にイタリア文化会館ではシンポジウムを開催しました
今回それに続くものとして 伊東マンショの出身地である宮崎のテレビ局 「テレビ宮崎」が制作した 肖像画にまつわる物語や伊東マンショの功績を描いたドキュメンタリー「時の旅人-伊東マンショ 肖像画の謎-」を上映し 上映後には 東京大学名誉教授小佐野重利氏 同作品のディレクター雪丸千彩子氏 肖像画発見の特報記事を担当した読売新聞社文化部長 前田恭二氏が鼎談しました
作品内容(テレビ宮崎)
450年ほど前 宮崎県西都市都於郡(とのこおり)に生まれた少年 伊東マンショ
伊東家当主の孫として生まれたマンショだが 8歳の時 一族が島津家との勢力争いに破れ 豊後(現在の大分県)へと敗走する
キリシタン大名・大友宗麟が治める豊後 マンショはそこでキリスト教に出会い 後にイエズス会が計画した「天正遣欧少年使節」の主席正使として 2人のローマ教皇に謁見する
そして 彼らは未だ知られていなかった「日本」や「日本人」の存在をヨーロッパに知らしめた
しかし マンショたちが帰国の途に着く頃 日本ではキリシタン弾圧が始まり 彼らの功績は日本の歴史の表舞台からは消え去ってしまった
日本初の外交官とも言うべき役割を果たしたマンショは 宮崎が誇る偉人の一人だが 彼の存在や功績 宮崎県出身であることを知る人は少ない
2014年 「イタリア・ミラノで伊東マンショの肖像画が発見された」とのニュースが報道され 2016年 宮崎での里帰り展が実現した
これまでのマンショの姿と言えば 16世紀当時の新聞(版画)やスケッチ画でしか偲ぶことは出来なかったが 今回発見された肖像画は 16歳のマンショの表情を生き生きと描いた油絵
肖像画は400年以上前 その時代を確かに生きたマンショのより人間らしい魅力 現実味が伝わってくる1枚だ
発表に至るまでには イタリア人女性研究者による5年にも及ぶ研究があったことも分かった
この肖像画はどのような過程を経てマンショだと突き止められたのか 使節4人の肖像画が描かれたという記録は残るものの 行方知れずとなっていた肖像画は 400年以上もの間どこにあったのか
そして誰が何のために描かせたのか…肖像画にまつわる物語や された謎を紐解きながら 時の人 伊東マンショの功績や 最新の研究結果に迫るドキュメンタリー番組
* この番組は「FNSドキュメンタリー大賞」ノミネート作品でした
* * *
この番組では 地元宮崎県からこのような人物が輩出されたことを誇りに思う地元の方々が出てきます 伊東マンショ(1570?~1612)がわずか8才で豊後落ちをしたその道を案内する地元のガイドの方 歴史研究家 あるいは子供たちがマンショの歌を歌いながら 手作りの兜をかぶりお祭りに参加するシーンに加えて(ローカル局の番組なので特にそちらをクローズアップした) 2014年にミラノで発見されたこのマンショの16才の若き頃の肖像画が どうやってマンショの肖像画だとわかり 誰が描いたのかがわかったか その奇跡を辿っています
それは この絵を保管するミラノ・トリヴルツィオ財団(La Fondazione Trivulzio)のパオラ・ディリコさんというイタリア人研究者がこの絵と出合ったことに始まります
西洋人ではない このfanciullo(少年)のまなざしに強く惹かれ 誰が描かれたのかをつきとめたいと研究を始めました
最初はフィリピン人かと思ったそうです ですが上司に日本研究者がおり 豊後の文字が解読されたことから急展開し 1585年という年号と場所が判明され 絵の裏側に「Mansio」とあったことから 伊東マンショの肖像画と確定されたとのこと
絵の特定って大変なのですよね...
16才でミラノに行った彼は 12才で2年半もかけて「天正遣欧少年使節」の主席正使として航行しました パオラさんの「自分の子ならジェラートを買いに ひとりではまだ行かせないような年の子どもが 国の代表として海外に行ったのです」との驚きの言葉が印象的でした
キャンバスの枠にはティントレットとのサインがあり 父親ヤコポが描き 息子ドメニコが襟や帽子等を手直ししたとのこと 当時ティントレットは黄色を描くのに鈴鉛黄を使っていたことからも特定されました
1585年にヴェネツィアを訪れた一行は 描かれたこの肖像画は 儀式のための大作の下絵として描かれましたが ヴェネツィアとバチカンとの対立により儀式用の大作が描かれなくなったことから 肖像画を売るために のちに襟を大きく描いたり帽子も手直しされたとのこと
さらに この絵はティントレット公房で描かれて ヴェネツィアからカルビオ侯爵(スペイン人)の手にわたり 彼のローマ・ナポリ駐在にも絵は付き添い やがて侯爵の死後に他の膨大な作品とともに競売にかけられ フィレンツェの貴族が競り落とした時は名前も「少年の絵」というくらいしかなく やがてその貴族の娘がミラノに嫁入りする時の嫁入り道具のひとつとして輿入れリストにあったという 400年あまりの絵の来歴に固唾をのみました... 日本よりもヨーロッパの方が絵の来歴が確実にたどれるのですね
パオラさんが番組のラストで「旅人だったマンショは 絵になってからも旅人だったのですね 運命ですね...」とつぶやくところで終わっています
そしてまた マンショ自身も 宮崎に生まれて8才で豊後(大分)落ち 16才で天正遣欧少年使節としてヨーロッパに行き 帰国後は 1587年の豊臣秀吉によるバテレン追放令発布等で 43才で病死との人生を辿ります
若いうちにルネサンス期のヨーロッパをこの目で見て 帰国後に布教に力を尽くすはずが 時代の転換期の中で数奇な運命をたどったのですね...
鼎談では 絵の発見を特報記事にされた読売新聞文化部長 番組を制作したテレビ宮崎のディレクターのお二人が 東大名誉教授の小佐野重利氏の司会により 番組や特報記事制作にまつわる様々なお話をしてくださいました
貴重な番組とお話が聞けて 大変嬉しく思います 素晴らしいイベントをありがとうございました
開催のお知らせは こちら
2018年1月10日(水)NHK BSプレミアムで「400年後の真実~慶長遣欧使節の謎に迫る~」が放送されたそうです ← 見逃した~...
* 写真は 富士美術館で開催された「遥かなるルネサンス」展のチラシ 右が伊藤マンショの肖像画
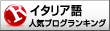 イタリア語ランキング
イタリア語ランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
この日は第3回フォスコ・マライ―ニ賞授賞式に引き続き ドキュメンタリー「時の旅人-伊東マンショ 肖像画の謎-」上映会と鼎談を聞きました テレビ宮崎制作の番組は九州全土で放映されたのですが 今回東京ではまず ここイタリア文化会館での上映となりました
天正遣欧少年使節のひとり 伊東マンショの肖像画がミラノで発見されたとの報道があったのは2014年のことでした 2016年 ドメニコ・ティントレット作のこの肖像画が 東京国立博物館で特別展示され その機会にイタリア文化会館ではシンポジウムを開催しました
今回それに続くものとして 伊東マンショの出身地である宮崎のテレビ局 「テレビ宮崎」が制作した 肖像画にまつわる物語や伊東マンショの功績を描いたドキュメンタリー「時の旅人-伊東マンショ 肖像画の謎-」を上映し 上映後には 東京大学名誉教授小佐野重利氏 同作品のディレクター雪丸千彩子氏 肖像画発見の特報記事を担当した読売新聞社文化部長 前田恭二氏が鼎談しました
作品内容(テレビ宮崎)
450年ほど前 宮崎県西都市都於郡(とのこおり)に生まれた少年 伊東マンショ
伊東家当主の孫として生まれたマンショだが 8歳の時 一族が島津家との勢力争いに破れ 豊後(現在の大分県)へと敗走する
キリシタン大名・大友宗麟が治める豊後 マンショはそこでキリスト教に出会い 後にイエズス会が計画した「天正遣欧少年使節」の主席正使として 2人のローマ教皇に謁見する
そして 彼らは未だ知られていなかった「日本」や「日本人」の存在をヨーロッパに知らしめた
しかし マンショたちが帰国の途に着く頃 日本ではキリシタン弾圧が始まり 彼らの功績は日本の歴史の表舞台からは消え去ってしまった
日本初の外交官とも言うべき役割を果たしたマンショは 宮崎が誇る偉人の一人だが 彼の存在や功績 宮崎県出身であることを知る人は少ない
2014年 「イタリア・ミラノで伊東マンショの肖像画が発見された」とのニュースが報道され 2016年 宮崎での里帰り展が実現した
これまでのマンショの姿と言えば 16世紀当時の新聞(版画)やスケッチ画でしか偲ぶことは出来なかったが 今回発見された肖像画は 16歳のマンショの表情を生き生きと描いた油絵
肖像画は400年以上前 その時代を確かに生きたマンショのより人間らしい魅力 現実味が伝わってくる1枚だ
発表に至るまでには イタリア人女性研究者による5年にも及ぶ研究があったことも分かった
この肖像画はどのような過程を経てマンショだと突き止められたのか 使節4人の肖像画が描かれたという記録は残るものの 行方知れずとなっていた肖像画は 400年以上もの間どこにあったのか
そして誰が何のために描かせたのか…肖像画にまつわる物語や された謎を紐解きながら 時の人 伊東マンショの功績や 最新の研究結果に迫るドキュメンタリー番組
* この番組は「FNSドキュメンタリー大賞」ノミネート作品でした
* * *
この番組では 地元宮崎県からこのような人物が輩出されたことを誇りに思う地元の方々が出てきます 伊東マンショ(1570?~1612)がわずか8才で豊後落ちをしたその道を案内する地元のガイドの方 歴史研究家 あるいは子供たちがマンショの歌を歌いながら 手作りの兜をかぶりお祭りに参加するシーンに加えて(ローカル局の番組なので特にそちらをクローズアップした) 2014年にミラノで発見されたこのマンショの16才の若き頃の肖像画が どうやってマンショの肖像画だとわかり 誰が描いたのかがわかったか その奇跡を辿っています
それは この絵を保管するミラノ・トリヴルツィオ財団(La Fondazione Trivulzio)のパオラ・ディリコさんというイタリア人研究者がこの絵と出合ったことに始まります
西洋人ではない このfanciullo(少年)のまなざしに強く惹かれ 誰が描かれたのかをつきとめたいと研究を始めました
最初はフィリピン人かと思ったそうです ですが上司に日本研究者がおり 豊後の文字が解読されたことから急展開し 1585年という年号と場所が判明され 絵の裏側に「Mansio」とあったことから 伊東マンショの肖像画と確定されたとのこと
絵の特定って大変なのですよね...
16才でミラノに行った彼は 12才で2年半もかけて「天正遣欧少年使節」の主席正使として航行しました パオラさんの「自分の子ならジェラートを買いに ひとりではまだ行かせないような年の子どもが 国の代表として海外に行ったのです」との驚きの言葉が印象的でした
キャンバスの枠にはティントレットとのサインがあり 父親ヤコポが描き 息子ドメニコが襟や帽子等を手直ししたとのこと 当時ティントレットは黄色を描くのに鈴鉛黄を使っていたことからも特定されました
1585年にヴェネツィアを訪れた一行は 描かれたこの肖像画は 儀式のための大作の下絵として描かれましたが ヴェネツィアとバチカンとの対立により儀式用の大作が描かれなくなったことから 肖像画を売るために のちに襟を大きく描いたり帽子も手直しされたとのこと
さらに この絵はティントレット公房で描かれて ヴェネツィアからカルビオ侯爵(スペイン人)の手にわたり 彼のローマ・ナポリ駐在にも絵は付き添い やがて侯爵の死後に他の膨大な作品とともに競売にかけられ フィレンツェの貴族が競り落とした時は名前も「少年の絵」というくらいしかなく やがてその貴族の娘がミラノに嫁入りする時の嫁入り道具のひとつとして輿入れリストにあったという 400年あまりの絵の来歴に固唾をのみました... 日本よりもヨーロッパの方が絵の来歴が確実にたどれるのですね
パオラさんが番組のラストで「旅人だったマンショは 絵になってからも旅人だったのですね 運命ですね...」とつぶやくところで終わっています
そしてまた マンショ自身も 宮崎に生まれて8才で豊後(大分)落ち 16才で天正遣欧少年使節としてヨーロッパに行き 帰国後は 1587年の豊臣秀吉によるバテレン追放令発布等で 43才で病死との人生を辿ります
若いうちにルネサンス期のヨーロッパをこの目で見て 帰国後に布教に力を尽くすはずが 時代の転換期の中で数奇な運命をたどったのですね...
鼎談では 絵の発見を特報記事にされた読売新聞文化部長 番組を制作したテレビ宮崎のディレクターのお二人が 東大名誉教授の小佐野重利氏の司会により 番組や特報記事制作にまつわる様々なお話をしてくださいました
貴重な番組とお話が聞けて 大変嬉しく思います 素晴らしいイベントをありがとうございました
開催のお知らせは こちら
2018年1月10日(水)NHK BSプレミアムで「400年後の真実~慶長遣欧使節の謎に迫る~」が放送されたそうです ← 見逃した~...
* 写真は 富士美術館で開催された「遥かなるルネサンス」展のチラシ 右が伊藤マンショの肖像画
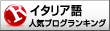 イタリア語ランキング
イタリア語ランキング
コスタンティーノ・ドラッツィオ講演会「カラヴァッジョの秘密(Caravaggio Segreto)」に行ってきました(2017.10.30)@イタリア文化会館
昨年3月に「カラヴァッジョ展」を見に行ってからひさびさのカラヴァッジョの講演会ですが この日は 新しく発見された資料を踏まえて最新にアップデートされてこの 月に出版された本「カラヴァッジョの秘密(Caravaggio Segreto)」の著者自らの講演会で 通訳はこの本を翻訳された方とあって 丁寧に補足して説明してくださり さらには内容も新説の発表とあって 聴いていて身体がふわっと宙に浮いてしまいそうな興奮!! この本もサイン入りでたくさんの方が買い求めていました!!
* * *
昨年邦訳が出版された『レオナルド・ダ・ヴィンチの秘密 天才の挫折と輝き』(2016, 河出書房新社)と同じ<秘密>シリーズ第一作で、イタリアでベストセラーとなった『カラヴァッジョの秘密』
17世紀以降の西洋絵画に絶大な影響を与えたカラヴァッジョ その常軌を逸した人格と 成功への執着が生み出した彼の傑作は 今なお永遠に生きる
―カラヴァッジョの革新的な光と闇の手法と 理想化することなく聖と俗を見つめた視点は バロックという新時代の美術を開花させる原動力となった
波乱に満ちた短い生涯を生き生きと物語った最新・最良の決定版! 本書は“秘密シリーズ”の第一弾で、イタリアで大きな成功を収めた(本の紹介より)
本書邦訳の出版を機に来日する著者ドラッツィオが 謎多き天才画家カラヴァッジョの魅力の秘密について熱く語ってくださいました
講演者は原稿も持たず スクリーンの絵をひとつひとつ とても迫力のある聞きやすいイタリア語で説明してくださり とてもよくわかりました♡
1571年に彼がミラノで洗礼(battesimo)を受けた書類も この本には収録されています そのため 近郊のカラヴァッジョ村出身ではなくミラノ出身とのこと
1600年は カラヴァッジョ(1571-1610年)が 生まれ故郷のミラノからローマ にやってきて4年めでした これは知られているようにミラノに来たのは1592年ではなく 2013年以降に 1596年だと判明したそうです (詳しくは著書を) そのため1592-95年は「空白の4年間」として 書類なども残されておらず謎が残るとのこと
この1600年は大聖年(Giubileo)であり ファルネーゼ家はカラヴァッジョに 2人の画家がなしえなかったサン・ルイジ・デイ・フランチェージ教会コンタレッリ礼拝堂の室内装飾を依頼した これはおそらく彼のパトロン デル・モンテ枢機卿の力添えによるもの
このときに描かれたのが『聖マタイの殉教 (Martyrdom of Saint Matthew)』と『聖マタイの召命』で たちまちのうちに大評判となりました
しかしカラヴァッジョの絵は ジョルジョーネやティツィアーノ(ヴェネツィア派)の真似だと後に揶揄されたエピソードを 二つの絵を対比した上で語ってくださいました
「トカゲに噛まれた少年」(1593-4) これは 注文主もないままに自主的に描いた一作 画家としての道をつくるため(per farsi strada) パンテオンの周囲で開催される新人画家たちの展示会で披露したそうで 実は 感情表現の練習のために ザリガニに噛まれて泣く子どもの絵の模写が当時は広く行われており カラヴァッジョはそれを一歩進めて 「たった今トカゲに噛まれたばかりの」少年(実はモデルはミンニーティ)の 様々な感情の絡まった表情を まるで写真のように瞬間を切り取った「即時性」を際立たせて描いたのです
次は「トランプ詐欺師」(1598年頃) 3人を描いた絵で右端の男は詐欺師で ベルトの背中側にはさまった偽カードを出そうとしている臨場感が描かれています これはカラヴァッジョの転機となる作品であり 庶民の日常生活を描いている風俗画のひとつ
しかし彼は絵画よりも 刀剣不法所持等の乱行の数々でローマにおいて有名であり 難しい人物とされていたのです
そんな彼に 初めての公共の場での絵画の仕事が来ます それは前述の1600年 サン・ルイジ・ディ・フランチェージ教会コンタレッリ礼拝堂の室内装飾であり ここで「聖マタイの殉教」「聖マタイの召命」「聖マタイと天使」のマタイ三部作が フレスコ画ではなくカンバス画で描かれました フレスコ画はやり直しがきかないためだとのこと
ここで初めて彼は 注文主に合わせて 報酬のために明るい光を(ローマ風)描かずに 本来の影(scuro)を描く これがキアロスクーロよりもに強い明暗法 テネブリズムです
また1951年の調査により この「聖マタイの殉教」の絵の下には すでに完成された他の絵があったことがわかりました これは このフランチェージ教会は一般人は入れず 右の壁に描かれた「聖マタイの殉教」を見ることになると気付いたためとのこと
そしていよいよ「聖マタイの召命」 これは右端のキリストがマタイを示して呼ぶシーンですが 誰が聖マタイかは何十年もの論争がありました (イタリアでは真ん中の髭の男 ドイツでは左端の青年がマタイではないかとの論争がある) 著者はこう証明したのです: 右上から入る光に照らされた 左から三番目の(真ん中の)髭の男の「手の甲」は 光を受けずに暗い それは左端の若者ではなく 自分自身を指示しているのではないか? 若者を差しているのであれば光があたっているはずとのこと そういわれてみれば...
また ひげを蓄えていることが他の絵とも共通しており (文盲の市民のために分かりやすく描く必要があった) また帽子にコインがついているのは当時の徴税人の制服で...つまり 聖マタイはいったい誰なのか... これを聞いた時は私も椅子からふわりと身体が宙に浮くような高揚感を覚えました 過去に証明されたものが くつがえされた瞬間に居合わせたような...!!
彼はそしてこの仕事で得たお金でローマにアパートを借りることができ モデルを雇い キアロスクーロの技法で描いた ひとつの絵には そのアパートの灯り取りの小さな窓が描かれている 実際に彼は窓から差す光を描いたのだ
彼は見えるものを描いた いや 見えるものしか描かなかった そのためモデルを用いた 金のない時代は金を払わずにすむ友人等を あるいは娼婦を 時にはテヴェレ川に上がった水死体となった娼婦を 眠っている姿として「死んだあとも」描いたという...
1606年に彼は殺人事件を起こし ローマからナポリに逃げる そしてマルタ島へ マルタ騎士団を除名されて次はシチリアのシラクサ そして再びナポリへ さらには恩赦を求めてローマへと向かう途中に ポルト・エルコレで熱病で客死...39才の若さでした
この逃亡資金を得るために 大きな絵を急いで描く必要ができ バックを黒で下塗りして描いた 「節約技法(pittura risparmio)」が生み出されました 粗悪な材料のため損傷が激しいとのこと
最後の作品「聖ウルスラの殉教」(1610年6月) 亡くなる1か月前に描かれたという この絵の右上には自画像が描かれています 彼は自画像をその絵の中に描くことがありました 様々な意味を込めて...
こうして彼は その絵の技術を 人生のそれぞれの転換期において その人生と重ね合わせながら その都度改革してきたのです...
彼の真筆とされるものは現在45点 またそうではないかと考えられる作品も同じくらいの数があるといいます しかし将来の研究により また新たな発見があるかもしれないと 残っている書類が少なく それだけに講演者自身も 空白の4年間を含めて 限られた中での作業だったとのこと 実際に 2013年以降に見つかった資料をもとに最新にアップデートされたカラヴァッジョの本なのですね
著者自身は宗教画「ホロフェルネスの首を斬るユディト」(1598-99)が好きとのこと 大男を手にかける(斬首する)ユディトの意志と 寝ている間に首を斬られるホロフェルネスの驚きと苦しみの感情表現の比較が気に入っているそうです
最新の資料を元に書かれたこの「カラヴァッジョの秘密」を 皆さんサインをいただきながら手にしていかれました
あなたは どのカラヴァッジョの絵がお好きですか?
本は こちら
開催のお知らせは こちら
素晴らしい講演会を開催してくださいましたイタリア文化会館様に心よりお礼申し上げます
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
昨年3月に「カラヴァッジョ展」を見に行ってからひさびさのカラヴァッジョの講演会ですが この日は 新しく発見された資料を踏まえて最新にアップデートされてこの 月に出版された本「カラヴァッジョの秘密(Caravaggio Segreto)」の著者自らの講演会で 通訳はこの本を翻訳された方とあって 丁寧に補足して説明してくださり さらには内容も新説の発表とあって 聴いていて身体がふわっと宙に浮いてしまいそうな興奮!! この本もサイン入りでたくさんの方が買い求めていました!!
* * *
昨年邦訳が出版された『レオナルド・ダ・ヴィンチの秘密 天才の挫折と輝き』(2016, 河出書房新社)と同じ<秘密>シリーズ第一作で、イタリアでベストセラーとなった『カラヴァッジョの秘密』
17世紀以降の西洋絵画に絶大な影響を与えたカラヴァッジョ その常軌を逸した人格と 成功への執着が生み出した彼の傑作は 今なお永遠に生きる
―カラヴァッジョの革新的な光と闇の手法と 理想化することなく聖と俗を見つめた視点は バロックという新時代の美術を開花させる原動力となった
波乱に満ちた短い生涯を生き生きと物語った最新・最良の決定版! 本書は“秘密シリーズ”の第一弾で、イタリアで大きな成功を収めた(本の紹介より)
本書邦訳の出版を機に来日する著者ドラッツィオが 謎多き天才画家カラヴァッジョの魅力の秘密について熱く語ってくださいました
講演者は原稿も持たず スクリーンの絵をひとつひとつ とても迫力のある聞きやすいイタリア語で説明してくださり とてもよくわかりました♡
1571年に彼がミラノで洗礼(battesimo)を受けた書類も この本には収録されています そのため 近郊のカラヴァッジョ村出身ではなくミラノ出身とのこと
1600年は カラヴァッジョ(1571-1610年)が 生まれ故郷のミラノからローマ にやってきて4年めでした これは知られているようにミラノに来たのは1592年ではなく 2013年以降に 1596年だと判明したそうです (詳しくは著書を) そのため1592-95年は「空白の4年間」として 書類なども残されておらず謎が残るとのこと
この1600年は大聖年(Giubileo)であり ファルネーゼ家はカラヴァッジョに 2人の画家がなしえなかったサン・ルイジ・デイ・フランチェージ教会コンタレッリ礼拝堂の室内装飾を依頼した これはおそらく彼のパトロン デル・モンテ枢機卿の力添えによるもの
このときに描かれたのが『聖マタイの殉教 (Martyrdom of Saint Matthew)』と『聖マタイの召命』で たちまちのうちに大評判となりました
しかしカラヴァッジョの絵は ジョルジョーネやティツィアーノ(ヴェネツィア派)の真似だと後に揶揄されたエピソードを 二つの絵を対比した上で語ってくださいました
「トカゲに噛まれた少年」(1593-4) これは 注文主もないままに自主的に描いた一作 画家としての道をつくるため(per farsi strada) パンテオンの周囲で開催される新人画家たちの展示会で披露したそうで 実は 感情表現の練習のために ザリガニに噛まれて泣く子どもの絵の模写が当時は広く行われており カラヴァッジョはそれを一歩進めて 「たった今トカゲに噛まれたばかりの」少年(実はモデルはミンニーティ)の 様々な感情の絡まった表情を まるで写真のように瞬間を切り取った「即時性」を際立たせて描いたのです
次は「トランプ詐欺師」(1598年頃) 3人を描いた絵で右端の男は詐欺師で ベルトの背中側にはさまった偽カードを出そうとしている臨場感が描かれています これはカラヴァッジョの転機となる作品であり 庶民の日常生活を描いている風俗画のひとつ
しかし彼は絵画よりも 刀剣不法所持等の乱行の数々でローマにおいて有名であり 難しい人物とされていたのです
そんな彼に 初めての公共の場での絵画の仕事が来ます それは前述の1600年 サン・ルイジ・ディ・フランチェージ教会コンタレッリ礼拝堂の室内装飾であり ここで「聖マタイの殉教」「聖マタイの召命」「聖マタイと天使」のマタイ三部作が フレスコ画ではなくカンバス画で描かれました フレスコ画はやり直しがきかないためだとのこと
ここで初めて彼は 注文主に合わせて 報酬のために明るい光を(ローマ風)描かずに 本来の影(scuro)を描く これがキアロスクーロよりもに強い明暗法 テネブリズムです
また1951年の調査により この「聖マタイの殉教」の絵の下には すでに完成された他の絵があったことがわかりました これは このフランチェージ教会は一般人は入れず 右の壁に描かれた「聖マタイの殉教」を見ることになると気付いたためとのこと
そしていよいよ「聖マタイの召命」 これは右端のキリストがマタイを示して呼ぶシーンですが 誰が聖マタイかは何十年もの論争がありました (イタリアでは真ん中の髭の男 ドイツでは左端の青年がマタイではないかとの論争がある) 著者はこう証明したのです: 右上から入る光に照らされた 左から三番目の(真ん中の)髭の男の「手の甲」は 光を受けずに暗い それは左端の若者ではなく 自分自身を指示しているのではないか? 若者を差しているのであれば光があたっているはずとのこと そういわれてみれば...
また ひげを蓄えていることが他の絵とも共通しており (文盲の市民のために分かりやすく描く必要があった) また帽子にコインがついているのは当時の徴税人の制服で...つまり 聖マタイはいったい誰なのか... これを聞いた時は私も椅子からふわりと身体が宙に浮くような高揚感を覚えました 過去に証明されたものが くつがえされた瞬間に居合わせたような...!!
彼はそしてこの仕事で得たお金でローマにアパートを借りることができ モデルを雇い キアロスクーロの技法で描いた ひとつの絵には そのアパートの灯り取りの小さな窓が描かれている 実際に彼は窓から差す光を描いたのだ
彼は見えるものを描いた いや 見えるものしか描かなかった そのためモデルを用いた 金のない時代は金を払わずにすむ友人等を あるいは娼婦を 時にはテヴェレ川に上がった水死体となった娼婦を 眠っている姿として「死んだあとも」描いたという...
1606年に彼は殺人事件を起こし ローマからナポリに逃げる そしてマルタ島へ マルタ騎士団を除名されて次はシチリアのシラクサ そして再びナポリへ さらには恩赦を求めてローマへと向かう途中に ポルト・エルコレで熱病で客死...39才の若さでした
この逃亡資金を得るために 大きな絵を急いで描く必要ができ バックを黒で下塗りして描いた 「節約技法(pittura risparmio)」が生み出されました 粗悪な材料のため損傷が激しいとのこと
最後の作品「聖ウルスラの殉教」(1610年6月) 亡くなる1か月前に描かれたという この絵の右上には自画像が描かれています 彼は自画像をその絵の中に描くことがありました 様々な意味を込めて...
こうして彼は その絵の技術を 人生のそれぞれの転換期において その人生と重ね合わせながら その都度改革してきたのです...
彼の真筆とされるものは現在45点 またそうではないかと考えられる作品も同じくらいの数があるといいます しかし将来の研究により また新たな発見があるかもしれないと 残っている書類が少なく それだけに講演者自身も 空白の4年間を含めて 限られた中での作業だったとのこと 実際に 2013年以降に見つかった資料をもとに最新にアップデートされたカラヴァッジョの本なのですね
著者自身は宗教画「ホロフェルネスの首を斬るユディト」(1598-99)が好きとのこと 大男を手にかける(斬首する)ユディトの意志と 寝ている間に首を斬られるホロフェルネスの驚きと苦しみの感情表現の比較が気に入っているそうです
最新の資料を元に書かれたこの「カラヴァッジョの秘密」を 皆さんサインをいただきながら手にしていかれました
あなたは どのカラヴァッジョの絵がお好きですか?
本は こちら
開催のお知らせは こちら
素晴らしい講演会を開催してくださいましたイタリア文化会館様に心よりお礼申し上げます
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
特別展 レオナルド×ミケランジェロ展開催中です(2017.10.5~11.23)@岐阜市歴史博物館
織田信長公岐阜入城・岐阜命名450年記念特別協賛事業
特別展 レオナルド×ミケランジェロ展が開催中です
2017年10月5日(木)~11月23日(木・祝)
岐阜市歴史博物館は こちら
15世紀イタリアで画家として才能を発揮し、建築、化学、解剖学の分野にまで関心を広げ「万能人」と呼ばれたレオナルド・ダ・ヴィンチ。
10代から頭角を現し「神のごとき」と称された世紀の天才彫刻家ミケランジェロ・ブオナローティ。
本展は、芸術家の力量を示すうえで最も重要とされ、巨匠の手の動きや対象を見つめるまなざしを直接感じることのできる自筆素描画作品を中心に、ライバルとも評される両者の芸術を対比する日本初の展覧会です。
レオナルドの「最も美しい」とされる素描〈少女の頭部〉や、ミケランジェロが手掛けた日本初公開の等身大のキリスト像をはじめ、フィレンツェ カーサ・ブオナローティやトリノ王立図書館所蔵品を中心に素描画、油彩画、大理石像、書簡など約65点が一堂に会します。
今なお世界の芸術に影響を与える、二人の天才。その息吹と鼓動を会場でご体感ください。
詳しくは こちら
* ダビンチの《 髭のある男性頭部(チェーザレ・ボルジャ?)》は あのチェーザレ・ボルジャ??興味深いです!
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
織田信長公岐阜入城・岐阜命名450年記念特別協賛事業
特別展 レオナルド×ミケランジェロ展が開催中です
2017年10月5日(木)~11月23日(木・祝)
岐阜市歴史博物館は こちら
15世紀イタリアで画家として才能を発揮し、建築、化学、解剖学の分野にまで関心を広げ「万能人」と呼ばれたレオナルド・ダ・ヴィンチ。
10代から頭角を現し「神のごとき」と称された世紀の天才彫刻家ミケランジェロ・ブオナローティ。
本展は、芸術家の力量を示すうえで最も重要とされ、巨匠の手の動きや対象を見つめるまなざしを直接感じることのできる自筆素描画作品を中心に、ライバルとも評される両者の芸術を対比する日本初の展覧会です。
レオナルドの「最も美しい」とされる素描〈少女の頭部〉や、ミケランジェロが手掛けた日本初公開の等身大のキリスト像をはじめ、フィレンツェ カーサ・ブオナローティやトリノ王立図書館所蔵品を中心に素描画、油彩画、大理石像、書簡など約65点が一堂に会します。
今なお世界の芸術に影響を与える、二人の天才。その息吹と鼓動を会場でご体感ください。
詳しくは こちら
* ダビンチの《 髭のある男性頭部(チェーザレ・ボルジャ?)》は あのチェーザレ・ボルジャ??興味深いです!
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
2017 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展が開催されます(2017.7.1~8.13)@板橋区立美術館
今年もまたボローニャ国際絵本原画展が開催されます:
於 板橋区立美術館
会 期:2017年7月1日(土)〜8月13日(日)
開館時間:9時30分~17時(入館は16時30分まで)
休 館 日:月曜日(7月17日は祝日のため開館し、翌日休館)
主 催:板橋区立美術館、一般社団法人日本国際児童図書評議会(JBBY)
世界でも最大級の規模を誇る絵本原画コンクールとして知られる「ボローニャ国際絵本原画展」 51回目となる2017年に入選した26か国75作家の作品全点を展示します
会期中には、絵本に関するさまざまなイベントも予定しています
ボローニャ・チルドレンズ・ブックフェアとボローニャ国際絵本原画展
イタリアの古都ボローニャで毎年春に開催される児童書専門の見本市「ボローニャ・チルドレンズ・ブックフェア」は、版権の売買のみならず、児童書の新たな企画を生み出す場として、50年以上の歴史を誇ります。今年も世界各地から1,000以上の出版社が出展し、たくさんの来場者でにぎわいました。
このブックフェアに伴って行われる「ボローニャ国際絵本原画展」は、新人イラストレーターの登竜門としても知られ、本展をきっかけに多くの絵本作家が生まれています。その魅力は、実験的な試みを積極的に受け入れ、多様な絵本表現が見られることです。
国籍の異なる5人の審査員は毎年入れ替わり、応募作品は 有名作家の作品も新人の作品も同じテーブルに並べられて審査されます。
今年は過去最多となる3,368(61か国)の応募があり、26か国75人(組)が入選しました。板橋区立美術館ではその全作品を紹介します。
特別展示1 フアン・パロミノ
メキシコの絵本作家フアン・パロミノ(Juan Palomino)をご紹介します。パロミノは、2016年にボローニャ展に入選し、同時に「ボローニャ・SM出版賞」を受賞した注目の作家です。受賞を記念して刊行された新作絵本「はじまりの前に」(Antes del primer día)は、マヤの神話をもとにしたお話です。世界や動物、人間がどのように作られたのか、壮大な物語を描いた17枚の原画を展示します。
特別展示2 見て めくって 感じる 日本の絵本
今年のブックフェアでは、日本語を知らない読者も楽しめるという観点で選書された約50冊の日本の絵本を展示するブースが評判を呼びました。
板橋区立美術館ではこれらの絵本を紹介するとともに、連続講座「夏の教室」でこのテーマを掘り下げます。赤ちゃん絵本からノンフィクション絵本まで、言語の壁を越えて伝わる新しい日本の絵本の魅力をお楽しみください。
関連イベント
本展期間中、講演会やワークショップなど、絵本に関する多数のイベントを開催します。
講演会
◆ 「ボローニャ展入選者たちに聞く」
2017年7月1日(土) 14:00~15:30
講師:綾野本汰、オオノ・マユミ、コクマイトヨヒコ、古郡加奈子、山本まもる、渡辺アンヤラット
◆ 「イタリア人と日本人、絵本をどう料理する?—フュージョン絵本の制作過程」
2017年7月8日(土)14:00~15:30
講師:ガブリエレ・レバリアーティ(麗澤大学講師)
◆ 「20世紀の美術館建築」
2017年7月9日(日)14:00〜15:30
講師:山名善之(東京理科大学教授)
◆ 「『ぼーると ぼくと くも』と一緒に、ボローニャ・ブックフェアに行ってみた!」
2017年7月15日(土)14:00~15:30
講師:加藤休ミ(クレヨン絵本作家)・兼森理恵(らいおんbooks編集部)
◆ 「初受賞で初海外」
2017年7月22日(土) 14:00~15:30
講師:ヨシタケシンスケ(絵本作家)・若月眞知子(ブロンズ新社代表)
◆ 「ぼくの仕事」
2017年7月30日(日) 14:00~15:30
講師:スティーヴン・グアルナッチャ(イラストレーター、デザイナー)
◆ 「2017ボローニャ・ブックフェア総復習」
2017年8月12日(土) 14:00~15:30
講師:広松由希子(絵本評論家)・松岡希代子(板橋区立美術館副館長)
講座
◆ 第20回 夏のアトリエ「本でなければならない本」
2017年7月25日(火)~29日(土)の5日間 10:00〜16:00
講師:スティーヴン・グアルナッチャ(イラストレーター、デザイナー)
◆ 第14回 夏の教室「絵で読む、感じる 日本の絵本」
2017年8月4日(金)・5日(土)の2日連続 10:30〜17:00
広松由希子(絵本評論家)、きたむらさとし(絵本作家)、佐々木紅(福音館書店編集部)、土居安子(大阪国際児童文学振興財団主任専門員)、村山純子(エディトリアルデザイナー)、児島なおみ(絵本作家)
◆ 第9回 ティーンズ 絵本のアトリエ
2017年8月3日(木)、10日(木)の2日間 10:00~15:00
講師:宮崎詞美(横浜美術大学准教授)
子どもむけ
◆ 一時保育
2017年7月6日(木)10:00~12:00
◆ ひよこアトリエ・たぬきアトリエ
2017年7月2日(日)10:00〜12:00 ひよこアトリエ/14:00〜16:00 たぬきアトリエ
「数字スタンプのちいさな絵本」むらかみひとみ(絵本作家)
2017年8月6日(日)10:00〜12:00 ひよこアトリエ/14:00〜16:00 たぬきアトリエ
「まっしろ!ふわふわ!くもをつくろう!」加藤休ミ(クレヨン絵本作家)
◆ しかけ絵本をつくろう– 紙箱でポップアップ!-
2017年8月8日(火)、9日(水)、11日(金・祝)の3日間 14:00~16:00
講師:岡村志満子(グラフィックデザイナー)
くわしくはこちら
カフェ・ボローニャ Café Bologna
ボローニャ展の会期限定で、手作りのパンが自慢のカフェがオープンします。洋書など関連絵本が充実したブックショップも併設。
会期中毎日OPEN!(10:30〜17:00 ラストオーダーは16:30)
夏はぐるーっと絵本展めぐり
夏に絵本展を開催する他館と共に入館料の相互割引を行います。
くわしくは こちら
ボローニャ展 関連企画
都内各地で入選者などによる関連展示が行われます。
くわしくは こちら
ボローニャ展ポスターの話
板橋区立美術館のボローニャ国際絵本原画展のポスターの絵は、毎年さまざまなアーティストによる描き下ろしです。今年は、今回の入選作家・古郡加奈子(ふるごおりかなこ)さんが、ブックフェアと板橋区立美術館のにぎわいを1枚の絵にしてくださいました。
さまざまな登場人物やボローニャの町の名所もたくさん描き込まれています。
開催のお知らせは こちら
このお知らせを書くと あぁ夏だな~ と感じます...
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
今年もまたボローニャ国際絵本原画展が開催されます:
於 板橋区立美術館
会 期:2017年7月1日(土)〜8月13日(日)
開館時間:9時30分~17時(入館は16時30分まで)
休 館 日:月曜日(7月17日は祝日のため開館し、翌日休館)
主 催:板橋区立美術館、一般社団法人日本国際児童図書評議会(JBBY)
世界でも最大級の規模を誇る絵本原画コンクールとして知られる「ボローニャ国際絵本原画展」 51回目となる2017年に入選した26か国75作家の作品全点を展示します
会期中には、絵本に関するさまざまなイベントも予定しています
ボローニャ・チルドレンズ・ブックフェアとボローニャ国際絵本原画展
イタリアの古都ボローニャで毎年春に開催される児童書専門の見本市「ボローニャ・チルドレンズ・ブックフェア」は、版権の売買のみならず、児童書の新たな企画を生み出す場として、50年以上の歴史を誇ります。今年も世界各地から1,000以上の出版社が出展し、たくさんの来場者でにぎわいました。
このブックフェアに伴って行われる「ボローニャ国際絵本原画展」は、新人イラストレーターの登竜門としても知られ、本展をきっかけに多くの絵本作家が生まれています。その魅力は、実験的な試みを積極的に受け入れ、多様な絵本表現が見られることです。
国籍の異なる5人の審査員は毎年入れ替わり、応募作品は 有名作家の作品も新人の作品も同じテーブルに並べられて審査されます。
今年は過去最多となる3,368(61か国)の応募があり、26か国75人(組)が入選しました。板橋区立美術館ではその全作品を紹介します。
特別展示1 フアン・パロミノ
メキシコの絵本作家フアン・パロミノ(Juan Palomino)をご紹介します。パロミノは、2016年にボローニャ展に入選し、同時に「ボローニャ・SM出版賞」を受賞した注目の作家です。受賞を記念して刊行された新作絵本「はじまりの前に」(Antes del primer día)は、マヤの神話をもとにしたお話です。世界や動物、人間がどのように作られたのか、壮大な物語を描いた17枚の原画を展示します。
特別展示2 見て めくって 感じる 日本の絵本
今年のブックフェアでは、日本語を知らない読者も楽しめるという観点で選書された約50冊の日本の絵本を展示するブースが評判を呼びました。
板橋区立美術館ではこれらの絵本を紹介するとともに、連続講座「夏の教室」でこのテーマを掘り下げます。赤ちゃん絵本からノンフィクション絵本まで、言語の壁を越えて伝わる新しい日本の絵本の魅力をお楽しみください。
関連イベント
本展期間中、講演会やワークショップなど、絵本に関する多数のイベントを開催します。
講演会
◆ 「ボローニャ展入選者たちに聞く」
2017年7月1日(土) 14:00~15:30
講師:綾野本汰、オオノ・マユミ、コクマイトヨヒコ、古郡加奈子、山本まもる、渡辺アンヤラット
◆ 「イタリア人と日本人、絵本をどう料理する?—フュージョン絵本の制作過程」
2017年7月8日(土)14:00~15:30
講師:ガブリエレ・レバリアーティ(麗澤大学講師)
◆ 「20世紀の美術館建築」
2017年7月9日(日)14:00〜15:30
講師:山名善之(東京理科大学教授)
◆ 「『ぼーると ぼくと くも』と一緒に、ボローニャ・ブックフェアに行ってみた!」
2017年7月15日(土)14:00~15:30
講師:加藤休ミ(クレヨン絵本作家)・兼森理恵(らいおんbooks編集部)
◆ 「初受賞で初海外」
2017年7月22日(土) 14:00~15:30
講師:ヨシタケシンスケ(絵本作家)・若月眞知子(ブロンズ新社代表)
◆ 「ぼくの仕事」
2017年7月30日(日) 14:00~15:30
講師:スティーヴン・グアルナッチャ(イラストレーター、デザイナー)
◆ 「2017ボローニャ・ブックフェア総復習」
2017年8月12日(土) 14:00~15:30
講師:広松由希子(絵本評論家)・松岡希代子(板橋区立美術館副館長)
講座
◆ 第20回 夏のアトリエ「本でなければならない本」
2017年7月25日(火)~29日(土)の5日間 10:00〜16:00
講師:スティーヴン・グアルナッチャ(イラストレーター、デザイナー)
◆ 第14回 夏の教室「絵で読む、感じる 日本の絵本」
2017年8月4日(金)・5日(土)の2日連続 10:30〜17:00
広松由希子(絵本評論家)、きたむらさとし(絵本作家)、佐々木紅(福音館書店編集部)、土居安子(大阪国際児童文学振興財団主任専門員)、村山純子(エディトリアルデザイナー)、児島なおみ(絵本作家)
◆ 第9回 ティーンズ 絵本のアトリエ
2017年8月3日(木)、10日(木)の2日間 10:00~15:00
講師:宮崎詞美(横浜美術大学准教授)
子どもむけ
◆ 一時保育
2017年7月6日(木)10:00~12:00
◆ ひよこアトリエ・たぬきアトリエ
2017年7月2日(日)10:00〜12:00 ひよこアトリエ/14:00〜16:00 たぬきアトリエ
「数字スタンプのちいさな絵本」むらかみひとみ(絵本作家)
2017年8月6日(日)10:00〜12:00 ひよこアトリエ/14:00〜16:00 たぬきアトリエ
「まっしろ!ふわふわ!くもをつくろう!」加藤休ミ(クレヨン絵本作家)
◆ しかけ絵本をつくろう– 紙箱でポップアップ!-
2017年8月8日(火)、9日(水)、11日(金・祝)の3日間 14:00~16:00
講師:岡村志満子(グラフィックデザイナー)
くわしくはこちら
カフェ・ボローニャ Café Bologna
ボローニャ展の会期限定で、手作りのパンが自慢のカフェがオープンします。洋書など関連絵本が充実したブックショップも併設。
会期中毎日OPEN!(10:30〜17:00 ラストオーダーは16:30)
夏はぐるーっと絵本展めぐり
夏に絵本展を開催する他館と共に入館料の相互割引を行います。
くわしくは こちら
ボローニャ展 関連企画
都内各地で入選者などによる関連展示が行われます。
くわしくは こちら
ボローニャ展ポスターの話
板橋区立美術館のボローニャ国際絵本原画展のポスターの絵は、毎年さまざまなアーティストによる描き下ろしです。今年は、今回の入選作家・古郡加奈子(ふるごおりかなこ)さんが、ブックフェアと板橋区立美術館のにぎわいを1枚の絵にしてくださいました。
さまざまな登場人物やボローニャの町の名所もたくさん描き込まれています。
開催のお知らせは こちら
このお知らせを書くと あぁ夏だな~ と感じます...
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
「レオナルド・ダ・ヴィンチ×ミケランジェロ展」が開催中です(2017.6.17~9.24)@三菱一号館美術館
宿命の対決!
失われた作品が追随者によって伝えられる - 『レダと白鳥』に見る二人の対比
15世紀イタリアで画家として才能を発揮し、建築、科学、解剖学の分野にまで関心を広げ「万能人」と呼ばれたレオナルド・ダ・ヴィンチ。
10代から頭角を現し「神のごとき」と称された世紀の天才彫刻家ミケランジェロ・ブオナローティ。
本展は、芸術家の力量を示す上で最も重要とされ、全ての創造の源である素描(ディゼーニョ)に秀でた2人を対比する日本初の展覧会です。
素描のほかに油彩画、彫刻、手稿、書簡など、トリノ王立図書館やカーサ・ブオナローティ所蔵品を中心におよそ65点が一堂に会します。(うち日本初公開作品を含む。)
「最も美しい」素描とされる、レオナルド作《少女の頭部/〈岩窟の聖母〉の天使のための習作》と、ミケランジェロ作《〈レダと白鳥〉の頭部のための習作》を間近で見比べる貴重な機会となります。
於 三菱一号館美術館 (東京駅5分、他)
会期:2017年6月17日(土)~9月24日(日)
開館時間:10:00~18:00(祝日を除く金曜、第2水曜、会期最終週平日は20:00まで)※入館は閉館の30分前まで
休館日:月曜休館(但し、祝日は開館)
ミケランジェロ・ブオナローティ(未完作品、17世紀の彫刻家の手で完成)《十字架を持つキリスト(ジュスティニアーニのキリスト)》が、7月11日(火)から9月24日(日)まで公開されることに決まりました。
詳しくは こちら
* 情報をいただきましたlci様にお礼申し上げます
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
宿命の対決!
失われた作品が追随者によって伝えられる - 『レダと白鳥』に見る二人の対比
15世紀イタリアで画家として才能を発揮し、建築、科学、解剖学の分野にまで関心を広げ「万能人」と呼ばれたレオナルド・ダ・ヴィンチ。
10代から頭角を現し「神のごとき」と称された世紀の天才彫刻家ミケランジェロ・ブオナローティ。
本展は、芸術家の力量を示す上で最も重要とされ、全ての創造の源である素描(ディゼーニョ)に秀でた2人を対比する日本初の展覧会です。
素描のほかに油彩画、彫刻、手稿、書簡など、トリノ王立図書館やカーサ・ブオナローティ所蔵品を中心におよそ65点が一堂に会します。(うち日本初公開作品を含む。)
「最も美しい」素描とされる、レオナルド作《少女の頭部/〈岩窟の聖母〉の天使のための習作》と、ミケランジェロ作《〈レダと白鳥〉の頭部のための習作》を間近で見比べる貴重な機会となります。
於 三菱一号館美術館 (東京駅5分、他)
会期:2017年6月17日(土)~9月24日(日)
開館時間:10:00~18:00(祝日を除く金曜、第2水曜、会期最終週平日は20:00まで)※入館は閉館の30分前まで
休館日:月曜休館(但し、祝日は開館)
ミケランジェロ・ブオナローティ(未完作品、17世紀の彫刻家の手で完成)《十字架を持つキリスト(ジュスティニアーニのキリスト)》が、7月11日(火)から9月24日(日)まで公開されることに決まりました。
詳しくは こちら
* 情報をいただきましたlci様にお礼申し上げます
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
Giovanni先生の写真展に行きサルデーニャ・シチリアの景色に包まれました(2017.6.17)@京橋アイランドギャラリー(6.25まで開催)
サルデーニャ出身のGiovanni先生が シチリアとサルデーニャ等で写した写真の展示会に2日目に早速行ってきました!! 出身地のサッサリでも写真展示会があったそうです!!
Giovanni Piliarvu 写真展 Isole
遠い島、古い島。島の風はいにしえの話を語って、岩肌を刻んで波を動かす。
シチリアとサルデーニャの静かな物語が風景の上に舞い降りると、
古代の地中海の薫りが漂う。
その薫りはそこで過ごした瞬間と結ばれている。
その場所は空からの光と色で刻まれている。
その空は地中海の一番大きな二つの島を上から見つめている。
遥か遠い昔から。 / Giovanni Piliarvu
ジョバンニが生まれ育ったサルデーニャ島は、イタリアでも屈指の美しさを誇るのだと自ら語る。古い歴史と大自然が織りなす壮大な風景と対話をしながら、一枚一枚丁寧に写し撮られた作品は、まるで映画の一場面のようだ。
出品作品はサルデーニャ島を中心に、イタリア各地の美しい風景写真を25点展示販売いたします
会 期 2017年6月16日(金)-25日日) 11:00-19:00
入場無料 会期中無休
会 場 Island Gallery
東京都中央区京橋1-5-5 B1 tel / 03-3517-2125 (京橋駅そば、東京駅八重洲南口)
協 賛 マルマン株式会社 Canson Infinity
写真展は こちら
* * *
在廊時間を狙っていったのですが 道にまよってしまい(笑) Giovanni先生不在中に写真展を観に行きました そのあとで大崎まで知人の出品した日本剪画美術展に足を延ばし 剪画を見たり講評を聞いてきました この時期展覧会が多いですね~
明日また吉祥寺のLCI文化セミナーのあとで行けたら行って どの写真にしようか決めてきたいのですが...飾る場所が~(笑)
2日目に行ったのにもうたくさんの赤いシールが貼られていてビックリ!! それが夕陽(tramonto)のシチリアの海辺の写真が吸い寄せられるように美しくて...シールもすでにたくさん💛
現地をよく知るGiovanni氏ならではの写真なのだそうです 何年に一度かの天気や波の具合がフィットした瞬間をとらえた写真もあるのです...迷います...どれにしようか
額入りのと額なし(自分で額をつけてもよし) 最小はA4版で1万円を切るので お店とかでなくとも 個人宅にも飾れそうです ← なので迷うわけ(笑)
身近にイタリアの風景を置いておきたい方 また今後売れ出す前の今のうちにという方 ぜひご覧になってみてください(^_^)v 2回目の個展開催です♪
イタリア語のテキストばかりにお金を使ってきた私も ここでようやくイタリアの風景写真を手元に置こうかと... ← だから飾る場所だってば~(笑)
先生の在廊時間や絵の説明は こちら
追加(6/18)
というわけでLCI文化セミナーのあとでまた行って とうとう生まれて初めて買いましたGiovanni先生のシチリアの写真!! 世界遺産にもなった(Val di Not/2002年登録)のラグーサの町 シクリ/Scicliの夜明け 名付けて”Bergamotto”!! 夕べこの景色が瞼に浮かび やはりこれだと感じていた 今まで絵は旅先で買ったけど写真を買うのは実は初めて♡

日曜なので人が多く 次々と先生の生徒さん達が写真を買ってくださり いい生徒さんたちだなぁ~(#^.^#) 先生の教えていらっしゃる高円寺piazzaItaliaの生徒さんたちはとても気さくで楽しい方たちです 先生のお父様やMattia先生とも色々お話できました♪ セミナー出てよかった!
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
サルデーニャ出身のGiovanni先生が シチリアとサルデーニャ等で写した写真の展示会に2日目に早速行ってきました!! 出身地のサッサリでも写真展示会があったそうです!!
Giovanni Piliarvu 写真展 Isole
遠い島、古い島。島の風はいにしえの話を語って、岩肌を刻んで波を動かす。
シチリアとサルデーニャの静かな物語が風景の上に舞い降りると、
古代の地中海の薫りが漂う。
その薫りはそこで過ごした瞬間と結ばれている。
その場所は空からの光と色で刻まれている。
その空は地中海の一番大きな二つの島を上から見つめている。
遥か遠い昔から。 / Giovanni Piliarvu
ジョバンニが生まれ育ったサルデーニャ島は、イタリアでも屈指の美しさを誇るのだと自ら語る。古い歴史と大自然が織りなす壮大な風景と対話をしながら、一枚一枚丁寧に写し撮られた作品は、まるで映画の一場面のようだ。
出品作品はサルデーニャ島を中心に、イタリア各地の美しい風景写真を25点展示販売いたします
会 期 2017年6月16日(金)-25日日) 11:00-19:00
入場無料 会期中無休
会 場 Island Gallery
東京都中央区京橋1-5-5 B1 tel / 03-3517-2125 (京橋駅そば、東京駅八重洲南口)
協 賛 マルマン株式会社 Canson Infinity
写真展は こちら
* * *
在廊時間を狙っていったのですが 道にまよってしまい(笑) Giovanni先生不在中に写真展を観に行きました そのあとで大崎まで知人の出品した日本剪画美術展に足を延ばし 剪画を見たり講評を聞いてきました この時期展覧会が多いですね~
明日また吉祥寺のLCI文化セミナーのあとで行けたら行って どの写真にしようか決めてきたいのですが...飾る場所が~(笑)
2日目に行ったのにもうたくさんの赤いシールが貼られていてビックリ!! それが夕陽(tramonto)のシチリアの海辺の写真が吸い寄せられるように美しくて...シールもすでにたくさん💛
現地をよく知るGiovanni氏ならではの写真なのだそうです 何年に一度かの天気や波の具合がフィットした瞬間をとらえた写真もあるのです...迷います...どれにしようか
額入りのと額なし(自分で額をつけてもよし) 最小はA4版で1万円を切るので お店とかでなくとも 個人宅にも飾れそうです ← なので迷うわけ(笑)
身近にイタリアの風景を置いておきたい方 また今後売れ出す前の今のうちにという方 ぜひご覧になってみてください(^_^)v 2回目の個展開催です♪
イタリア語のテキストばかりにお金を使ってきた私も ここでようやくイタリアの風景写真を手元に置こうかと... ← だから飾る場所だってば~(笑)
先生の在廊時間や絵の説明は こちら
追加(6/18)
というわけでLCI文化セミナーのあとでまた行って とうとう生まれて初めて買いましたGiovanni先生のシチリアの写真!! 世界遺産にもなった(Val di Not/2002年登録)のラグーサの町 シクリ/Scicliの夜明け 名付けて”Bergamotto”!! 夕べこの景色が瞼に浮かび やはりこれだと感じていた 今まで絵は旅先で買ったけど写真を買うのは実は初めて♡

日曜なので人が多く 次々と先生の生徒さん達が写真を買ってくださり いい生徒さんたちだなぁ~(#^.^#) 先生の教えていらっしゃる高円寺piazzaItaliaの生徒さんたちはとても気さくで楽しい方たちです 先生のお父様やMattia先生とも色々お話できました♪ セミナー出てよかった!
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
「ヴェネツィアングラス二千年の旅 ~古代ガラスの源流にみるロマン~」展開催のお知らせ(2017.4.29~11.26)@箱根ガラスの森美術館
2017年特別企画展 ─ヴェネチアン・グラス二千年の旅展─
会期:2017年4月29日(祝土)~2017年11月26日(日)まで 会期中無休
古代ローマ帝国時代 ガラス製法は飛躍的な発展を迎えました
パイプの先に熔けたガラスを巻き付け 空気を吹き込んで制作する吹きガラスの技法が発明され 貴重品だったガラスを 多くの人々が手にすることができるようになりました
高度に発展したガラス製法はローマ帝国の衰退後 ヴェネチアのガラス職人たちの情熱と技術で復活を遂げます
職人たちは古代ガラスの製法や 形体の復元に留まらず 創意工夫を重ねて繊細華麗な作品に昇華させました
長年の風化の影響で銀化し 虹色の輝きを放つようになった古代ガラスと その影響を受け発展を遂げたヴェネチアン・グラスを展示し ガラスの歩んだ時空を超えた旅を辿ります
1章 ガラスの誕生と多様なガラス器の登場
初期のガラス器は 固まった後に中の粘土を掻き出して作る「コア・グラス」や 模様入りのガラス片同士を熔着する「モザイク・グラス」などが作られました
これらは 一部の特権階級しか所持することができない貴重品でした
ガラス製法の一大転機が訪れたのは 古代ローマ帝国領内のシリアで 「宙吹き技法」が発明され 量産が可能になってからです
その一方で「モザイク・グラス」などの装飾されたガラス器は 富裕層のステータスや東方世界との貿易のため アレクサンドリアなどで作り続けられていました
技術の革新によりガラスの価値は 日常品と貴重品に二極化されていきました
2章 古代ガラス技法の継承とヴェネチアン・グラスの黄金時代
西ローマ帝国の消滅後 古代ローマのガラス製法は一部失われましたが 宙吹き 熔着装飾などのガラス製法は 東地中海地域 シリア・パレスティナ地方などで引き継がれます
さらに東のササン朝ペルシャでは精巧な「切子碗」が生まれ 西はコンスタンティノポリスや 日本の正倉院にも伝来していたそうです
中東地域で継承されたガラス製法は 7世紀以後「イスラム・グラス」として開花しますが やがて存亡の危機に瀕します
既にヴェネチアは 1291年の法令により ガラス職人をムラーノ島に強制移住させ ガラス製法の流失を防ぐ保護政策を打ち出しました
そしてこのシリアの争乱から逃れてきたガラス職人を受け入れ ヴェネチアン・グラスはさらなる発展を迎えました
3章 古代への憧れと、再現される古代ガラスの技法
16世紀に黄金時代を迎えたヴェネチアも 18世紀末から苦難の時代が到来しました
1797年のナポレオンのヴェネチア侵攻後の仏墺間の条約により ヴェネチア共和国はオーストリア領となり ボヘミアやイギリスのガラス産業の台頭や 輸出入に伴う関税などが重くのしかかり ムラーノ島では18世紀末から不況を打破できるほどの大きな技術的進歩もなくなりました
ガラス職人の失業率が増える中 復活の兆しが見え始めたのは 「古代のガラス」に対する関心の強まりと 往時の技術の復活に取り組もうとする人々の登場でした
18世紀中頃から始まった「ポンペイ遺跡の発掘」や 1870年代の「トロイ遺跡の発掘」による古代文明への注目は ヴェネチアのガラス職人たちにも広がりました
以後 現在まで 古代のガラスの形態や技法などからの着想を得て さらに創意工夫を施したヴェネチアン・グラスが多数制作されているのです
ヴェネツィアングラス二千年の旅 ~古代ガラスの源流にみるロマン~」展は こちら
箱根ガラスの森美術館は こちら
ツアーで行ったことがありますが きれいでした~(*^^*)

美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
2017年特別企画展 ─ヴェネチアン・グラス二千年の旅展─
会期:2017年4月29日(祝土)~2017年11月26日(日)まで 会期中無休
古代ローマ帝国時代 ガラス製法は飛躍的な発展を迎えました
パイプの先に熔けたガラスを巻き付け 空気を吹き込んで制作する吹きガラスの技法が発明され 貴重品だったガラスを 多くの人々が手にすることができるようになりました
高度に発展したガラス製法はローマ帝国の衰退後 ヴェネチアのガラス職人たちの情熱と技術で復活を遂げます
職人たちは古代ガラスの製法や 形体の復元に留まらず 創意工夫を重ねて繊細華麗な作品に昇華させました
長年の風化の影響で銀化し 虹色の輝きを放つようになった古代ガラスと その影響を受け発展を遂げたヴェネチアン・グラスを展示し ガラスの歩んだ時空を超えた旅を辿ります
1章 ガラスの誕生と多様なガラス器の登場
初期のガラス器は 固まった後に中の粘土を掻き出して作る「コア・グラス」や 模様入りのガラス片同士を熔着する「モザイク・グラス」などが作られました
これらは 一部の特権階級しか所持することができない貴重品でした
ガラス製法の一大転機が訪れたのは 古代ローマ帝国領内のシリアで 「宙吹き技法」が発明され 量産が可能になってからです
その一方で「モザイク・グラス」などの装飾されたガラス器は 富裕層のステータスや東方世界との貿易のため アレクサンドリアなどで作り続けられていました
技術の革新によりガラスの価値は 日常品と貴重品に二極化されていきました
2章 古代ガラス技法の継承とヴェネチアン・グラスの黄金時代
西ローマ帝国の消滅後 古代ローマのガラス製法は一部失われましたが 宙吹き 熔着装飾などのガラス製法は 東地中海地域 シリア・パレスティナ地方などで引き継がれます
さらに東のササン朝ペルシャでは精巧な「切子碗」が生まれ 西はコンスタンティノポリスや 日本の正倉院にも伝来していたそうです
中東地域で継承されたガラス製法は 7世紀以後「イスラム・グラス」として開花しますが やがて存亡の危機に瀕します
既にヴェネチアは 1291年の法令により ガラス職人をムラーノ島に強制移住させ ガラス製法の流失を防ぐ保護政策を打ち出しました
そしてこのシリアの争乱から逃れてきたガラス職人を受け入れ ヴェネチアン・グラスはさらなる発展を迎えました
3章 古代への憧れと、再現される古代ガラスの技法
16世紀に黄金時代を迎えたヴェネチアも 18世紀末から苦難の時代が到来しました
1797年のナポレオンのヴェネチア侵攻後の仏墺間の条約により ヴェネチア共和国はオーストリア領となり ボヘミアやイギリスのガラス産業の台頭や 輸出入に伴う関税などが重くのしかかり ムラーノ島では18世紀末から不況を打破できるほどの大きな技術的進歩もなくなりました
ガラス職人の失業率が増える中 復活の兆しが見え始めたのは 「古代のガラス」に対する関心の強まりと 往時の技術の復活に取り組もうとする人々の登場でした
18世紀中頃から始まった「ポンペイ遺跡の発掘」や 1870年代の「トロイ遺跡の発掘」による古代文明への注目は ヴェネチアのガラス職人たちにも広がりました
以後 現在まで 古代のガラスの形態や技法などからの着想を得て さらに創意工夫を施したヴェネチアン・グラスが多数制作されているのです
ヴェネツィアングラス二千年の旅 ~古代ガラスの源流にみるロマン~」展は こちら
箱根ガラスの森美術館は こちら
ツアーで行ったことがありますが きれいでした~(*^^*)

美術館・ギャラリーランキング
当サークルで「ティツィアーノ展見学会&イタリアンランチの会」を開きました(2017.2.26)@東京都美術館&Le quattro stagioni
サークルの企画で 「ティツィアーノ展見学会&イタリアンランチの会」を開きました 今回は参加者11名と大勢でした♪
日曜午前でしたが さほど混んでいなくて見やすかったです 上野の美術館は広くてその分ゆっくり見られますね♡ (年齢と共に暗い部屋での小さな字が見えなくなって...トホホ)
吉祥寺にあるLCIで ティツィアーノ展の講座を担当されていらしたArianna先生がゲストでいらしてくださり 主な絵の説明をしてくださいました
ルネッサンスのフィレンツェ派は素描重視のフレスコ画が主でレオナルド、ミケランジェロ、ラファエロ等
ヴェネツィア派は色彩重視の油彩画が主でティツィアーノ、ティントレット、ヴェロネーゼ等がおり またヴェネツィアは湿度が高いためフレスコ画は向いていません
今回の展覧会では ティツィアーノ作品は7作品 あとはヴェロネーゼ ティントレット ベッリーニ(ティツィアーノの師匠)ecc... ティツィアーノ以外の画家の絵も見られるからこそ 彼の絵の素晴らしさが際立つのですね
最初は「復活のキリスト」(1510-12年、ウフィツィ美術館) これは20才頃の作品でとても勇壮な絵です
ともかく「フローラ」(1515年頃、ウフィツィ美術館)の肌の美しさ モデルも若いし画家も若いし...左手のチョキの形は婚礼・婚約を表すそうです cortigiana(高級娼婦)がモデルともされています
ちょうどこの日の朝「日曜美術館」でティツィアーノ展の特集をやっていたのですが この中に出てきたボッティチェリの「春」のフローラよりも このティツィアーノの「フローラ」の方が若くてふくよかですね
「ダナエ」(1544-46年,カポディモンテ美術館)は ファルネーゼ枢機卿が「ウルビーノのヴィーナス」(1538年頃、ウフィツィ美術館、2008年に来日)の様な裸婦像を依頼したそうです
上体をあげて足を開いているポーズがエロティックで ユピテルが黄金の雲となってダナエと交わろうとするシーンで 金貨の雨も描かれていますが これとは別に 天使ではなく老婆がその金貨の雨をエプロンで集める絵もあり 象徴的です こちらの「ダナエ」(1553,54年、プラド美術館)は フェリペ2世の依頼とのこと
当時は神話の物語を隠れみのに裸体を描いた時代で 「ダナエ」の描かれたいきさつと当時の背景を知ってから見るとまた違いますね
「教皇パウルス3世の肖像」(1543年,カポディモンテ美術館)は後期の肖像画ですが 教皇自身がティツィアーノのモデルとなって描かれた作品で 狡猾な老人の表情と ビロードの地マントの描き方が素晴らしいです ルネサンス期にここまでの筆感を表現した画家はおらず 人物を斜めに配して空間性を強調しています
晩年に描かれた「マグダラのマリア」(1567年、カボディモンテ美術館)も素晴らしかった...何回かこのテーマで描いていたそうで その中の最後の作品です 円熟の魅力ですね
これはローマのアレッサンドロ・ファルネーゼに贈られたと考えられています この表情から訴えかけるものが伝わってきますね
彼は88才と高齢で 晩年の自画像が残っています
また アンドレア・スキアヴォーネの版画もありました ヴェネツィア派の輪郭を知ることができた貴重な展覧会でした
* * *
終了後 たまたま出口でやっていた「ヴェネツィアのマスク」を被って皆で記念写真!!←ちょうどヴェネツィアのカーニバルの時期です♪

このあと上野公園を歩いて ランチはいつもの上野Le quattro stagioni ←個室です(^_^)
カンタンな総会 自己紹介や近況 そして「イタリアの世界遺産クイズ」をやり 景品は渋谷Bunkamura様からいただいた当選の景品♪ ←楽しみは皆で分け合いましょう~♡

会員さんの中にもイタリア語を頑張ってらっしゃる方 いろんな検定を受けている方もちらほら...今回はLCIのアリアンナ先生もいらしてくださり大盛況でした!!
夕方まで上野公園の中でコーヒーを飲みながら久しぶりのお喋り... このサークルも結成10年が経ちました
いつもこんな感じで楽しくやっています♪ さて翌日はベネチアンガラスフュージング体験です!!
「ティツィアーノとヴェネツィア派展」は こちら (東京都美術館/4月2日まで)
次は「Mucha(ミュシャ)展」です (2017.3.8~6.5)@国立新美術館
上野のイタリアン Le quattro stagioniは こちら
 美術館・ギャラリー ブログランキングへ
美術館・ギャラリー ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村
サークルの企画で 「ティツィアーノ展見学会&イタリアンランチの会」を開きました 今回は参加者11名と大勢でした♪
日曜午前でしたが さほど混んでいなくて見やすかったです 上野の美術館は広くてその分ゆっくり見られますね♡ (年齢と共に暗い部屋での小さな字が見えなくなって...トホホ)
吉祥寺にあるLCIで ティツィアーノ展の講座を担当されていらしたArianna先生がゲストでいらしてくださり 主な絵の説明をしてくださいました
ルネッサンスのフィレンツェ派は素描重視のフレスコ画が主でレオナルド、ミケランジェロ、ラファエロ等
ヴェネツィア派は色彩重視の油彩画が主でティツィアーノ、ティントレット、ヴェロネーゼ等がおり またヴェネツィアは湿度が高いためフレスコ画は向いていません
今回の展覧会では ティツィアーノ作品は7作品 あとはヴェロネーゼ ティントレット ベッリーニ(ティツィアーノの師匠)ecc... ティツィアーノ以外の画家の絵も見られるからこそ 彼の絵の素晴らしさが際立つのですね
最初は「復活のキリスト」(1510-12年、ウフィツィ美術館) これは20才頃の作品でとても勇壮な絵です
ともかく「フローラ」(1515年頃、ウフィツィ美術館)の肌の美しさ モデルも若いし画家も若いし...左手のチョキの形は婚礼・婚約を表すそうです cortigiana(高級娼婦)がモデルともされています
ちょうどこの日の朝「日曜美術館」でティツィアーノ展の特集をやっていたのですが この中に出てきたボッティチェリの「春」のフローラよりも このティツィアーノの「フローラ」の方が若くてふくよかですね
「ダナエ」(1544-46年,カポディモンテ美術館)は ファルネーゼ枢機卿が「ウルビーノのヴィーナス」(1538年頃、ウフィツィ美術館、2008年に来日)の様な裸婦像を依頼したそうです
上体をあげて足を開いているポーズがエロティックで ユピテルが黄金の雲となってダナエと交わろうとするシーンで 金貨の雨も描かれていますが これとは別に 天使ではなく老婆がその金貨の雨をエプロンで集める絵もあり 象徴的です こちらの「ダナエ」(1553,54年、プラド美術館)は フェリペ2世の依頼とのこと
当時は神話の物語を隠れみのに裸体を描いた時代で 「ダナエ」の描かれたいきさつと当時の背景を知ってから見るとまた違いますね
「教皇パウルス3世の肖像」(1543年,カポディモンテ美術館)は後期の肖像画ですが 教皇自身がティツィアーノのモデルとなって描かれた作品で 狡猾な老人の表情と ビロードの地マントの描き方が素晴らしいです ルネサンス期にここまでの筆感を表現した画家はおらず 人物を斜めに配して空間性を強調しています
晩年に描かれた「マグダラのマリア」(1567年、カボディモンテ美術館)も素晴らしかった...何回かこのテーマで描いていたそうで その中の最後の作品です 円熟の魅力ですね
これはローマのアレッサンドロ・ファルネーゼに贈られたと考えられています この表情から訴えかけるものが伝わってきますね
彼は88才と高齢で 晩年の自画像が残っています
また アンドレア・スキアヴォーネの版画もありました ヴェネツィア派の輪郭を知ることができた貴重な展覧会でした
* * *
終了後 たまたま出口でやっていた「ヴェネツィアのマスク」を被って皆で記念写真!!←ちょうどヴェネツィアのカーニバルの時期です♪

このあと上野公園を歩いて ランチはいつもの上野Le quattro stagioni ←個室です(^_^)
カンタンな総会 自己紹介や近況 そして「イタリアの世界遺産クイズ」をやり 景品は渋谷Bunkamura様からいただいた当選の景品♪ ←楽しみは皆で分け合いましょう~♡

会員さんの中にもイタリア語を頑張ってらっしゃる方 いろんな検定を受けている方もちらほら...今回はLCIのアリアンナ先生もいらしてくださり大盛況でした!!
夕方まで上野公園の中でコーヒーを飲みながら久しぶりのお喋り... このサークルも結成10年が経ちました
いつもこんな感じで楽しくやっています♪ さて翌日はベネチアンガラスフュージング体験です!!
「ティツィアーノとヴェネツィア派展」は こちら (東京都美術館/4月2日まで)
次は「Mucha(ミュシャ)展」です (2017.3.8~6.5)@国立新美術館
上野のイタリアン Le quattro stagioniは こちら






























