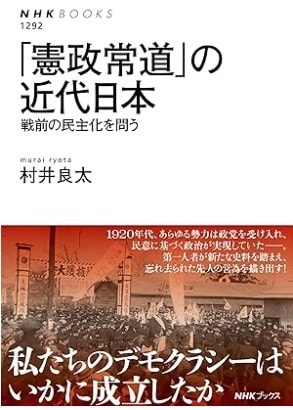
日本の強靭な側面、その水脈 非植民地化・民主主義・小作解放250210
1931年かに尾幌川中流域の農場で、小作人たちが異を主唱した。
1955年当時、畑作農家経営体数125戸ほど。道のり500メートル内外に農業経営体が存立する海岸線に位置する盆地農村。
住民の大半は開村50年を経過したばかりの<顔なじみ>。平穏な集落で<小作騒動>。
信じられぬ事実、1973年に刊行された集落を取り囲む自治体史の記載で知った。
記載したのは酔うと家人にバイオリンを持たせてきて「船頭小唄」を演奏。
のちに、この方。実は中核都市の歌人会長も務めた、なかなかの<粋人>であった。
史料は存在かもしれないが、そこは表面には出さずに、若き日の記憶で記載。
しかしすでに学部を終え、記載者を幼いころから知る筆者は即座に思った。
「農地改革、それはGHQが示した戦後5大改革の一ではあるが」「しかし、先行する動き=古作者の地主に対する発意と行動が先行してあった地域もある」。
そこから、敗戦で暖雑。そうかもしれないが、戦後改革の前提は、すでに昭和初期までに一部には顕在化していた。
その思いを更に高めと名が、野口悠紀雄氏が「戦前と戦後、繋げて考えよう」。
そんな提言異に接したtのは20世紀も末のこと。
25年2月。 「民主主義は米国のプレゼントなどではない――100年前に達成されていた日本の民主的政治体制」を読んだ。
「政党の存在意義がわからなくなるようなケース」「政党支持率が落ちても政党の存在を前提とした政治システム自体はびくともs8ない」。
そう設問し、村井良太著『「憲政常道」の近代日本 戦前の民主化を問う』( (NHKブックス 1292 250127)を紹介する。
https://mag.nhk-book.co.jp/article/67093 「NHK出版 民主主義 アメリカから」のキーワードでたどりつける。
大航海時代に植民地化を避けた戦国日本。戦後民主主義の前提に大正デモクラシー、農地改革を誘導した小作騒動発生地。
意外に強かった日本。戦前と戦後を結節する<水脈=伏流水>として記憶しておこう
1931年かに尾幌川中流域の農場で、小作人たちが異を主唱した。
1955年当時、畑作農家経営体数125戸ほど。道のり500メートル内外に農業経営体が存立する海岸線に位置する盆地農村。
住民の大半は開村50年を経過したばかりの<顔なじみ>。平穏な集落で<小作騒動>。
信じられぬ事実、1973年に刊行された集落を取り囲む自治体史の記載で知った。
記載したのは酔うと家人にバイオリンを持たせてきて「船頭小唄」を演奏。
のちに、この方。実は中核都市の歌人会長も務めた、なかなかの<粋人>であった。
史料は存在かもしれないが、そこは表面には出さずに、若き日の記憶で記載。
しかしすでに学部を終え、記載者を幼いころから知る筆者は即座に思った。
「農地改革、それはGHQが示した戦後5大改革の一ではあるが」「しかし、先行する動き=古作者の地主に対する発意と行動が先行してあった地域もある」。
そこから、敗戦で暖雑。そうかもしれないが、戦後改革の前提は、すでに昭和初期までに一部には顕在化していた。
その思いを更に高めと名が、野口悠紀雄氏が「戦前と戦後、繋げて考えよう」。
そんな提言異に接したtのは20世紀も末のこと。
25年2月。 「民主主義は米国のプレゼントなどではない――100年前に達成されていた日本の民主的政治体制」を読んだ。
「政党の存在意義がわからなくなるようなケース」「政党支持率が落ちても政党の存在を前提とした政治システム自体はびくともs8ない」。
そう設問し、村井良太著『「憲政常道」の近代日本 戦前の民主化を問う』( (NHKブックス 1292 250127)を紹介する。
https://mag.nhk-book.co.jp/article/67093 「NHK出版 民主主義 アメリカから」のキーワードでたどりつける。
大航海時代に植民地化を避けた戦国日本。戦後民主主義の前提に大正デモクラシー、農地改革を誘導した小作騒動発生地。
意外に強かった日本。戦前と戦後を結節する<水脈=伏流水>として記憶しておこう




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます