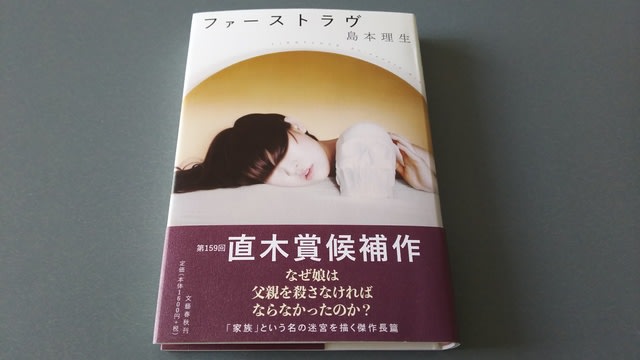
今回ご紹介するのは「ファーストラヴ」(著:島本理生)です。
-----内容-----
「動機はそちらで見つけてください」
父親を刺殺した容疑で逮捕された女子大生・聖山環菜の挑発的な台詞が世間をにぎわせていた。
臨床心理士の真壁由紀は、この事件を題材としたノンフィクションの執筆を依頼され、環菜やその周辺の人々と面会を重ねていくが……。
なぜ娘は父親を殺さなければならなかったのか?
「家族」という名の迷宮を描く傑作長篇。
第159回直木賞受賞作。
-----感想-----
当初、帯に「なぜ娘は父親を殺さなければならなかったのか?」とあり、好きな作家の新作ですが内容が恐ろしそうでこの作品は読まないでおこうと思いました。
しかし7月に選考される第159回直木賞の候補になったのを知り興味を持ちました。
「第159回直木賞候補作」と書かれ新しくなった帯の内容紹介を見ると臨床心理士の主人公が父親を刺殺した女子大生の事件に関わっていくとあり、かなり興味が強まりました。
島本理生さんは中学生の頃から臨床心理学の本をたくさん読んでいて作品にも登場することがあり、内容を見ると特にフロイトの精神分析学の本をたくさん読んでいたのではと思います。
今回は主人公が臨床心理士とあり、今日の島本理生さんを形作る重要な要素の一つ「臨床心理学」と正面から向かい合う小説になることが予想され、並々ならぬものを感じこれはぜひ読むべきだと思い、書店に行って小説を手に取りました。
スタジオまでの廊下は長くて白すぎる。
踵を鳴らしているうちに、日常が床に塵のように振り落とされて、作られた顔になっていく。
この最初の二つの文で一気に物語に引き込まれました。
特に二文目が良く、一歩歩くごとに主人公の表情が変化していくのが伝わってきて、この作品の一文一文を丁寧に読みたくなりました。
主人公は臨床心理士の真壁由紀で、物語は由紀の一人称で語られます。
冒頭では東京のスタジオで「子供が寝てから相談室」というテレビ番組の収録をしていました。
7月19日、アナウンサー志望の女子大生、聖山環菜(かんな)がキー局の二次面接の直後に父親の那雄人(なおと)を刺殺して、夕方の多摩川沿いを血まみれで歩いていたところを逮捕されます。
環菜は警察の事情聴取に「動機はそちらで見つけてください」と言っています。
由紀は新文化社という出版社から環菜の半生を臨床心理士の視点からノンフィクションにまとめることを依頼されています。
由紀は真壁我聞(がもん)と10年前の春に結婚していて、正親(まさちか)という小学四年生の子供がいます。
我聞は結婚式場のカメラマンをしていますが普段は主夫として家の中のことをしています。
夜遅くに帰宅した由紀が正親に「ちょっと!なんでまだ起きてるの」と言うのを見てこれが本来の姿なのだと思い、家に帰れば本来の姿に戻れるのを見て安心しました。
この切り替えは大事だと思います。
我聞が迦葉(かしょう)から電話がかかってきたと言います。
迦葉は我聞の弟で弁護士をしていて、由紀の反応を見て迦葉と由紀には何か因縁があるのだと思いました。
由紀のクリニックは目白通り沿いにあり、浅田七海という若い女性を相手に由紀のカウンセリングの様子が描かれています。
初対面の時、七海は自分は本来はこんなところに来るようなタイプではないと言っていました。
この強がりは初対面までの七海は心療内科に行ったり臨床心理士に話を聞いてもらったりすることを「恥ずかしいこと」と考えていて、まさか自分がそうなるとはという恥の気持ちが現れていると思われ、強がるのはよく分かります。
迦葉が環菜の国選弁護人に選ばれます。
迦葉は環菜の事件は裁判員裁判になるためどれだけ同情を買えるかが重要で、そんな時に由紀が環菜の本を書くのには反対だと言います。
また迦葉はよく軽口を言い、のらりくらりとしていて掴み所がない印象があります。
由紀は環菜と面会します。
臨床心理士としてカウンセリングの仕事に就いて今年で9年目と語っていて、大学院卒で大学は一年休学していることから今年で34歳になると分かりました。
迦葉の苗字は庵野で我聞と血はつながっておらず、我聞の両親は迦葉の伯父さん伯母さんになります。
由紀は大学院の修論を書き終えた時に妊娠し、大学卒業後に報道写真家を目指していた我聞がその夢をやめて子供を育てるから結婚しようと言います。
環菜から由紀に手紙が来て、自身のことが知りたいので本を出しても良いと綴られていました。
本人にもなぜ父親を殺したのか、自身の心が分からないようです。
また環菜の母親の昭菜には被告側の証人として出ることを許否され、検察側の証人として出ることが明らかになり、母親と娘が法廷で対立することになります。
迦葉と由紀は母親が検察側に回ったことから何かが隠されていると感じます。
迦葉はあの家庭に何が起きていたか見つけなくてはいけないと言い、さらに由紀の立場なら違う手掛かりが掴めるかも知れないと言います。
由紀は環菜に次の面会までに母親との関係や思い出を手紙にしてもらいたいと言います。
手紙から母親への心理を探るのだと思いました。
由紀が迦葉に言った「私たち、本当は協力できるほどお互いのことを許してないでしょう?」という言葉は印象的でした。
単に臨床心理士が環菜の殺人の動機に迫るだけに留まらず、由紀と迦葉にも因縁があるのが物語の緊迫感を増しています。
環菜から届いた手紙には母よりも父のことの方が多く書かれていました。
由紀との面会で環菜はずっと嘘つきと言われてきたことが明らかになり、誰に言われていたのか気になりました。
由紀は次の手紙で初恋から事件の日までの恋愛について何でも良いから教えてほしいと頼みます。
環菜が大学時代に付き合っていた賀川洋一に話を聞くと環菜は父親と仲が悪かったと言い、さらに虚言癖があると言います。
秋になり、環菜の親友の臼井香子(きょうこ)に話を聞くと香子も環菜の父親が嫌いだと言います。
父親はたまに家のアトリエで美大生の教え子達に教えていて、そのデッサンのモデルを環菜にさせていました。
さらに中学三年生の時に美大生の一人に言い寄られ、親にはお前が気を持たせたんだから責任取って自分で何とかしろと言われて落ち込んでいたことが明らかになります。
このくらいまで読んだところで、文章がこれまで読んだ作品よりシンプルな印象を持ちました。
「誰々が「○○」と語った。」といった文章がよくあり、繊細な感情や情景の表現よりもシンプルな会話の進みを重視しているように見えます。
ただし由紀が環菜を観察しながら話す時の描写は詳しく書いてあり、上手く緩急が付いていると思いました。
由紀は環菜に絵のモデルをしていた時に母親はどうしていたかを聞き、母親に注目しているのがよく分かりました。
デッサン会は必ず母親がいない土曜日の午後に行われていました。
由紀が美大生達の印象を聞くと環菜は「気持ち悪い」と言い直後に酷く取り乱し、明らかにデッサン会が環菜の精神に重大な影響を与えていたのが分かりました。
また女性が男性に酷い目に遭わされるという、臨床心理学以上に島本理生さんの作品によく見られる特徴が今回も出ていると思いました。
由紀と迦葉が病院に入院している母親に面会に行くと母親は父親の擁護と環菜を突き放すことを言い、由紀は香子と母親のデッサン会への温度差に違和感を持ちます。
環菜には自傷癖があり、由紀が環菜の腕の傷を見たことはあるかと聞くと母親は小学校に遊びに行っていた時に鶏に襲われた傷だと言い、私はこれを見て母親にかなりの不信感を持ちました。
さらに母親は環菜が精神的に追い詰められていたのも気づいていて「でも、そんなの最終的には本人がどうにかするしかないでしょう」と言い、環菜に対しては突き放すことしか言わないです。
由紀は「十代の少女のように無責任な主張」と胸中で語っていました。
環菜の出生には特殊な事情があり、そのため環菜は両親の役に立とうと必死でした。
由紀に語った「私が嘘をつくことで母は安心してました」という言葉は特に印象的でした。
父親は環菜のアナウンサー志望の就活に反対して対立していましたが、由紀は環菜が就活に反対されただけで殺人を犯すようには見えないと感じます。
父親のデッサン会に参加していた南羽澄人(すみと)に話を聞けることになります。
年末、富山に住む南羽のところに新文化社で由紀のノンフィクションを担当している辻という男と行き話を聞くと、当時のスケッチブックに環菜が描かれていました。
裸の男の背に寄りかかっていて異様な雰囲気を感じました。
由紀の母親が成人式の朝に、父親が海外出張のたびに児童買春していたことを打ち明けます。
晴れの日に水を差すことを言うのは最悪だと思います。
この母親は娘に過度に干渉する特徴があり、自身が夫のことで悩んでいるのに娘だけ晴れやかになるのが許せず、自身と同じように悩むべきだと思って言ったのだと思います。
由紀の母親への鬱屈した気持ちも印象的で、二人の親子関係がどうなるのかも気になりました。
由紀と迦葉が大学時代に仲が良かった頃の回想があり、
ある時仲が悪くなると迦葉が由紀の目の前で他の女性と仲良くしているのを見せつけたりするようになり、徹底した嫌がらせをしてきて陰湿だと思いました。
やがて由紀は我聞と付き合うようになり、二ヶ月が過ぎた晩秋の日、我聞が由紀を弟の迦葉に紹介したいと言います。
迦葉はショックを受け、これは由紀が復讐のために我聞と付き合ったと思ったのだと思います。
ただし迦葉に同情の余地はなく、人に徹底して嫌がらせをするなら自身に跳ね返ってくることも覚悟すべきです。
2月に行われる裁判まで時間が少なくなります。
母親のことをあまり語らず自身が悪いといったことばかり言う環菜を見て由紀は次のように思います。
こちらだってプロだ。いつまでも好き勝手なことは言わせない。
この言葉を見て一気に緊迫感が増しました。
由紀と辻は古泉裕二という小学六年生の時の環菜と付き合っていた男に話を聞きに行きます。
環菜は由紀との面会で小泉をとても慕っているように話していましたが、二人が話を聞くと小泉に酷い目に遭わされていたことが分かります。
環菜の人生は男性に酷い目に遭わされ続けたのだと思いました。
環菜の心を助けたい由紀が興味深いことを語ります。
今を変えるためには段階と整理が必要なのだ。見えないものに蓋をしたまま表面的には前を向いたようにふるまったって、背中に張り付いたものは支配し続ける。
なぜなら「今」は、今の中だけじゃなく、過去の中にもあるものだから。
これはフロイトの精神分析学の「過去にあった何らかの出来事がトラウマとなり現在の性格に影響を与える」という考えに基づく言葉だと思います。
この考えは島本理生さんの他の作品にも登場していて、かなり重要な考えになっている気がします。
母親がありもしないことを由紀に言ったのを知り環菜が初めて怒ります。
虚言癖があるのは母親のほうでした。
由紀は環菜が怒ったことを「長い眠りの終わりに立ち会った」と表現していました。
環菜はこれまでの発言を撤回し「父親を殺すつもりはなかった」と言い、ついに戦う気持ちになります。
環菜が心を取り戻したのを機に由紀と迦葉も和解の時を迎えます。
和解の後、由紀がクリニックのソファーで軽く眠った時、自身も十年前にここで診察を受けていたことが分かります。
臨床心理士になる人は自身も酷い目に遭っていたことがよくあるようです。
人は、もう一度、生まれることができる。
環菜もきっと。
由紀は自身が抱え込んでいた闇に光が当たった時のことを思い出しながらこのように思います。
ついに裁判を迎えます。
検察の主張に迦葉は「争います」と言い、無罪を主張して全面対決になります。
どんどん緊迫した雰囲気になり引き込まれていきました。
判決は緊張しました。
裁判の間読んでいてずっと続いた押し潰されそうな圧迫感も印象的でした。
この数か月、ずっと私の心に向き合ってもらえたこと、ずっと忘れません。本当にありがとうございました。
私はこれを見て、環菜の心がずっと向き合ってもらえたありがたさを感じ取れるまでになり、ありがとうを言うことができて良かったと思いました。
迦葉とペアを組む北野という弁護士が序盤で由紀に以前から本の執筆に興味があったのかと聞いた時、「はい。私はこの仕事で有名になりたいんです」と言っていた真意も明らかになります。
裁判が終わって緊迫した雰囲気が和らいだところに気持ちが明るくなる素晴らしい言葉があり物語構成の上手さを感じました。
環菜、迦葉、由紀それぞれの心の開放も大きなテーマになっていたと思います。
そしてこの作品は終り方がとても良かったです。
由紀が抱えていた心の不安の最後の一つがついになくなり、明るく晴れやかな気持ちで読み終えることができました。
島本理生さんは今回、芥川賞系の作家さんらしい繊細な表現をほとんど使っておらず、作中にあったように自身も作家としてもう一度生まれようとしているように見えました。
「リトル・バイ・リトル」「生まれる森」「大きな熊が来る前に、おやすみ。」「夏の裁断」 で四度芥川賞の候補になりましたが受賞はできませんでした。
しかし第159回直木賞の候補になったのを見て嬉しくなり、私の心は島本さんに直木賞や本屋大賞を受賞してほしいと強く願っているのがよく分かりました。
当代きっての大作家に駆け上がってほしいです

※7月18日、見事第159回直木賞に選ばれました

おめでとうございます


※「島本理生さんと芥川賞と直木賞 激闘六番勝負」の記事をご覧になる方はこちらをどうぞ。
※図書レビュー館(レビュー記事の作家ごとの一覧)を見る方はこちらをどうぞ。
※図書ランキングはこちらをどうぞ。









