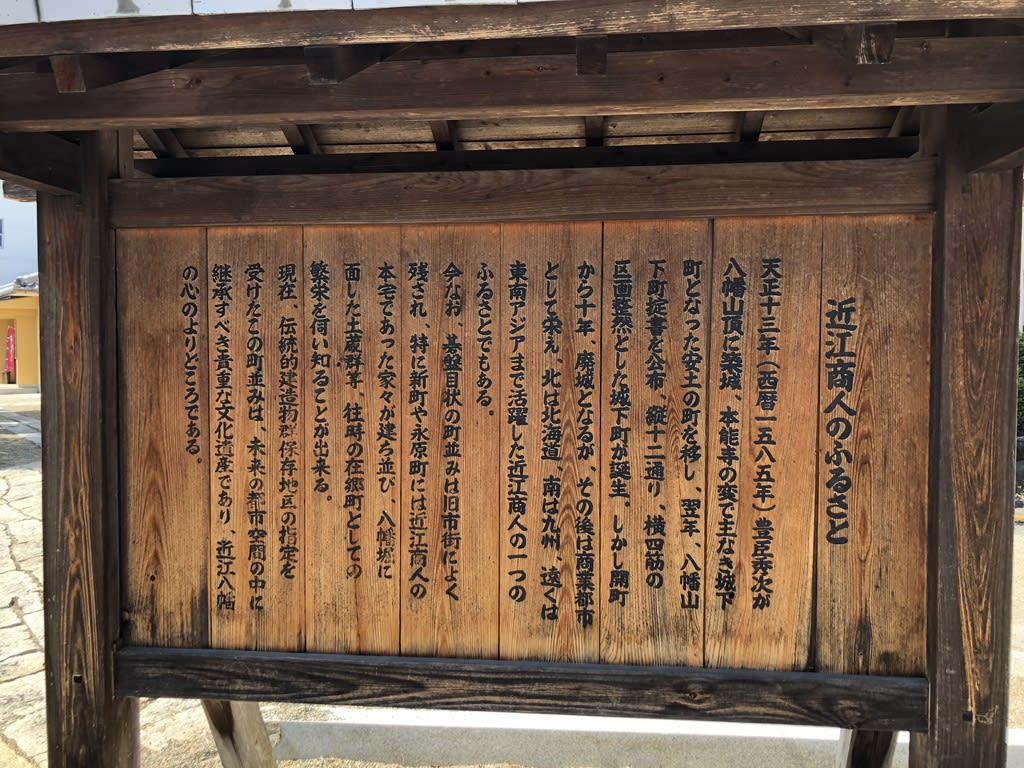立山雷鳥沢付近にて
ライチョウさん、そこを通して頂けませんか?
雷鳥や恋の季節にお邪魔虫
タイトル「お馬が通る」
ネタバレ:多くの方はご存じでしょうが 「小林一茶:雀の子そこのけそこのけお馬が通る」から引用しました。

もうすぐ一ノ越

立山 雄山

剣岳が見える
https://youtu.be/uObnzN0DZ7g?t=3
立山雄山山頂よりパノラマ
立山雄山山頂よりパノラマ
黒部立山アルペンルートは何度か通った
今回は久しぶりに立山に登った
最初に来たのは何十年か前の学生時代
神戸から弟と一緒に剣岳に登ったことを思い出した
登攀道具一式をキスリングリュックに詰めた
ザイル、カラビナ、ハーケン、ボルト、ハーネス、ハンマーなど一式
重量は40kg以上あったかな
持ち上げるのにも苦労した
室堂から雷鳥沢へ
雷鳥沢を登るだけでバテバテになった
雷鳥沢から剣御前を通って剣沢へ
そこで一泊
翌日は剣沢を下り平蔵谷の出合へ
平蔵谷の雪渓をつめて剣岳に直登した
結局はピッケルとアイゼンのみのフリークライムだった
剣岳に登るために六甲山の岩場や沢筋で練習した
自宅は王子公園の近くにあった
王子公園から登ると青谷があり摩耶山へのコースがある
阪急の芦屋川から上に高座の滝がある
近くに芦屋のロックガーデンがある
藤木久三さんが岩登りで遊んだといわれる場所だ
ボクはそこで懸垂下降やロープワークの練習をした
六甲で花崗岩の荒い肌触りの岩カベでハーケンやボルトの試し打ちをした
弟と六甲山以外の山に行ったのは剣岳のみかな
その後に弟は勤務先の会社に仲間と山岳部を作った
しばらくして仲間が滑落して命を落としたか重傷を負った
山岳部は解散し山から離れたようだ
ボクもほかのことで忙しくなり根を詰めた山登りから離れた
その後は犬の散歩と称して時々は山に行った
山行回数が増えたのはこの数年のことだ

立山雄山山頂より
遠くに槍ヶ岳が見える
穂高も見える
ジャンダルムも識別できる

今回の立山には山スキーの下見に来た
一ノ越から雷鳥沢にかけていい斜面がある