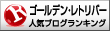昭和20年8月15日、日本は無条件降伏を受け入れ終戦を迎えた。
軍隊から郷里にもどり、終戦の昭和20年の暮れ、父は母と結婚し、昭和22年に私が生まれた。
父は再び生船(なません)に乗った。終戦後、食糧事情が非常に悪かった。百姓も食料を手放すことに渋く、女の人は一張羅の着物を持ち込み、泣く泣く米や芋と交換してもらったらしい。
ただ、祖父と父は戦後も生船で運んでいた魚があったため、百姓の家へ行って米と交換してもらったそうだ。祖父も父もお前には、つまり私のことだが、ひもじい思いをさせたことはないと言っていた。
その後、戦争が終わって少し世の中が落ち着いたころ、私の妹が生まれ、その後に弟が生まれた昭和28年ごろ、父は何か思うところがあったのだろう、陸(おか)に上がり、神戸に駐留していた米軍、つまり進駐軍に勤務を始めた。米国兵に食事を調理して提供するコックとして勤務した。
進駐軍に勤務する従業員一同、日本人が主体となって、神戸の須磨浦公園で運動会があり、家族もみんな参加した。私が7歳のころだった。その時に父親たちが作り、みんなに振舞われたアイスクリームがとてもこの世のものとは思われないほど美味しくて、口の中でとろけて夢中でむさぼり食べた。今でいえばハーゲンダッツのようなサーティワンのような本物のアイスクリームだ。そのころは氷のアイスキャンデーや人工甘味サッカリンのアイスしかなかった時代だ。
この時、褐色の飲み物も一緒に提供された。一口飲んだが薬臭くて刺激があって泡が噴き出て、いったん口に入れたものの吐き出すわけにもいかず、思い余って飲み込んでしまったが、食道から胃まで、その液体は暴れながら訳も分からず落ちていった。何とも不思議な飲み物だった。
これがボクのコカコーラの、アメリカの初体験だった。