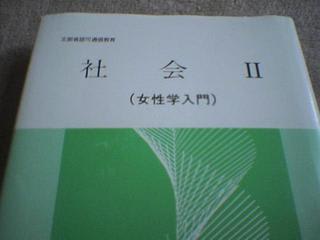「今日は黙って見ていろ。」
そう私が言うと、皆、一言も口をきかずに私の横に並び、いつものように記録の用意を始めた。サンプルは、相変わらず幽霊のようにユラユラと揺れていた。
「やぁ、おはよう。ハーシェル。」
彼が気づくように、わざと大きな音を立ててドアを閉め、私は中に入った。彼は顔を上げ、私を認めると、目を吊り上げて急にわなわなと震えだした。
「まだ生きていたのか・・・!」
私は、彼の息がかかるほど近くまで顔を近づけた。
「それはこっちの言うセリフだ。」
「なんだとっ!」
逮捕されて間もなく軍服を脱がされて下着姿で過してきた彼の体臭が鼻を突き、私は一歩後ずさった。
「この間の新聞を見ただろう。おまえはもう、この世には居ない人間なのだ。おまえは、病院で私を襲ったあの日にもう死んでるんだ。なぜ早く死なんのだ?」
「おまえを殺してからだ!おまえを・・・!」
ハーシェルの目は、私を睨みつけて離さなかったが、体は彼が言葉を発するたびに小さく前後に揺れ動いた。
「私を殺してどうする?」
「おまえを殺しておれが・・・、このおれが総統を守るのだ!」
「・・・あの時と同じだな、ハーシェル。」
私はそう言うと、彼がいる反対側の壁際まで行き、再びハーシェルと向き合った。そして白衣のポケットから銃を取り出し、銃口をハーシェルに向けた。彼の歯がギリギリと音を立てていた。
「・・・どうする気だ!」
「あの時と同じだ。ハーシェル。」
彼が何かの拍子に大きく前につまづき、両手が上に引っ張られた。バンザイをしたような格好になったが、かろうじて膝を付くまでには至らなかった。
「・・・殺してやる!おれを笑うやつはみんな殺してやる!」
「あの時おまえは、ナイフで私の右手を刺した。そしてそのナイフで逆に自分が恥をかかされると、今度は私を陥れようと教官に告げ口をした。」
真っ白な壁に囲まれた2人だけの空間に時折響く、ハーシェルの吐息を私は穏やかに聞いていた。
「ちくしょう!おれを放せ!総統とボルマンを連れて来い!」
「・・・しかしその結果、私は総統に引き抜かれ、おまえはナチス失格だと言われた。」
彼が私の言葉を無視して鎖を引きちぎろうともがいているのが、構えた銃越しに見えた。
「・・・そうだ!おまえのせいだ!おまえのせいでおれは!」
「いいか、ハーシェル。思い出せ。これはおまえの銃だ。」
「それはおれのだ!返せ!その銃でもう一度おまえを撃ってやる!」
彼の右腕が一瞬私の方に伸びたが、鎖がピンと張り、その先に繋がっている手錠が彼の手首に食い込んだ。
「そうだ。おまえはこの銃で私を撃った。」
私は、彼の左足を狙い、引き金を引いた。一瞬彼は黙り込み、まるで他人事のように、血の噴き出した自分の左足を見つめていた。ペンキをこぼしたように、ハーシェルの足元の白い床が真っ赤に染まった。
(つづく)