何も変わらず
あの「喫茶店」が
まだ残っていた

「神保町」という町は、ある年代にとっては古本屋と喫茶店という2つのキーワードでくくられてしまう。
さらに忘れてならない、もう1つのキーワードがある。
それは日本最高のカレーの激戦区だということだ。
古書街を通りぬけて、一歩路地に入れば、時間の止まったような店がまだまだ残っている。
神保町では、「カフェ」ではなく、あくまで「喫茶店」。
そう呼ぶことしか許されないのが、歴史がつまっている老舗喫茶店のポリシーであろう。
古本を探して、昔ながらの喫茶店で、やっと探し当てた本を開く至福のひととき。
そんなささやかな喜びを演出してくれる。
それが「神保町」なのだ。
誰にも教えたくない、とっておきの喫茶店があるものです。
「えいっ!!」
今回はバラしちゃいましょう。
靖国通り沿いにある古本のデパート「小宮山書店」の横を右折して、最初の路地の手前にあるのが「ミロンガ ヌオーバ」です。
1953年の創業。タンゴフアンには欠かせない喫茶店。
というのは、オーナーがタンゴオタク。アルゼンチンタンゴを主体とした500枚以上のLPを用意している。
ターンテーブルが2台。アルテックのスピーカーも完備している熱の入れよう。
音楽を聴かせる喫茶店ならではのシステム。
なんでも明大タンゴ研究会のメンバーがお店の常連ときいた。

コーヒーの味にはもともと定評があります。
但し、運ばれてくるまで15分~20分程度のお覚悟が必要。
ワタクシの注文はストレート・モカマタニー。
コーヒー豆の鮮度には、細心の注意を払っているそうです。
ブレンド、ストレートともに炭火焼焙煎となり、挽き立ての香りの豊かなコーヒーの味。
やっぱ、人に淹れてもらうコーヒーは美味しい!!

さりげない目配りと気配りがある。
背の低い椅子も、シャンデリア風の照明も。そして絵画にも・・・。
テーブル、インテリアともに無垢材を使っています。
「昭和の喫茶店ってさ、きっとこうだったよね」
と言いたくなる、超アナログの風景です。

看板でもお気付きでしょうが、メニューのもう1つの特色はビールの品揃えの豊富なこと。
ギロチンやギネスなど世界のビールが50種類以上。
最近はビールを飲みながら本を読んでいる若い女性客が多いとか。

週末は古書店巡りを終えた人が一息入れるために来店することが多かった。
ところが最近、ちょいと異変が・・・。
近隣に古い名作映画を1日4本上映する「神保町シアター」ができた。しかも格安料金。
お目当ての作品が上映されるまでの時間潰しの客が多いらしい。
古書、音楽、名作映画、がっつりフードなど神保町にやってくる目的はさまざまですが、「ミロンガ」のレンガ造りの外観、黒檀のような輝きを見せるインテリア。
忘れてならないのが、「極上のコーヒー」。
だから、いつも行きたくなるお店「ミロンガ」なのかもしれません。
次回は「人形町ぶらり散歩」です。












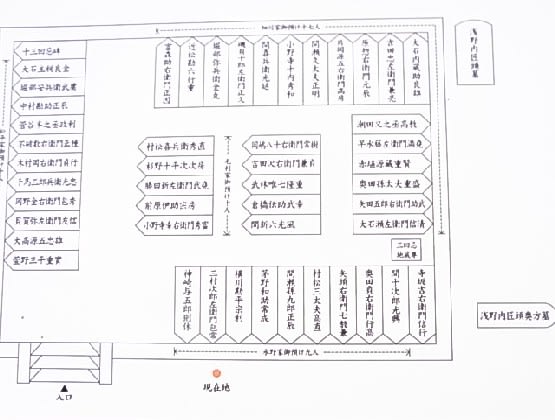
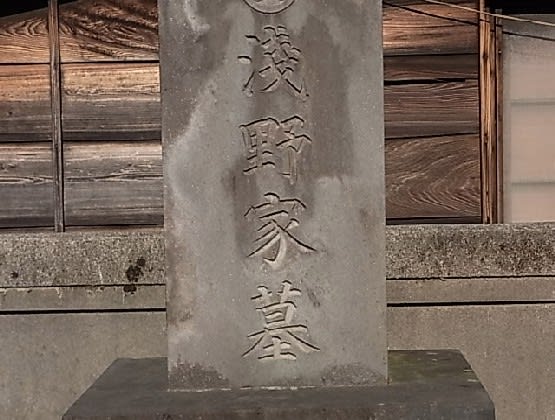
















 抜き!!」もいかがなものかと、結局は使わせていただきました(笑)。
抜き!!」もいかがなものかと、結局は使わせていただきました(笑)。














