9月25日(木)
NPO法人子どもネットや千代(Linnks参照)主催による、子育て支援スキルアップ講座の
講演会「子育て支援について」(講師/深谷昌志先生―東京成徳短期大学幼児教育科・教授)
に参加してきた。
深谷先生は、「子育て支援」と「子どものサポート」という研究テーマの中で、特に、「育児不安と少子化の関係」について、日本だけでなく世界各国の「お母さんの子育て」調査をなさっている。
「少子化」が騒がれて久しくなるが、一向に終息しないばかりか、深刻さは増すばかり。
その背景と傾向を考えると、どこかで歯止めをかけないと、これからの未来は相当暗いものになることが予想される。
少子化の傾向の最大の原因は、「育児不安」にあると考えられる。
「働く主婦」への対応はかなり充実してきていると思う。その後の親子関係についてはその家庭の事情によるだろうが・・・。
だが、妊娠・出産・育児のために、仕事をやめ、核家族で、都心部の高層マンションや、郊外の団地・ベットタウンで子育てをやっている、いわゆる「専業主婦」たちが陥っている「密室育児」状況からくる「育児不安」はかなり深刻だ。
それも、高学歴で、キャリアウーマンの高齢出産の人ほど重症になる傾向が強いのだそうだ。
また、その子が、望んで生まれた場合と、望まぬ妊娠で生まれた場合では、更に状況は変わってくる。
前者の場合は、産み月までの間に母になる心構えや、赤ちゃんへの関心が強まっていく。
一方、後者の場合は、ギリギリまで働き、母になる覚悟も準備も出来てい無いところで出産を迎える。
生んだ後も、早めの社会復帰が優先され、すんなり戻られれば良いが、そうではない場合、自分だけ損したような、社会に取り残されたような気持ちになってしまう。
育児不安と仕事をやめたときの気持ちとの関係を見てみると、止めたときの「残念」な気持ちが強いほど、育児不安傾向は強い。
更に、妊娠した時にあまり嬉しくなかった人は、出産後の、
「自分の子が可愛く思えない」とか、
「この子さえいなければ・・・」と言うマイナスの気持ちに転化していってしまう傾向が強い。
そのはなはだしい結果が、「育児ノイローゼ」となり、「幼児虐待」に繋がっていく場合があるのだ。
たとえ、核家族でも、夫が育児を夫婦の共同作業だと考えてくれるような人なら大丈夫。
人生経験の少ない若いお母さんでも、農村部では育児不安が少ないそうだ。
育児不安の背景の中には、「不慣れ」と「不安」(核家族による孤立)の連続性が考えられる。
最初の子どものとき、大変ながらも、夫を始めたくさんの周りの人の協力と理解を得られて、育児の楽しさや、我子ならではの可愛さを実感することが出来れば、その子が2~3歳ぐらいになれば、自然と兄弟が欲しくなってくるものだと思う。
それが、「もう、子どもはたくさん!」「育児は大変なだけで、楽しくない」「どうして私だけが大変で、痛い思いをしなきゃならないの?」「自分の子どもが可愛く思えない」などと言う気持ちに陥っていたら、とても第2子、第3子を生みたいという気持ちにはなれないのも無理はない。
また、育児不安の背景の中に、その母親が育ってきた環境と言うのがある。
その人の「親性」が育つかどうかは、どういう母親にどう育てられてきたかでかなり違ってくる。
将来母親になるための必要な心構えよりも、自立したキャリアウーマンになるための学歴を重視した教育だったかどうか・・・。
小さい子が好きな母親に育てられたかどうか・・・。
たとえ、フルタイムで働いていたとしても、親戚付き合い、近所付き合い、地域活動やPTA活動などに積極的な母親に育てられたかどうか・・・。
実際、赤ちゃんや小さい子に対して、どう接していいかわからず、出産直後の参院で、泣いている赤ちゃんの隣で耳をふさいで泣いている新米ママの姿はあまりに痛々しい。
そういう人の多くは、自分が出産するまで、赤ちゃんに1度も触れたことが無いと言う人が多い。
子どもは、子ども時代、自分の親には良くも悪くも人格形成上、多大な影響を受けて育つ。
大人になる過程で、それは、指針ともなり、反面教師にもなっていくのだが、不思議なことに、家庭を持ち、親になると、良くも悪くも、自分が親に育てられたように子育てをしようとする。
若い頃は、親の育て方を否定し、批判していたのに、自分が受けたと同じ虐待を繰り返してしまう「アダルトチルドレン」は、その最も悪い例だ。
そういう夫と結婚してしまった場合、その嫁ぎ先との関係も考えると、「育児不安」は決定的なものとなる。
「少子化」によるさまざまな方面での悪影響は、国の根底を揺らがせ、ひっくり返すほどの深刻さを感じる。
「経済政策」や「政治改革」も大事だが、「少子化問題」や、「教育問題」にも目を向け、早急に対応策を考えなくてはならないと思う。
講演の中で、先生は、「それぞれの社会に、それぞれの子どもの問題がある」ということで、調査に訪れられた諸外国が抱える問題を話された。
例えば、韓国・・・・・受験問題
中国・・・・・一人っ子政策
欧・米・・・・離婚・再婚による複合家族問題
アジア・・・児童就労問題
そして、日本・・・・・少子化と、学力低下(値打ちが下がる一方の学歴)
そして今の日本の子どもの問題として、「子ども達が地域に参加していない」ことを指摘されていた。子ども達はどうしたら地域で生活していけるかと言うことは、同時に、家庭教育の低下のみならず、地域の教育力の低下も大きな問題だ。
そのためにも、第一子が3歳になるまでの子育て支援の問題への対応と充実化は、早急に取り組まねばならないことだと思う。
NPO法人子どもネットや千代(Linnks参照)主催による、子育て支援スキルアップ講座の
講演会「子育て支援について」(講師/深谷昌志先生―東京成徳短期大学幼児教育科・教授)
に参加してきた。
深谷先生は、「子育て支援」と「子どものサポート」という研究テーマの中で、特に、「育児不安と少子化の関係」について、日本だけでなく世界各国の「お母さんの子育て」調査をなさっている。
「少子化」が騒がれて久しくなるが、一向に終息しないばかりか、深刻さは増すばかり。
その背景と傾向を考えると、どこかで歯止めをかけないと、これからの未来は相当暗いものになることが予想される。
少子化の傾向の最大の原因は、「育児不安」にあると考えられる。
「働く主婦」への対応はかなり充実してきていると思う。その後の親子関係についてはその家庭の事情によるだろうが・・・。
だが、妊娠・出産・育児のために、仕事をやめ、核家族で、都心部の高層マンションや、郊外の団地・ベットタウンで子育てをやっている、いわゆる「専業主婦」たちが陥っている「密室育児」状況からくる「育児不安」はかなり深刻だ。
それも、高学歴で、キャリアウーマンの高齢出産の人ほど重症になる傾向が強いのだそうだ。
また、その子が、望んで生まれた場合と、望まぬ妊娠で生まれた場合では、更に状況は変わってくる。
前者の場合は、産み月までの間に母になる心構えや、赤ちゃんへの関心が強まっていく。
一方、後者の場合は、ギリギリまで働き、母になる覚悟も準備も出来てい無いところで出産を迎える。
生んだ後も、早めの社会復帰が優先され、すんなり戻られれば良いが、そうではない場合、自分だけ損したような、社会に取り残されたような気持ちになってしまう。
育児不安と仕事をやめたときの気持ちとの関係を見てみると、止めたときの「残念」な気持ちが強いほど、育児不安傾向は強い。
更に、妊娠した時にあまり嬉しくなかった人は、出産後の、
「自分の子が可愛く思えない」とか、
「この子さえいなければ・・・」と言うマイナスの気持ちに転化していってしまう傾向が強い。
そのはなはだしい結果が、「育児ノイローゼ」となり、「幼児虐待」に繋がっていく場合があるのだ。
たとえ、核家族でも、夫が育児を夫婦の共同作業だと考えてくれるような人なら大丈夫。
人生経験の少ない若いお母さんでも、農村部では育児不安が少ないそうだ。
育児不安の背景の中には、「不慣れ」と「不安」(核家族による孤立)の連続性が考えられる。
最初の子どものとき、大変ながらも、夫を始めたくさんの周りの人の協力と理解を得られて、育児の楽しさや、我子ならではの可愛さを実感することが出来れば、その子が2~3歳ぐらいになれば、自然と兄弟が欲しくなってくるものだと思う。
それが、「もう、子どもはたくさん!」「育児は大変なだけで、楽しくない」「どうして私だけが大変で、痛い思いをしなきゃならないの?」「自分の子どもが可愛く思えない」などと言う気持ちに陥っていたら、とても第2子、第3子を生みたいという気持ちにはなれないのも無理はない。
また、育児不安の背景の中に、その母親が育ってきた環境と言うのがある。
その人の「親性」が育つかどうかは、どういう母親にどう育てられてきたかでかなり違ってくる。
将来母親になるための必要な心構えよりも、自立したキャリアウーマンになるための学歴を重視した教育だったかどうか・・・。
小さい子が好きな母親に育てられたかどうか・・・。
たとえ、フルタイムで働いていたとしても、親戚付き合い、近所付き合い、地域活動やPTA活動などに積極的な母親に育てられたかどうか・・・。
実際、赤ちゃんや小さい子に対して、どう接していいかわからず、出産直後の参院で、泣いている赤ちゃんの隣で耳をふさいで泣いている新米ママの姿はあまりに痛々しい。
そういう人の多くは、自分が出産するまで、赤ちゃんに1度も触れたことが無いと言う人が多い。
子どもは、子ども時代、自分の親には良くも悪くも人格形成上、多大な影響を受けて育つ。
大人になる過程で、それは、指針ともなり、反面教師にもなっていくのだが、不思議なことに、家庭を持ち、親になると、良くも悪くも、自分が親に育てられたように子育てをしようとする。
若い頃は、親の育て方を否定し、批判していたのに、自分が受けたと同じ虐待を繰り返してしまう「アダルトチルドレン」は、その最も悪い例だ。
そういう夫と結婚してしまった場合、その嫁ぎ先との関係も考えると、「育児不安」は決定的なものとなる。
「少子化」によるさまざまな方面での悪影響は、国の根底を揺らがせ、ひっくり返すほどの深刻さを感じる。
「経済政策」や「政治改革」も大事だが、「少子化問題」や、「教育問題」にも目を向け、早急に対応策を考えなくてはならないと思う。
講演の中で、先生は、「それぞれの社会に、それぞれの子どもの問題がある」ということで、調査に訪れられた諸外国が抱える問題を話された。
例えば、韓国・・・・・受験問題
中国・・・・・一人っ子政策
欧・米・・・・離婚・再婚による複合家族問題
アジア・・・児童就労問題
そして、日本・・・・・少子化と、学力低下(値打ちが下がる一方の学歴)
そして今の日本の子どもの問題として、「子ども達が地域に参加していない」ことを指摘されていた。子ども達はどうしたら地域で生活していけるかと言うことは、同時に、家庭教育の低下のみならず、地域の教育力の低下も大きな問題だ。
そのためにも、第一子が3歳になるまでの子育て支援の問題への対応と充実化は、早急に取り組まねばならないことだと思う。












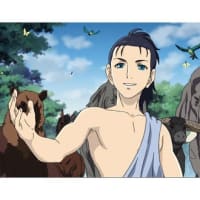







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます