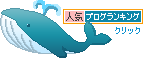癇癪を起こす、泣き叫ぶ、物を投げる、ひっくり返って暴れる、黙り込む。。さまざまな方法で子供達は「うまくいかなかった事」「できる/やろうと思っていた事ができないとなった状況」などに、その気持ちを表す方法として、上記のような態度を見せる事があります。
どれもどちらかというと不適切と判断されてしまう表現方法。
これらも、子供個人に得意不得意があり、不得意な子にはより丁寧に、時間をかけて(子供によっては数年単位)接して続ける事で成長が期待できます
関わる大人側は、できるだけ子供が発する「負のエネルギー」に気持ちを揺さぶられないように踏ん張る。
そして、気持ちへの共感と、ポジティブな声掛け、状況によっては適切な言動の提案。は、子供達の気持ちの切り替えや、適切な感情表現を身につける学びにつながります。
これは1例ですが
形ある物を崩す事に楽しさを感じる段階に満足すると、今度は形あるものを作る事が楽しくなってきます。
でも、毎回うまく作れるわけではない。 何度かやってみても思い通りにいかない時もある。
こんな時、多くの子供達がフラストレーションを感じ、癇癪を起こしたり、使っていた物に当たったり、投げたり、足で蹴ってみたり。そんな姿を目にします。
「ブロックなどで物を積み上げる遊び」に関しては、崩れてしまった時に 明るいトーンで「もう1回🎵」と声かけをするのはおすすめです
なかなか実行できない場合は、私がやってみせる場合もあります。
そして、崩れたら「もう1回🎵」と言って作り直す。
今日はマグナタイルを使って、積み上げをしている子がいました

立たせるのも、少しコツが必要です
そして、この上に別のタイルを積んでいくの

やりたいことは伝わってくるんだけど、デザイン的に難易度高いし、遊んでいた子の力加減なども考えると割とすぐに崩れちゃうだろうな。。と観ていました

上手にね、この小さいタイルを2、3枚は積み上げていたんですが、やはり崩れちゃう。
そして、それが嫌で「わ〜!!」っと癇癪を起こしたのですが
私がそっと「もう1回🎵 もう1回作ってみたらいいんじゃない?」と声をかけました。
この子の場合は、自分で実行に移せたので、私は近くで見守っていました
この時点でひっくり返ったり気持ちの切り替えが難しい子には、「壊れちゃって嫌だったね。壊れたらまた作ったらいいよ」などと声をかけ、私が代わりに作って見せて、崩れちゃったら「もう1回🎵」と言って作り直す姿を見せたり、一緒に作って同じような働きかけをしています
今回の子は、やっぱり2、3枚乗せると崩れちゃう。でもしばらく近くで様子を見ていたので、毎回崩れたら「もう1回🎵」と明るいトーンで声をかけました
すると、癇癪を起こす事をやめ、何度か繰り返すうちに子供自ら「もう1回🎵」と言って作り直すようになりました
ここまで来たら、私の役割は終了。
できた作品を崩れる前に写真を撮って、ママとパパに送るね。と伝えました。
我が子&お預かりの子達、仕事で行ったキンダーやデイケアでも何度も試していますが おすすめの方法です
そして、小さい頃から「思い通りにいかなかった事や状況」に対して、ポジティブに気持ちの切り替えに導いてもらえる経験の積み重ねは、Resilienceを身につける練習になります。
日常の遊びや生活の中で出会う「そうじゃない〜」「違う〜!」「なんで〜」と感じたであろう子供達にとっての困難な出来事は、大人目線では大した事がなくても、目の前の事に一生懸命な子供達本人にとってはもちろん「重要」であり、決して些細な事ではないのだけど、気持ちの切り替えが難しい子達にとっても そんな状況こそ、心の回復力を鍛える良き練習の機会となります
特に切り替えが難しい子には 「〜したかったよね。」「〜で嫌だったよね」などの共感は効果があります。 でも、癇癪を起こしている最中、感情がたかぶっている最中は 残念ながら何を言っても「その子の名前を言っただけでも」さらに癇癪がひどくなる事もあるので、あまりに火がついたような癇癪の場合は、落ち着いてからのアプローチがおすすめです
成功率が100%じゃなくても、何度か繰り返すうちに少しずつ変わって行く姿が見られると思います
癇癪などの不適切な言動は特に幼少期のお子さん達にはよく見られる光景ですが、子供自身が適切な言動を学べないまま思春期になり、大人になると、本人の心、とてもしんどいと思うんですよね。