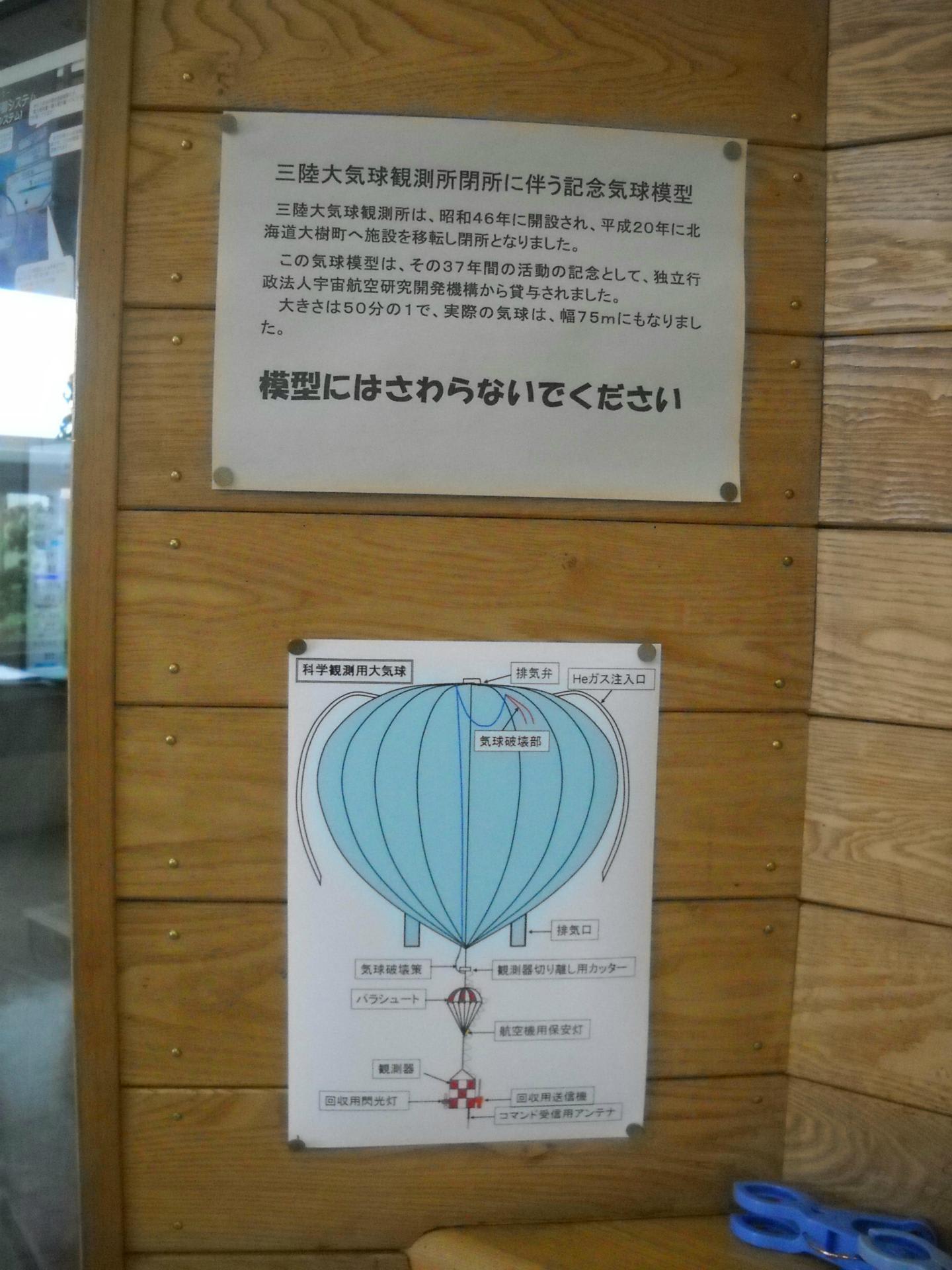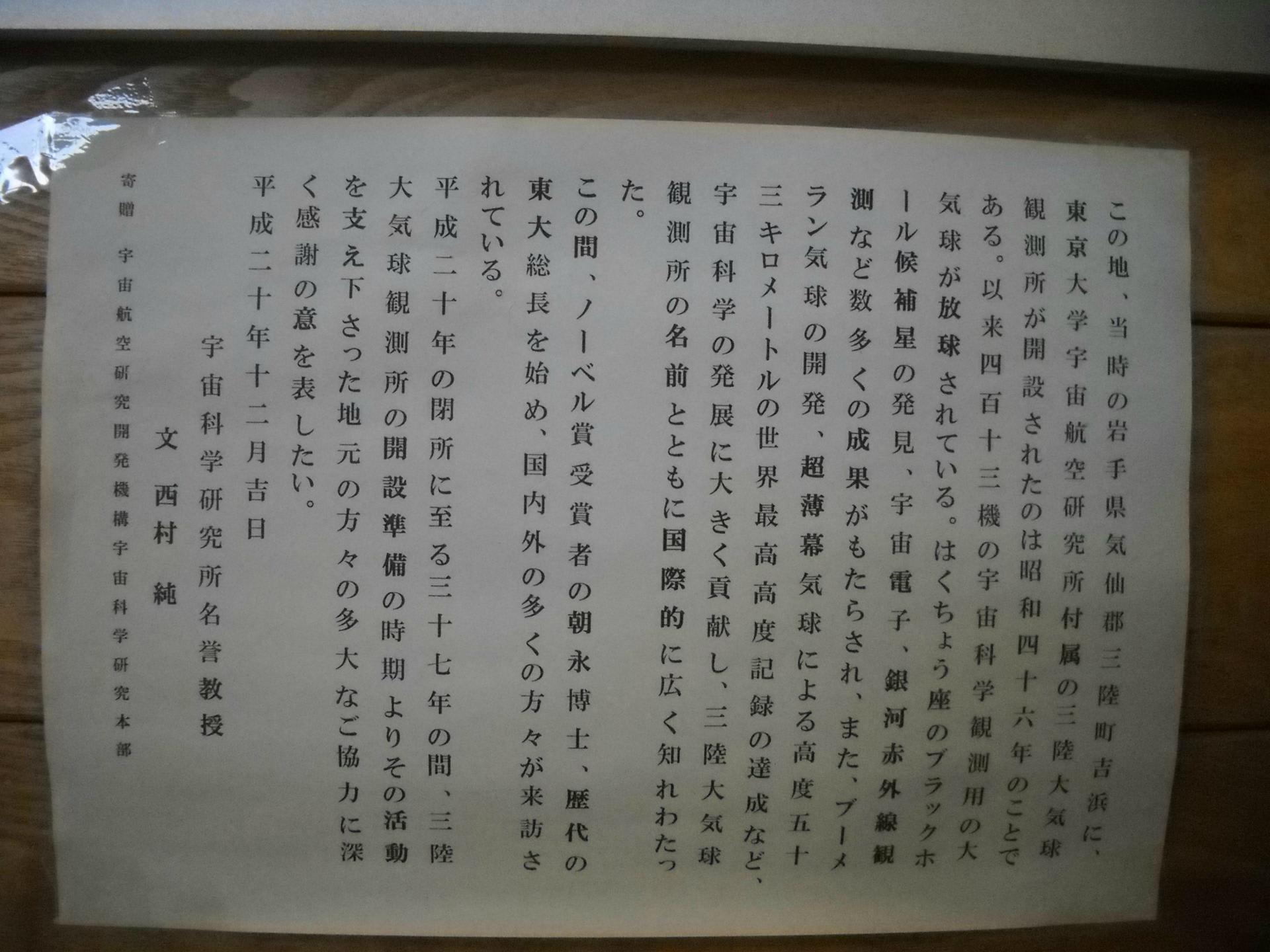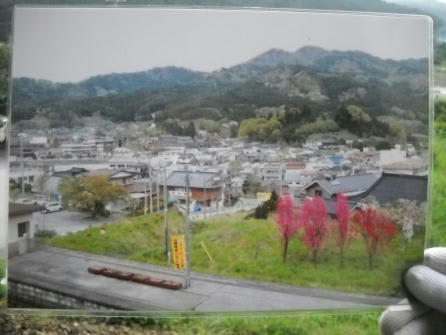気仙沼から前谷地までの気仙沼線は、気仙沼駅と柳津駅が不通のため、BRTを乗り継ぎます。

14分の待ち合わせで、10時55分発柳津行に乗りました。

気仙沼駅を発車した間もなく一般道から、本来線路が敷かれているはずの所からレールを取り外し、舗装された専用道に入りました。

踏切では信号が付いていて、鉄道とは逆に専用道の側に遮断桿が設置されていました。

全線専用道ではないため、途中で一般道に入ったり入ったりの繰り返しです。

岩松駅陸前階上駅間では、地盤のかさ上げ工事が進められていました。

陸前階上駅。跨線橋がそのまま残され、駅だったことが分かります。

鉄道トンネルだったところもそのまま活用されています。

本吉駅。鉄道の駅がまだそのままで、手つかずでした。

防潮堤のかさ上げ工事の真っ最中。

歌津駅そのものは高いところにあり被害を受けていないようでしたが、駅前は御覧の通りの被害。


路盤ごと流された清水浜駅付近。

コンクリート製の橋桁も、御覧の通りでした。

本来の気仙沼線にはないこの駅は、高台にあり南三陸町の仮の中心地で、南三陸町役場仮庁舎や南三陸診療所がある、南三陸町総合体育館「ベイサイドアリーナ」付近に設置されています。

ベイサイドアリーナの向かい側にある、WFPと書かれたテントは、災害ボランティアセンターです。

南三陸町の中でも被害が大きかった志津川地区に入りました。
防災対策庁舎です。

志津川駅があった所です。

BRTの志津川駅は、内陸に入ったところにあります。

テレビなどでよく紹介される「南三陸さんさん商店街」はここにあります。

志津川河口にある水門の壊れたままでした。

歩いて渡ることのできる荒島周辺に見える筏は、わかめの養殖でしょうか。

高台にあるといっても2階まで被害に遭いながらも、180日間にわたって600人の被災者を受け入れたことで有名な「ホテル観洋」。

陸前戸倉駅付近では、 BRT専用道にするための工事が行われていました。

ここから内陸に入ります。
陸前横山駅付近です。ごく普通の景色に変わりました。

12時54分、柳津駅到着。

ここから、13時25分の本来の気仙沼線で前谷地駅に向かいます。

乗客は他に誰もいません。

前谷地駅には13時25分に到着して、今度は石巻線に乗り換えて女川駅を目指します。

石巻線は、女川駅付近は壊滅状態なので、手前の浦宿駅まで列車で行き代行バスに乗り換えることになります。
小牛田からの、13時51分発浦宿行がやってきました。「石巻線マンガッタンライナー」の車輌です。


車輌の中にも、石巻にゆかりのある石ノ森章太郎氏のマンガキャラクターが描かれていました。

だんだん雨脚が速くなってきました。

14時36分に浦宿駅に到着しました。

この駅も海岸沿いにあるため津波の被害を受けたところです。

14時41分の代行バスで女川駅に向かいます。

一時小降りになった雨の、女川に向かうほど再び強くなりました。外の景色などの写真はここまでとなりました。


「きぼうのかね」商店街へ。
「きぼうのかね」とは、震災後、瓦礫の中からひとつだけ発見されたJR女川駅前にあったからくり時計の鐘ことで、女川高校のグラウンドにオープンした仮設商店街の一角に飾られえいました。

この商店街には、食料品や衣料品、中華料理、焼肉、カフェなどの飲食店や電気屋、本屋、クリーニング屋、自転車屋、タクシーなどなどいろいろな店が集まっている、被災地最大級規模の仮設商店街だそうですが、買い物客はほとんどいませんでした。

いくつかの商品を買いましたが、「きぼうのかね商店街」のシールが貼られていました。

再び「石巻線マンガッタンライナー」浦宿駅16時39分発小牛田行にのって、石巻へ向かいます。

石巻駅には17時2分の到着。
石巻駅にも石ノ森作品がたくさんありました。


ポストの上にも。

駅前には、津波の浸水位置を示す表示がありました。

石巻からは、仙台に向かいます。
震災前は、仙石線の電車が直通していましたが、現在一部区間が不通になっているため、列車と代行バスの乗り継ぎで向かう方法が一般的ですが、1日1往復だけ小牛田を経由する、どこの駅にも停まらない直通快速があります。
その18時17分発の直通快速に乗り、仙台には19時38分に到着しました。
つづく
※投稿した今日、平成27年3月21日は、石巻線が女川まで全線開通する日です。