愛知県岡崎市に行ったら、ぜひ訪れてもらいたいのが大樹寺です。

住宅街の真ん中にある地味なお寺で、京都のような存在感は全然ありませんが、このお寺にはここでしか見れない貴重な文化財があります。
それは徳川歴代将軍の等身大の位牌です。15代将軍の位牌がずらーっと並んでいます。
なぜこんなものがこのお寺にあるのか?家康の遺言に従って、この寺におさめられるようになったらしいですが、それだけ家康はこのお寺に恩義を感じ、特別な寺と思っていた理由は何か?
「林先生、ご存知でしたか?」とぜひ聞いてみたいですね。
答えは、大高城から逃れてこの寺に逃げ込んだ家康は、今川義元が討たれたと聞いて、「もはやこれまで、ここで自害しよう」としたらしいのですが、それをこの寺の住職が諭したという言い伝えがあるのです。
家康がここで死んでいたら歴史は全く別のものになっていたと思うと、感慨深いものがありますね。
等身大の位牌とともに、徳川家康の座像もあります。これは教科書の写真に使われているもので、徳川家康と言えばこの顔!というあの顔のオリジナルが見れます。

これは多宝塔。天文4年(1535年)建立らしいです。500年もどうしてこの姿を保っていられるのか、すごいの一言。

これはビスタラインと呼ばれています。写真だと分かりにくいけど、真っ正面に岡崎城が見えます。
直線距離で岡崎城とこの寺が繋がっています。
かなり距離が離れていますが、直線距離で繋がるように建造するって、どうやって作ったんだろう?
当時は周りに何もなかったから、案外目で確認しながら作ったら、うまくできちゃったとか、そういうことなのかな?
岡崎城の天守閣から、この寺をいつも見守っていたんでしょうね。















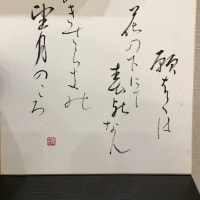




ビーナスラインというお色気?言葉をお寺で、しかも将軍家を祀る場所で、使わない言葉だと思うんですけど。
正解は、ビスタライン。以下岡崎HPより引用。
ビスタラインの「ビスタ」は「眺望・展望」を意味し、大樹寺と岡崎城を結ぶ約3キロメートルの直線を「ビスタライン」と呼んでいます。
これは徳川三代将軍家光が、寛永18年(1641)、家康の十七回忌を機に、徳川家の祖先である松平家の菩提寺である大樹寺の伽藍の大造営を行う際に、「祖父生誕の地を望めるように」との想いを守るため、本堂から三門、総門(現在は大樹寺小学校南門)を通して、その真中に岡崎城が望めるように伽藍を配置したことに由来しています。
ビスタってそういう意味だったのですね。
でもビーナスもいいと思いません?
それにしてもさすが詳しいですね。恐れ入りました!