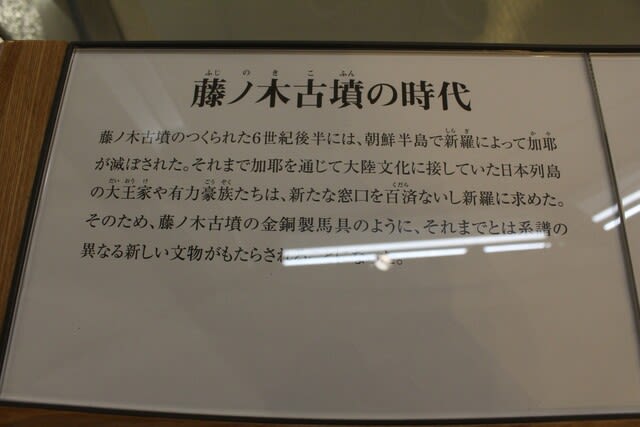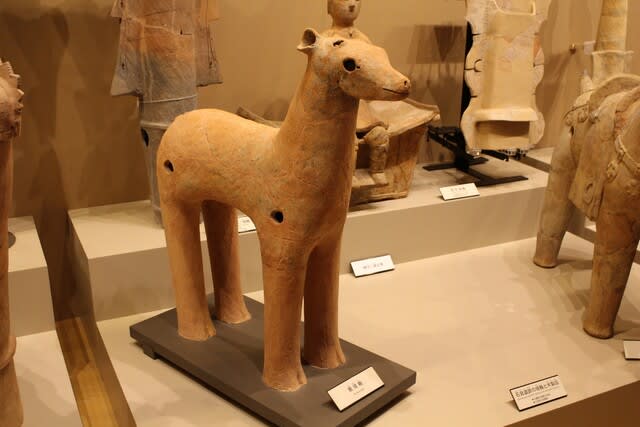<続き>
橿原考古学研究所付属博物館展示の品々を、長きに渡り紹介してきた。今回で最終回である。






体系立てて展示されているのは、理解しやすく有難い。次の展示は5世紀の出土遺物で時代は、棺桶の時代より1世紀遡る。


御所市南郷大東遺跡から木製の導水施設が出土した。橿原考古学研究所によれば、覆屋の中で水の祭祀が行われていたとする。結論を先に記せば、これは囲形埴輪の導水土製品と極似していたことから、殯所(ひんしょ・もがりどころ)における遺体洗浄に関わる施設(ココ参照)と考えられる・・・と云うことで、この木樋が橿考研付属博物館でみることが出来たのは幸いであった。
<連載・了>