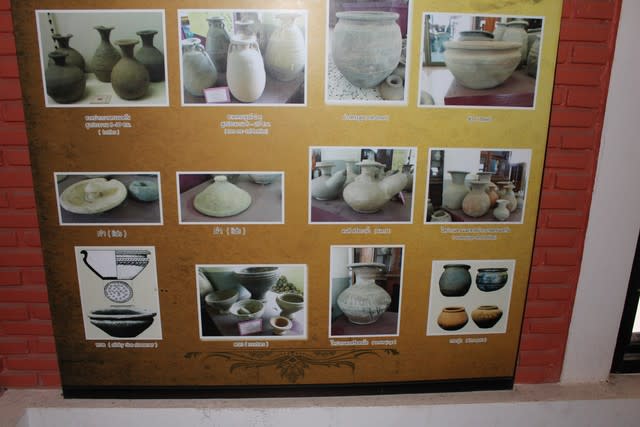過日、チェンマイ・エキシビション&コンベンション・センターで開催のLAN NA EXPO 2018に行ってみた。前回は2015年のそれを見ているので、今回で2回目である。年々規模が大きくなっているか、縮小しているかは分からない。

中央ゲートであったかどうか忘れたが、写真のゲートを潜り直ぐ右手のブースに木彫の職人が出展していた。それが以下の写真である。
素材はチーク材であろうか? 職人さんに聞くのを忘れてしまった。

タイでホンと呼ぶハムサの彫像である。ハムサはブラフマー神の乗り物である。

ケースにはナーガの彫像が収まっている。蓮池であろうか蓮花の彫り物も見事である。何やら出目金のように見える双魚の彫像があった。



これは何ぞや、職人氏に尋ねるとปลาอานนท์(プラー・アーノン:アーノンと呼ぶ魚)だと、教示して頂いた。
タイに於ける宇宙観は、西方インドの影響つまり、ヒンズーや南伝上座部仏教の思想を受け継いでいる。それによると須弥山(スメール)は宇宙の中心で、プラー・アーノン(サット・ヒマパーンに棲む魚)によって支えられ水面に浮かんでいる。そこは天の神から地獄の悪鬼までの住処である。神か鬼かについては、知恵と徳行により区別される。

プラー・アーノンは須弥山を支えているが、姿勢を保っているため窮屈で、時々動くことが在る。その体を動かすと地震を起こすという。仏教に於ける世界観は須弥山を中心に七山八海で構成されている。従ってプラー・アーノンは7匹棲息するという。
長々と記述したが、ヒンズーや仏典に登場する聖獣や聖魚が、木彫の対象になる北タイ。中世以来の原風景をみる想いであった。
<了>