




























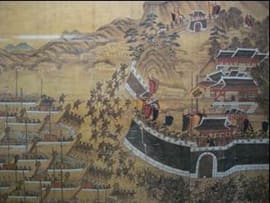

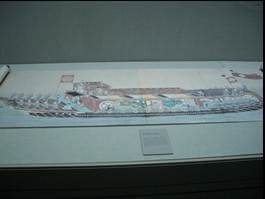


過日「タイサンカンペンの青磁の皿(15Ⅽ)」として、インターネット・オークションに出品されていた。それが下の青磁盤である。


これは一見してパヤオの刻花文盤である。その特徴として波状の刻花文が見込みに描かれていること、あまり広くない鍔縁を持ち、その鍔縁まで白化粧されている点である。通常胎土は黒褐色で高台裏が、そのように見えるのが特徴であるが、写真のように肌色に発色する盤も多々ある。高台を映した写真で、詳細を見ることはできないが、外側面の釉薬は高台間際まで掛っているのもパヤオの特徴であり、この盤もそれに該当しているように思われる。
過去からパヤオとサンカンぺーンの判別は難しいと云われてきたが、近年の窯址発掘調査により、その区別はできるようになってきた。特に当該盤のような刻花文はパヤオには存在するが、サンカンぺーンには存在しない。
判別に苦労するのは、印花双魚文の盤である。確かにこれはよく似ている。しかし、これも近年の研究により判別方法が分かった。サンカンぺーンの双魚は腹鰭が1箇所、背鰭が2箇所に対し、パヤオは腹鰭が2箇所、背鰭が1箇所である。もう1点決定的な判別方法として、パヤオの双魚文盤の高台裏が黒褐色に対し、サンカンぺーンのそれはやや薄い褐色である。
パヤオの特徴を良く説明しているのは、J/C/Shaw氏の書籍である。そのパヤオ窯に関する部分を見ると特徴が記載されているので、長文ではあるが紹介しておく。

Payao窯:J/C/Shaw著作「Northern Thai Ceramics」Second Edition 1989より
以下は1981年に発刊された初版当時の執筆内容である。
パヤオ窯は説明し辛い点が多々ある。パヤオ窯の最初の報告者はNimmanahaeminda(二ンマナハエミンダ)氏で、チャムパワイ地区のメータム川流域で発見された。そこはパヤオの南10kmの処である。
焼物はサンカンぺーンやカロンのそれと似ていると云われている。Journal of the Siam Society Vol64,Part2,1976の中で、スピンクス氏は「アユタヤ時代の土器」というタイトルの記事の後半で、チャムパワイ窯の地図を明示した。それには地図だけで、何の説明やコメントも記載されていなかった。
パヤオのワット・リー(Wat Lee)付属博物館とワット・シーコムカム(Wat Srikomkam)は、幾つかの褐色と青磁の陶磁を保有している。しかし、実際の窯址は発見されておらず多くの人々は、その実在に疑問を持っている。だが現在、窯址がパヤオの南12-14kmのチャムパワイ地区で発見された。
そこはメータムと云う川が流れる環濠集落跡で、村人が言うには多くの陶片とブロックで覆われていた。村人は多くの陶片が、そこより1km南でも発見されたとも言うが、何もEvidenceが残っていない。
多くの陶片は褐色釉であったが、メータム川とその周辺では青磁の陶片であった。窯場は水田の中の丘陵地で、その端(麓)に構築されていた。陶片は物原や窯の周囲の溝で見ることができるが、その陶片は青磁と褐色釉で固く、廃棄物も見られた。更に緑がかった窯壁のブロックも見ることができた。
<褐色釉>
環濠集落跡からの陶片の多くが、魅力的な暗褐色で釉薬は薄い。胎土は砂粒含みの粗雑さを持っているが、大きめな異物は含んでいない。
焼成後の無釉の素地は、チョコレートのような褐色、赤褐色の煉瓦色、黄褐色に発色するが、時たま明るい黒色に焼きあがる。
陶片が示すのは、多くが大壺、さまざまなサイズの球根のように膨らんだ貯蔵壺、口縁が無釉の盤と二重口縁壺である。焼成補助具は使用されなかったと考えられる。
瓶の陶片もパヤオとパーンで沢山発見された。それらを見ると明らかに関連性が考えられ、美しい栗色の釉薬で覆われていた。それらの幾つかは、淡い青磁の口縁を持ち、2色に掛け分けされた釉薬で覆われていた。様々なデザインの小さな初歩的な耳が頻繁に使われた。そして時々首回りには印花文で装飾されていた。
<青磁釉>
パヤオ青磁の胎土の特徴は黒いことで、幾つかは砂噛みをして、橙褐色または白みかかった灰色を呈している。通常黒褐色系の胎土に白土で化粧掛けされており、深いミルク色に発色した青磁で、更に淡いオリーブ色に発色した青磁もある。
それらの外側面には、しばしば褐色釉を用いており、内面の青磁釉とコンビネーションしている。盤の口縁は釉剥ぎされている。また壺類の内面にも釉は掛っていない。その壺類は浮彫りと印花文の繰返し装飾が用いられた。
黒褐色系の胎土は、多くの小さな白い不純物を含有している。小さな壺や瓶の多くは、高台は低かったり、まったく無いものもある。青磁釉を用いた焼成物の中心は、盤、皿、鉢、大小の壺類であった。
<硬質陶磁>
硬質の黒い陶片で、それらの一部はしばしば十字の印花文で覆われており、6つのマウンドの周辺で発見された。多くは無釉であるが、幾つかは淡いオリーブグリーンの釉が掛っている。これらの硬質陶磁の多くは、中形サイズの貯蔵壺である。
パヤオ窯址については、従来十分な資料がなかったが、調査が進んだ現在(1980年代)褐色釉と青磁が生産されていたことが明らかとなった。更なる研究により、タイの陶磁生産においてパヤオは重要な位置を占めていることが証明されるであろう。
Payao Notes for Second Edition 1989
新しい窯址がチャムパワイの南で、古くからの都市であるブアロイ(Bua Loi)で発見された。表土に散乱する陶片の多くは青磁で、褐色釉も混ざっていた。それらは盤と壺が中心であった。特徴としては、黒色系の胎土に白化粧されていることである。
盤の白化粧では、無釉の口縁まで化粧土で覆われ、外側面にまで及んでいる事例もあった。見込みやカベットは、しばしばスカラップ模様(扇形の連続模様)で装飾されている。
文様線は化粧土が乾く前に、その上から描かれているが、やや幅広の筆のようなもので描かれたものもある。そして何れも胎土を削るまでには至っていない。そして厚く掛った化粧土は、幅広の線文様の中に筋状の突起を残しているのが特徴である。
時々黒化粧が白化粧の上に掛けられたものがある(当該ブロガーは未見ではあるが)。白系統の胎土をもつ小さい壺には、黒の象嵌の装飾がある。
盤には、しばしば印花双魚文が多いが、小さいものの印花の象文、馬文もある(実際に馬の印判が出土し、パヤオのワット・シーコムカムで保存されている)。他の印花文としてメダリオン(メダルのような円形文様)、ピクン花文、鋸歯文、方形文、波状文、半円文、矢印文、菱形文、花瓶の頸回りを囲む鎖状印花文もある。
青磁釉は青ざめた黄色から暗いオリーブ色まで幅広い。時々無釉の初歩的で機能しない握手、小さい乳首のように尖った装飾、平らで輪ないしはS状の装飾が、青磁や褐色釉の大型の壺の装飾の中心であったと思われる。
焼成具は使用していないと思われたが、平らな輪状の焼成具が盤の底部に隠れている状態で発見された。
従来知られていなかった2つのタイプの盤、皿がターク(Tak)からもたらされた。
1. 青磁の皿で青じみた緑黄色から暗オリーブ色の印花双魚文で、口縁から見込みにかけてのカベットに筋状の鎬文をもっていた。それらの幾つかはサンカンぺーンのようだ・・・それらの数点の廃棄物はサンカンぺーンの窯址で見られ、高台回りも似ている。その他の盤もよく似ているが、高台間際まで釉が掛ったり、口縁の無釉の部分の幅が広いのが、パヤオの特徴である。
2. 大小の盤は通常、黄色がかった釉薬―時々美しい蜂蜜のような緑色で、見込みに印花文ないしは刻花文(化粧土の上からの線描きであるが、刻花と表現している書籍を多々見かけるので刻花文と表現する)を持つが、それらがターク(Tak)の墳墓址から発見された。
それらの刻花文は美しく、釉薬の下に淡く箒の掃き跡が残ったような渦巻き文が、見込みやカベットに描かれ、反復的な印花文、方形文やピクンの花文、時々繊細な曲線や波線でも装飾されている。
これらの陶磁の幾つかは、サンカンぺーンとも思われる。なぜならこれらの盤、皿とマッチングする陶片は、パヤオの窯址から出土したとの報告に接していないことによる。しかし残念ながら、ターク出土の盤の蛍光X線分析の結果は、サンカンペーン、パヤオ出土陶片の分析結果と比較し、そのどちらとも一致していない。
パヤオは市街の西に広がるパヤオ湖とともに神秘的で、古代からの歴史に彩られている。パヤオ窯はまだ謎が多い。ターク丘陵の埋葬現場で発見された青磁印花盤や刻花文で装飾された瓶や壺は、サンカンぺーンではなくパヤオで生産されたものと信じている。
参考HP
www.geocities.jp/goldeneggfamily4/details3001.html