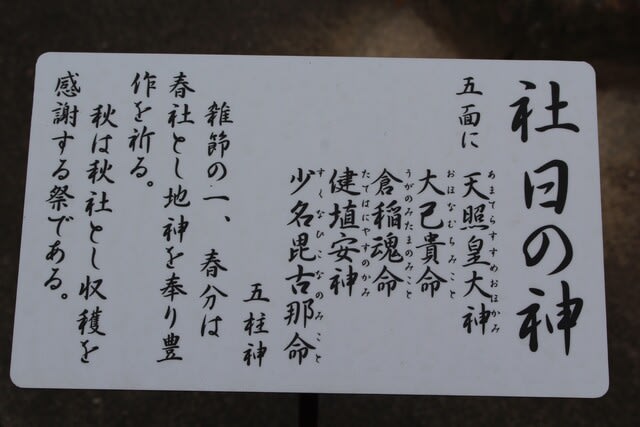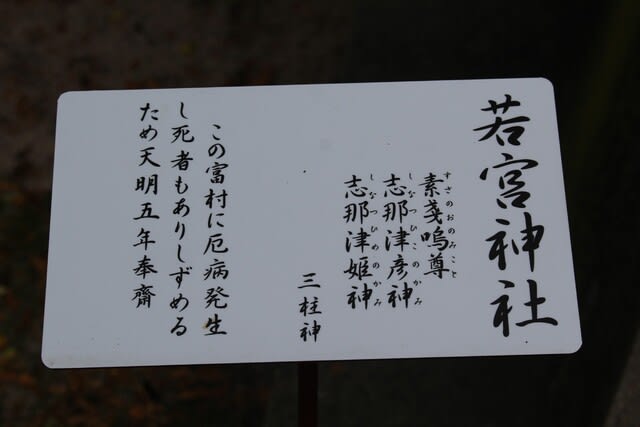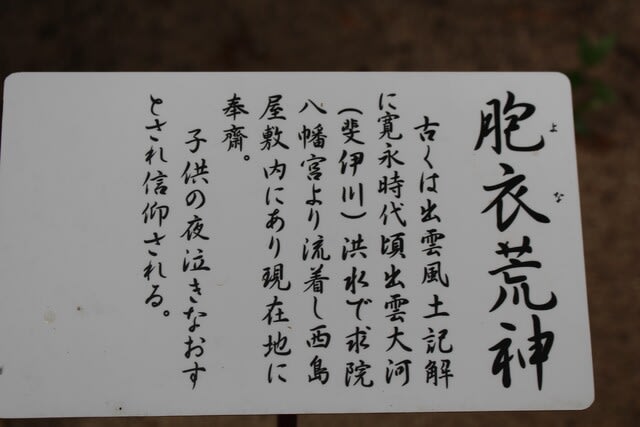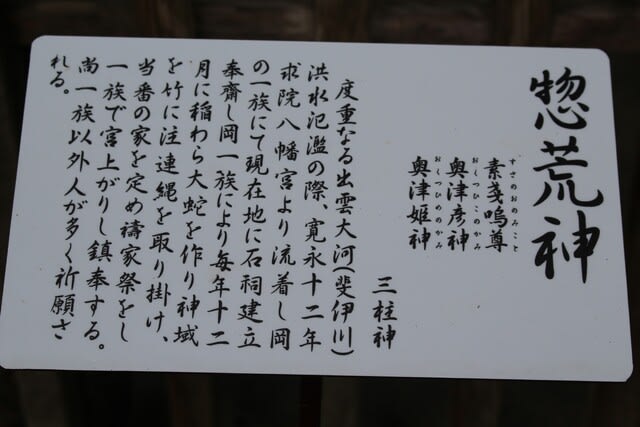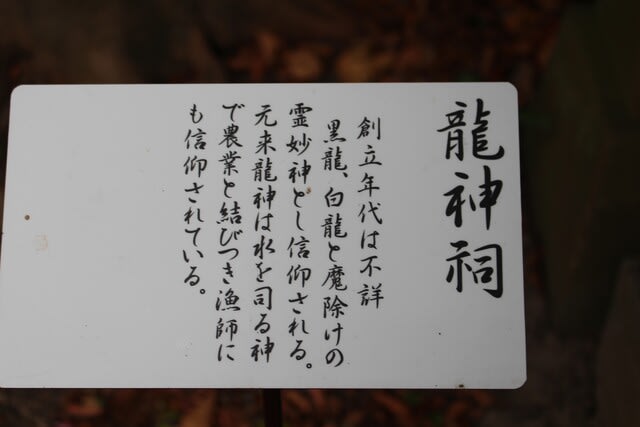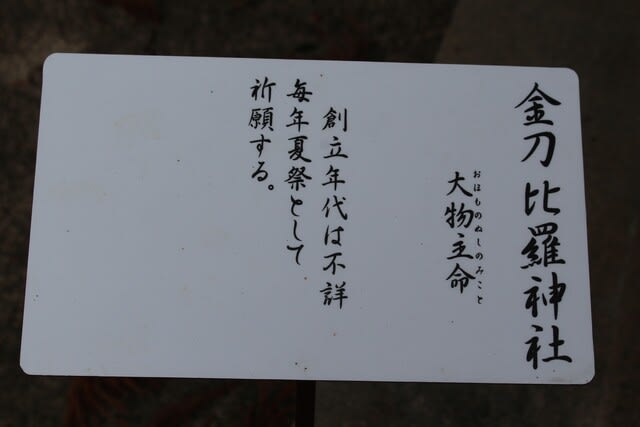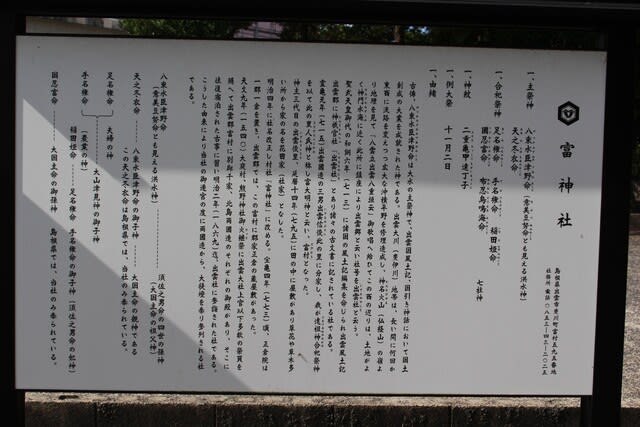――荻原秀三郎著『稲と鳥と太陽の道』―― シリーズ(9)
“稲作地帯の鳥竿習俗は、稲の豊穣祈願と密接に関連している。穀霊を運ぶのは鳥の役割の一つであり、一方で死霊を運ぶ役割も担っていた。ところが、稲の豊穣をもたらす、その鳥を射落とす神事がある。”・・・として千葉県沼南町高柳の三本足の烏(カラス)を描いた的を弓矢で射落とす神事を紹介しておられる。
我が島根県では旧・八束郡(現・松江市)にも、そのような神事は存在するようだが、隠岐の島に現存している。それは、五箇地区の荒神さんと呼ぶ客神、牛頭天王を祀る山田神社の山田客祭風流(やまだきゃくまつりふりゅう)での矢を射る神事である。そこではカラスとネズミ(兎から鼠に変化した?)の絵が描かれた的をめがけて矢を射る神事が行われている。

(写真出典:隠岐の島町HP)
この的に矢が当たるか否かで、この年の豊作を占うものだと一般的に云われているが、はたしてそうかと荻原秀三郎氏は問いかけている。
つまり、“的は必ず射当てねばならぬこと、当たらなければ近くに寄ってでも射当て、最終的に破る事例も存在するという。一般論の豊凶占いでは説明がつかない”・・・と、氏は指摘しておられる。では何のために的を射るのか?
“中国の天地創世神話である盤古神話と射日神話につながる。巨人・盤古の死体化生モチーフ及び弓の名人羿(げい)が九つの太陽を射落とす『射日神話』によるものである。太古に天と地は陰陽に感じて盤古という巨人を生んだ。盤古が死ぬとき、その体がいろいろなものに化して万物が生まれた。息は風雲となり、声は雷となり、左の眼は太陽となり、右の眼は月となり・・・”と続く。
更に別の伝承によれば、“その太古に太陽は十個あり、地中に住み、地中で湯浴みしている。東の果ての湯谷の上に巨大な扶桑の木があり、十個の太陽は湯谷の扶桑をつぎつぎ昇って、一日ずつその梢から天空へと旅たち、西の果ての蒙谷に沈み、地の下(水中)をもぐってほとぼりをさまし、再び湯谷に帰っていた。太陽にはそれぞれ烏(カラス)が住んでいて、樹上から飛び立っていた。あるとき、十個の太陽が一度に空を駆け巡った。大地の草木は、みるみる焼け焦げた。弓の名手・羿が太陽の中にいるカラスを九羽まで射落とし、地上の人々は焼死を免れた(山海経・淮南子)。”
荻原秀三郎氏は、射日神話の事例を種々説明されているが、何のために的を射るか・・・・について、結論らしきものは示されていない。結局これらの事例が物語るのは、安直ながら天下平穏と豊作祈願であろう。
<シリーズ(9)了>