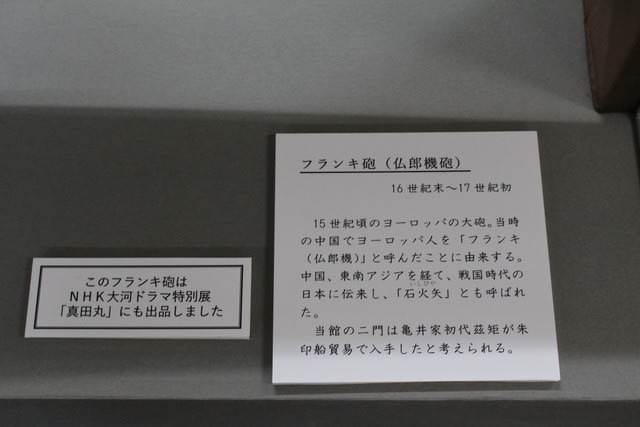以下の古代関連施設と遺跡を『青銅器と勾玉』の聖地と呼ぶことにする。

これらを順次紹介したいと考えている。最近思うことがある。古代出雲に限らず弥生期の倭国は、東アジアとの交易を主としながらも国際的な交易が存在したであろうとの想いである。
それは弥生期の玉類に、インド・パシフィックビーズと呼ばれる朱色のビーズが首飾りとして、出雲の地から出土する。この起源は、紀元前2世紀の南インドと云われ、紀元前1世紀にはスリランカやタイへも伝播したと云われている。北タイの山岳少数民族の朱色ビーズの首飾りと極似しているのである。その繋がりは学問的な証明は困難であろうが、根源は繋がっているであろう。それらのことも含めて順次紹介したいと考えている。
<続く>