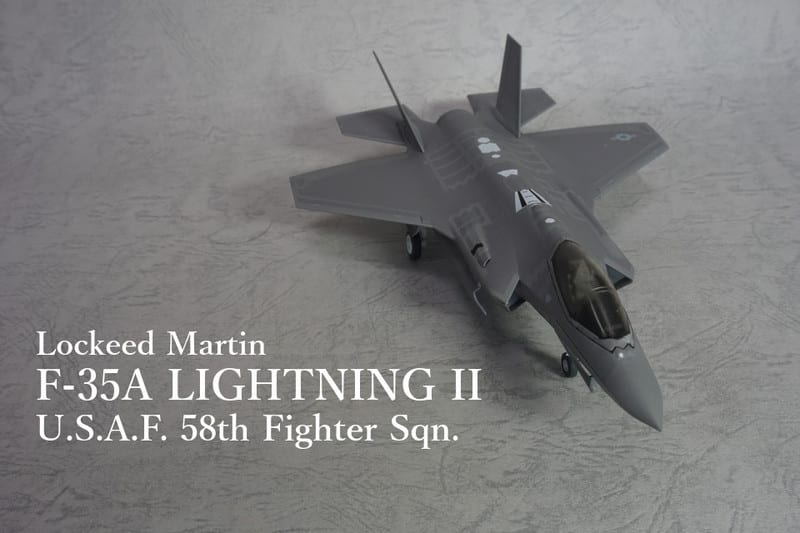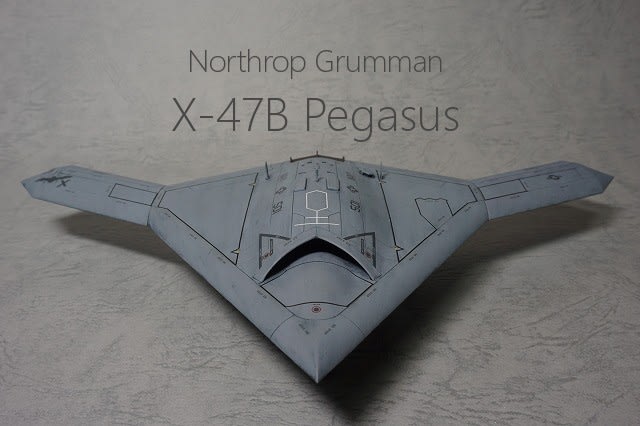ヤンクス航空博物館のスターファイターハンガー編。どんどん見ていきましょう。
次は
ダグラスSBD-4ドーントレス (1940年・57機目)。アメリカ海軍の急降下爆撃機でして、ミッドウェー海戦で日本の空母をボコボコに沈めてくれたやつです。
ダグラス製・・・ということになっていますが、元々は全翼機フェチことジャック・ノースロップ率いるノースロップ社が開発したXBT-2が原型でした。が、その頃のノースロップはダグラス傘下の会社でして、なんだかんだあって(手抜き)ダグラスが開発と生産を引き継ぐことになりました。ノースロップはその後1939年に独立して再出発しています。
SBDの意味は、SBが偵察・爆撃機(Scout/Bomber)でDがダグラス製を表しています。本当はSBとDの間に数字が入るんですが、1機種目は省略されます。海軍機の型式は右から左へ読んでいくと、意味がすんなり頭に入りやすいと思います。
SBDなら、ダグラスの造った(D)1番目の(1は省略)偵察爆撃機(SB)となります。F4Uコルセア戦闘機ならヴォートの造った(U)4番目の(4)戦闘機(F)といった具合です。
このSBD-4つまり4型は、3型(SBD-3)のマイナーチェンジ版でプロペラ形状や電気系統を変えた型式だそうな。
前から。SBDの実機を見たのはこれが初めてです。機体構造は奇をてらったものはなくごく普通という感じ。そこがまた良いのですが。
空母艦載機としては初期の機体なので主翼は折りたためません。
その代わりではありませんが、これの主翼は取り外すことが出来ます。主翼の主脚の根本のすぐ外側に継ぎ目のような出っ張りがあるのが分かると思います。あれは本当に継ぎ目でして、そこから外側の主翼は別パーツになっています。なので外そうと思えば外せると思いますが、頻繁に着脱することを考えた設計ではないと思うんで、やはりこの状態のまま運用していたでしょう、普通に。
ちなみにこの主翼を継ぎ目でつなぐという手法は上記のジャック・ノースロップがダグラス傘下だった時代に編み出した方法と言われています。
最初にそれが採用されたのがノースロップ「ガンマ」という聞いたことのない機体(現存はしているらしい)です。その後、ダグラスDC-1やDC-3にもこの構造が採用されています。さらに、ダグラスの技師を引き抜いてきたらしいノースアメリカンのT-6やBT-14にも同じ構造がありますので、当時の流行のような感じで使われていました。
SBDと言えば穴空き式のダイブブレーキ。これ一番の特徴かも。
SBDは急降下爆撃機という分類の飛行機でして、これは目標に向かって降下して突っ込みながら爆弾を相手に投げつけるという爆撃機です。ただ真っすぐに飛んで爆弾をぽいと落とすだけの水平爆撃よりも命中率が高いのです。
もっと言えば、射撃した後はほぼ運任せな戦艦の主砲弾と比べても高い命中率を出します。戦艦の射撃はたいてい20km以上の遠距離で行われるものですが、撃ってから着弾まで1分強かかってしまいます。その間に相手は移動しているわけで、その1分後の未来予測をせにゃならんのですが、これがとても難しい。
一方で急降下爆撃機による爆撃は、いわば飛行機で戦艦の砲弾を目標の至近距離まで運んでいってそこで切り離して爆撃するわけで。
で、急降下爆撃する時は文字通り機体を急降下させるんですが、普通の飛行機がそんな機動を取ると速度が過大になってしまって急降下姿勢からの機体の引き起こしが出来ず自分自身も地面や海上に爆撃してしまうことに。
そこでこの穴の空いた板、ダイブブレーキがガバッと展開されることにより空気抵抗を増やして速度の増加を防いでおるのです。展開する時は主翼の上下に開くようになっています。
ちなみにフラップとして使うこともできまして、その時は上下分割のダイブブレーキを一体化させて下側に下げてフラップに使います。
後ろから。
ダイブブレーキが上下2枚あるのが分かるかと。
SBDの天蓋の中には操縦手と尾部銃手、後方に撃つ銃が収まるので分割部分が多くて窓枠もたくさん。
胴体下面。
飛び出している四角い口みたいなのは、エンジンのオイルラジエーターの空気取入口です。口は可動式になっていて、空気の流入量(=冷却能力)を調整していたと思われ。
その後ろにある二股の棒は爆弾を懸架するアーム。爆弾を切り離す時はこのアームがびよよ~んと前方に向かって展開して爆弾を放り投げます。
なんでまたそんな面倒な装置を付けたのかというと、ただそのまま爆弾を切り離すとプロペラと当たってしまいます。すると次にどうなるかは想像できると思います。
なので爆弾を機体から離れた状態で投げつける必要があり、このアームが生まれたわけです。
VIDEO
みんな大好き1対40より。6分10秒あたりからSBDが急降下爆撃するんですが、アームが伸び切ったところで爆弾を切り離すことでプロペラを避けているのがよく描写されているかと。
アニメのCGとはいえ、結構プロペラの外側ギリギリを通すんだなと。
SBDの主翼の残骸。原型の主翼ですか。
これはヘンダーソン基地の滑走路の南約90mのところで発見されたもの。1942年の日本軍の砲撃でやられたらしい。ということは1942年10月に行われたヘンダーソン基地艦砲射撃の時の損傷でしょうね。
いずれレストアに回されるのでしょうか?
その横にあった
ベル モデル47D-1 (OH-13E) (1946年・58機目)
エンジンの馬力が足りないために重量対策をした結果骨と皮だけみたいな機体になってしまいどうにも頼りない感じに。あんまり安心して乗れないなぁ・・・。
それでも当時は画期的な機体であったのは違いなく、6,200機以上が造られたそうな。
御存知アメリカ海軍のデブ、
グラマンF6F-5ヘルキャット (1942年・59機目)
F4Fの後継となる次期主力戦闘機の座をF4Uコルセアと争って負けたはずだったんですが、F4Uは空母での運用に難があったとかなんとかでそこから引きずり降ろされ代わりにF6Fが敗者復活して主力の座を射止め、日本をけちょんけちょんにしてやる(アメリカ曰く撃墜損害比率19:1...)というシンデレラストーリーに。
ただし戦争が終わると制空戦に特化した単能機とも言えるF6Fは、爆撃機にも使えて他でもつぶしが利くF4Uに今度は自分がその座を奪われてしまったのだ・・・。その頃になるとF4Uも空母運用に問題ない段階まで改良されましたからね。
このように書くとどこか儚さを感じる戦闘機です。
この機体は1945年3月に就役して、護衛空母USSカサブランカのVF-14飛行隊に配属されたそうな(小型の護衛空母でF6Fを運用できたのか?という疑問符は付くが)。ちなみにこの空母、1943年7月からの1年間でほぼ週一ペースで1隻ずつ計50隻建造しまくったことから呼ばれている「週間護衛空母」の最初の1隻目だったりします。
USSカサブランカの場合、1942年11月に起工、翌年4月に進水、7月に就役とありえねー速さです。これは、これを考えたやつがあのリバティ船をバカスカ造りまくったヘンリー・カイザーだからというのが多分にあるでしょう。
これについて書き始めるとまた長くなるので(笑)断腸の思いで割愛。
そして終戦後はやはりいらない子にされたんですがスクラップにはされず、オレンジ色に塗られて遠隔操作式の無人標的機にされたのでした。
それでも死にきれずにヤンクスにやってきて、大戦時の状態に復元されて今に至ります。
機首にはシャークマウスが描かれています。たぶん機首の空気取入口が口に見えたからでしょうかね。目は充血していて口からは涎が垂れていて生々しい印象。
正面。やはり空気取入口が口に見えますやな。
空気取入口は3分割されていますが、中央がオイルクーラー用、左右がエンジン用の取入口だったような。
艦載機と言えば主翼の折りたたみ機能です。主翼を後方へ折り畳んで胴体と平行にするという手の込んだ方式です。
脚。F4Uが脚が長くなるのを抑えるためにあれこれ苦心したのをよそに何の気なしに短い脚を配置しているのを見ると、これが経験の差かしら?とも思わんでもないです。
F6Fはここまで。
!?!? こっこここコイツは・・・!!
羽の付いたカヌー!?
おいおいおい、ここに置いてあるのかっ!
うわ!本物だ!夢にまで見た
グラマンG-21Aグース 様じゃないですか!(60機目)
ネット上でカルト的人気のある洋画「コマンドー」(1985年)の劇中に登場したものと同型の飛行艇です。登場人物のシンディがG-21について言い放った台詞
「こんなの飛行機じゃないわ!羽の付いたカヌーよ!」 はファンの間で知らぬ者はいないほど。
現存機がスミソニアンに保存されていることは知っていたので、いつの日かそこを襲撃する際に実機と相見えようと機会を伺っていたのですが、思っていたよりもだいぶ早くそれが叶ってしまいましたね。これは事前には知らなかったことだったので、完全に不意打ちですよ。
いやでも、映画俳優にでもバッタリと会ったみたいだ。嬉しいな~。
水上に着水できる飛行艇なので胴体は縦に長く、胴体下面は船のような形状になっています。波をかぶらないように主翼とエンジンは胴体の上の高翼配置になっているのも飛行艇の特徴。
んで、実機の方はと言うと、1937年に初飛行した双発の水陸両用飛行艇です。コマンドー公開の時点で50年近く前の飛行機であり、そりゃシンディもオンボロ扱いするよなというところ。
元は民間機として開発されたのですが、アメリカのロングアイランドに住む金持ちがニューヨークへの通勤の足に使いたいと開発を依頼したもの・・・だそうだ。なんとまぁ。
後にグラマン鉄工所なんて呼ばれるように頑丈な作りで水陸両用の汎用性の高さは軍にも目をつけられて、初飛行の翌年にはアメリカ陸軍がOA-9として採用。さらにアメリカ海軍もJRFの名前で採用しました。JR貨物みたいな名前だな。
この機体は軍に就役した経歴は無いらしく、カリフォルニアのカタリナ航空で本土と島を結んでいたそうな。今はヘリコプターに置き換えられて全部引退しているそうです。
それでもまだ現役の機体も残っているらしいです。特筆すべきは、カナダのパシフィックコースタル航空の所有している4機で、未だに定期便に使用されている模様です。
見た目が意外と近代的なもんですから忘れてしまいがちですが、第二次世界大戦前の機体ですからね。もう驚異的ですね。一度乗ってみたいもんだ。
地上に着陸する時のための脚。胴体への収納式になっているので飛行時や水上走行時に抵抗を抑えます。
胴体に脚を収納するのはこの時期のグラマンらしい手法ですが、他のメーカーの飛行艇もこうだったのかしら?
グラマンF4Fワイルドキャット・・・と見せかけて本当は
ゼネラルモーターズFM-2ワイルドキャット (61機目)。いやまあ、両者は細かいサブタイプを除けば同じ機体なんですが。
F4Fを開発したグラマンは、主力の座を逃したはずのF6Fヘルキャットに海軍から受注が入ると、そっちの生産に集中しなければならなくなりました。大手メーカーのように見えるグラマンですが、自社の生産能力はそれほど高いわけではなかったようで、F6FとTBFアベンジャー雷撃機の生産だけで手一杯になってしまいます。とはいえF4Fにも護衛空母の艦載機向けに未だ需要がありました。
そこで、自動車メーカーのゼネラルモーターズ(GM)が所有していた航空機生産用の工場でF4Fを(それとTBFも)ライセンス生産するようになったのでした。なおGMは航空機生産用の部門、イースタン・エアクラフトを当時立ち上げています。
SBDの項で書いたように海軍の型式名の一部は製造メーカーを表しています。GMには"M"が割り振られたので、型式名もF4FからFM(GMの造った1番目の戦闘機)に変わっています。
脱線しますと、4FとFMは合わせて7,700機が造られたんですが、その内約5,200機はFMです。実に7割近くがGM製のFMなのです。現存機も半数以上はFMでして、F4Fは比較的貴重ということになります。
なのでもし正確な型式名を望むのなら、博物館の解説板でF4Fと書かれているものがあったらちょっと疑ってかかったほうがいいでしょう。知名度で言えばFMよりもF4Fの方が高いので、たとえ中身はFMでもF4Fと解説されている場合がたまにあるらしい。
F4F-3/-4とFM-2の見分け方は、主翼根本の下面にあるオイルクーラーのこぶのような出っ張りです。FM-2にはこれが付いていませぬ。
ただしFM-1はF4F-4と同型なのでどう見分けて良いのか知りませぬ。機銃の数が違うらしいですけど、よく調べてないのでやっぱり分かりません(手抜き
それと、カウリング上部にある過給器用の空気取入口とカウリング内側の過給器のインタークーラー用空気取入口もありませぬ。F4F-4には搭載されていた過給器がFM-2では外されているので。ただ、各形式によるこれらの有無はなんだかややこしいので詳しく調べておらず。各自研究してください(丸投げ
こっちもF6F同様片方の主翼が折り畳まれています。
最初から畳められたわけではなくて、途中の4型からの機能です。F4Fは翼を畳むと畳まないでは横に並べた時の機数が5:2でして、これの省スペース化で空母への搭載機数はかなり良くなったのでしょうし、とりあえず最低限の数があればいい護衛空母では船体の小型化にも繋がったんじゃないかなと思います。
F4Fは脚が可愛いと思うわけです。
胴体に脚を収納する方式でして、当時のグラマン機の特徴でした。これはグラマンの専売特許だったという話もありますが、話の出処をよく覚えておりませぬ。
結構支柱が多くて複雑なのだなという印象。あと、主脚カバーってこれにも取り付けられていたんですね。知らなんだ。
といったところで今日はここまで。
その24へ→
![]()