「名古屋にSOUL JAZZ旅行 #2-2」のつづきは、いよいよエスカレーターでトヨタ博物館の2階に上がり 、
、
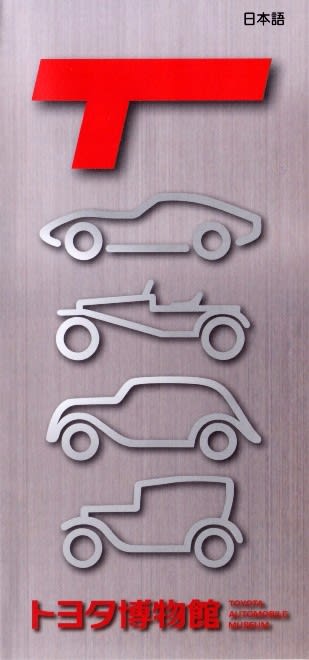
まずは、やはり、来ましたかぁ~
こちらのクルマでした。
ベンツ パテント モトールヴァーゲン [1886]【レプリカ】です。
カール・ベンツが製作した世界最初 のガソリン自動車で、私もTVや写真で見て、形は知っておりました。
のガソリン自動車で、私もTVや写真で見て、形は知っておりました。
説明板 を転記しますと、
を転記しますと、
ベンツ パテント モトールヴァーゲン [レプリカ] (1886 ドイツ)
ガソリン自動車の第1号といわれるベンツの三輪車で、1886年に作られた。棒ハンドルで前輪を操向しており、時速15kmで走行可能であった。
だそうで、スペックは、
全長:2,547mm 全幅:1,454mm 全高:1,623mm
車両重量:313kg ホイールベース:1,450mm
エンジン形式:水冷単気筒 総排気量:984cm^3
最高出力:0.7kW/0.9HP/400min^-1
後ろから見ますと、
水平に設置されたフライホイール(はずみ車)とか、ベルトとか、チェーンとか、機構がむき出しです。
よく見ると、エンジンは水平に置かれていまして、ピストンは車体に対して前後に動き、それがクランクを通じて水平方向の回転運動に変えられ、ギアを通じて垂直方向の回転運動になり、そこからベルトを通じてドライブシャフトに伝わり、ドライブシャフトからチェーンを通じて車輪を廻す、、、という動力の流れがよく判ります
このベンツ パテント モトールヴァーゲンから8年、「フランス、アメリカにも出荷された史上初の量産車」という説明が加えられていたのが、ベンツ ヴェロ [1894]でした。
四輪車になっています。
説明板 によれば、
によれば、
フライホイールを垂直にセットしたエンジン、プーリーとベルトによる2段変速ができ、時速21kmで走行した。
だそうです。
排気量は1,045cm^3(cc)と、ベンツ パテント モトールヴァーゲンとはほとんど同じですが、変速機能が加わったり、速度が向上 したりと、着実に進歩しています。
したりと、着実に進歩しています。
ただ、いかにも馬車の御者席のような運転席、、っつうか、運転者+αしか乗れないという状況に変わりはありません。
つまり、初期の自動車は、「人を運ぶ機械」ではなく「人が動くための機械」だったということでしょうか?
この状況は、パナール ルヴァッソール B2 [1901]でも同じ。
ところが、ロールスロイス 40/50HP シルバーゴースト [1910]になると、
「人を運ぶ機械」になっています。
さらに、イスパノイザ 32CV H6b [1928]では、
前席は御者席の伝統に則って革張り、後席は馬車の伝統に則ってクロス張りと、完全に「ショーファードリブン」の高級車 に変貌しています。
に変貌しています。
この辺りまで来て、私は、自分が大変な勘違いをしていたことに気づきました
私、トヨタ博物館を、歴代のトヨタ車を軸としたトヨタ自動車の史料館 的なイメージを持っていたのですが、現実は、一企業の枠を超えた、普遍的な自動車博物館でした
的なイメージを持っていたのですが、現実は、一企業の枠を超えた、普遍的な自動車博物館でした
う~む…、トヨタ博物館って深い… と、心を入れ換え
と、心を入れ換え 、トヨタ博物館の探訪
、トヨタ博物館の探訪 を続けたのでありました。
を続けたのでありました。
 つづき:2017/09/26 名古屋にSOUL JAZZ旅行 #2-4
つづき:2017/09/26 名古屋にSOUL JAZZ旅行 #2-4

























