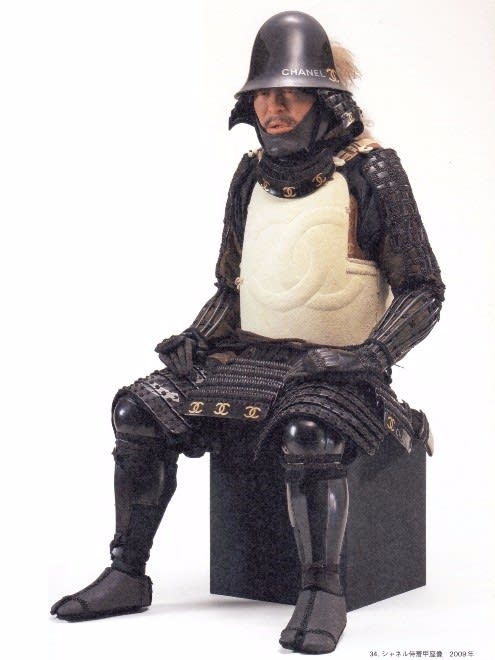「名古屋にSOUL JAZZ旅行 #2-1」のつづきです。
今年2月、私はガラケーからスマホに乗り換えました(こちらの記事をご参照方)。
ご多分にもれず、私もいろいろなアプリをインストールしたわけですが、その一つに、JAF(日本自動車連盟)のデジタル会員証があります。
これまで私、JAFの会員証は、クルマ に乗せたカードホルダーに入れっぱなしでした。
に乗せたカードホルダーに入れっぱなしでした。
これでも、JAFのロードサービスが必要になった場合(私は、2度、自宅駐車場で、バッテリーあがり でお世話になりました。平日ならほぼ毎日クルマを走らせている現在の「カーライフ」ではあり得ない
でお世話になりました。平日ならほぼ毎日クルマを走らせている現在の「カーライフ」ではあり得ない シチュエーションですが…)、クルマのセンターコンソールに入れたカードホルダーから会員証を取りだしてJAFのサービスマン
シチュエーションですが…)、クルマのセンターコンソールに入れたカードホルダーから会員証を取りだしてJAFのサービスマン に見せるには、何の問題もありませんでした。
に見せるには、何の問題もありませんでした。
ただ、世の中にはJAFの会員証を見せると入場料・料金が割引される施設がけっこうあるもので、窓口でJAFの優待サービスがあることを知って、「JAFの会員証を持ってくるんだった… 」となったことが何度もありました。
」となったことが何度もありました。
それが、スマホがJAFの会員証代わりになれば、クルマで出かけたとき以外でも、優待を受けられるっつうわけです。
で、トヨタ博物館、施設の性格上、JAFの優待がないはずはないだろう という目論見どおり、JAFの優待がありまして、団体料金(一般:1,000円⇒800円)で入館できました
という目論見どおり、JAFの優待がありまして、団体料金(一般:1,000円⇒800円)で入館できました
考えてみれば、JAFの優待を使ったのは、これが初めて なんだなぁ
なんだなぁ

トヨタ博物館に入館して最初に展示されていたのは、
トヨタ2000GTでした。
このモデルは、レース仕様でして、
1967年、トヨタは最大の輸出市場であるアメリカにおける企業イメージの向上と技術成果のフィードバックを目的に、米国トヨタ内にレース部門を新設。レース活動は、シェルビー・アメリカンに委託。SCCA Cプロダクションクラスに向けて、予備車1台を含む計3台の2000GTがレースカーに仕立てられた。
ノーマルからの主な変更点は、エンジン出力が約200HPまで高められ、レース専用のタイヤとホイールやサスペンションなどにより車高が約60mm下げられたことなどで、レースに向けた様々な改良が加えられている。
だそうです。
そして、
本車両は(1968年の13のレースシリーズに参戦し)、総合3位の成績を収めた実車両で、6月4日(日)に開催された「TOYOTA 2000GT 生誕50周年祭」に参加するため、アメリカより運び込まれたもの。(現オーナーの) Craig Zinn氏のご厚意により6/25(日)まで当館にて展示の予定。
ということで、今、トヨタ博物館に行っても観られません ので悪しからず…
ので悪しからず…
それはともかく、きれいな曲線 です。
です。
しかも、小ぶりなサイズもイイ
スポーツカーはこれくらいの大きさじゃないとなぁ… と思います。

さて、「お約束」っぽいトヨダAA型乗用車[1936] (ただしレプリカ)を眺めて、
エスカレーターで2階に昇り 、いよいよトヨタ博物館の「本編」が始まります
、いよいよトヨタ博物館の「本編」が始まります のはずなんですが、ここでまた寄り道…
のはずなんですが、ここでまた寄り道…
「トヨタ初の生産型乗用車」だという「トヨダAA型」、「トヨタ」ではなく「トヨダ」ですのでお間違えなく

この辺の事情(?)について、トヨタのHPの説明を転記しておきましょう。
トヨタ自動車の「トヨタ」は、創業者豊田佐吉の苗字、「豊田(トヨダ)」に由来します。じつは、初期の乗用車に添えられたエンブレムは、漢字の読みをそのままローマ字で表記した「TOYODA」でした。しかし、この会社名であり、かつブランド名であった「トヨダ」は、1936年に行われた「トヨダ・マーク」の懸賞募集を経て「トヨタ」へと変わることになります。
この変更の理由は、まず「トヨダ」よりも「トヨタ」のほうが、濁音がなく、さわやかで言葉の調子もいいこと。そして日本語で「トヨタ」と書いた場合、総画数が縁起がいいとされる「8画」になること。さらに創業者の苗字である「トヨダ」から離れることで、個人の会社から社会的企業へと発展するという意味も込められていました。
だそうです。
「トヨタかトヨダか」については、こちらの記事でも書いておりますので、ご興味がおありでしたらどうぞ
で、「トヨダAA型」の運転席周りは、今のクルマと違って極めてシンプル。
一方、後部座席は、シンプルなのは前席と一緒なんですが、なんともエレガント です。
です。
アシストグリップの代わりにタッセル付きの紐がぶら下がっているんですから
現在、アシストグリップの代わりにこんな紐をぶら下げることは認められているのか、車の保安基準とか協定規則とかをザッと見た のですが、あまりにも詳細かつ複雑な規定で、真相究明はあきらめました…
のですが、あまりにも詳細かつ複雑な規定で、真相究明はあきらめました…
そして、負け惜しみ的に、こんな事細かな規定が、「非関税障壁だ 」と突っ込まれる由縁なのかもしれないな、と思った次第。
」と突っ込まれる由縁なのかもしれないな、と思った次第。
例によって、酔っ払った引き手が、左右には動くのだけれど、山車はさっぱり前に進まない 状況みたいになってしまいましたので、きょうはここまでといたします。
状況みたいになってしまいましたので、きょうはここまでといたします。
 つづき:2017/09/21 名古屋にSOUL JAZZ旅行 #2-3
つづき:2017/09/21 名古屋にSOUL JAZZ旅行 #2-3


















 と、もともと
と、もともと
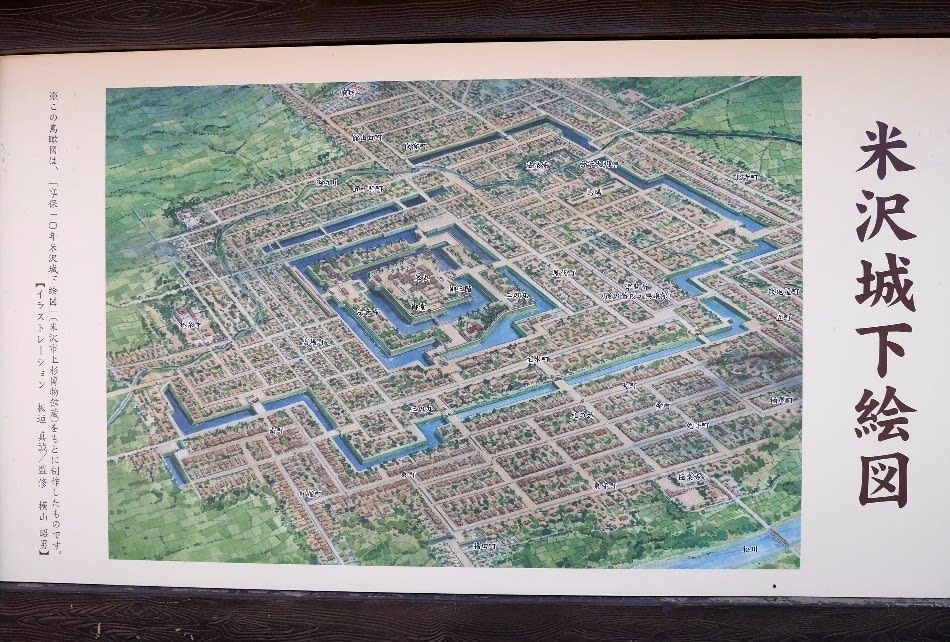



 しつつ、
しつつ、








 二段譜)
二段譜)

 それを
それを
 言われてみれば、
言われてみれば、



















 の解説によれば、
の解説によれば、
























 が
が















 ときのお話は
ときのお話は









 して、
して、 の展覧会
の展覧会