オリンピックでは 陸上競技がスタートしました。
聞いて、ビックリ!?!?
100メートル女子は 56年ぶりの出場!?
400メートル女子は 44年ぶりの出場!?
出場できたことは 何かが変わってきたということで、喜ばしいことですが、なぜ日本人は マラソンに強く、短距離に弱いのか??
運動生理学的な話を講習会や日常の教室などで、陸上競技を例にすることがあります。
エネルギー供給機構では 大きく分けて、無酸素運動~有酸素運動、もう少し細かく分けて・・・
ATP-CP系~解糖系~TCA回路系~脂質分解系というサイクルで、短時間高パワー~長時間低パワーの違いがあり、短距離走~マラソンの時間と照らし合わせて、説明します。
パワーの違いに関しては エネルギー源の違いで、パワフルな力を出せるのは 筋肉に蓄えられているグリコーゲン。
グリコーゲンは 筋肉内に蓄えられているので、筋肉量が多いほうが パワフルな力が出せるということになります。
今回、北島康介選手もウエイトトレーニングをして、上半身の筋肉が かなり多くなっていましたよね。
マラソン選手の身体と短距離選手の身体とを比べると、腕の筋肉の太さは かなり違います。
でも、マラソン、短距離にかかわらず、日本の陸上選手は 他の国の選手と比べると、筋肉が少ないように感じます。
筋肉をつけていないのか? つかないのか?
つけていない・・・というのは トレーニングの質や量だと思います。
走るだけでは 筋肉の量は 増えないでしょうし、ウエイトトレーニングの質や量によっても、筋肉の質や量が かわります。
つかない・・・というのは 日本人、アジア人の体質なのか?
メダル獲得数が 一番多い中国でも、現在、短距離走は 予選を通過する選手はいません。
これも生理学的な側面で、早くパワフルに収縮する筋肉=速筋、ゆっくりと持続的に収縮する筋肉=遅筋があり、多くの人は 半々の割合で持っているそうです。
人によっては その割合が 遺伝的に、どちらかよりで、どんな競技がむいているか?のアスリート開拓に繋がったり、トレーニング内容を決める手立てにもなります。
実際に遺伝検査を行って、アスリートのトレーニングに役立てているケースもあります⇒
http://www.sportsstyle.co.jp/ACTN3/voice.html
トレーニングによって、その割合は 変わらないのですが、乳酸が多く発生するぐらいの強いトレーニングを行うことにより、遅筋は増えないけれど、速筋は 増えるそうです。
参考文献:トレーニング生理学 芳賀 脩光 大野 秀樹
運動生理学を考えながら、オリンピック観戦・・・
実に、効率の良い勉強方法だ!!・・・ということにしておいてください。
今は 運動生理学よりも・・・
あ~~~研究計画書を書かなきゃ!!
聞いて、ビックリ!?!?
100メートル女子は 56年ぶりの出場!?
400メートル女子は 44年ぶりの出場!?
出場できたことは 何かが変わってきたということで、喜ばしいことですが、なぜ日本人は マラソンに強く、短距離に弱いのか??
運動生理学的な話を講習会や日常の教室などで、陸上競技を例にすることがあります。
エネルギー供給機構では 大きく分けて、無酸素運動~有酸素運動、もう少し細かく分けて・・・
ATP-CP系~解糖系~TCA回路系~脂質分解系というサイクルで、短時間高パワー~長時間低パワーの違いがあり、短距離走~マラソンの時間と照らし合わせて、説明します。
パワーの違いに関しては エネルギー源の違いで、パワフルな力を出せるのは 筋肉に蓄えられているグリコーゲン。
グリコーゲンは 筋肉内に蓄えられているので、筋肉量が多いほうが パワフルな力が出せるということになります。
今回、北島康介選手もウエイトトレーニングをして、上半身の筋肉が かなり多くなっていましたよね。
マラソン選手の身体と短距離選手の身体とを比べると、腕の筋肉の太さは かなり違います。
でも、マラソン、短距離にかかわらず、日本の陸上選手は 他の国の選手と比べると、筋肉が少ないように感じます。
筋肉をつけていないのか? つかないのか?
つけていない・・・というのは トレーニングの質や量だと思います。
走るだけでは 筋肉の量は 増えないでしょうし、ウエイトトレーニングの質や量によっても、筋肉の質や量が かわります。
つかない・・・というのは 日本人、アジア人の体質なのか?
メダル獲得数が 一番多い中国でも、現在、短距離走は 予選を通過する選手はいません。
これも生理学的な側面で、早くパワフルに収縮する筋肉=速筋、ゆっくりと持続的に収縮する筋肉=遅筋があり、多くの人は 半々の割合で持っているそうです。
人によっては その割合が 遺伝的に、どちらかよりで、どんな競技がむいているか?のアスリート開拓に繋がったり、トレーニング内容を決める手立てにもなります。
実際に遺伝検査を行って、アスリートのトレーニングに役立てているケースもあります⇒
http://www.sportsstyle.co.jp/ACTN3/voice.html
トレーニングによって、その割合は 変わらないのですが、乳酸が多く発生するぐらいの強いトレーニングを行うことにより、遅筋は増えないけれど、速筋は 増えるそうです。
参考文献:トレーニング生理学 芳賀 脩光 大野 秀樹
運動生理学を考えながら、オリンピック観戦・・・
実に、効率の良い勉強方法だ!!・・・ということにしておいてください。
今は 運動生理学よりも・・・
あ~~~研究計画書を書かなきゃ!!











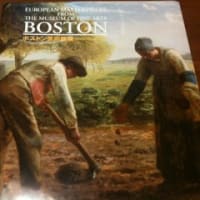







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます