花壇シリーズ
№5

今日の<マメ科の樹木花>は、「エニシダ」の花です。
<「エニシダ」(金雀枝)Cytisus Hybrids>
一般に「エニシダ」と称するのは、常緑低木の品種の Cytisus scoparius を指す由
マメ科の特徴の蝶型の花を咲かせます、花色は、黄色が基本ですが、ピンク、白、赤い斑入り等が有ります。
樹木の姿は、箒型で、葉は、三出複葉で互生します。
「エニシダ」の名前の由来は、ラテン語 genista(ゲニスタ)、スペイン語の hinista(イニエスタ)が
日本に入って「エニスタ」→「エニシダ」になった由、”金雀枝”は、黄色い花を金色の雀に喩えて
枝に群がった様子を著わしたのでしょうか、尚、英名の Broom は、箒です。
”箒” の名前は、細かく分枝した枝振りが<ホウキ>に似ているからとのこと
ヨーロッパ原産で、中国経由で、日本に入ってきたとのこと。
マメ科、エニシダ属、落葉、半常緑低木、学名 Cytisus scoparius 、英名 broom、Scotch broom
「ホオベニエニシダ」(頬紅金雀枝)Cytisus scoparius form.andreanus も面白い色合いです。
翼弁に赤色の斑が入る姿が、頬紅を指した様なので、此の名前が、付いた由
別名「ニシキエニシダ」(錦金雀枝)、落葉低木
園芸種には、 白い花弁に、翼弁が、黄色の花も(Cytisus scoparius 'Moon light' )
交雑種と思われる「ベニバナエニシダ」(紅花金雀枝)も紅紫色の翼弁の花を咲かせています。
他に、草丈が低く花も少ない「ヒメエニシダ」(姫金雀枝)Cytisus × spachianus や
白い花で箒状の枝が見事な落葉低木の「シロバナエニシダ」(白花金雀枝)Cytisus multiflorus が、有ります。
<各画像は、クリックで拡大表示します>





































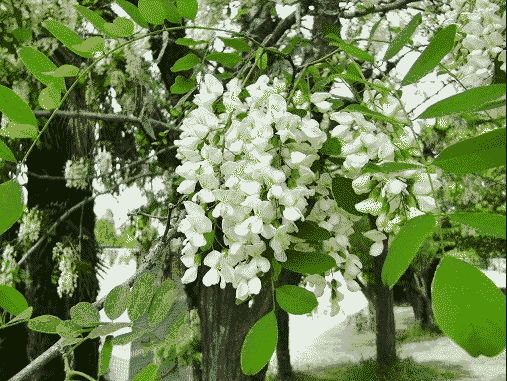
















 「ブルーハイビスカス」が、咲きます、名前は、「ハイビスカス」ですが、ハイビスカス属の「ハイビスカス」とは違って、アリオギネ属です、花の姿も似ていますが、「ブルーハイビス......
「ブルーハイビスカス」が、咲きます、名前は、「ハイビスカス」ですが、ハイビスカス属の「ハイビスカス」とは違って、アリオギネ属です、花の姿も似ていますが、「ブルーハイビス......




