クイズ番組で、小中学校の給食実施率を問う問題の正解を聞いて「ヘェ~!!」と思った。
自分は、小中学校では100%給食が行われていると思っていたが、文科省の平成30年データによると
・小学校-全19,635校、給食実施99.1%(19,453校)で、給食形態は完全給食98.5%・補食給食0.3%・ミルク給食0.3%
・中学校-全10,151校、給食実施89.9%( 9,122 校)で、給食形態は完全給食86.6%・補食給食0.4%・ミルク給食2.9% となっていた。
給食ができない学校や補食(おかず)給食やミルク給食しかできない学校には、それぞれに事情があってのことだろうが、不謹慎にも「ミルク給食とは」と懐かしく感じた。
敗戦後の困窮・食糧難時代、児童の栄養不良解消を目途とした「ミルク給食」があった。当時は米軍放出ミルクと呼ばれていたが、Wikipediaでは米軍放出とララ支援物資が混在していた様である。供されたミルクは脱脂粉乳で、子供心にも臭い・不味いと悪評であったが、今にして思えば「米・雑穀しか食べたことが無かった田舎者」のカルチャーショックであったのかもしれない。
ともあれ、当時の最大罰は「背丈ほどもあったミルク缶に閉じ込められる」ことであったが、悪臭と粉塗れの苦痛から反省した子もいたであろうが、自分への矯正は疑問である。
脱脂粉乳の給食は昭和27年には終了したとされているが、小学校2年生の担任先生とミルク缶体罰の記憶から正しいのだろうと思える。
先日のテレビで、昭和18年生まれの自分よりは遥かに若い方が「今後も戦争悲劇の語り部として活動する」と述べられていた。
自分ですら敗戦後の窮乏の一端を経験しているだけで戦争の悲惨さは知らない。まして自分より年下の方が何をどう語るのかは知らないが、恐らく敗戦後の僅かな体験を後付の知識で補強し今様の倫理観で脚色した「真実」を語られるのだろうものの、昭和30年代まで自分の周りの大人は、むしろ「これくらい何だ。戦地で苦労した兵隊さんを思え」が一般的で、反戦・反軍が広く市民権を得たのは、朝鮮戦争特需で漸くに一息付けた頃からであったように思う。
20年以上も前に、妹尾河童氏が「少年H」という私小説を上梓された、著書で妹尾氏が、ミッドウェィ敗戦やガダルカナルの玉砕をリアルタイムに知ったことで反戦・反軍の意を強固にする過程を述べていることに対して、小林よしのり氏が、それらは軍・政権中枢しか知り得ない厳秘で、地方に住む妹尾氏は知り得ないと反論したことが思い出される。
戦争の語り部は必要であるのかもしれないが、既に戦争・戦場の悲惨さを知っている・体験している人の多くが鬼籍にあることを思えば、語るに際しては体験と伝聞・知識を峻別されて正しく表現されることを望むものである。



















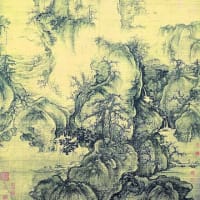
私が学生のころに横井庄一氏がグアムから、小野田寛郎氏がフイリッピンから帰還されたのを思い出しました。横井氏はまもなく大東亜戦争を批判する発言をし、小野田氏は沈黙を守った記憶があります。横井氏に対し多少の驚きを覚えました。短期間に日本の状況を理解され、それに対し自分の意見を述べられたことです。
私が二人と同じ状況だったらどういう態度をとるであろうか?
世間の状況を理解するのに多大な時間が掛かるかもしれないし、あるいは戦争に負けたことに対する怒りと憤りでわめき散らすかもしれない。
それとも小野田氏みたいに沈黙を守るであろうか。
語り部の方には、戦争で亡くなった方々の無念の思いを汲み上げて語って欲しいものです。
木下惠介監督の映画「陸軍」の最後の場面は、田中絹代氏演じる母親が息子の出兵の行進を泣きながら追いかけ、息子は笑って応える姿です。私はその場面を観ると涙が溢れてきます。
7世紀の唐・新羅連合軍に対する北九州の守りのため子供を東北の地に置いていく防人の歌があります。これもジーンときます。
これらは非常な運命に従って自分の役割をはたす人達の思いが私に伝わって来たからでしょう。
語り部の方には人々の運命と役割について深い洞察を持って語ってほしいものです。
コメントを有難うございます。
これまでに、講演会や誌面で多くの語り部に出会いましたが、共通しているのは「実体験」・「出所不明の受け売り」が混然したケースが多かったように思えます。
実体験に基づく主張に対しては、好悪を捨てて傾聴すべきと考えますが、後者に対しては特定の結論への誘導が目立ち、鼻白む思いがします。