経済面の小さな記事で、食用コオロギ飼育が企業として成り立っていることを知った。
記事は、NTT東が食用コオロギ飼育のベンチャー企業にAIを用いた管理を支援するという内容であった。
既に昆虫食を提供する飲食店があるとは聞いていたので、飼育は虫かごやプランタンによる内職程度だろうと思っていたが、企業による工場生産であったのかと驚いている。
記事で昆虫食は、《人口増に対して食肉生産が追い付かないと予測される中、環境負荷が少ないタンパク源として注目されている》と結ばれていたので、マニアの昆虫食から国民食と変化する日も近いのかもしれない。また、現在市場に出回っている食品の成分表示に書かれた「タンパク質」も、実は昆虫であり自分もそれとは知らずに食べていることも考えられる。
ちなみに、Amazonでも一袋2000円程度で数多くラインアップされているところを見れば、昆虫食は既にマニア限定ではなくなったと考えるべきであるように思える。
歴史本では、○○の大飢饉では「ネズミや蛇はおろか「虫までも」食べて飢えを凌いだ」と記述されていることも多いが、タンパク源確保に関しては先祖返りも現実になりそうである。
戦後の食料難時代、生まれ育った九州の寒村ではコオロギ・バッタ等の虫は履いて捨てるほどいた。後年に東北地方を中心としてバッタの佃煮や蜂の子の唐揚げを食べる文化・風習があることを知ったが、食文化の違いからであろうが九州ではそれらを食べることは無かった。そういえば銀座の高級店でも供される「タラの芽」も、生まれ在所にはタラの木が自生していたものの、芽を食べたことは無いのは誰も思いつかなかったのであろうか。
最後に昆虫食をWikipediaでは《ハチの幼虫、イナゴなど、昆虫を食べることである。食材としては幼虫や蛹(さなぎ)が比較的多く用いられるが、成虫や卵も対象とされる。アジア29国、アメリカ大陸23国で食べられ、アフリカの36国では少なくとも527種の昆虫が食べられており、世界で食用にされる昆虫の種類を細かく集計すると1,400~2,000種にものぼるといわれる》と解説されている。
近い将来「えエ!!~またコオロギ?」と子供が叫ぶ日も近いのかもしれない。














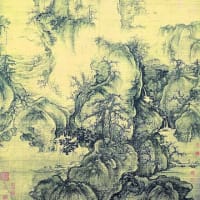





数十年前にTBSラジオ番組「小沢昭一的こころ」を聞いていたら、小沢昭一氏が長野県で講演した際、夜に接待を受けたそうです。高級クラブで高級酒などを勧められほろ酔い気分になっていると新たに「おつまみ」がでてきてよく見ると「蚕」だったそうです。幼虫「モスラ」を小さくしたものです。何かの冗談だろうと思っていたら、側の若くてきれいなホステス達がおいしそうに食べているのを見てビックリしたそうです。
主催者の方が勧めるので何とか頑張って一匹食べようとしたら「蛾」も沢山皿に盛られていたそうです。成虫「モスラ」です。上目遣いに主催者の顔を見たら、口の周りに鱗粉がたくさん着いており口の端から緑色の汁が流れていたとのことです。不気味な顔にさすがの小沢氏も卒倒しそうになり「ダメだ!もうダメだ!助けてくれ!」と思ったそうです。
話し上手な小沢氏のことだから面白可笑しく話したのだろうと思って、長野出身の友人に聞くと「蚕」はスーパーで売っているとのことでした。
小学生の時、蜂の子を生きたまま食べたことがあり、特に蜜蜂の幼虫は歯で噛むとプッチとして蜜の味がして美味しかった思い出があります。イナゴの佃煮もありました。
昆虫が食卓に上るにはまだ時間がかかると思います。昆虫を食する事に対する国民に気持ちは「小沢昭一的こころ」でまだ満ちているからしばらく時間がかかるでしょう。
おはようございます。
現役時、寄港地の一杯飲み屋の「お通し」がイナゴの佃煮でした。酔った勢いで口にしましたが、ところどころにピンと突っ張り出た足は、素面ではだめだろうと思ったことを思い出しました。
まァ残りの人生では「虫の姿煮」とは無縁でいられるだろうと思っています。