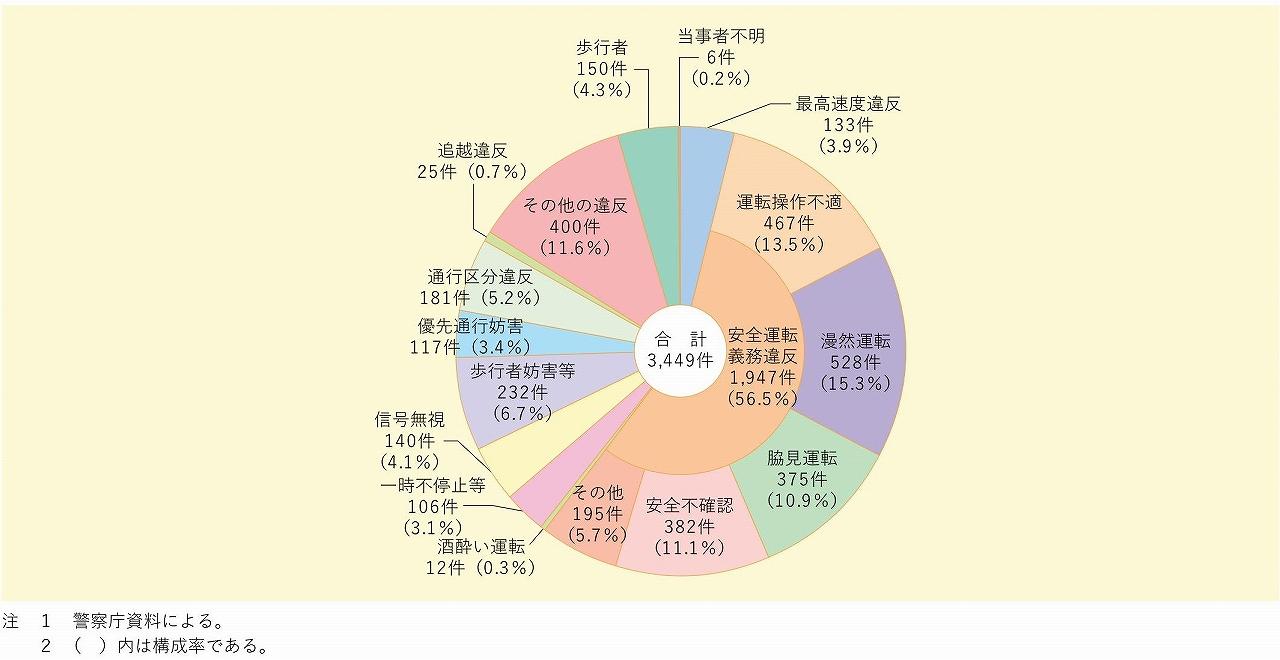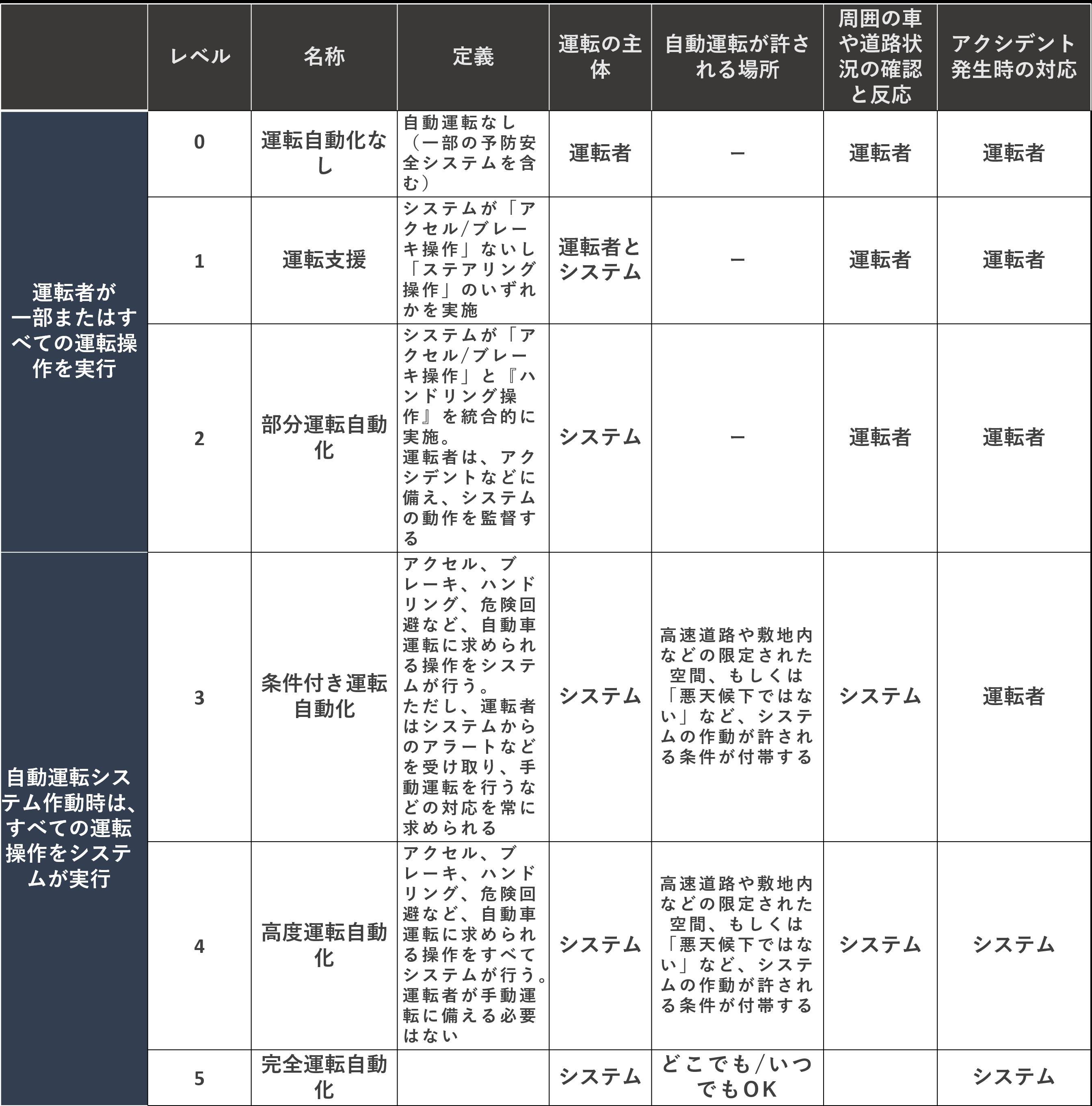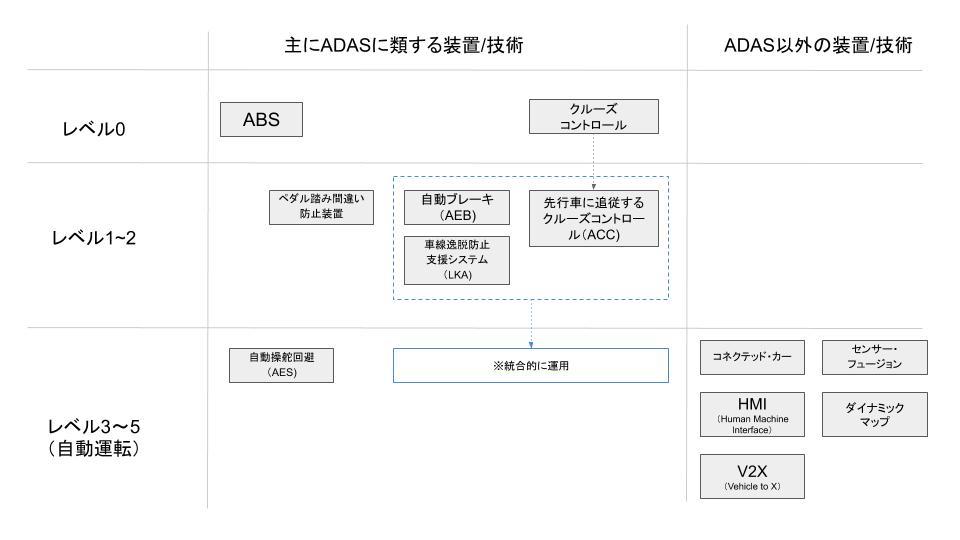主に一般企業での就職を目指したい精神障害(うつ病、統合失調症、適応障害、不安障害など)や発達障害(アスペルガー症候群、ADHD、広汎性発達障害など)、知的障害のある方のための社会的スキルやコミュニケーション力向上のトレーニングを行っております。 自分の適職を知るために自己理解や職業理解を深め、自分にあった仕事を選んで就職し、長く働き続けられるような支援を実施しています。
就労移行支援事業所チャレンジド・アソウがトレーニングの見学・体験会を開催します。
主に一般企業での就職を目指したい精神障害(うつ病、統合失調症、適応障害、不安障害など)や発達障害(アスペルガー症候群、ADHD、広汎性発達障害など)、 知的障害のある方のための社会的スキルやコミュニケーション力向上のトレーニングを行っております。
自分の適職を知るために自己理解や職業理解を深め、自分にあった仕事を選んで就職し、 長く働き続けられるような支援を実施しています。
チャレンジド・アソウはこんな方におすすめ
●一般企業への就職を目指す障害者の方
●仕事が続かず悩んでいる方
●就職後もサポートを受けたい方
●心身の不調が続きブランクが長く不安な方
など 、当事者やその保護者、支援者の皆さま
無料で気軽に参加できる、トレーニング体験来て、参加して体感できる
チャレンジド・アソウに実際にご来所いただくことで、立地や施設、トレーニング中の環境などがわかります。
個別で社員と話ができる
通所に関する質問やご希望など、社員が個別で相談を承ります。
一緒に話すことで、どんな社員がいるのかを知っていただけます。
支援内容が自分の希望と合っているかがわかる
トレーニングを実際に体験することで、支援内容を実感することができます。
通所のイメージがつかめないという方にもおすすめです。
内容、アクセス、お申込みなど、詳しくは下記をご覧ください
当日のプログラム
① 受付・見学 13:00~13:20
受付スタッフにお名前をお伝えください。
受付が終わりましたら、進行中のトレーニングの様子をご見学いただけます。
チャレンジド・アソウでのトレーニングの様子を肌で感じてみて下さい。
② 会社説明 13:20 ~ 13:45
会社説明では、チャレンジド・アソウがどのような取り組みをしているかを紹介いたします。
事業所概要、トレーニング、カリキュラム、一日の流れ、定着支援など、資料を用いて説明いたします。
③ 体験トレーニング 13:55 ~ 14:30
会社説明後の休憩をはさんだ後は、チャレンジド・アソウのカリキュラムから
トレーニングを体験していただけます。
④ 個別面談 14:30 ~ 15:00
体験後は社員との個別での面談タイムが設けられています。
障害のこと、就労移行での支援内容、疑問や不安などなんでもお話下さい。
【事業所説明】
新大阪事業所では、訓練生が発表形式で参加者のみなさんに説明を行います。
日々のカリキュラムの成果をご覧いただけます。
大阪事業所では、スライド画像を用いてチャレンジド・アソウの取組をご紹介いたします。
いつもトレーニングを受けている訓練生の目線で社員の説明を受けることができます。
【メモを取る・作業する】
休憩をはさみ、職場での作業指示をメモする練習を行います。
社員から口頭で指示を受けメモを取り、不明点の質問をします。
とったメモを見ながら指示通りの作業に取り組む、実務的なトレーニングを体験頂けます。
トレーニング内容は、初めての方でもチャレンジして頂ける内容です。
日時・会場
2019年10月17日(木)実施
株式会社チャレンジド・アソウ 大阪事業所
〒540-0026
大阪市中央区内本町2-4-16
オフィスポート内本町9階
電話:06-6809-2456
FAX:06-6809-2457
Email:challenged-aso@ahc-net.co.jp
2019年10月24日(木)実施
株式会社チャレンジド・アソウ新大阪事業所
〒532-0011
大阪市淀川区西中島1-11-16
新大阪CSPビル本館1階
電話:06-6309-7060
FAX:06-6309-7061
Email:challenged-aso@ahc-net.co.jp
お申込み方法
電話、FAX(チラシ裏面お申込み用紙)、メール、HPのお問い合わせフォームからお申込みください