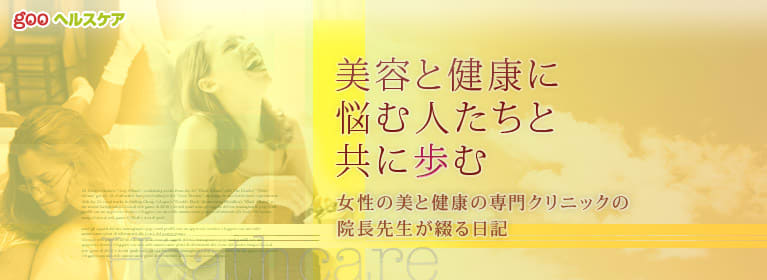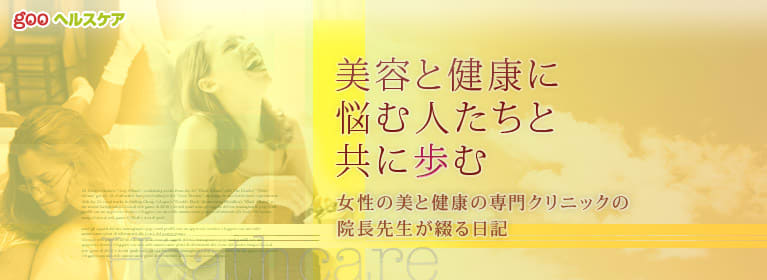
|
|
みなさん、こんにちは。
2018年になり、早くも1週間が経ちましたが、
いかがお過ごしですか?
今の時期はダイエット中の方にとってはとても厳しい時期ですよね。
中には正月太りをしてしまった方もいらっしゃると思います。
さて本日は、
「七草粥」についてお話しいたします。
七草粥は、
人日の節句(1月7日)の朝に食べられている、
行事食です。
七草粥には、
・セリ
・ナズナ
・ゴギョウ
・ハコベラ
・ホトケノザ
・スズナ
・スズシロ
といった早春の頃一番に芽吹く七草が含まれており、
今年1年の無病息災を祈願して食べるものだと言われています。
それだけでなく、
年末年始の暴飲暴食によって疲れた胃を休め、
野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補う目的や、
日常の食生活に戻るひとつの区切りという意味もあります。
実際に七草の中には、
胃腸の消化吸収を助け、
デトックス効果が期待できる食材もあります。
正月太りをしてしまった方は、
七草粥のように
消化が良く低カロリーのものを中心とした食事を心掛け、
徐々に日々の生活に戻していきましょう。
では。

みなさん、明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
さて、みなさんはどのように年末年始をお過ごしになりましたか?
今の時期は食べる機会が多く、
中々ダイエットが上手くいかない方という方も多いと思います。
本日は年末年始に良く食べる食材「餅」についてお話いたします。
餅はダイエットには向かない食材だと思われていますが、
実際にはどうなのでしょか。
餅のカロリーは、
・切り餅1個(50g) 約118kcal
・切り餅2個(100g)は、約236kcal です。
一方白米は、
ご飯お茶碗並盛(140g)で約240kcal のため、
カロリー数からみると、
ダイエット中、餅は絶対食べてはいけない食材ではなく、
お正月くらいは食べても良いのではと考えます。
また、
・磯辺焼き 約133kcal(餅1個使用)
・ぜんざい 約336kcal(餅1個使用)
と、調理法によってカロリーは大幅に変化するため、注意が必要です。
餅を食べる際は1口20回以上噛むことを意識し、
くれぐれも食べ過ぎには注意しましょう。
では。

みなさん、こんにちは。
今の時期、冷えたビールのお供に枝豆を召し上がる方も多いのではないでしょうか。
枝豆は未熟な大豆を収穫したもので、一般的な枝豆は黄大豆という品種ですが、
本日は、枝豆の中でも今が旬の「だだちゃ豆」についてお話ししたいと思います。
だだちゃ豆は山形県庄内地方の鶴岡市で栽培されている大豆の品種で、
「だだちゃ」は庄内地方で「お父さん」を意味する方言です。
一般的な枝豆よりさやの産毛や豆自体がやや茶色がかっており、
香りが豊かで、味が濃く、甘みが強いのに加えて、
オルニチン、メチオニン、カリウム、食物繊維、GABA、葉酸など、
栄養価が非常に高いのも特徴です。
中でも、疲労回復や二日酔い改善に効果がある事で知られているオルニチンは
一般的な枝豆よりもだだちゃ豆の方が含有率が高く、
オルニチンを多く含む代表的な食材であるシジミよりも
だだちゃ豆の方が多いという分析結果も出ています。
また、うまみ成分であるアミノ酸の一種「アラニン」も豊富である他、
脂肪燃焼効果を高める「カルニチン」を合成する原料となる「メチオニン」、
むくみ解消効果が期待できる「カリウム」など、嬉しい効果が沢山あります。
ダイエット中の間食としても優れており、
不足しがちな植物性タンパク質を補うことが出来ます。
塩分を摂り過ぎないよう、塩を入れないで茹でて食べる事をおすすめします。
美味しくて栄養価も高い食材であるだだちゃ豆。
是非、食卓に摂り入れてみてはいかがでしょうか。
では。

みなさん、こんにちは。
みなさんは1日にどれくらいお酢を摂取されていますか?
意識的に摂り入れないとなかなか難しいかとは思いますが、
お酢には健康に嬉しい効果がたくさんあります。
中でも、お酢を摂取する事による
メタボ、生活習慣病対策について色々と臨床試験が行われており、
その健康効果が実証されています。
「お酢の効果」
お酢を毎日15~30ml(大さじ1杯~2杯)程度摂取することで、
①内臓脂肪減少
②血中脂質の低下
③血圧低下
④血糖値上昇抑制
などへのサポートが期待できます。
特にお酢は高血圧予防の強い味方です。
人間は塩分を摂りすぎると体内の塩分濃度を下げようと
水分を過剰に摂取するため、血圧が上がってしまいます。
そのため高血圧の方には減塩食が薦められていますが、減塩食は味気ないですよね。
そこで、塩の代わりにお酢を使って味付けをすることで、
塩分を控えながらも満足感のある味に調理することが出来ます。
今はインターネットなどでもお酢を使ったレシピがたくさん掲載されていますので、
積極的に日々の食卓に摂り入れてみてくださいね。
では。

みなさん、こんにちは。
本日はビタミンDについてお話ししたいと思います。
ビタミンDは骨の形成に大きく関与している栄養素で、
紫外線の刺激により体内で合成されます。
欠乏すると大人の場合には骨軟化症、
子どもの場合はくる病を発症する可能性があると言われています。
また、高齢者になると骨粗鬆症などを引き起こす原因にもなり、
閉経後の女性は女性ホルモンの低下によりそのリスクが増大します。
近年では食の欧米化に伴う魚離れなど、
食生活の変化によるビタミンD不足も懸念されています。
先日「20代の女性が週3回以上日焼け止めを使った場合、
血中のビタミンD濃度が常に「欠乏状態」になっていた。」という記事を目にしました。
https://mainichi.jp/articles/20170712/k00/00e/040/241000c
この研究結果に関して、はっきりとしたことは申し上げられませんが、
研究チームによると、「直ちに病気になるわけではないが、
ビタミンDを含む食品で補ってほしい」との事でした。
ビタミンDは紫外線を浴びることや、製剤処方のほかに、食事からも摂取できます。
シラスや鮭などの魚介類、卵(卵黄)、きのこ類などに含まれますので、
上手に食卓に摂り入れ、ビタミンD不足解消を心掛けましょう。
では。

みなさん、こんにちは。
“オスモチン(osmotin)”という成分をご存知でしょうか?
オスモチンは野菜や果物に含まれる植物由来のペプチドでファイトケミカルのひとつです。
“ファイトケミカル(フィトケミカル/phytochemical)”とは、
植物由来の化学物質のことで、
主に植物の色素や香り成分、アクやえぐみ・辛味などに含まれています。
ファイトケミカルの中でもオスモチンは
トマト・ジャガイモ・トウモロコシ・ピーマン・サクランボなどに含まれており、
メタボリックシンドロームや糖尿病を予防する効果が期待できます。
そのメカニズムとして、
オスモチンにはアディポネクチンの受容体を活性化させる働きがあります。
アディポネクチンとは脂肪細胞から分泌されるホルモンの一種で、
脂肪燃焼・抗炎症・動脈硬化の抑制・インスリンの働きをサポートする作用があり、
これによりメタボリックシンドロームや糖尿病など、
生活習慣病の予防に効果的とされています。
植物に含まれるオスモチンは人体のアディポネクチンと似た構造と働きをしている為、
オスモチンを体内に取り込む事でアディポネクチンの代役として働いてくれます。
つまりオスモチン含有の食物を摂取する事で脂肪と糖の代謝が促進され、
アディポネクチンと同様の効果を得る事が期待できます。
オスモチンは日常的に取り入れやすい食品に含まれておりますので、
是非、日々の食事に取り入れてみてくださいね。
では。

みなさん、こんにちは。
普段炭酸水は飲まれますか?
ヨーロッパでは古くから炭酸水を飲む文化がありますが、
美容や健康にも良い事から近年では日本でも
飲食店やコンビニなどでも目にするようになりましたよね。
ダイエットに効果的だという声も多く耳にします。
炭酸水(無糖)を使用したダイエットには様々な意見があるようですが、
飲む量やタイミングが重要で、きちんと守れば効果的なダイエットが出来そうです。
まず、飲む量は少量過ぎると空腹を感じさせるホルモンである
「グレリン」が増加する事でかえって食欲が増し、過食になる傾向があります。
食前か食中に約500~1000ml飲むことで胃が炭酸によって膨らむ為、
少量の食事で満腹感が得られ食べ過ぎを防いでくれます。
また、炭酸水は腸の蠕動運動を亢進させます。
炭酸水にも種類が沢山ありますが、
中でも硬度の高い「ペリエ」などは便秘にも効果的だそうです。
炭酸水を上手く利用すればダイエットに効果的だと考えますが、
くれぐれも1日3食バランスの良い食事を摂った上で、炭酸水をプラスして下さいね。
では。

みなさん、こんにちは。
いつも何気なく食べている「もやし」には、
大きく分けて3種類あることをご存知ですか?
一般的な「緑豆もやし」、
細い形状の「ブラックマッペ」、
そして豆がついている「大豆もやし」に分かれ、
それぞれ暗所で発芽されたものです。
本日は、韓国料理のナムルでよく使われている
「大豆もやし」についてご説明します。
大豆もやしは、
総カロリー量 100gあたり37kcal
1袋(約192g) 71kcal
と、緑豆もやし(1袋30kcal)よりカロリーは高いですが、
ダイエットの強い味方といえます。
その理由として、
大豆もやしには、
イソフラボン
レシチン
サポニン
ビタミンB1、C、E、K、
葉酸
食物繊維
などが含まれており、
カリウムは、緑豆もやしに比べ約2.8倍多く含有しているため、
利尿作用に優れており、むくみ改善効果が期待できます。
さらにレシチンにはコレステロール低下作用、
サポニンには脂肪の吸収を抑えてくれる作用もあります。
女性のダイエットにも有効で、PMS(月経前症候群)にみられる
食欲増強、イライラ感などに対して、
大豆もやしに含まれるγーアミノ酸(GABA)が精神を安定させ、
リラックスさせる効果もあるようです。
また女性ホルモンを整える意味で、イソフラボンも効果的であると言えます。
調理の仕方は様々ですが、
ビタミンCを失わないためにも過熱しすぎないことが大切です。
このようにダイエットに有効的である大豆もやしを、
食事の中に取り入れてみてはいかがでしょうか。
特に女性の場合は生理前、生理中に摂取することをおすすめします。
ただし、大豆もやしばかりを食べる単品ダイエットはくれぐれもしないよう、お気を付けください。
では。

みなさん、こんにちは。
皆さんアスパラガスは好きですか?
一番美味しい旬の時期がやってきました。
アスパラガスにはホワイトとグリーンがありますが、
栄養たっぷりなのはグリーンでしょう。
アスパラガスは100gで22kcalと低カロリーで、
その成分中には、アミノ酸の一種であるアスパラギン酸、
β-カロチン、ビタミンB、C、E、さらにメチルメチオニン、
穂先部分には特に多くのルチン(ビタミンP)が含まれています。
< 効能 >
・ビタミンB…疲労回復、脂肪燃焼効果
・ビタミンE…血流改善効果
・ビタミンC…美白効果
・ルチン…利尿効果、むくみ改善、血管を丈夫に
・アスパラギン酸…睡眠効果、新陳代謝促進、滋養強壮
・メチルメチオニン…タバコの解毒効果
・食物繊維…便秘解消
また、カロチン、ビタミンE、ビタミンCを同時に摂取することが出来る為、
抗酸化作用が高く、アンチエイジング、癌の抑制、美容にも効果があります。
ダイエット中の方も野菜の一つとして摂取してみてはいかがですか?
ただし、いつも私がブログで申し上げている通り、
アスパラガスばかりを摂る単品ダイエットはしないようにしましょう。
では。

みなさん、「MXフラクション」をご存知でしょうか?
「MXフラクション」は舞茸だけに存在する多糖類(βーグルカン)の成分です。
主な効果は、血糖値の急上昇を抑え、コレステロール値を下げる効果があります。
つまり「MXフラクション」は、インシュリンの過剰分泌を抑え、
さらに体内でのブドウ糖の合成も抑制する働きがあります。
また肝臓でのコレステロールの合成を抑制し、
腸管でのコレステロールの吸収をおさえ、排出を促進するということです。
舞茸には「MXフラクション」だけでなく、
不溶性食物繊維、キノコに含まれるキノコキトサンを含むことも、ダイエットには有効だと考えます。
舞茸自体のカロリーも100g/16kcalと低カロリーです。
調理法や摂り方は割愛いたしますが、
バランスのとれた食事の中での舞茸の摂取が大切ですので、
単品ダイエットにならないよう注意してくださいね。では。

|
|