今朝、文藝春秋の3月号が郵送されてきました。
すぐに、今年の芥川賞を受賞した黒田夏子の、”abさんご”を読み始めました。
”受像者”を始めとして15の短編を集めたものです。
読み始めてすぐに、読むのに難渋する作品であることが分かりました。
冒頭の書き出し部分をアップしてみます。
aというがっこうとbというがっこうのどちらにいくのかと、会うおとなたちのくちぐちにきいた百にちほどがあったが、
きかれた小児はちょうどその町を離れていくところだったから、aにもbにもついにむえんだった。
これは小説というよりも、実験的な散文詩の寄せ集めのように思えます。
確かに日本語の柔らかさは感じられますが、読み疲れがたまっていきます。
頭の中でひらがなを漢字に変換して、高校時代の古典文学の解読を強制されるからです。
面白さを感じることもなく、半分でギブアップしてしまいました。
今日は日本中で文藝春秋を手にした人々が苦しんだことだろうと思います。
すぐに、今年の芥川賞を受賞した黒田夏子の、”abさんご”を読み始めました。
”受像者”を始めとして15の短編を集めたものです。
読み始めてすぐに、読むのに難渋する作品であることが分かりました。
冒頭の書き出し部分をアップしてみます。
aというがっこうとbというがっこうのどちらにいくのかと、会うおとなたちのくちぐちにきいた百にちほどがあったが、
きかれた小児はちょうどその町を離れていくところだったから、aにもbにもついにむえんだった。
これは小説というよりも、実験的な散文詩の寄せ集めのように思えます。
確かに日本語の柔らかさは感じられますが、読み疲れがたまっていきます。
頭の中でひらがなを漢字に変換して、高校時代の古典文学の解読を強制されるからです。
面白さを感じることもなく、半分でギブアップしてしまいました。
今日は日本中で文藝春秋を手にした人々が苦しんだことだろうと思います。










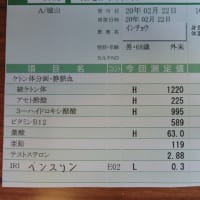
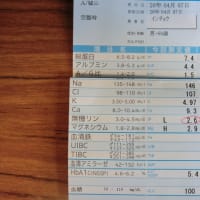
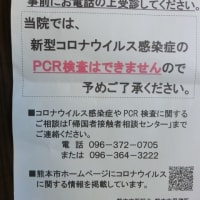

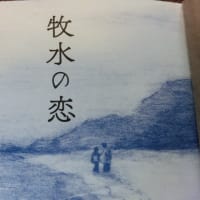
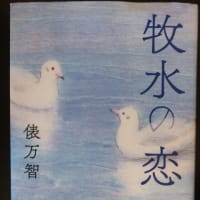
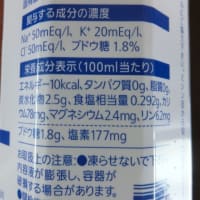


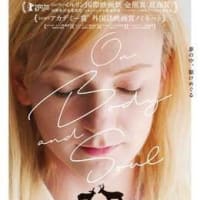

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます