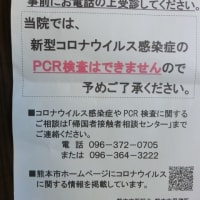庄司薫の、”赤頭巾ちゃん気をつけて ”よりも4年早い1964年に芥川賞を受賞した作品です。
私は高校時代に読んだのですが、今日、読み返してみました。
私の記憶ではヒロインは優子でした。
東大生である主人公の文夫は20歳のときに、仲間内のレクリエーションとして男女3人ずつで野尻湖畔にある東大寮に旅します。
その中の優子という20歳の東大生と交際を始めます。
しかし、やがてはデイトの回数も減っていき、二人は疎遠になっていきます。
そして優子は東大の教室で睡眠薬自殺をします。
病院に集まった友人達は優子を悼みます。
しかし、そのシーンで文夫は友人達を憎むのです。
私たちは蒸し暑い病院の中庭の日陰で、優子の両親の上京を待った。
みなよくしゃべった。
それは、殆ど快活とさえみえた。
私は彼らを憎んだ。
わたしは、彼らが優子の死を充分悼まなかったことを憎んだのではない。
彼らは充分悼んでいた。
だが、それにもかかわらず、いや、おそらくは、自分たちが友人である優子の死を悼まぬ訳はないと素直に信じられればこそ、
彼らは、自分が今人生の大事とかかわりあっているのだという意識に興奮し、無意識のうちに快活にさえなっていたのだ。
そして私は、彼らのそうした快活さを憎んだ。
この部分を初めて読んだ私は、柴田翔の観察力と表現力に舌を巻きました。
そして優子という名前とともに私の脳裏に深く刻み込まれたのです。
私にとっての、 ”されどわれらが日々ー”は、まさにこのくだりなのです。
ところが、実際のヒロインは文夫の遠い親戚でもある幼なじみの節子でした。
驚きました。
途中で挿入される優子のエピソードが強烈だったので、本筋がごっそりと記憶から抜け落ちていたのです。
優子も一筋縄ではいかないような性格だったのですが、節子になると、もはや手に負えません。
それでも前半から婚約するくらいまでは、なんとかついて行くことができました。
ところが、終盤の行動や手紙に至っては、もうお手上げです。
柴田翔がこの作品を書いたのは、計算すれば、20代の後半です。
私は節子という性格の女の存在は 嘘 だと思います。
若かった柴田翔が観念として作り上げたモンスターでしょうが、ありえません。
鼻白んでしまうと表現すれば良いのでしょうか、まるで心に響きません。
私は、とんでもない悪人が正義の味方にやつけられた時に、いきなり改心して善人になるというストーリーを幼い頃から憎みました。
幼心にも 嘘 を嗅ぎつけていたのでしょう。
そんなことを思い起こさせる作品でした。