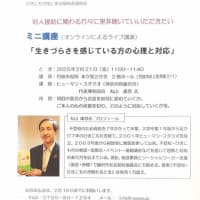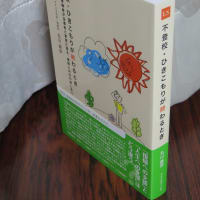8月26日~28日、私は出張研修のため関西に滞在しました。メインのスケジュールは「第11回登校拒否・不登校問題全国のつどい(大阪大会)」への参加です。
そこで私は、青年のひきこもりを考える分科会で、1日目と2日目とで違うグループに入ったのですが、1日目に入ったグループで考えさせられることがありました。
そのグループには、関西を代表する不登校の専門家のひとりである、某大学の先生がおられました。そして、参加している親御さん方が、相次いでわが子への対応に関する迷いを語られたことから、話はしだいに「親の本気」「親の覚悟」についての内容になりました。
そして時間がたつにつれ、その先生をはじめ何人かの参加者が、長引くひきこもりへの対応のあり方として「わが子に自立を迫るか、わが子を一生支えていくかのいずれかを、親は覚悟を決めて選択しよう」と、親御さん方に本気になるよう盛んに助言していました。
聞いていて私は「親御さんにとって、覚悟を決めるのは難しいこと。だから助言は親御さんを楽にしないだろう」と感じていました。
もっとも、こういう研修会は1回限りのものですし、時間にも限りがあります。そのような場では、出てきた話題について「こうするべき」という結論を導き出して時間内にまとめる、という進行の仕方になるのは、当然のことでしょう。
私だって、同じような場である青少年支援セミナーや、一方的に発信するメルマガでは、似たようなことをやっているわけですから。
ただ、あの場では、親御さんに「○○だから覚悟が決まらないんですね」などと、覚悟が決まらない事情や気持ちをみんなで共有し、そのことについて一緒に考える時間を過ごしたほうが、参加していた親御さん方が楽になれたのではないかと思ったのです。
結論をはっきりと打ち出せば、その話題に該当する参加者への助言にはなります。しかし、そこはあえて結論を出さずに、みんなで「ああでもないこうでもない」と、グダグダ語り合ううちに終わってもよかったのではなかったか、というわけです。
当メルマガでも再三お話ししているように「そんなこと気にするな」とか「常識を捨てようよ」とか「親はこうすべきです」とか、それらは本人自身・親御さんご自身が、とっくにわかっていることばかりです。
わかっているけど実行できない、実行できるようになることを阻む状況があるわけです。
そのような状況は、助言や指導によって一朝一夕に変えられるものではありません。
なぜなら、本人や親御さんは、日々苦しい思いに耐えながら過ごしています。気持ちに余裕はなく、したがって状況を変える力を発揮することは難しいと思うのです。
本人や親御さんが楽になり、気持ちに余裕ができてこそ、初めて状況を変える力が発揮できるようになるわけです。
そしてそれは、先ほど研修会の例でお話ししたように、助言するよりも、本人や親御さんの現在の状態を肯定し、そこに寄り添って共に歩むことでしか実現しないと思います。
確かに、これを研修会でやれば時間がつぶれます。つまり、このような考え方での援助によって、本人や親御さんが楽になり、気持ちに余裕ができるまでには、ある程度の時間が必要です。それでも、時間をかけたらかけただけの効果はあるわけです。
さて、私はまさにそういう考え方を相談業務で実践しています。
不登校やひきこもりになって、どうすればよいか悩んでいる本人はもちろん、そういうわが子にどう対応したらよいかお迷いの親御さんに対して、私は「こうすべきだ」と助言することはほとんどありません。
せいぜい、話し合っていてお互い見えてきたことについて「そういうことならこうしたらどうですか?」と提案する、という程度です。
しかも、私の提案と違うことをおやりになっても、問題にすることはありません。次にそこから話を続ければいいだけのことです。
つまり私の援助は、本人や親御さんを「望ましい方向にまっすぐ進むよう導く」のではなく「歩いている本人や親御さんに付いて歩き、一緒にあっち行ったりこっち行ったりしながら、望ましい方向を見つけ出していく」というイメージなわけです。
このような私の援助方針のもとになっているのは「スクールソーシャルワーク(SSW)」という、本人や親御さんに寄り添い、共に歩むパートナーになる方法です。
同時にSSWは、家族・学校・地域といった環境全体を視野に入れて、それに関わっているあらゆる要因や人の関係を調整し活用して、協力体制をつくります。
そうすることで、本人や親御さんが楽になり、気持ちに余裕ができて、状況を変える力が発揮できるようになるわけです。
「旅は道連れって言うじゃないですか。幸せを見つける旅にお供させてください。幸せのありかは誰も知らないけど、私は地図を持っているのでお役に立てます。幸せに通じる道を一緒に探しましょう。」
私はこう言いたいのです。
2006.10.04 [No.130]
このコラムに続く3回シリーズ「周囲の助言、ウソとホント」の第1回に読み進む
そこで私は、青年のひきこもりを考える分科会で、1日目と2日目とで違うグループに入ったのですが、1日目に入ったグループで考えさせられることがありました。
そのグループには、関西を代表する不登校の専門家のひとりである、某大学の先生がおられました。そして、参加している親御さん方が、相次いでわが子への対応に関する迷いを語られたことから、話はしだいに「親の本気」「親の覚悟」についての内容になりました。
そして時間がたつにつれ、その先生をはじめ何人かの参加者が、長引くひきこもりへの対応のあり方として「わが子に自立を迫るか、わが子を一生支えていくかのいずれかを、親は覚悟を決めて選択しよう」と、親御さん方に本気になるよう盛んに助言していました。
聞いていて私は「親御さんにとって、覚悟を決めるのは難しいこと。だから助言は親御さんを楽にしないだろう」と感じていました。
もっとも、こういう研修会は1回限りのものですし、時間にも限りがあります。そのような場では、出てきた話題について「こうするべき」という結論を導き出して時間内にまとめる、という進行の仕方になるのは、当然のことでしょう。
私だって、同じような場である青少年支援セミナーや、一方的に発信するメルマガでは、似たようなことをやっているわけですから。
ただ、あの場では、親御さんに「○○だから覚悟が決まらないんですね」などと、覚悟が決まらない事情や気持ちをみんなで共有し、そのことについて一緒に考える時間を過ごしたほうが、参加していた親御さん方が楽になれたのではないかと思ったのです。
結論をはっきりと打ち出せば、その話題に該当する参加者への助言にはなります。しかし、そこはあえて結論を出さずに、みんなで「ああでもないこうでもない」と、グダグダ語り合ううちに終わってもよかったのではなかったか、というわけです。
当メルマガでも再三お話ししているように「そんなこと気にするな」とか「常識を捨てようよ」とか「親はこうすべきです」とか、それらは本人自身・親御さんご自身が、とっくにわかっていることばかりです。
わかっているけど実行できない、実行できるようになることを阻む状況があるわけです。
そのような状況は、助言や指導によって一朝一夕に変えられるものではありません。
なぜなら、本人や親御さんは、日々苦しい思いに耐えながら過ごしています。気持ちに余裕はなく、したがって状況を変える力を発揮することは難しいと思うのです。
本人や親御さんが楽になり、気持ちに余裕ができてこそ、初めて状況を変える力が発揮できるようになるわけです。
そしてそれは、先ほど研修会の例でお話ししたように、助言するよりも、本人や親御さんの現在の状態を肯定し、そこに寄り添って共に歩むことでしか実現しないと思います。
確かに、これを研修会でやれば時間がつぶれます。つまり、このような考え方での援助によって、本人や親御さんが楽になり、気持ちに余裕ができるまでには、ある程度の時間が必要です。それでも、時間をかけたらかけただけの効果はあるわけです。
さて、私はまさにそういう考え方を相談業務で実践しています。
不登校やひきこもりになって、どうすればよいか悩んでいる本人はもちろん、そういうわが子にどう対応したらよいかお迷いの親御さんに対して、私は「こうすべきだ」と助言することはほとんどありません。
せいぜい、話し合っていてお互い見えてきたことについて「そういうことならこうしたらどうですか?」と提案する、という程度です。
しかも、私の提案と違うことをおやりになっても、問題にすることはありません。次にそこから話を続ければいいだけのことです。
つまり私の援助は、本人や親御さんを「望ましい方向にまっすぐ進むよう導く」のではなく「歩いている本人や親御さんに付いて歩き、一緒にあっち行ったりこっち行ったりしながら、望ましい方向を見つけ出していく」というイメージなわけです。
このような私の援助方針のもとになっているのは「スクールソーシャルワーク(SSW)」という、本人や親御さんに寄り添い、共に歩むパートナーになる方法です。
同時にSSWは、家族・学校・地域といった環境全体を視野に入れて、それに関わっているあらゆる要因や人の関係を調整し活用して、協力体制をつくります。
そうすることで、本人や親御さんが楽になり、気持ちに余裕ができて、状況を変える力が発揮できるようになるわけです。
「旅は道連れって言うじゃないですか。幸せを見つける旅にお供させてください。幸せのありかは誰も知らないけど、私は地図を持っているのでお役に立てます。幸せに通じる道を一緒に探しましょう。」
私はこう言いたいのです。
2006.10.04 [No.130]
このコラムに続く3回シリーズ「周囲の助言、ウソとホント」の第1回に読み進む