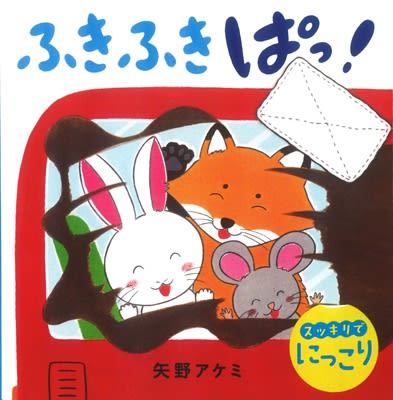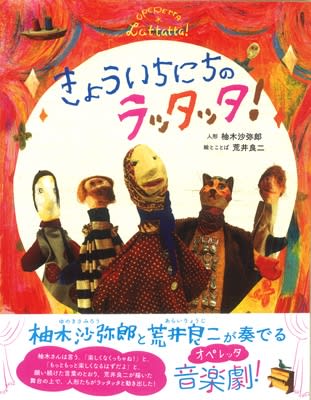本日は「絵本レベルアップコース」1回目の授業です。講師は高畠純さん。
先ずは頭の体操をしましょう。
3〜4人のグループに分かれて、高畠さんが言う「言葉」から連想するものをどんどん書いていきます。

頭の体操。連想するものを書いていく
①秋と言えば
栗、柿、サンマ……など思いつくままに書いていきます。
②冬と言えば
●●●……
③ホームセンターで売っているもの
●●●……
次は「しりとり」です。
④イヌからしりとりを始めて、 書いていきます。
イヌ→ぬりかべ→ベルト→●●●●……
⑤次に動物といえば
ウシ、イヌ、サイ、●●●●……
⑥人間の動作といえば
ねる、あくび、走る、●●●●……
⑦人間の感情といえば
笑う、怒る、泣く、●●●●……
⑧食べ物のメニュー
オムライス、ラーメン、餃子、●●●●……
⑧乗り物の種類
バス、車、飛行機、空飛ぶじゅうたん、●●●●……
さあ、頭が柔らかくなりましたか!
次はワークショップです。
純さんが持ってきました袋の中には「動物」の名前が入っています。袋から1枚引いてそこにある名前で「しりとり絵本」を作ります。
何もないところから絵本を作るにはハードルが高いので、このようにヒントとなるテーマがあれば、すこしは制作しやすいかと思います。
例えば 「くま」でしたら、「ま」から始まる言葉ではなく、くまの前に言葉をつける。やさしいくま→まの悪いネコ→●●●●→●●●●→●●●●→最後の言葉は「ん」で終わるか「や」で終わる。

個別に絵本のダミーを講評
今日の授業は以上です。
ではまた12月にお会いしましょう!