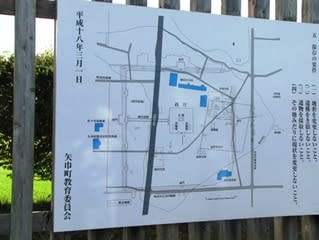ず~と昔から、武夷山のお茶「大紅袍」の茶の木を見たいと憧れていた。
福建省で台湾の向かいの位置だから、すこし涼しくなってからと思っているうちに行く機会を逃していた。
やっと やっと 念願がかなった。
今思い出しても、いい旅だった。
◆9月24日(晴~曇)福州は気温25度で蒸し暑い
関西国際空港~中国福州まで 福州泊

福州に着いた

福州の朝の通勤風景
車も増えているが、自転車 電動自転車(エコ対策で政府が推奨している)
スクーター バイクが相変わらず多い

街角で朝食の人たち
バスで武夷山まで(4時間ほどかかった)
着いてすぐ食事 予想外においしい(山菜中心と言われていたのにとんでもない)
茶葉を使った料理は期待していたが、スープからいためものまで使われていた
写真以外に、焼き飯とスイカ 野鳥のスープが付いている

茶葉がそのままで炒められていた
苦味が思いのほか良い

万頭のたれにも茶葉が入っている

キノコの種類は豊富でしゃきしゃきとしておいしい


きくらげ よくつかわれている

鹿肉 においもなく食べやすい

ウサギの肉 思いのほか甘辛ダレでおいしかった


パスタ 名古屋のきしめんのような麺

鶏肉


キャベツの炒めもの

川魚のフライ

これ、蛇の焼酎漬け(閩 ミン 蛇を門の中に閉じ込めたの意)
昔 武夷山は蛇が多くて困っていたが、蛇を閉じ込めてこの文字を当てたといわれている。この文字は、現在は車のナンバーの最初ははすべて使われている)
◆午後から登山
中国の人たちは、登山が好きだと知っていたけれどこの旅では800メートルほどの登山が計画されていることを知らなかった。見上げれば遊山客が蟻のように岩山の階段にへばりついて上っている。40分後に頂上でと言われて休み休み登り始める。
曇り空がありがたい。自然複合世界遺産に登録されているだけあり、下から吹き上げてくる 風が心地よい。

この岩山に上る(古代海からの隆起によりできた1枚岩)
こんな山が36峰ある
![]()
リスも遊んでいる 名も知らない鳥はたくさん トンボや蝶もいる


さあ スタート

3分の1くらいにある東屋

こんな休憩所もある

40分かけて汗をふきふき山頂へ
頂上では、蒋介石夫人 宗美麗が住んでいた部屋が展示されていた。

見下ろせば九曲渓がはるかかなたに見下ろされる。明日は竹の筏下りだ。

下り道で、駕籠に乗った女性たちとあったら「これに座っているのも、しんどいで~ かいてくれている方たちに、きずつないわ~」(関西の旅人見たい 聞く余裕もないがさもありなんと思う)

自然林の中をほっとしながら、下山
あ~ あ~ 疲れた
◆9月25日(土) 福州 ~ 武夷山
玉宝山登山
印象武夷山(チャン イーモウ監督 360度転回の舞台劇)観賞
◆9月26日(日) 武夷山 ~ 福州
九曲渓筏下り
水簾洞
大紅袍景観地区
◆9月27日 福州 ~ 関西国際空港
福建省で台湾の向かいの位置だから、すこし涼しくなってからと思っているうちに行く機会を逃していた。
やっと やっと 念願がかなった。
今思い出しても、いい旅だった。
◆9月24日(晴~曇)福州は気温25度で蒸し暑い
関西国際空港~中国福州まで 福州泊

福州に着いた

福州の朝の通勤風景
車も増えているが、自転車 電動自転車(エコ対策で政府が推奨している)
スクーター バイクが相変わらず多い

街角で朝食の人たち
バスで武夷山まで(4時間ほどかかった)
着いてすぐ食事 予想外においしい(山菜中心と言われていたのにとんでもない)
茶葉を使った料理は期待していたが、スープからいためものまで使われていた
写真以外に、焼き飯とスイカ 野鳥のスープが付いている

茶葉がそのままで炒められていた
苦味が思いのほか良い

万頭のたれにも茶葉が入っている

キノコの種類は豊富でしゃきしゃきとしておいしい


きくらげ よくつかわれている

鹿肉 においもなく食べやすい

ウサギの肉 思いのほか甘辛ダレでおいしかった


パスタ 名古屋のきしめんのような麺

鶏肉


キャベツの炒めもの

川魚のフライ

これ、蛇の焼酎漬け(閩 ミン 蛇を門の中に閉じ込めたの意)
昔 武夷山は蛇が多くて困っていたが、蛇を閉じ込めてこの文字を当てたといわれている。この文字は、現在は車のナンバーの最初ははすべて使われている)
◆午後から登山
中国の人たちは、登山が好きだと知っていたけれどこの旅では800メートルほどの登山が計画されていることを知らなかった。見上げれば遊山客が蟻のように岩山の階段にへばりついて上っている。40分後に頂上でと言われて休み休み登り始める。
曇り空がありがたい。自然複合世界遺産に登録されているだけあり、下から吹き上げてくる 風が心地よい。

この岩山に上る(古代海からの隆起によりできた1枚岩)
こんな山が36峰ある
リスも遊んでいる 名も知らない鳥はたくさん トンボや蝶もいる


さあ スタート

3分の1くらいにある東屋

こんな休憩所もある

40分かけて汗をふきふき山頂へ
頂上では、蒋介石夫人 宗美麗が住んでいた部屋が展示されていた。

見下ろせば九曲渓がはるかかなたに見下ろされる。明日は竹の筏下りだ。

下り道で、駕籠に乗った女性たちとあったら「これに座っているのも、しんどいで~ かいてくれている方たちに、きずつないわ~」(関西の旅人見たい 聞く余裕もないがさもありなんと思う)

自然林の中をほっとしながら、下山
あ~ あ~ 疲れた
◆9月25日(土) 福州 ~ 武夷山
玉宝山登山
印象武夷山(チャン イーモウ監督 360度転回の舞台劇)観賞
◆9月26日(日) 武夷山 ~ 福州
九曲渓筏下り
水簾洞
大紅袍景観地区
◆9月27日 福州 ~ 関西国際空港