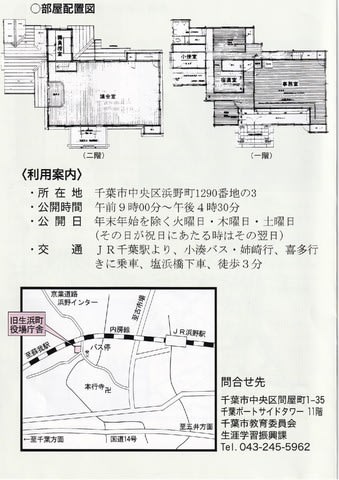上中里駅から京浜東北線で東十条駅に来ました。
ここから十条駅に向かいます。

突然に踏切です。
最近都会の真ん中で平面交差の踏切があるのは珍しい。
電車の車輪は大きいですね。

十条駅です。昔(のことを言うと笑われますが)赤羽線と言って池袋と赤羽の間をコトコト走っていました。が
いまや埼京線になり渋谷方面から大宮まで通勤線として活躍しています。
さらには川越線に乗り入れ八高線の高麗川駅、そして電化区間は八王子駅まで、また北に向かえば気動車に乗って高崎まで秩父の山々をのんびり見ながら旅ができます。
そんなわけでこの辺も近いうちに高架線になるそうです。大動脈です。

TVでおなじみ十条銀座の商店街が見えてきました。

魚屋さん、少し時間が早いせいかまだ人はまばらです。

でも行列の出来ている店舗もあります。

あいにく休みですがこの店はよくTVの中継に出ますね。店一杯に焼き鳥など並べておいしそうです。

かなり長いアーケード街になっています。
砂町銀座、戸越銀座とならんで十条銀座。
ご隠居の子供のころはどこの駅前にでも見られた風景ですが、駅前にすら大型スーパーができてまわりは寂しくなりました。
商店街がシャッター通りにになったら今度はダイエーが倒産したりして世の中、目まぐるしいです。

十条銀座が終わると青空が見える富士見銀座となりました。
銀座通りの大安売りです。
この先は環七通りになります。見渡しても大きなスーパーも見られないのでこの辺が繁盛しているのでしょうか。

東十条駅の方に戻ると十条富士が鎮座していました。
古墳と想定される塚を利用して築山されたようです。
地元では「おふじさん」と呼ばれて親しまれているそうです。

場所はこじんまりとしていますが、6/30、7/1の大祭(山開き)は沢山のテントが出て店が並ぶそうです。
小高い丘でも山開きというのはいいですね。

都心でも神社仏閣のある場所には大木が茂っていていいですね。
スダジイは暖地性の照葉樹林で福島県から台湾の見える与那国島まで日本の暖かい場所ならどこにでも見られる木です。
伊豆半島になんか冬旅行するとクス、タブの木、ツバキなどの常緑樹が山一杯に覆いかぶさっています。
紅葉する木も美しいですが陽ざしを浴びた暖かそうな常緑樹と沖を流れる紺碧の黒潮、白い灯台でもあればなおさら素晴らしい景色です。
砂漠などは原油が出て儲かっていても緑は少なそう。地球って公平にできていますね。
人間の歴史は森や林をみるとすぐにぶった切って宅地や農地にしますが将来のためにも緑を残したいですよね。