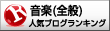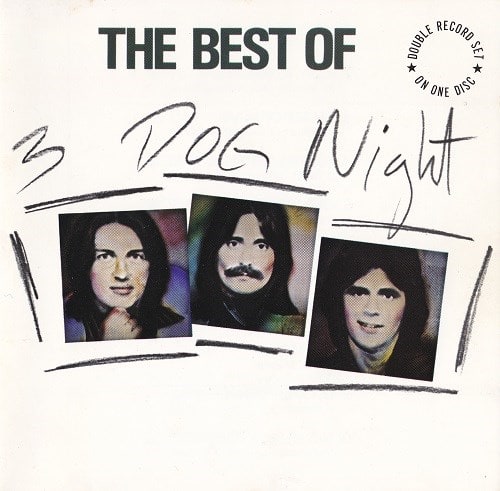日本中津々浦々で繰り広げられた熱い応援もむなしく、わが阪神タイガースはクライマックス・シリーズで2連敗し、今シーズンの戦いは終了いたしました。
何を隠そう、ぼくも小学1年の時以来の阪神ファンでして、時にはこうやって思い出したように野球ネタの記事をエントリーすることもあります。
というわけで、タイガースの諸選手、スタッフ、ファンの方々に「いつもありがとうございます」の意味を込めて、「阪神タイガースの歌」についていろいろ書いてみたいと思います。
俗に「六甲颪」(ろっこうおろし)と言われていますが、それはあくまで通称で、正式には「阪神タイガースの歌」といいます。(ぼくもてっきり「六甲颪」が正式名だと思ってました)
1936年に「大阪タイガースの歌」として発表され、1961年に球団名が「阪神」に変わったのを契機に「阪神タイガースの歌」と改題されました。ちなみに、この曲は、現存する12球団の球団歌の中で最も古いものです。

熱狂する甲子園球場右翼席。名物のジェット風船。
作詞者の佐藤惣之助氏は詩人・作詞家で、著名な詩人・作家の萩原朔太郎の義弟にあたります。代表作に「赤城の子守唄」(歌・東海林太郎)、「湖畔の宿」(歌・高峰三枝子)、「人生の並木路」(歌・ディック・ミネ)などがあります。
作曲者の古関裕而氏は戦前、戦後を通じて多数の歌謡曲、マーチ、応援歌、軍歌を手掛けています。主な作品には、夏の高校野球で有名な「栄冠は君に輝く」のほか、「長崎の鐘」(歌・藤山一郎)、「君の名は」(歌・織井茂子)、「高原列車は行く」(歌・岡本敦郎)などがあります。
意外なことに、わがタイガースのライバルでもある読売ジャイアンツの歌「巨人軍の歌(闘魂こめて)」と中日ドラゴンズの「ドラゴンズの歌」の作曲者も、古関氏だったんですね。
「六甲颪」の通称は朝日放送アナウンサーで、熱烈な阪神ファンとしても知られた中村鋭一氏の発案だそうです。「六甲颪」は、中村氏が1970年代に自分が司会を務めていた番組「おはようパーソナリティ中村鋭一です」で、阪神が勝利した翌日に番組内で歌われたことによって多くのファンに広められました。1973年に発売された中村氏の歌による「六甲颪」はなんと40万枚以上のヒットを記録したそうです。
なお、「六甲颪」とは、冬に神戸市の北側に位置する六甲山系から吹き降ろす、乾燥して冷たい風のことで、実際に甲子園球場に吹く「浜風」とは発生の原理が違うそうです。プロ野球シーズンである4~10月には六甲颪は吹きません。
さて、今シーズンのわがタイガースは、頼りになるのがリリーフ陣のいわゆるJFKだけ、という有様ながら、終盤戦で怒涛の10連勝を記録、一時は最大12ゲーム差もあった首位との差をひっくり返す快進撃でわれわれファンを熱狂させてくれました(ヌカ喜び、とも言いますが・・・(--;))。来年は先発投手を育て、林・桜井・狩野らを始めとする若手陣をさらに伸ばして、ペナントを奪回してもらいたいものであります。

[歌 詞]
◆阪神タイガースの歌
■発表
1936年2月
■作詞
佐藤惣之助
■作曲
古関裕而
■歌
中野忠晴(1936年リリース)
中村鋭一(1972年リリース シングル売上40万枚以上)
立川清登(1980年リリース
道上洋三(1985年リリース)
トーマス・オマリー(1994年リリース) ほか
レコードの時代からコンパクト・ディスクの時代へ移っていった1980年代、その時点で400枚以上のLPレコードを持っていたぼくは、その大半を中古専門店に持ち込んで処分してしまいました。
「もうCDに買い換えたから必要ない」と割り切ってしまったのですが(今考えると、もったいないことをした、という気持ちです)、「CDが出たらまた買えばいい」と判断して処分したものもたくさんありました。その中にはスリー・ドッグ・ナイトのオリジナル・アルバムも5、6枚含まれていたはずです。

一時はとても大きな人気を誇ったバンドだったので、すぐCD化されると思ったのが大きな間違いでした。待っても待っても復刻される気配はなく、ようやく見つけたのがこのベスト・アルバムでした。その間、辛うじて所持していたベスト・アルバム2枚とライヴ・アルバムをレコードで聴いてしのいでいたわけです。
スリー・ドッグ・ナイトはぼくが大好きなアメリカン・ロック・バンドのひとつです。リズム&ブルーズをベースに、高度なアレンジと演奏力で次々と名曲を発表、一時はヒット・パレードの常連でした。
リリースしたシングル23枚、うちTop50以内が21枚、Top30以内が19枚、そして全米1位3曲を含む10枚がTop10にランクされています。ミリオン・セラーは7曲です。
また、発表したオリジナル・アルバム14枚のうち、Top30以内が12枚、Top10以内が5枚と、アルバム・セールスでも抜群の好成績を誇っています。

このバンドの特徴は、何といっても3人のヴォーカリストを擁していたことでしょう。それぞれがリード・ヴォーカルを取れる力の持ち主で、黒人音楽に傾倒していました。とくにチャック・ネグロンはその芸名からわかる通り、ニグロ、つまり黒人への憧れをオープンにしていたようです。実際、彼のヴォーカル・スタイルは、まるで黒人シンガーが歌っているのかと思わせられるほど黒っぽいものです。
このベスト・アルバムには20曲が収録されていますが、いずれもシングル・カットされたもの。とくに日本で人気の高かった「喜びの世界」「オールド・ファッションド・ラヴ・ソング」をはじめ、「ワン」「イーライズ・カミング」「ママ・トールド・ミー」など、数々のヒット曲が収められています。
中でもぼくが好きなのは、オーティス・レディングのアレンジを踏襲した「トライ・ア・リトル・テンダーネス」です。この曲でリード・ヴォーカルを取るコリー・ウェルズの異様な黒っぽさと演奏は、オーティス版に勝るとも劣らないエモーショナルかつスリリングな出来栄えだと思います。
また、コリーの黒っぽいヴォーカルの中では、ブルーズの「ネヴァー・ビーン・トゥ・スペイン」などもとても気に入ってます。
奇異なのは、これらのヒット曲はすべてカヴァーであることです。でも、逆に言うと、無名でも大いなる可能性を秘めた曲を掘り起こす眼力があった、ということでしょうね。

これだけヒット曲を持つバンドのアルバムがなかなか再発されなかったのは不思議です。版権の関係か何かでしょうか。現在では何タイトルか復刻されているみたいですね。
「スリー・ドッグ・ナイト」という一風変わったバンド名ですが、これは「寒い夜は三匹の犬と寝るとよい」というオーストラリアの原住民の言い伝えに由来したものだそうですね。

スリー・ドッグ・ナイトはいったん1977年にいったん解散しましたが、1983年に再結成。現在はダニー・ハットンとコリー・ウェルズを中心に、おもにライヴで活動しているようです。
◆ベスト・オブ・スリー・ドッグ・ナイト/The Best Of Three Dog Night
■歌・演奏
スリー・ドッグ・ナイト/Three Dog Night
■リリース
1982年
■プロデュース
リチャード・ポドラー、ガブリエル・メクラー、ジミー・イエナー/Richard Podolor, Gabriel Mekler, Jimmy Ienner
■収録曲
① 喜びの世界/Joy to the World (Hoyt Axton)
② イージー・トゥ・ビー・ハード/Easy to Be Hard (Galt MacDermot, James Rado, Gerome Ragni)
③ ファミリー・オブ・マン/The Family of Man (Jack Cnrad, Paul Williams)
④ 人生なんてそんなものさ/Sure As I'm Sittin' Here (John Hiatt)
⑤ オールド・ファッションド・ラヴ・ソング/An Old Fashioned Love Song (Paul Williams)
⑥ ママ・トールド・ミー/Mama Told Me(Not to Come) (Randy Newman)
⑦ トライ・ア・リトル・テンダネス/Try a Little Tenderness (Jimmy Campbell, Reginald Connelly, Harry Woods)
⑧ シャンバラ/Shambala (Daniel Moore)
⑨ レット・ミー・セレナーデ・ユー/Let Me Serenade You (John Finely)
⑩ ネヴァー・ビーン・トゥ・スペイン/Never Been to Spain (Hoyt Axton)
⑪ ブラック & ホワイト/Black and White (David l. Arkin, Earl Robinson)
⑫ ピース・オブ・エイプリル/Pieces of April (Dave Loggins)
⑬ ライアー/Liar (Russ Ballard)
⑭ アウト・イン・ザ・カントリー/Out in the Country (Roger Nichols, Paul Williams)
⑮ ショウ・マスト・ゴー・オン/The Show Must Go On (David Courtney, Leo Sayer)
⑯ イーライズ・カミング/Eli's Coming (Laura Nyro)
⑰ ワン・マン・バンド/One Man Band (Billy Fox, January Tyme, Tommy Kaye)
⑱ ワン/One (Harry Nilsson)
⑲ ブリックヤード・ブルース/Play Something Sweet (Brickyard Blues) (Allen Toussaint)
⑳ セレブレイト/Celebrate (Gary Bonner, Alan Gordon)
■録音メンバー
ダニー・ハットン/Danny Hutton (vocals)
チャック・ネグロン/Chuck Negron (vocals)
コリー・ウェルズ/Cory Wells (vocals)
マイク・オールサップ/Mike Allsup (guitar)
ジミー・グリーンスプーン/Jimmy Greenspoon (keyboards ①~③,⑤~⑱,⑳)
スキップ・コンテ/Skip Konte (keyboards ④⑲)
ジョー・シャーミー/Joe Schermie (bass ①~③,⑤~⑦,⑩~⑭,⑯~⑱,⑳)
ジャック・ライランド/Jack Ryland (bass ④⑧⑨⑮⑲)
フロイド・スニード/Floyd Sneed (drums, percussions)
今日は一日中薄曇りで、ちょっと肌寒かったので、早くも薄手のセーターを着て過ごしました。それでも秋の空気はなんとなく清々しく感じられるものです。
昼間、少し部屋を片付けようと思い立って、押入れの中を引っ張り出してみたのですが、その中に「ビートルズ詩集」(全2巻 角川文庫)があるのを見つけました。
懐かしい~。これ多分、中学生の時に買ったんだと思います。
値段を見ると、1冊300円!。古本屋さんで買ったのかもしれないな~。
ビートルズを聴き始めたのが小学生の時。中学時代にその熱が高まり、レコードだけでなく、関連の本も何冊も買った記憶があるのですが、引越しの時にでも紛れたのでしょう、大半の本を失くしてしまいました。
「ビートルズ詩集1&2」も失くしたと思っていた中の2冊だったので、思いがけず見つけることができて、少々ハッピーです。

CDにおける歌詞の訳者は山本安見氏だったけれど、この本の訳者は片岡義男氏。156曲が原題のABC順に並べられています。でも、目次を見ると、タイトルもほとんど日本語訳されているので、とっさに原題を思い出すことができない曲もいくつかあります。例えば「きみと生きなければ」(ゴット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ)、「命がけでにげろ」(ラン・フォー・ユア・ライフ)、「うまくゆくはず」(ウィ・キャン・ワーク・イット・アウト=恋を抱きしめよう)などです。
片岡氏は「あとがき」で次のように語っています。
「トータルな体験の世界からはなれて、レノン=マッカートニー曲の詞のみを日本語にうつしかえることに対する疑問はのこしたまま、日本語訳は無色で透明なものに仕上がるよう心がけた。そしてその心がけは、ほぼつらぬかれた」
「(略)どの曲にもさぞや独特ないろどりがほどこされ、においが織りこまれているはずだと思ってしまうのだが、意外にそうではない。かたちづくられている世界は、どの曲においてもかなり広くて透明なのだ」
「ビートルズの歌がこのようであるからには、意訳は無限に可能である」
そして、レコードから言葉をとらえ、そのまま訳した、ということです。
つまり、完璧な訳を目指したのではなくて、片岡氏流の意訳である、というわけですね。
今まで曲、つまりメロディー中心に聴いてきたので、せっかく詩集が見つかったのをきっかけに、歌詞も味わいながら曲を楽しむのも悪くない、と思っているところです。
人気blogランキングへ←クリックよろしくお願いします<(_ _)>
いわゆる「第3期ディープ・パープル」の傑作です。
このアルバムからヴォーカリストとベーシストが交代していますが、それがパープルの新たなセールス・ポイントになっています。
つんざくようなハイ・トーン・ヴォイスの持ち主だったイアン・ギランに代わるデヴィッド・カヴァーデイルのヴォーカルは、R&Bの影響を受けたソウルフルなもので、とても個性的です。デヴィッドはマーヴィン・ゲイらのソウル・シンガーからも大きな影響を受けているそうですね。
新ベーシストは元トラピーズのグレン・ヒューズ。ヴォーカリストとしても評価が高いグレンの持ち味はイアン・ギランばりのシャウトです。ソウルフルなデヴィッドとメタリックで豪快なグレンとのツイン・ヴォーカルは、間違いなくパープル・サウンドに新たな風を送り込んでいます。
1曲目の「紫の炎」からボルテージは最高潮。
この曲のリフは実にスリリング。「スモーク・オン・ザ・ウォーター」などと並ぶハード・ロックの名曲です。当時のギター少年は大抵この曲のコピーにも挑んでいたのではないでしょうか。間奏部分にJ.S.バッハのコード進行が使われているというのも有名な話ですね。とくにジョン・ロードの弾くオルガン・ソロはとても美しく、強く印象に残ります。イアン・ペイスのドラムも溌剌としているし、デヴィッドとグレンのコーラス・ワークも曲に厚みを与えているし、とにかく、パープルのレパートリーの中では、三本の指に入るくらいの名曲ではないでしょうか。
この時期以降のライヴでは欠かせない「ユー・フール・ノー・ワン」と「ミストゥリーテッド」も注目曲ですね。
「ユー・フール・ノー・ワン」はドラムスの刻むスピーディーな16ビートがイントロです。テーマに突入するや、ふたりのヴォーカルの厚いコーラス、ギター、オルガン、ベース、ドラムスが一体の音の塊となって押し寄せてきます。まさに迫力満点。ライヴではよくこの曲でドラムがソロを取っています。
「ミストゥリーテッド」はパープル版ブルースだと言っていいのではないでしょうか。
いわゆるブルースのコード進行ではありませんが、この曲に込められた想いはまさにブルースでしょう。粘るような重いリズムに乗って、デヴィッドのどこまでもソウルフルなヴォーカルが冴えわたります。リッチーのギターもとてもヘヴィです。この曲の間奏はリッチーのギターの独壇場ですね。
後年、パープル解散後、リッチーが結成したレインボウも、デヴィッドが結成したホワイトスネイクも、この曲をレパートリーとしていたようです。ただし二人の考え方は正反対で、リッチーが「これはギターのための曲だ」と言っているのに対し、デヴィッドは「ヴォーカル曲に決まっているだろ」と反論していたそうです。
アルバムラストを飾る「"A"200」、インストゥルメンタルなんですが、これがまたカッコいい曲なんです。ギター・ソロがまさに鬼気迫る出来栄え。リッチーが縦横無尽に弾きまくっています。
もしも、数あるディープ・パープルのアルバムの中から3枚選べ、と言われたら、そうですね、やっぱり「ライヴ・イン・ジャパン」「マシン・ヘッド」と、この「紫の炎」になるでしょうか。でも「イン・ロック」や、ライヴでの「紫の炎」が収録されている「メイド・イン・ヨーロッパ」のど迫力も捨て難いんですよね。
◆紫の炎/Burn
■歌・演奏
ディープ・パープル/Deep Purple
■リリース
1974年2月15日
■プロデュース
ディープ・パープル/Deep Purple
■収録曲
[side A]
① 紫の炎/Burn (Blackmore, Lord, Paice, Coverdale, Hughes) ☆イギリス45位
② テイク・ユア・ライフ/Might Just Take Your Life (Blackmore, Lord, Paice, Coverdale, Hughes) ☆アメリカ91位
③ レイ・ダウン、ステイ・ダウン/Lay Down, Stay Down (Blackmore, Lord, Paice, Coverdale, Hughes)
④ セイル・アウェイ/Sail Away (Blackmore, Coverdale)
⑤ ユー・フール・ノー・ワン/You Fool No One (Blackmore, Lord, Paice, Coverdale, Hughes)
⑥ ホワッツ・ゴーイン・オン・ヒア/What's Goin' on Here (Blackmore, Lord, Paice, Coverdale, Hughes)
⑦ ミストゥリーテッド/Mistreated (Blackmore, Coverdale)
⑧ "A" 200/"A" 200 (Blackmore, Lord, Paice)
☆=シングル・カット
■録音メンバー
デヴィッド・カヴァーデイル/David Coverdale (lead-vocals)
ジョン・ロード/Jon Lord (keyboards, synthesizer)
リッチー・ブラックモア/Ritchie Blackmore (guitar)
グレン・ヒューズ/Glenn Hughes (bass, vocals)
イアン・ペイス/Ian Paice (drums)
■チャート最高位
1974年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)9位、イギリス3位、日本(オリコン)11位
1974年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)71位
8月16日に名ドラマーのマックス・ローチが逝去してから、彼のプレイが聴けるアルバム『サキソフォン・コロッサス』をたびたび聴いています。
これはソニー・ロリンズがリーダーとしてクレジットされているもので、どのジャズ・ガイド・ブックを見ても必ず紹介されている、名盤中の名盤です。
ぼくがこのアルバムを買った時は、まだジャズを聴き始めた頃で、どのアルバムから買っていいのか分からなかったので、そういうガイド・ブックの類の記事を参考にしたものでした。

マックス・ローチ
1曲目の「セント・トーマス」がカリプソ調の明るく、親しみ易い演奏だったので、「ジャズの高い垣根」みたいなものを感じることなく、分からないなりにもアルバムを通して聴くことができました。
今、こうやって聴いてみると、やはり名盤と言われているだけあって、そのサウンドはぼくの耳を充分に刺激してくれます。
バックの三人の好演がロリンズのプレイをより引き立てています。
幹の太い木を思わせるようなどっしりした4ビートを堅実に刻むベースのワトキンス。とくに「モリタート」や「セント・トーマス」の中間部、「ブルー・セヴン」のイントロ、また「ストロード・ロード」のロリンズとデュオとなる部分などで聴かせてくれるウォーキング・ベースは、それだけで曲を引っ張っていけるようなグルーヴィーなものです。
ピアノのフラナガンは、こういったセッションで抜群の実力を発揮します。ツボを心得たブロック・コードの入れ方がスウィンギー。コロコロ転がるようなソロもシブいですね。
ドラムスのローチがボトムからしっかりとリズムを支えているような感じです。ロリンズがソロを取っている間はよけいな手数を入れるのは控えていますが、盛り上げどころは熟知しているようで、フィル・インはもちろん、ダイナミクス(音の強弱)ひとつで曲に彩りをつけているところなど、さすがです。また、ワトキンスとのコンビネーションも抜群で、このふたりで作るリズムの太い芯は少々のことでは揺らぎはしないと思います。

ソニー・ロリンズ
ロリンズのテナーって、とても温かい感じがしますね。よく彼のサックスは「豪快」だと言われます。けれど、ちょっとデリケートなところもあって、激しく吹きまくるだけでないのが分かります。雄々しさと抑え気味なところのバランスが絶妙なんです。
彼のよく歌うサックスは、インプロヴィゼイション部分でたっぷり堪能できます。分かり易いアドリブ展開も魅力だし、音色なども、聴いていてちっとも疲れない心地良いものです。
軽快な「セント・トーマス」~バラードの「ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ」~速めの4ビート「ストロード・ロード」~親しみ易いメロディーが楽しい4ビートの「モリタート」~タイトル通りブルージーな「ブルー・セヴン」と、曲順も「これしかない!」って感じです。流れがごく自然に感じられるんです。

ソニー・ロリンズ
秋の夜長にはジャズがとても合います。でもこれは、よく晴れた日の午後に聴いても気持ち良いアルバムだと思います。
秋の訪れとともに、ぼくがジャズを聴く日も増えることでしょう。
◆サキソフォン・コロッサス/Saxophone Colossus
■演奏・・・ソニー・ロリンズ4
ソニー・ロリンズ/Sonny Rollins (tenor-sax)
トミー・フラナガン/Tommy Flanagan (piano)
ダグ・ワトキンス/Doug Watkins (bass)
マックス・ローチ/Max Roach (drums)
■プロデュース
ボブ・ワインストック/Bob Weinstock
■レコーディング・エンジニア
ルディ・ヴァン・ゲルダー/Rudy Van Gelder
■リリース
1956年
■録音
1956年6月22日 (ニュージャージー州ハッケンサック、ヴァン・ゲルダー・スタジオ)
■収録曲
A① セント・トーマス/St. Thomas (Rollins)
② ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ/You Don't Know What Love Is (Raye, DePaul)
③ ストロード・ロード/Strode Rode (Rollins)
B④ モリタート/Moritat (Brecht, Weil)
⑤ ブルー・セヴン/Blue Seven (Rollins)
■レーベル
プレステッジ/Prestige
今インストールしているのはノートン・アンチ・ウィルス。
毎年10月はこのソフトの更新時期なのです。
パソコンに対する知識がほとんどないぼくにとって、この更新が一大事。
今日の夕方、パソコンの画面を何気なく見ていると、
「ポン」と出てきたのが「更新期限は明日まで」というお知らせ。
これはもうイヤでも更新せざるを得ない。
該当部分を次々クリックしていって購入までは無事完了。
問題はこれをダウンロードしてインストールすることです。
ダウンロードは難なくクリア。
ところがインストール段階になってからがたいへんでした。
言葉としては知っているけれども意味を分かってない単語が続々と。
「アンインストール」「アカウント」「プロダクトシリアル」「サインイン」etc・・・
とにかく、次へ次へと進んでみる。
もう自分でも何がどうなっているのか分からない状態です。
そしてついに「今日中にアカウントを作成して下さい」の一文で躓きました。
「あかうんと、ってなんじゃい」
メールアドレスとIDを記入しなければならないのですが、
IDに何を記入して良いのかが分からない・・・。(無知)
それまでに出てきた数字やらアルファベットやら、何を記入しても「違います!」のマークが・・・。
最後に、いつもぼくがIDとして使っている文字を記入してみると、やっと次へ進むことができました。
といっても今どの段階にいるのかが分からない。
とにかく指定されたように進んで行くだけです。
そんなこんなでインストールし終えたのが開始から2時間以上経ってから。
ところが、その結果「まだ不完全」の表示が出てガックリです・・・。
そのあとは、自分でこれを書いてても思い出せないような手順でなんとかこなしていきました。
作業がようやく終わったのが開始から4時間以上経った午後8時半。
ほんと、ヤレヤレです。
でも、これだけ手間暇かけて作業を行ったにもかかわらず、パソコンに対する知識が増えたかというと疑問です。
とにかく分からない単語が多すぎる。
時間もかかりすぎ。
その手順が今だいたいどの段階なのかが分からない。
これだけパソコンが普及したこの時代、もっとスキル・アップしなければ(汗)。
人気blogランキングへ←クリックよろしくお願いします<(_ _)>
この曲は、ロバータの歌った中では最高に美しいバラードではないでしょうか。
バックの編成はごくシンプルで、ピアノ、アコースティック・ギターにストリングスが加わるだけです。その中で、つぶやきかけるように、そして高音部では伸びやかに歌うロバータの声が、一種厳かに聞こえてきます。

ロバータは著名なジャズ・ピアニスト兼シンガーのレス・マッキャンに認められて、1969年にデビュー・アルバム『ファースト・テイク』を発表します。『愛は面影の中に』は、その中に収録されていたものです。
この曲は、もともとはユアン・マッコールが1950年代に書いたもので、1962年にはキングストン・トリオがレコーディングしています。ロバータはデビュー前に学校で教鞭を取っていましたが、合唱団を指導する時によく練習で歌わせていたそうです。
1971年、クリント・イーストウッドが監督兼主演で『プレイ・ミスティ・フォー・ミー(邦題…恐怖のメロディー)』という映画を制作しました。これはイーストウッドの監督第1作です。ラジオのディスクジョッキーが恐ろしい事件に巻き込まれる、というミステリー映画で、エロール・ガーナーの作で有名な曲『ミスティ』が効果的に使われました。このあたりが大のジャズ好きで知られるイーストウッドらしいところですが、彼はロバータのファンでもあったので、『愛は面影の中に』を主題曲として使いました。
曲の使用にあたっては、イーストウッド自身が直接ロバータ本人に電話をかけて、許可を貰えるよう頼んだんだそうです。

ロバータ・フラック『ファースト・テイク』
そこでレコード会社は、『ファースト・テイク』発表後3年経った1972年にこの曲をシングル・カットし、映画の公開に合わせて発表したわけです。しかし、なにせ強烈な刺激やビートを持つ音楽がチャートを賑わせている状況だったので、静かに歌われるこのバラードがどれほど売れるのか、レコード会社もさほど期待していなかったようです。
しかし72年4月から6週間に渡ってこの曲は全米チャートの1位に上り詰め、ミリオン・セラーとなる大ヒットを記録しました。そしてグラミー賞の1972年度レコード・オブ・ジ・イヤーと、ソング・オブ・ジ・イヤーを獲得したという訳です。
フォークとゴスペルを合わせたような静かなイントロはとても清らか。ナチュラルな感のあるロバータの歌は知的で、美しいです。
ピアノとアルコ(弓)で弾かれるコントラバスのみの伴奏となるエンディング、これがまた雰囲気があって良いんですね。

この曲はロバータが録音する前に、ピーター・ポール&マリーやブラザース・フォアなど、フォーク系のミュージシャンがレパートリーとして取り上げています。
そのほか、アンディ・ウィリアムス、シャーリー・バッシー、レターメン、最近ではセリーヌ・ディオンなどもこの曲を取り上げていますね。
[歌 詞]
[大 意]
初めてあなたに会った時 私はあなたの瞳にバラ色の太陽を想った
暗く果てのない空に 月とたくさんの星を贈ったのはあなた
初めてあなたとキスした時 世界が私の手の中で震えたように感じた
とらわれた小鳥のふるえる心のように それは私の意のまま
初めてあなたを強く抱いた時 私の胸にあなたの鼓動が伝わってきた
そしてふたりの喜びが世界を満たすでしょう
この世が終わる時まで
この世が終わる時まで
■愛は面影の中に (The First Time Ever I Saw Your Face)
■録音
1968年
■収録アルバム
ファースト・テイク/First Take(1969年)
■シングル・リリース
1972年3月7日
■作詞・作曲
ユアン・マッコール/Ewan MacColl
■プロデュース
ジョエル・ドーン/Joel Dorn
■録音メンバー
ロバータ・フラック/Roberta Flack (piano, vocals)
バッキー・ピザレリ/Bucky Pizzarelli (guitars)
ロン・カーター/Ron Carter (bass)
エマニュエル・グリーン/Emanuel Green (violin)
ジーン・オルロフ/Gene Orloff (violin)
アルフレッド・ブラウン/Alfred Brown (viola)
セルワート・クラーク/Selwart Clarke (viola)
セオドア・イスラエル/Theodore Israel (viola)
チャールズ・マックラッケン/Charles McCracken (cello)
ジョージ・リッチ/George Ricci (cello)
■チャート最高位
1972年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位(1972年4月15日付~5月20日付 6週連続計6週)、イギリス14位
1972年年間チャート アメリカ(ビルボード)1位
 『愛は面影の中に』
『愛は面影の中に』
思い返してみると、このアルバムを聴いてみたい、と思ったきっかけは、あの「ホワイト・ルーム」が入っていたからでした。クリームのレパートリーの中でも名高い曲です。
「カッコいい曲だ」というのはロック好きだった友人に聞かされていました。そんな時に「クリームっていうバンド、知ってる?好きなんだっら貸してやるぞ」と言われて、興味津々で借りて帰ったのが、この『クリームの素晴らしき世界』でした。
ぼくはまだ中学生だったので、全編通じて聴いてもどこがどう良いのか分かりませんでした。
改めて聴いてみて「スゴいな~」と思ったのは、どっぷりロックに漬かっていた20歳過ぎの頃だったと思います。
その時は、「ホワイト・ルーム」よりも、むしろ「クロスロード」の演奏の方に感動を覚えました。三人がその圧倒的な演奏技術をフルに発揮して収束していく様は「凄まじい」の一言に尽きると思います。

この『クリームの素晴らしき世界』は二枚組で、スタジオ盤とライヴ盤に別れています。当時は一枚ずつバラ売りされていたらしいですね。
スタジオ盤は、どちらかというと、スタジオならではの実験性が見え隠れしています。
プロデューサーのフェリックス・パパラルディがヴィオラやトランペット、オルガンなどで参加していて、ポップな要素も出しながら、当時としてはちょっとプログレッシヴな音作りを試みているようです。
ライヴ盤の方は、まさに原題の「Wheels Of Fire」そのものの、熱気にあふれたインプロヴィゼイションが繰り広げられています。
その中でも、「クロスロード」「スプーンフル」は、三人のスリル満点の壮絶なインタープレイが聴かれる、ロック史上に残る名演だと思います。
また「列車時刻」ではジャック・ブルースのハーモニカ・ソロ、「いやな奴」ではジンジャー・ベイカーのドラム・ソロがたっぷり聴くことができます。さながら、三人それぞれの見せ場を再現しているようです。

極端に言ってしまえば、スタジオとステージでは別のバンドが演奏しているようにも聴こえます。スタジオではポップだったり、プログレッシヴだったり、さまざまな方法論を試みているようです。
しかしライヴでは、ブルースをベースにした三人のぶつかり合いによって、各自の強烈な個性を引き出し合っているようです。これはまさに、ロックというよりジャズといった方が良いのではないでしょうか。
ベースを弾いていた自分としては、ジャック・ブルースの、派手で音数の多いスピーディーなベース・ラインに憧れて、よくコピーしていたものです。そういう意味でもこれは懐かしいアルバムです。
◆クリームの素晴らしき世界/Wheels Of Fire
■歌・演奏
クリーム/Cream
■収録曲
Side-A
① ホワイト・ルーム/White Room (Jack Bruce, Peter Brown)
② トップ・オブ・ザ・ワールド/Sitting on Top of the World (Walter Vinson, Lonnie Chatmon arr.Chester Burnett)
③ 時は過ぎて/Passing the Time (Ginger Baker, Mike Taylor)
④ おまえの言うように/As You Said (Bruce, Brown)
Side-B
⑤ ねずみといのしし/Pressed Rat and Warthog (Baker, Taylor)
⑥ 政治家/Politician (Bruce, Brown)
⑦ ゾーズ・ワー・ザ・デイズ/Those Were the Days (Baker, Taylor)
⑧ 悪い星の下に/Born Under a Bad Sign (Booker T. Jones, William Bell)
⑨ 荒れ果てた街/Deserted Cities of the Heart (Bruce, Brown)
Side-C
⑩ クロスロード/Crossroads (Robert Johnson arr.Eric Clapton)
⑪ スプーンフル/Spoonful (Willie Dixon)
Side-D
⑫ 列車時刻/Traintime (Bruce)
⑬ いやな奴/Toad (Baker)
■アルバム・リリース
1968年7月(アメリカ)、1968年8月9日(イギリス)
■プロデュース
フェリックス・パパラルディ
■録音メンバー
☆クリーム/Cream
エリック・クラプトン/Eric Clapton (guitar, vocal)
ジャック・ブルース/Jack Bruce (vocal, lead-vocal, bass, cello, harmonica, acoustic-guitar, recorder)
ジンジャー・ベイカー/Ginger Baker (drums, percussion, spoken-word⑤)
★ゲスト
フェリックス・パパラルディ/Felix Pappalardi (viola, bell, organ, trumpet, tonette)
■チャート最高位
1968年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス3位(2枚組)・7位(1枚組)