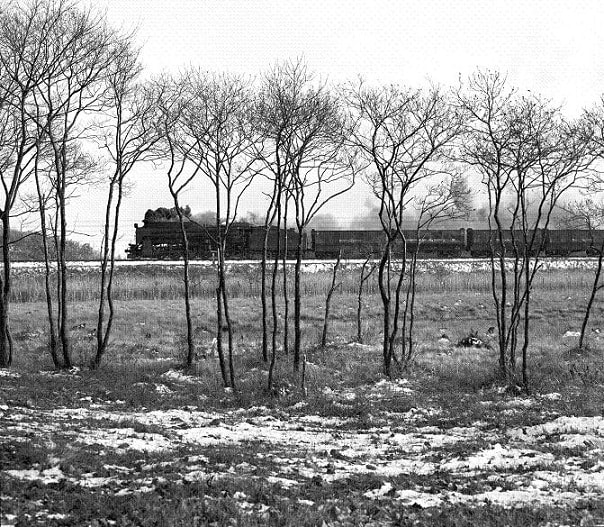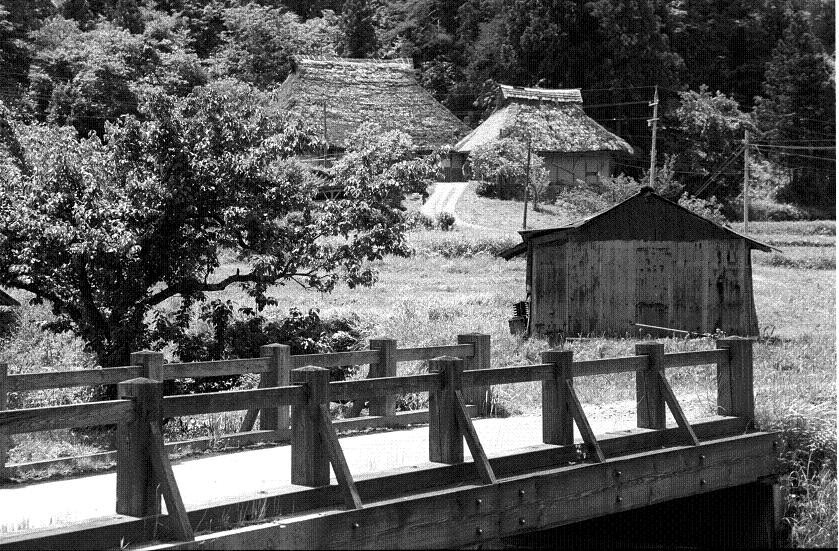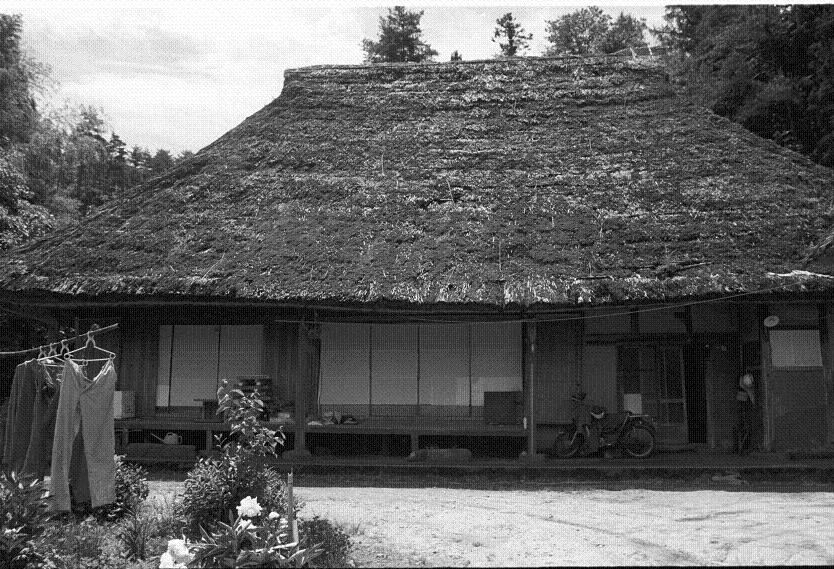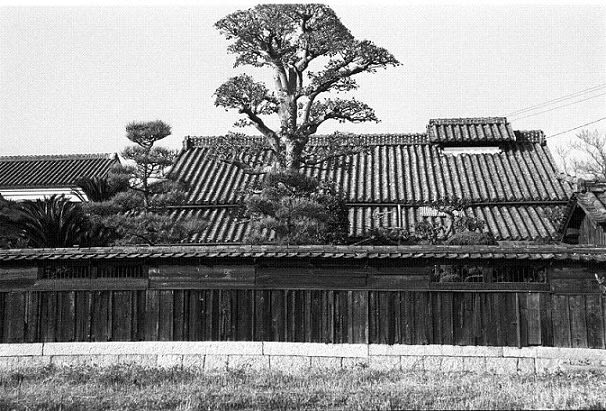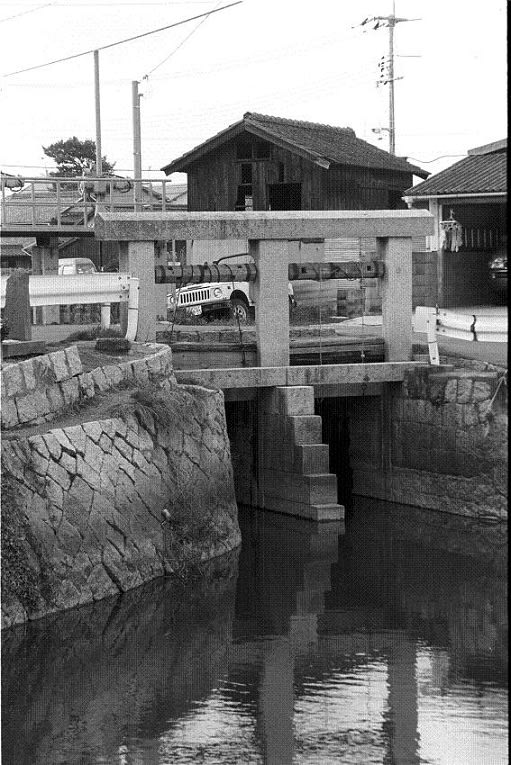撮影場所 倉敷市中庄
岡山県南部は洪積地のため農業用水がクリークのように張り巡らされている。
その農業用水に昔からの石の橋が架かっていた。
護岸もコンクリート三面張りでなく棒杭による土留めのまま
護岸が崩れ段々川幅が広くなる。ここまでの広さはいらないであろう。
棒杭の土留めの時は生態系も豊かであったと思う、ドジョウやウナギも棲みやすいし亀も棲む事ができた。蛙もダルマ蛙は足が短くジャンプが出来ず生息地を減らしている。
ある日、山陽線から見た石橋を撮影にきた。撮影に来たのは二回だけ
何のために撮影にきたのか、どう使おうとしたのか不明のまま
はっきりした目的もなくとりあえず撮っておこうと思ったのか
田圃も宅地にある程度かわるかという思いもあった。
しかし、撮影する以上は500カ所くらい撮影しないと作品にならない。
機関車を撮るにも木造駅舎を撮るにも木の半鐘を撮るにも500は撮影したい。
そんな意識もないまま撮影している。
岡山南部の干拓地をすべて回り「岡山平野の農業用水石橋」というテーマで撮影できたはずだ。





岡山県南部は洪積地のため農業用水がクリークのように張り巡らされている。
その農業用水に昔からの石の橋が架かっていた。
護岸もコンクリート三面張りでなく棒杭による土留めのまま
護岸が崩れ段々川幅が広くなる。ここまでの広さはいらないであろう。
棒杭の土留めの時は生態系も豊かであったと思う、ドジョウやウナギも棲みやすいし亀も棲む事ができた。蛙もダルマ蛙は足が短くジャンプが出来ず生息地を減らしている。
ある日、山陽線から見た石橋を撮影にきた。撮影に来たのは二回だけ
何のために撮影にきたのか、どう使おうとしたのか不明のまま
はっきりした目的もなくとりあえず撮っておこうと思ったのか
田圃も宅地にある程度かわるかという思いもあった。
しかし、撮影する以上は500カ所くらい撮影しないと作品にならない。
機関車を撮るにも木造駅舎を撮るにも木の半鐘を撮るにも500は撮影したい。
そんな意識もないまま撮影している。
岡山南部の干拓地をすべて回り「岡山平野の農業用水石橋」というテーマで撮影できたはずだ。