ナビゲーターをした房野さんから、レポートが届きました。
日時:平成30年11月17日 14:00~14:40
場所:浜田市世界こども美術館 コレクション室
第50回浜田市美術展記念 「橋本明治デッサン展」
作品名:「初雲雀」1973年 下絵4点
作 者:橋本明治 1904年~1991年
ナビゲーター:房野 参加者:4名(内みるみる会員2名)


今回のコレクション室に展示されていたのは、橋本明治のデッサンや下絵がほとんどであったが、橋本明治の息子であり、日本画家でもある橋本弘安の作品もあり、橋本親子の作品展でもあった。日本画の「本画(完成作品)」は橋本弘安の「遠い花火」一点であったが、この作品は以前みるみるの鑑賞会で扱った作品でもあり、今回参加された鑑賞者は常連の方で、以前、この作品での鑑賞会に参加したことがあるとのことだったので、今回はそれとは別の日本画の「下絵(デッサン・試作品)」を鑑賞することにした。下絵で鑑賞会を行うのは初めてだったが、初めてだからこそ、一体どんな鑑賞会になるのか?!ワクワクしながら対話をスタートした。
選んだのは「初雲雀」という芸妓が画面中心に描かれた作品の下絵、4点。
4点のうち3点はほぼ構図もモチーフも同じで、芸妓の着物も全て黒。それ以外の敷物や手に持った扇子の配色が変えてある。今なら同じ下絵をコピーしてコンピュータで処理すれば、一瞬で配色を様々に試してみることもできるが、まだそういう機器がなかった時代の橋本明治は、同じ構図を手描きし、それに絵の具やパス等で着彩をしていた。しかもその塗り方はかなりラフで、細やかな質感などを追及するより、配色の組み合わせを確認したいがための下絵であるということが見て取れる。今回はこれらをじっくりと見比べることで作者の思考を読み取ることができるのではないか、と想像しながらナビゲートしていった。
<鑑賞者の意見>
・敷物の面積が大きく、その色次第で、作品の印象が変わる。緑、黄、赤茶、とかなり違う印象になる。自分は茶色の敷物の作品が好み。なぜなら、他のものより、着物の黒が美しく見えるから。
・左下の作品は後ろの金屏風がはっきりわかるように床との接地面のギザギザが克明に描かれ、敷物の手前の端がこの作品だけには入っている。モデルが「静」を表現し、金屏風の端の輪郭線が「動」を表現していて面白い。
・中心のモデルの着物は4点とも黒で固定してあり、背景の配色を色々試していることから、この黒をいかに美しく見せるかを作者は追及しているのではないだろうか。
・後ろの屏風の床面との接地面である輪郭線の位置が、左下のものとほかの3点は変えてある。人物の体の向きも微妙に変えてある。
・完成度としては下の2点が高いと思う。顔の造作や表情がはっきり描かれていて、特に右の下の作品は着物の透け具合まで細やかに描かれていることから、本画のイメージに近いものではないだろうか。
・自分がどれかもらえるとしたら、左下のものが良い。絵として完成度が高いし、マチスのようなざっくりとした色面が魅力的。
・左下のものに比べて、他の3点は金屏風の線が曖昧になっているのは、構成的に金屏風はさほど克明に描く必要はないと作者が判断した結果ではないだろうか。左下のものはいろいろなモチーフが細やかに描かれていて、見たままにスケッチしているように感じる。そのことからこれを早い段階で描いて、その後、他の3点のようにモチーフの構成をある程度決めてから色面の組み合わせを考えていったのではないかと思う。
・そうは言っても左下のものが最初のスケッチとは限らない。
・背中に見える帯の端が非常に重要なポイントになっていると思う。床の敷物と色が類似色になっていて色のつながりを作っている。扇子の色とも合わせているものもあるので、作者の試行錯誤が感じられる。
<ふりかえり・会員からの意見>
・同じ作品に向かう下絵が4点並んでいたが、描かれた順番が情報としてあればさらに考えやすかったかもしれない。
・少人数で自由に自分の意見を言える雰囲気で、ナビが自分の意見も述べていたが、根拠を確認したり、こまとめをしたりする場面が少なかった。
・他の意見をよく聞いて考えを構築していくというより、各々が言いたいことを言ったという印象。こまとめをするのは難しいが、散漫にならないようにすべき。
<ナビの自評>
・情報がないままに見たものを根拠に思考していくのも対話型鑑賞の醍醐味だと思うが、せめて本画の印刷物だけでも展示してあれば、下絵の順番を考えるヒントになって面白かったのではないか。
・会員からの指摘があったように根拠を明らかにし、こまとめをすることで意見を共有し、積み上げていくようなナビをしたい。
・普段から絵を描いておられる鑑賞者なので、技法や構成の工夫といった「描く側」からの視点で対話が進んだ。それはそれで話は尽きないのだが、他の視点で作品を味わっていくようなナビゲートのスキルも必要である。特に、普段絵を描かない、鑑賞もあまりしないといった方が同席していた場合でも、楽しく対話に参加できるような雰囲気を作らなくてはならない。
対話を通して作者の本画へ向かう途中の試行錯誤を感じることができた。今回は4点を見比べてそれぞれの違いを発見していき、その構成的な工夫を4枚の下絵から読み取っていくような鑑賞であった。日本画の制作過程に触れながら鑑賞するというスタイルで、下絵からも様々な発見と考察がなされた。ナビ自身も楽しみながら新しい発見を体験していくことができ、初めてのジャンルにチャレンジした甲斐があったと思う。
【みるみるの会からのお知らせ】

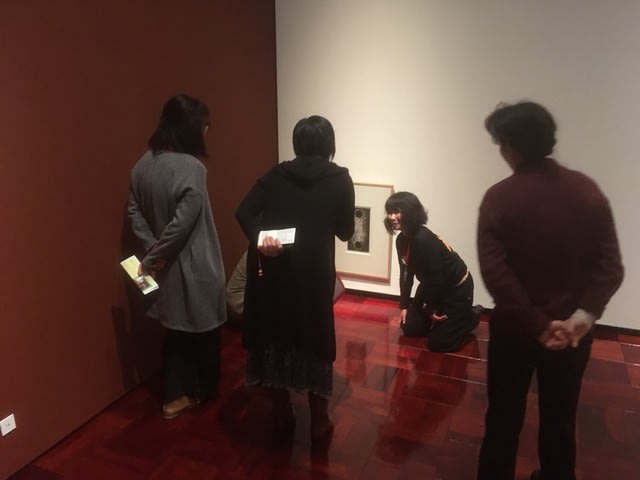

今年度も「みるみると見てみる?」が開催されます!(写真は昨年度の様子)
島根県立石見美術館(島根県益田市 グラントワ内)のコレクション展
「あなたはどう見る?-よく見て話そう美術について」(会期2019年1月23日~3月4日)の関連イベントです。
「みるみると見てみる?」コレクション展関連トークイベント
開催日時:2019年1月27日(日)
2月3日(日)、17日(日)、24日(日)
いずれも14:00から(40分程度を予定)
島根県立石見美術館 展示室Aにて
「あなたはどう見る?-よく見て話そう美術について」は、鑑賞者が自由に思いを巡らせたり、感想や意見を述べられるよう、
キャプションや解説を付けずに作品が展示されている展覧会です。
みるみるの会メンバーとともに、他の人の意見にも耳をかたむけながらじっくりと作品を味わってみませんか?
日時:平成30年11月17日 14:00~14:40
場所:浜田市世界こども美術館 コレクション室
第50回浜田市美術展記念 「橋本明治デッサン展」
作品名:「初雲雀」1973年 下絵4点
作 者:橋本明治 1904年~1991年
ナビゲーター:房野 参加者:4名(内みるみる会員2名)


今回のコレクション室に展示されていたのは、橋本明治のデッサンや下絵がほとんどであったが、橋本明治の息子であり、日本画家でもある橋本弘安の作品もあり、橋本親子の作品展でもあった。日本画の「本画(完成作品)」は橋本弘安の「遠い花火」一点であったが、この作品は以前みるみるの鑑賞会で扱った作品でもあり、今回参加された鑑賞者は常連の方で、以前、この作品での鑑賞会に参加したことがあるとのことだったので、今回はそれとは別の日本画の「下絵(デッサン・試作品)」を鑑賞することにした。下絵で鑑賞会を行うのは初めてだったが、初めてだからこそ、一体どんな鑑賞会になるのか?!ワクワクしながら対話をスタートした。
選んだのは「初雲雀」という芸妓が画面中心に描かれた作品の下絵、4点。
4点のうち3点はほぼ構図もモチーフも同じで、芸妓の着物も全て黒。それ以外の敷物や手に持った扇子の配色が変えてある。今なら同じ下絵をコピーしてコンピュータで処理すれば、一瞬で配色を様々に試してみることもできるが、まだそういう機器がなかった時代の橋本明治は、同じ構図を手描きし、それに絵の具やパス等で着彩をしていた。しかもその塗り方はかなりラフで、細やかな質感などを追及するより、配色の組み合わせを確認したいがための下絵であるということが見て取れる。今回はこれらをじっくりと見比べることで作者の思考を読み取ることができるのではないか、と想像しながらナビゲートしていった。
<鑑賞者の意見>
・敷物の面積が大きく、その色次第で、作品の印象が変わる。緑、黄、赤茶、とかなり違う印象になる。自分は茶色の敷物の作品が好み。なぜなら、他のものより、着物の黒が美しく見えるから。
・左下の作品は後ろの金屏風がはっきりわかるように床との接地面のギザギザが克明に描かれ、敷物の手前の端がこの作品だけには入っている。モデルが「静」を表現し、金屏風の端の輪郭線が「動」を表現していて面白い。
・中心のモデルの着物は4点とも黒で固定してあり、背景の配色を色々試していることから、この黒をいかに美しく見せるかを作者は追及しているのではないだろうか。
・後ろの屏風の床面との接地面である輪郭線の位置が、左下のものとほかの3点は変えてある。人物の体の向きも微妙に変えてある。
・完成度としては下の2点が高いと思う。顔の造作や表情がはっきり描かれていて、特に右の下の作品は着物の透け具合まで細やかに描かれていることから、本画のイメージに近いものではないだろうか。
・自分がどれかもらえるとしたら、左下のものが良い。絵として完成度が高いし、マチスのようなざっくりとした色面が魅力的。
・左下のものに比べて、他の3点は金屏風の線が曖昧になっているのは、構成的に金屏風はさほど克明に描く必要はないと作者が判断した結果ではないだろうか。左下のものはいろいろなモチーフが細やかに描かれていて、見たままにスケッチしているように感じる。そのことからこれを早い段階で描いて、その後、他の3点のようにモチーフの構成をある程度決めてから色面の組み合わせを考えていったのではないかと思う。
・そうは言っても左下のものが最初のスケッチとは限らない。
・背中に見える帯の端が非常に重要なポイントになっていると思う。床の敷物と色が類似色になっていて色のつながりを作っている。扇子の色とも合わせているものもあるので、作者の試行錯誤が感じられる。
<ふりかえり・会員からの意見>
・同じ作品に向かう下絵が4点並んでいたが、描かれた順番が情報としてあればさらに考えやすかったかもしれない。
・少人数で自由に自分の意見を言える雰囲気で、ナビが自分の意見も述べていたが、根拠を確認したり、こまとめをしたりする場面が少なかった。
・他の意見をよく聞いて考えを構築していくというより、各々が言いたいことを言ったという印象。こまとめをするのは難しいが、散漫にならないようにすべき。
<ナビの自評>
・情報がないままに見たものを根拠に思考していくのも対話型鑑賞の醍醐味だと思うが、せめて本画の印刷物だけでも展示してあれば、下絵の順番を考えるヒントになって面白かったのではないか。
・会員からの指摘があったように根拠を明らかにし、こまとめをすることで意見を共有し、積み上げていくようなナビをしたい。
・普段から絵を描いておられる鑑賞者なので、技法や構成の工夫といった「描く側」からの視点で対話が進んだ。それはそれで話は尽きないのだが、他の視点で作品を味わっていくようなナビゲートのスキルも必要である。特に、普段絵を描かない、鑑賞もあまりしないといった方が同席していた場合でも、楽しく対話に参加できるような雰囲気を作らなくてはならない。
対話を通して作者の本画へ向かう途中の試行錯誤を感じることができた。今回は4点を見比べてそれぞれの違いを発見していき、その構成的な工夫を4枚の下絵から読み取っていくような鑑賞であった。日本画の制作過程に触れながら鑑賞するというスタイルで、下絵からも様々な発見と考察がなされた。ナビ自身も楽しみながら新しい発見を体験していくことができ、初めてのジャンルにチャレンジした甲斐があったと思う。
【みるみるの会からのお知らせ】

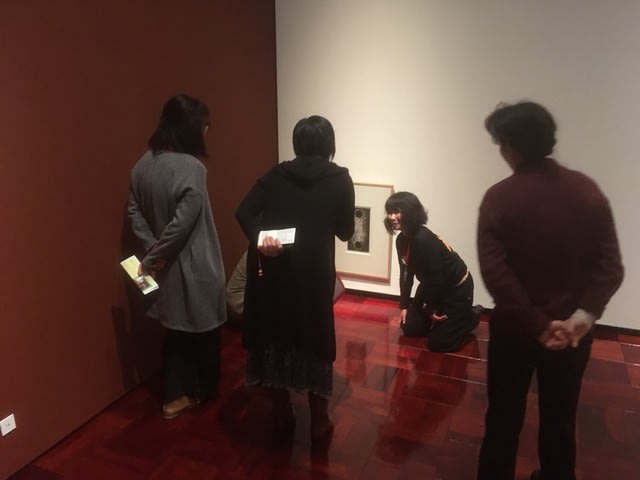

今年度も「みるみると見てみる?」が開催されます!(写真は昨年度の様子)
島根県立石見美術館(島根県益田市 グラントワ内)のコレクション展
「あなたはどう見る?-よく見て話そう美術について」(会期2019年1月23日~3月4日)の関連イベントです。
「みるみると見てみる?」コレクション展関連トークイベント
開催日時:2019年1月27日(日)
2月3日(日)、17日(日)、24日(日)
いずれも14:00から(40分程度を予定)
島根県立石見美術館 展示室Aにて
「あなたはどう見る?-よく見て話そう美術について」は、鑑賞者が自由に思いを巡らせたり、感想や意見を述べられるよう、
キャプションや解説を付けずに作品が展示されている展覧会です。
みるみるの会メンバーとともに、他の人の意見にも耳をかたむけながらじっくりと作品を味わってみませんか?
















