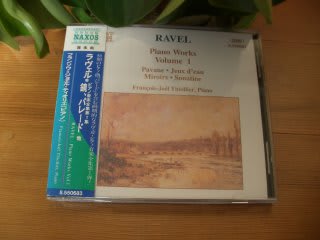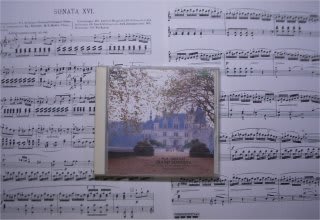ラフマニノフ交響曲というメランコリックで濃厚な音楽をしばらく聴いた後では、素朴で生命力あふれる音楽を聴きたくなります。ここ数日、通勤の音楽に聴いているのは、バルトークの「ルーマニア民俗舞曲」Sz.56です。全部で6曲からなる魅力的な小品は、作曲者34歳の1915年、トランシルヴァニア地方のルーマニア人の民族音楽を素材とした作品なのだとか。
I. ジョク・ク・バータ (1'03")
II. プラウル (0'29")
III. ぺ・ロック (1'01")
IV. ブチュメアーナ (1'23")
V. ルーマニア風ポルカ (0'27")
VI. マヌンツェル (0'48")
total=5'11"
出だしの音楽は、「のだめカンタービレ」あたりで取り上げられてはいないのかな?作曲当時から人気があったとのことですが、さもありなん。ゾルターン・コチシュのピアノ、1975年10月に荒川区民会館でデジタル(PCM)録音されており、制作はDENONの川口義晴、録音は林正夫、とクレジットされております。ごく初期のデジタル録音らしく、高域は硬質ですが、ピアノの低音の抜けが良いのがわかります。

とにかく、ジャケット写真のコチシュが若い!まるで少年のようです。そういえば、ハンガリーの若手三羽烏と言われていた頃は、もう30年以上も前になるのですね。
コチシュが弾くバルトーク、「アレグロ・バルバロ」や「古い踊りの歌」など、他の収録曲も魅力的です。
I. ジョク・ク・バータ (1'03")
II. プラウル (0'29")
III. ぺ・ロック (1'01")
IV. ブチュメアーナ (1'23")
V. ルーマニア風ポルカ (0'27")
VI. マヌンツェル (0'48")
total=5'11"
出だしの音楽は、「のだめカンタービレ」あたりで取り上げられてはいないのかな?作曲当時から人気があったとのことですが、さもありなん。ゾルターン・コチシュのピアノ、1975年10月に荒川区民会館でデジタル(PCM)録音されており、制作はDENONの川口義晴、録音は林正夫、とクレジットされております。ごく初期のデジタル録音らしく、高域は硬質ですが、ピアノの低音の抜けが良いのがわかります。

とにかく、ジャケット写真のコチシュが若い!まるで少年のようです。そういえば、ハンガリーの若手三羽烏と言われていた頃は、もう30年以上も前になるのですね。
コチシュが弾くバルトーク、「アレグロ・バルバロ」や「古い踊りの歌」など、他の収録曲も魅力的です。