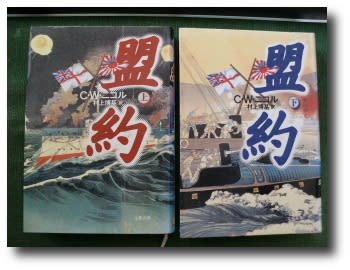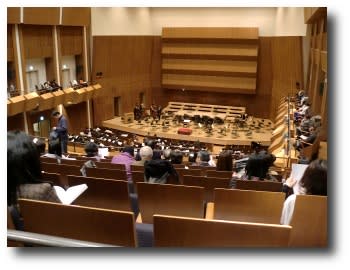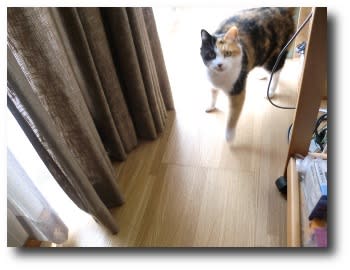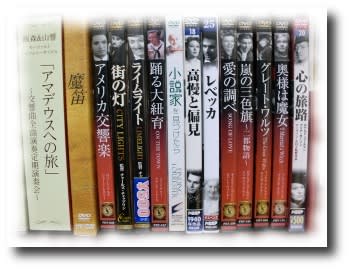山響こと山形交響楽団のモーツァルト全曲演奏プロジェクトも4年めの3回めを迎え、ちょうど半分まで来ました。本日のプログラムは、交響曲第21番と歌劇「魔笛」ハイライトの二つです。会場に入ると、お客さんの入りは、最前列に若干の空きがありますが、それ以外はほぼ満席の状態です。
音楽監督・飯森範親さんのプレトークでは、主に曲目についての説明でした。交響曲第21番イ長調K.134は、第3回イタリア旅行の前に作られた曲だそうで、第4楽章に総休止(ゲネラルパウゼ)が置かれるなど、いろいろな工夫がされている曲だそうな。休憩の後の「魔笛」は、「魔の笛」ではなくて「魔法の笛」という意味です、と指摘。このあたりは、初めてのお客様にも親切な解説です。作曲者モーツァルトも興行師シカネーダーも、いずれもフリーメーソンの会員で、このオペラはフリーメーソンの色濃い作品だと指摘します。ただし、フリーメーソンは陰謀組織ではなくて、現在も子供のための善意の活動をしたりしている組織で、東京交響楽団の音楽監督のスダーン氏も会員だとのこと。この会は3という数字を特別のものとして大切にするそうで、モーツァルトもこれにならっているそうです。すなわち、序曲の三和音、三人の侍女、三人の童子という具合です。
また、e-ONKYO を通じて、今回も演奏会の録音が配信されるとのこと。携帯電話の電源を再確認してくださいというお願いがありました。飯森さんに言われて、あわてて確認する人もけっこういましたね(^o^)/
さて、交響曲第21番です。ステージ上の楽器配列は、左側に第1ヴァイオリンが4プルト(8人)、コンサートマスターは高木和宏さん。その奥にチェロが5人とファゴットの高橋あけみさん、右にヴィオラが3プルト(6人)、その右に第2ヴァイオリンが4プルト(8人)という対向配置です。正面後方にはフルート(2)とホルン(2)、さらにその後方にコントラバス(3)という具合で、この曲ではオーボエの出番がありません。
第1楽章:アレグロ、イ長調、4分の3拍子。軽やかに跳ねるような始まりで、山響の弦楽セクションの美質を聴かせてくれます。ホルンとフルートも、全体の音の中に調和して響きます。ファゴットは、低い音域でのリズムの軽やかさをねらったものでしょうか。
第2楽章:アンダンテ、ニ長調、4分の2拍子。ゆったりとした緩徐楽章です。透明感のある音色で、フルートもホルンも突出せず、弦にブレンドされて響きます。曲想が変わると、ホルンがよく響きます。
第3楽章:メヌエット、イ長調、4分の3拍子。フルートが印象的。くるくる回るような、舞曲風のリズミカルな音楽です。
第4楽章:アレグロ、イ長調、2分の2拍子。こちらも舞曲風の音楽です。ゲネラルパウゼがあり、曲想が軽やかに転換します。けっこうインパクトがありますね!
ここで休憩です。すぐ近くの席を立った方、もしかして
「うに」さんこと作曲家の木島由美子さんでは?と思いました。
後半は、いよいよ歌劇「魔笛」ハイライト。演奏会形式ではありますが、モーツァルト晩年の傑作の、音楽の力を存分に味わえるはず。
楽器の配置が変更になっています。指揮台を中央に、左から順に第1ヴァイオリン(8)、チェロ(5)、ヴィオラ(6)、第2ヴァイオリン(8)、コントラバス(3)はチェロの奥で、その右にホルン(2)。正面奥の方にはフルート(2)、オーボエ(2)、さらにその奥にクラリネット(2)とファゴット(2)の木管が配置され、右隣にバロック・ティンパニが陣取ります。ヴィオラと第2ヴァイオリンの右後方にトランペット(2)、トロンボーン(3)。左端にあるのは、チェレスタでしょうか。
まず、序曲から。ふわっと透明な響きです。初めはやや緊張気味でしたが、しだいにワクワクしてくるような音楽の展開です。
序曲の後には、指揮者の飯森さん自身のナレーションで、このオペラのあらすじを説明します。時は古代、場所は先日ムバラク長期政権が崩壊したエジプト、という解説に、客席がどっとわきます。そこへタミーノが登場、大蛇と戦い気を失っていると、夜の女王に仕える三人の侍女が現れ、軽やかで優雅でちょいと色っぽい三重唱を歌います。緑が藤野恵美子さん、青が真下祐子さん、赤が佐藤美喜子さんで、
「コシ・ファン・トゥッテ」などですでにおなじみの方々です。
再び飯森ナレーションに続いて、会場内からパパゲーノが登場、パパゲーノのアリアを歌います。パパゲーノ役は高橋正典さん。衣装は燕尾服スタイルですが、動作・演技はコミカルです。飯森さん、ナレーションでかんでしまい、会場の笑いを誘います。このあたりの愛嬌も、音楽監督の人気の秘密かも(^o^)/
そこへ、思い込み男(^o^)タミーノのアリア。パミーナの絵姿に一目惚れです。タミーノ役は高野二郎さん。なかなかカッコいいタミーノで、とても立派な声です。
ナレーションでパミーナ救出の依頼が行われると、夜の女王が登場。濃紺のドレスに黒い手袋と妖艶ないでたちの夜の女王は、安井陽子さん。もう大迫力のソプラノ・アリアです!これに対比されるファゴットの低音が、実に見事でステキです。
さて、ナレーションにより舞台はザラストロの神殿に移ります。パミーナを救出するためにタミーノがやってきますが、そこで叡智を司る三人の童子が登場し、道を照らします。

三人の童子は、山形大学の音楽科の学生さんだそうです。写真は交流会でのものですが、清楚な感じがよく出ていました。
第二幕、ナレーションにより、ザラストロは高徳の僧であり、夜の女王こそ悪女であるという逆転が説明されます。合唱付きアリア、ザラストロと民衆の合唱です。ザラストロは同世代の藤野祐一さん。60人近い合唱は、山響アマデウス・コアを主体に山形大学・岩手大学で音楽を専攻する学生さんたちが加わったもののようで、実にハイレベルで見事なものでした。
そうしているうちに、パミーナと夜の女王の場面となります。白いドレスのパミーナに、夜の女王がザラストロ殺害を命じます。夜の女王のアリア「地獄の復讐にこの胸は燃え」です。いや~、すごい迫力、緊迫感。オケも鋭く切り込む音です。激しいアリアに、大拍手!
ナレーションは、タミーノとパパゲーノが無言の修行をしていると説明、三人の童子が二人を迎えます。オケも軽やかで、このあたり絶好調といった感じです。
そして、話しかけても答えてくれないタミーノに、パミーナの歌う悲しみのアリア。白いドレスのパミーナは吉原圭子さんで、切々と訴えかけるアリアは胸をうちます。悲しみにファゴットとフルートが寄り添い、嘆きとため息を表します。このあたりのモーツァルトの音楽のひとふしは、実に実に素晴らしいものです!
ナレーションが、試練に出発するタミーノとパミーナの別れを説明した後に、パミーナ、タミーノ、ザラストロの三重唱。ソプラノとテノールとバスの、声による絶妙のアンサンブルです。
ナレーションは、落第したパパゲーノを説明し、「恋人か女房がいれば」というパパゲーノのアリアが歌われます。ここでのチェレスタの音が、実にチャーミングです。こういう音色を選ぶモーツァルトのセンスにしびれます(^o^)/
ナレーション後、パミーナが母に渡された剣で死のうとしますが、三人の童子に助けられ、タミーノに再会。火と水の試練を乗り越え、再会と成就を喜びます。それを祝福する二人の門番の役柄は、衣装がないのでわかりにくいと感じましたが、アマデウス・コアのパートリーダーのお二人の声を堪能しました。小柄なパミーナは可憐な印象ですが、声は実に良く通ります。オーケストラは、バロック・ティンパニの音が歯切れ良く、なるほど昔の楽器を復元して用いる意味がよくわかりました。
そして再び圧倒的な合唱。「勝ったぞ、勝った!」が輝かしく響き、光の世界を象徴します。
当然のことながら、光が輝くほど闇は暗くなる。モノスタトスと夜の女王、三人の侍女が神殿に忍び込もうとしますが、雷にうたれてしまいます。モノスタトスは宮下通さん。いつもは軽妙な役が多いのですが、モノスタトスとは驚きでした。
ザラストロと合唱が登場、フィナーレです。軽やかさと輝きのある音楽が、華やかに展開されます。モーツァルトの音楽の持つ充実感を、ぞんぶんに味わうことができました。良かった~!客席の皆さんも、手が痛くなるほどの拍手、大拍手です。
そうそう、すぐ近くの席の方は、やっぱりうにさんでした(^o^)
息子さんにお祝いを申し上げ、ファン交流会に急ぎましたが、こちらは「紅藍物語」の木島さんと存じ上げていても、うにさんの方からはヘンな中年おじんとしか見えないかもしれず、最初はわからなかったかもしれませんね~(^o^;)>poripori
こちらは交流会の様子です。肖像権の問題もありますので、写真はごく小さく(^o^)/


今回も、たいへん素晴らしい演奏会となりました。ソリストの方々も、山形の聴衆の暖かさを感じておられたようで、また機会があれば、ぜひもう一度素晴らしい歌をお聴きしたいものだと感じました。
【追記】
山形新聞の朝刊に、もう
昨晩の演奏会の記事が掲載されておりました。さすがに地元紙。早い!もしかして当方の記事と競争してたりして(^o^)/ さすがにそれはないか(^o^)/