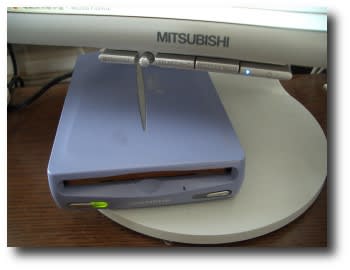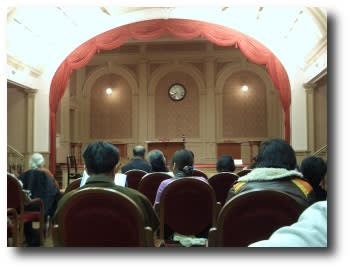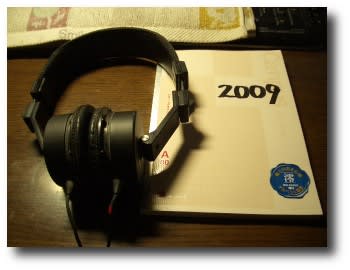リムスキー・コルサコフの「弦楽六重奏曲」の次に車に積み込んだのは、プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲のCDです。ボリス・ベルキンのヴァイオリン、マイケル・スターン指揮チューリヒ・トーンハレ管弦楽団の演奏で、今回は第2番を取り上げます。
プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第1番は、ロシア革命のその年に完成し、26歳の若さの作曲者御本人は母国を離れ、外国に亡命してしまいます。でも1933年にはソ連に帰国、この頃「ロミオとジュリエット」や「キージェ中尉」などを作曲し、好評を博します。同国の広告塔として、まだ優遇されていたであろう1935年に、このヴァイオリン協奏曲第2番が作られています。添付された解説書によれば、この作品が作曲された経緯は、フランスのヴァイオリニスト、ロベール・ソータンからの依頼によるものだそうで、演奏旅行中に第1楽章を書き始めたのはパリ、第2楽章はロシアの小都市ヴォロネジ、そしてスペインのマドリードで初演されたという記録があります。さて、なぜスペインなのか?
Wikipedia によれば、1935年といえば、ヒトラーがヴェルサイユ条約を破棄し、ナチス・ドイツの再軍備を宣言した年です。日本で言えば、美濃部達吉氏が天皇機関説で不敬罪に問われた頃。コミンテルンが第7回大会において人民戦線戦術を採用し、台頭するファシズムに危機感が高まっていた時代。やがてフランコ独裁にいたるスペイン内戦の直前、第2共和制末期に、プロコフィエフはソ連から演奏旅行を許可された(派遣された?)ことになります。まだ若く無鉄砲だった「赤いピアニスト」ではすでになく、40代半ばの分別ある大人として、自分が果たすべき広告塔の役割を自覚していなかったはずはないでしょう。
第1楽章、アレグロ・モデラート、4/4拍子。独奏ヴァイオリンが不安げな主題を奏しはじめ、オーケストラが受け継ぎます。独奏ヴァイオリンの速いパッセージを経て、ゆったりと下降する第2主題が登場、ぐっと盛り上がり、弦のピツィカートで静かにこの楽章が終わります。
第2楽章、アンダンテ・アッサイ~アレグレット、12/8拍子。独奏ヴァイオリンがあたたかく優しい主題を奏でます。背景でリズムを刻む管楽器が、人形か鉄腕アトムの歩行の効果音のようで面白い。変奏の後、アレグレットの中間部で登場するフルート・ソロが魅力的です。なんともプロコフィエフらしい、美しい緩徐楽章です。
第3楽章、アレグロ・ベン・マルカート、3/4拍子。カスタネットを伴い、どことなくスペイン風な旋律は、こうした演奏旅行の背景を考えると、納得できますし、どこか不安げでせわしなく、何かに急かされるような曲の雰囲気も、こうした時代背景を思えばよく理解できるような気がします。
この曲は、ハイフェッツが愛奏して世界的に知られるようになったのだとか。ハイフェッツの年代であれば、例えばヒルトン原作の映画「心の旅路」に描かれたような、両大戦間の不安な背景を知るだけに、この作品の美しさも不安感も、身近なものだったことでしょう。現代の私たちには、「それでもこの作品は美しい!」と感じることができるだけですが。
ボリス・ベルキン盤は、DENON COCO-70667 という型番のクレスト1000シリーズ中の1枚で、1993年にチューリヒ・トーンハレでデジタル録音されたもので、プロデューサーは川口義晴氏。録音も良好で、聴きやすいものです。
もう一枚、アイザック・スターン盤は学生時代に購入した懐かしいLPで、CBS-SONY の SONC 10400 という型番。やや速目のテンポで奏する全盛期のスターンのソロはたいへん見事なものですが、オーマンディ指揮フィラデルフィア管のバックもたいへん立派です。
■ボリス・ベルキン(Vn)、マイケル・スターン指揮チューリヒ・トーンハレ管
I=10'50" II=10'08" III=5'58" total=26'56"
■スターン(Vn)、オーマンディ指揮フィラデルフィア管
I=10'24" II=9'31" III=6'00" total=25'55"
プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第1番は、ロシア革命のその年に完成し、26歳の若さの作曲者御本人は母国を離れ、外国に亡命してしまいます。でも1933年にはソ連に帰国、この頃「ロミオとジュリエット」や「キージェ中尉」などを作曲し、好評を博します。同国の広告塔として、まだ優遇されていたであろう1935年に、このヴァイオリン協奏曲第2番が作られています。添付された解説書によれば、この作品が作曲された経緯は、フランスのヴァイオリニスト、ロベール・ソータンからの依頼によるものだそうで、演奏旅行中に第1楽章を書き始めたのはパリ、第2楽章はロシアの小都市ヴォロネジ、そしてスペインのマドリードで初演されたという記録があります。さて、なぜスペインなのか?
Wikipedia によれば、1935年といえば、ヒトラーがヴェルサイユ条約を破棄し、ナチス・ドイツの再軍備を宣言した年です。日本で言えば、美濃部達吉氏が天皇機関説で不敬罪に問われた頃。コミンテルンが第7回大会において人民戦線戦術を採用し、台頭するファシズムに危機感が高まっていた時代。やがてフランコ独裁にいたるスペイン内戦の直前、第2共和制末期に、プロコフィエフはソ連から演奏旅行を許可された(派遣された?)ことになります。まだ若く無鉄砲だった「赤いピアニスト」ではすでになく、40代半ばの分別ある大人として、自分が果たすべき広告塔の役割を自覚していなかったはずはないでしょう。
第1楽章、アレグロ・モデラート、4/4拍子。独奏ヴァイオリンが不安げな主題を奏しはじめ、オーケストラが受け継ぎます。独奏ヴァイオリンの速いパッセージを経て、ゆったりと下降する第2主題が登場、ぐっと盛り上がり、弦のピツィカートで静かにこの楽章が終わります。
第2楽章、アンダンテ・アッサイ~アレグレット、12/8拍子。独奏ヴァイオリンがあたたかく優しい主題を奏でます。背景でリズムを刻む管楽器が、人形か鉄腕アトムの歩行の効果音のようで面白い。変奏の後、アレグレットの中間部で登場するフルート・ソロが魅力的です。なんともプロコフィエフらしい、美しい緩徐楽章です。
第3楽章、アレグロ・ベン・マルカート、3/4拍子。カスタネットを伴い、どことなくスペイン風な旋律は、こうした演奏旅行の背景を考えると、納得できますし、どこか不安げでせわしなく、何かに急かされるような曲の雰囲気も、こうした時代背景を思えばよく理解できるような気がします。
この曲は、ハイフェッツが愛奏して世界的に知られるようになったのだとか。ハイフェッツの年代であれば、例えばヒルトン原作の映画「心の旅路」に描かれたような、両大戦間の不安な背景を知るだけに、この作品の美しさも不安感も、身近なものだったことでしょう。現代の私たちには、「それでもこの作品は美しい!」と感じることができるだけですが。
ボリス・ベルキン盤は、DENON COCO-70667 という型番のクレスト1000シリーズ中の1枚で、1993年にチューリヒ・トーンハレでデジタル録音されたもので、プロデューサーは川口義晴氏。録音も良好で、聴きやすいものです。
もう一枚、アイザック・スターン盤は学生時代に購入した懐かしいLPで、CBS-SONY の SONC 10400 という型番。やや速目のテンポで奏する全盛期のスターンのソロはたいへん見事なものですが、オーマンディ指揮フィラデルフィア管のバックもたいへん立派です。
■ボリス・ベルキン(Vn)、マイケル・スターン指揮チューリヒ・トーンハレ管
I=10'50" II=10'08" III=5'58" total=26'56"
■スターン(Vn)、オーマンディ指揮フィラデルフィア管
I=10'24" II=9'31" III=6'00" total=25'55"