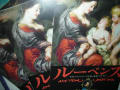「クインテットIV 五つ星の作家たち」に行ってきました(2018.1.13~2.18)@損保ジャパン美術館
またまた次の雪が降る前にと(笑) ようやくまったり見てきました「クインテットIV 五つ星の作家たち」@損保ジャパン美術館♪
『(前略)ポール・ゴーギャンは「芸術とはひとつの抽象なのだ」と言明し 絵画に思想・哲学的要素を取り入れましたが 5人の作家たちはゴーギャンの革新性を無意識に踏襲し 理知的な線と感覚的な色彩とを組合せ 世界を写すことと自己を表出する振幅の中で制作しています
私たちと同時代に制作された 手法と環境も異なる5人の作品を見ることは 「時代精神」に立ち会うことにほかなりません
具象と抽象の狭間の深い闇の中で 光を求めて彷徨い続けているのが現代作家たちであり 私たち自身でもあるのです(後略)』
いつもより少し広く感じられる美術館会場には5人の作家の作品がそれぞれ飾られており ますは船井美佐氏の立体作品 子どもが遊べるようにできていて 作家も子育て中の方のようで ちっちゃな遊び場スペースのようで嬉しくなります♡

次は竹中美幸氏の 35mmフィルムを彩色加工したスタイリッシュな作品

また水玉模様のような水彩とパステルの絵 それから「何処でもないどこか」という作品は 水彩に樹脂を水玉のように丸く貼りつけた 雨の窓のような不思議な作品でステキです

そして室井公美子氏の この世とあの世の境目をあらわすかのような抽象的な油彩の作品の数々 紫色の油絵が多く 第4回目となる今回のテーマ「具象と抽象の狭間」をとてもよく表しています

そして 田中みぎわ氏は 故郷の熊本で幼い頃過ごした川の思い出を 墨や胡粉等でにじみの出る麻紙や半紙にあらわした 日本画のような大きな作品の数々に圧倒されました
白と黒だけであらわした川辺 故郷の風景など...この作家はカタログに収録されていた5人のインタビューの中でも異色で テレビやラジオもなく 自然と触れ合うことを大切にする生活の中で 自らが自然と作品との触媒となるように創作活動を続けられており 実に考えさせられました 最新のものを常に追っている日々の中で こんな純粋な創作活動ってできるのだろうかと...

そして最後に チラシの写真で一番に目をつけていた青木恵美子氏の 実に立体的なアクリル絵の具の花びらの「INFINITY」シリーズ!! これはどうやって作ったんだろうかと...花びらの形をしたアクリル絵の具が立体的に「置かれて」いて 平面の絵というよりは花びらの立体造形のようなのです♡ 色も 白 赤 青 各色それぞれに魅力的です

 ← ここまで立体的に!!
← ここまで立体的に!!
「継続的な作品発表実績があり 将来有望な5人の中堅作家たちを紹介するシリーズ企画第4 弾」とのことで 今回初めて見に行ったのですが ひとりひとり個性が光っており また生き方もさまざまで 魅入ってしまいました
「クインテットIV 五つ星の作家たち」は こちら 2月18日(日)まで!
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
またまた次の雪が降る前にと(笑) ようやくまったり見てきました「クインテットIV 五つ星の作家たち」@損保ジャパン美術館♪
『(前略)ポール・ゴーギャンは「芸術とはひとつの抽象なのだ」と言明し 絵画に思想・哲学的要素を取り入れましたが 5人の作家たちはゴーギャンの革新性を無意識に踏襲し 理知的な線と感覚的な色彩とを組合せ 世界を写すことと自己を表出する振幅の中で制作しています
私たちと同時代に制作された 手法と環境も異なる5人の作品を見ることは 「時代精神」に立ち会うことにほかなりません
具象と抽象の狭間の深い闇の中で 光を求めて彷徨い続けているのが現代作家たちであり 私たち自身でもあるのです(後略)』
いつもより少し広く感じられる美術館会場には5人の作家の作品がそれぞれ飾られており ますは船井美佐氏の立体作品 子どもが遊べるようにできていて 作家も子育て中の方のようで ちっちゃな遊び場スペースのようで嬉しくなります♡

次は竹中美幸氏の 35mmフィルムを彩色加工したスタイリッシュな作品

また水玉模様のような水彩とパステルの絵 それから「何処でもないどこか」という作品は 水彩に樹脂を水玉のように丸く貼りつけた 雨の窓のような不思議な作品でステキです

そして室井公美子氏の この世とあの世の境目をあらわすかのような抽象的な油彩の作品の数々 紫色の油絵が多く 第4回目となる今回のテーマ「具象と抽象の狭間」をとてもよく表しています

そして 田中みぎわ氏は 故郷の熊本で幼い頃過ごした川の思い出を 墨や胡粉等でにじみの出る麻紙や半紙にあらわした 日本画のような大きな作品の数々に圧倒されました
白と黒だけであらわした川辺 故郷の風景など...この作家はカタログに収録されていた5人のインタビューの中でも異色で テレビやラジオもなく 自然と触れ合うことを大切にする生活の中で 自らが自然と作品との触媒となるように創作活動を続けられており 実に考えさせられました 最新のものを常に追っている日々の中で こんな純粋な創作活動ってできるのだろうかと...

そして最後に チラシの写真で一番に目をつけていた青木恵美子氏の 実に立体的なアクリル絵の具の花びらの「INFINITY」シリーズ!! これはどうやって作ったんだろうかと...花びらの形をしたアクリル絵の具が立体的に「置かれて」いて 平面の絵というよりは花びらの立体造形のようなのです♡ 色も 白 赤 青 各色それぞれに魅力的です

 ← ここまで立体的に!!
← ここまで立体的に!!「継続的な作品発表実績があり 将来有望な5人の中堅作家たちを紹介するシリーズ企画第4 弾」とのことで 今回初めて見に行ったのですが ひとりひとり個性が光っており また生き方もさまざまで 魅入ってしまいました
「クインテットIV 五つ星の作家たち」は こちら 2月18日(日)まで!
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング











 文化の時系列展示
文化の時系列展示

 文字はなかったので 結び目で数字をあらわした
文字はなかったので 結び目で数字をあらわした
 ← テキスタイルタイルは まるであじさいの花畑みたい...♡
← テキスタイルタイルは まるであじさいの花畑みたい...♡
 ←フィヨルドの地図
←フィヨルドの地図

 ← 山岳の木版画(撮影コーナー)
← 山岳の木版画(撮影コーナー)



 記念撮影コーナー (釣灯籠)
記念撮影コーナー (釣灯籠)