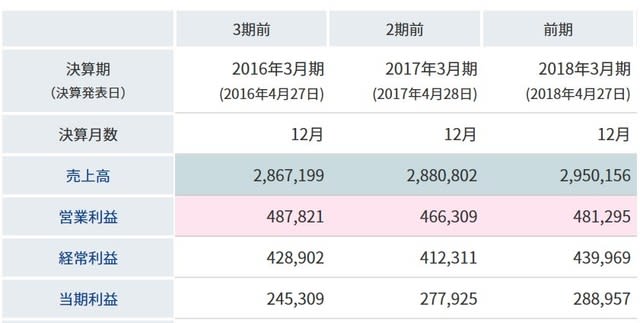ロイターは南太平洋の島国11カ国の財務書類を分析。その結果、この10年で中国の融資プログラムによる債務残高がほぼゼロから13億ドル超に膨れ上がっていることが明らかとなった。
オーストラリアが南太平洋地域に対して大規模な援助プログラムを提供しており、いまなお最大の支援国ではあるものの、2国間融資においては、いまや中国が最大の貸し手であることを財務書類は示している。
中国からの融資は、トンガの対外債務全体の6割以上、バヌアツのほぼ半分を占めている。金額では、パプアニューギニアが約5億9000万ドルと最大で、同国の対外債務全体の約4分の1を占めている。
「経済の脆弱(ぜいじゃく)性や収入源の希少さを踏まえれば、多くが過剰債務に陥るリスクが高い傾向にある」と、世界銀行のマイケル・カーフ局長(東ティモール・パプアニューギニア・太平洋島嶼国担当)はロイターの電話取材に対しこう語った。
「こうした国々の債務は持続可能と思われる限界に達しつつある」
<戦略ツール>
自国経済が台頭し世界的影響力が増す中、中国は2006年から南太平洋諸国への融資を増加させており、それは他国との関係を強化する取り組みの一環だと、大半の専門家はみている。融資パッケージはインフラ建設プロジェクトに参入する中国国有企業にも機会を提供している。
中国企業は同地域の至るところに施設を建設している。バヌアツのルーガンビル港埠頭は上海建工が建設。クック諸島ラロトンガ島の水道施設は国有の中国土木工程集団が建設中だ。
中国外務省の華春瑩報道官は、同国が持続不可能な債務に責任があるという証拠はないと主張する。
「関係国の希望に沿って、われわれはできる限りの金融支援を行い、社会的・経済的な発展を促進する上で必要とされる支援を提供している。そうした国々からは肯定的に受け止められ、歓迎されている」と、同報道官は記者会見でロイターの質問にこう答えた。
中国とトンガの関係は「非常に良い」と同報道官は語った。
しかしながら、スリランカが債務危機の悪循環に苦しむ中、中国が戦略的に重要な南部ハンバントタ港の建設に融資し運営権を得たことは、融資も強力な戦略ツールであると中国が認識していることを示していると、専門家は指摘する。
中国の対外融資と外交に関するハーバード大学による分析の共同執筆者であるサム・パーカー氏は、ハンバントタ港の一件は「警鐘」だと指摘。南太平洋には同様の脆弱性があると同氏は言う。
「他国に借金をさせようという壮大な陰謀が中国にあったとは思わないが、融資しているからにはそれを利用しようとするだろう。地理経済学的に、中国は攻勢を一段と強め始めている」
実際に、最近の米国家防衛戦略は、中国が、とりわけ自国の有利となるようインド太平洋地域の再編を近隣諸国に強いるなどして、「略奪経済」を利用し戦略目標を達成しようとしていると警告している。また、先月公表されたニュージーランドの防衛政策も、中国の台頭により、南太平洋で混乱が高まっていると強調した。
<台湾問題>
世界的規模で見れば、南太平洋諸国への融資は比較的小さく、こうした国々の戦略的重要性も明らかに低いが、同地域は中国にとって魅力がある。
米国とその同盟諸国は、中国に対し、第2次世界大戦の要衝とされた南太平洋の地域に軍事基地を築くことはしないよう警告している。
南太平洋の各国は国連などの国際フォーラムで投票権を有しており、資源豊富な海洋一帯を支配している。
さらに言えば、台湾と正式に外交関係を結ぶ国の3分の1が南太平洋にある。中国は台湾を言うことを聞かない自国の省の1つだとし、必要とあらば、力ずくで取り戻す構えを見せている。
長年、南太平洋の一部の国が変節を重ねてきた経緯もあり、台湾も中国も、融資や支援パッケージを使って忠誠を引きとめようとしている。
<融資の条件>
南太平洋諸国に対する中国の融資を巡る批判のほとんどは、融資が使用されるプロジェクトと融資条件に集中している。
クック諸島は、中国が主導する自国プロジェクトの一部について批判的である。同国は、裁判所や警察署など公的機関の建物建設のために融資を受けたほか、外国人労働者や輸入建材を使ったスタジアム建設のために無利子融資も受けている。
「多くの建物が基準を満たしておらず、いまにも倒壊しそうだ」と、クック諸島の法務相を務めたマーク・ショート氏は言う。
完成から10年もたっていないのにスタジアムはさび付き、安全性に問題があると同氏は話す。裁判所の地下にある独房は2時間以上いると酸欠になるため、外に仮設の刑務所が設けられたという。
中国による財政支援は無利子融資の形で行われることがほとんどだが、オーストラリアやニュージーランド、米国といった従来の支援国は無償で支援を提供し、融資は世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関に任せる傾向にある。
現在、南太平洋諸国のいくつかの政府に債務の返済圧力が高まっている。
中国が債務を免除する兆しは見せず、2013年にトンガの要請をはねつけている。ただし、元金返済を5年間猶予した。
トンガは2018─19年に対中債務の元金約570万ドルを返済する計画だが、これにより、同国の対外債務の年間元利払い費は2倍近くに跳ね上がる。また、これは総予算1億3500万ドルの約4%に当たる。
財政難により、トンガ政府は、五輪のように4年に1度開催される2019年のパシフィックゲームズ開催から手を引き、スポーツ好きの同国でゲーム運営を行おうとしていた大会組織委員会から法的措置を起こされている。