



丸キャリTravel×JR東海の日経セミナーのつづき
大神神社(おおみやじんじゃ)はお酒など“醸造”の神様。
一年の最初のお祭りは繞道祭(にょうどうさい)と言って、宮司が三角鳥居に入り杵と臼で火を切り、食べ物を作るお祭り。
この火をもらって家に帰り、ご飯を炊く。
有名なのは、八坂神社。
多くの神様の大祭は
2月 祈年祭(きねんさい)
11月 新嘗祭(にいなめさい)
そして、例祭(れいさい)。例祭は神社毎の日付で神社の由緒ある祭がある。
祭りは“待つ”
つまり、神の降臨を待つ、神社の大切な日。
だから祭りの期間は長いのです。
地鎮祭は神職が、降神するのを旬のものをお供えし接待する。
神様はお客様で大いに御神酒を飲んで食べてもらう。
儀式が終わると、速やかにお帰りいただき、神様が食べ終わった食べ物を“直会(なおらい)”=なおりあう、と言ういわゆる、宴会である。
もとの状態に直すということを“なおらい”というのである。
こうして、神様を接待し、後にお供え物をみんなで宴会として食べるのである。
だから日本人は昔から接待が大好きとなのである。
■■大神神社 繞道祭(にょうどうさい)
繞道祭は「ご神火(しんか)まつり」(地元では「おたいまつ」)とも称され、全国で最初に行われる神事 です。この繞道祭に用いられる「ご神火」は、新年の午前0時を期して、拝殿の東方の禁足地となって いる三ツ鳥居奥で神官によりきり出され、拝殿両側の燈籠に移されたあと、続いて繞道祭が行われます。
以下、詳しくは下記HPを参照
http://www.rekishikaido.gr.jp/time-trip/mailmagagine/200712/kawa0712.html
丸キャリTravel×JR東海の日経セミナーのつづき
古来、トイレのことは『便所』(べんじょ)と書き、びんしょと読んでいた。
びんしょとは臨時にする所で、あまりにも直接的なので、御不浄とか、雪隠とか手洗と間接的な表現にしていた。
さて、トイレの神様という唄かがあったがトイレの神様は唄にも出てくるように“女神様”らしいが、名も無い神様らしい。
だから昔は妊娠、5ヶ月目の戌の日に便所(びんしょ)に赤飯を供え、注連縄をし拝礼したらしい。
厄年(やくどし)は昔は役年と書き、男性25歳の時に村の大きな“役割”が回ってくる年とされていた。
村の大きな役割とは、神社に関することが多く、役年になると身を清めて、精進して神社の役割に努めるという意味だったそうだ。
本来はお祝いの年で、寿命が短かったこの時代は『この年まで生かしてくれて、ありがとう』とする感謝の年であったそうだ。
■厠神
http://www.youkaiwiki.com/entry/2014/05/30/%E5%A6%96%E6%80%AA%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%81%AE%E7%A5%9E%E2%80%95%E2%80%95%E5%8E%A0%E7%A5%9E
古来、トイレのことは『便所』(べんじょ)と書き、びんしょと読んでいた。
びんしょとは臨時にする所で、あまりにも直接的なので、御不浄とか、雪隠とか手洗と間接的な表現にしていた。
さて、トイレの神様という唄かがあったがトイレの神様は唄にも出てくるように“女神様”らしいが、名も無い神様らしい。
だから昔は妊娠、5ヶ月目の戌の日に便所(びんしょ)に赤飯を供え、注連縄をし拝礼したらしい。
厄年(やくどし)は昔は役年と書き、男性25歳の時に村の大きな“役割”が回ってくる年とされていた。
村の大きな役割とは、神社に関することが多く、役年になると身を清めて、精進して神社の役割に努めるという意味だったそうだ。
本来はお祝いの年で、寿命が短かったこの時代は『この年まで生かしてくれて、ありがとう』とする感謝の年であったそうだ。
■厠神
http://www.youkaiwiki.com/entry/2014/05/30/%E5%A6%96%E6%80%AA%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%81%AE%E7%A5%9E%E2%80%95%E2%80%95%E5%8E%A0%E7%A5%9E

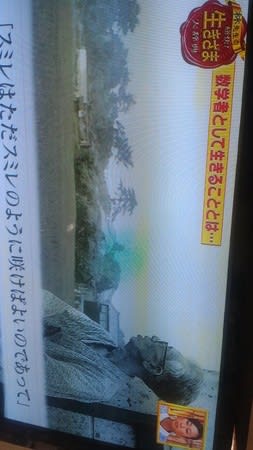
たまたま観ていた番組の2つで共通して出て来た『道元禅師』。
禅宗の曹洞宗の開祖だ。
個人的なには弘法大師空海が何となく好き。あのお焚き上げも迫力があっていい。
最澄よりは何か空海の方が好きというレベルであるが。
最近、爆笑問題がMCの宗教バラエティー番組『ぶっちゃけ寺』が話題だし、御朱印ガールなるものも、多数生息し始めている。
末法だと宗教が賑わうというがどおなんだろうか?
なにはさておき、良い話しだったのでご紹介。
ところで、ぶっちゃけ寺のBGMで流れているガンダーラは誰が歌っているのか、知っている人がいたら教えてちょ。
■道元禅師
放てば手に満てり
手を放したら手いっぱいに広がる。
普通、欲しい物は握りしめる、抱える、抱き込む、俺のものだとする。
ところが道元禅師は本当に大切なものは本当に大事なものは手を離しなさい。
放てばほら、手にいっぱい満ちますよ。
相手の心もそうです、引き寄せよう引き寄せようと思うと、得てして逃げる。
■岡潔 天才数学者
私は人には表現法がひとつあればよいと思っている。
『数学なんかをして人類にどういう利益があるのだ』と問う人に対しては、『スミレはただスミレのように咲けばよいのであって、そのことが春の野にどのような影響があろうとなかろうと、スミレのあずかり知らないことだ』と答えてきた。私についていえばただ数学を学ぶ喜びを食べて生きてきただけである。
人の中心は情緒である。
『情緒と日本人』より
人間も自然の中の1つであり、自然と人間がつながるためには知性とか理性とかではなく、情緒の部分てものをしっかりしておかなければ自然とつながらない。
松尾芭蕉とか道元禅師だとかメチャメチャ詳しい。
日本人が元々持っている情緒が古典の作品の中に現れているので、しっかりと勉強し、インスピレーション型の西欧に対して、日本人は情緒なんだとおっしゃっている。
夏は暑くて嫌だ、冬は寒いという言い方をするが、嫌だと思うのは内部にありそういった邪心のようなものを削ぎ落とせば、夏は夏でいいなぁ、冬は冬でいいなぁ、秋は秋でいいなぁと、そういう風に受け止められる。
それが芭蕉なんかの作品には詠まれている。
日本人は情緒が中心である。そういう中で自然とつながる。そういう生き方をしてうかなければいけない。
奇行といわれることが、ストレスを溜めない一番自然な状態をたもち、合理的なのである。
今日は明け方に雪が降ったくらい寒く、最高気温も5℃くらいということなので、ランチは美々卯でおうどんでも食べようかと。
寒いだけあって、美々卯は満席状態で賑わっていた。
周りはおばちゃんや日本酒で既に出来上がってるおじいちゃんなどで、ほのぼのとした時間が流れている。
ここへ来ると何かホッとする。
寒いだけあって、美々卯は満席状態で賑わっていた。
周りはおばちゃんや日本酒で既に出来上がってるおじいちゃんなどで、ほのぼのとした時間が流れている。
ここへ来ると何かホッとする。





















